
都市をつくる─『新建築』2019年12月号月評
「月評」は『新建築』の掲載プロジェクト・論文(時には編集のあり方)をさまざまな評者がさまざまな視点から批評する名物企画です.「月評出張版」では,本誌記事をnoteをご覧の皆様にお届けします!
(本記事の写真は特記なき場合は「新建築社写真部」によるものです)
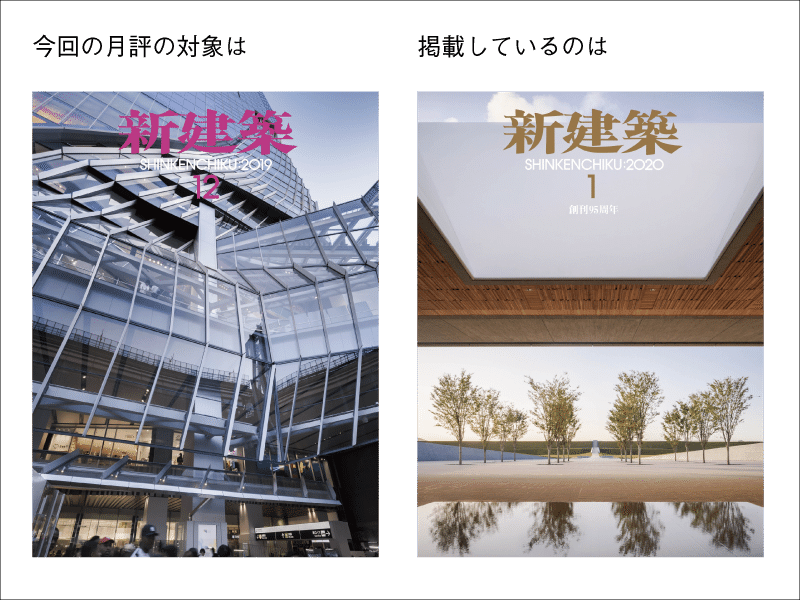
評者:羽藤英二
都市をつくる
この記事を読んで,ストリートを愛したジェイコブズの言葉
「都市の起源は黒曜市である」
を思い出した.
建築家が設計する建築は,黒曜石と言えようが,内藤廣は,その黒曜石を売る市を,設計することを希求した.市は商いをするための広場やバザール,売買を支える制度など,さまざまな要素から構成される.
ただし,今黒曜市に集う人はどこにもいない.黒曜石に価値がなくなったからだ.
土地に自然するナチュラルリソースと人を集める市の磁性は,都市の本質を指し示しているが,その磁力には賞味期限がある.
上海,シンガポール,深圳,雄安新区,東京を取り巻くアジアの都市間競争は激化している.五島慶太がつくった渋谷はその盛衰をかけて,賭けに出たと言っていい.フォスター+パートナーズやザハ事務所が,世界中の都市設計競技において,まったく新たな都市と建築の関係を提案する中,日本では,建築家が都市から撤退して半世紀以上経っている.
今の日本で,建築家に果たして何ができたか.
ジェイコブズではなく,モーゼスの香りがする日本的な密室の会議でしか進められない都市設計のもどかしさと困難さについて,あるいは建築設計から竣工までの期間が長くても数年であることを考えた時,都市をつくるその長きにわたる時間について,建築家を目指す若い人たち,あるいは淡々と図面を描き続ける建築家に,今都市をつくる仕事は,どのように届いただろうか.
しかも,渋谷の都市設計の青写真を描いたのは(建築家ではなく)交通を専門とする森地茂なのである.
交通の王として国内ほぼすべてと言っていい陸海空の交通プロジェクトを推進してきた森地が描いた渋谷の青写真は(内藤が記事の中の座談会で触れているように)ひと言でいえば渋谷の谷地形に蓋をするものだった.
東京全体の流動像の中で渋谷を国際ハブセンター都市としてさらなる発展を目指した森地の頭の中には,宮益坂と道玄坂を結ぶ水平方向の外科手術の術式が念頭にあったのではないか.
交通動線の外科的措置の延長線に,建築家の内藤廣が招かれて,渋谷の大改造は始まった.

交通は都市を変える
平成の東京を変えたプロジェクトを概観してみよう.
六本木・流山・柏の葉がまず思い浮かぶはずだ.これらはすべて(森地たちの)運輸政策審議会答申に基づいて首都に外挿された大江戸線(2000年)とつくばエクスプレス(2005年)の賜物である.そして今激変しようとしている渋谷もまた,平成後半(2008年)に開通した副都心線沿線の中核駅にあたり(もう一本は上野東京ライン,2015年).
その駅まち空間の基本構成は.路線の付け替えによって急増する新たな交通流動を渋谷に流し込むことを狙ったものだ.ただ,森地の外科手術は難易度が高かった.というのも,手術が行われる前の渋谷は,戦前の砂利鉄道の名残を残したターミナル駅前の単一地域構造を始原としていたから,谷地形に一駅だけというモノリシックな構造において駅にかかる流動処理の負担はきわめて大きくなる.
鉄道路線を地下に深く再配置し,同時に高層ビルを立体的にアーバン・コアという都市装置によって接続する.まもなくすれば,谷地形の地形に沿ったストリートに襞のよう展開されてきた街区の家賃は上がり始めるだろう.
渋谷の都市風景そのものを変える世界的に見ても難易度の高い無茶な計画と言っていい.正直,内藤廣はよくこんな仕事に取り組んだと思う.
皇居に向けた空間的余地のあるシンボリックな行幸通りと容積操作によって分かりやすく復元された東京駅丸の内駅舎(本誌1211)と後背高層ビル群,国鉄由来の余裕のある大規模敷地にリニアを地下に串ざし,アイコンになる駅舎を中心に高層ビル群と共に林立させる品川.
これらの新旧東京駅と言っていい都市たちと比して,渋谷は複数のプレイヤーとスパゲッティコードのような鉄道と歩行者動線の存在が問題を複雑にしていた.交通が分からなければ都市はできない.しかしそれは,優れた建築家の職能をも超えたものだったはずだ.
日本の建築家で交通に挑んだのは,私が知る限り,過去にふたり,丹下健三と磯崎新である.丹下は東京計画1960で,磯崎はスコピエの都市計画から始まって,各国の都市設計競技において勝利を収め,今もフォスターや,ザハとコンペで競っている.バベルの塔は,単一言語をバラバラにされて建設現場は混乱をきたして瓦解した.建築家は交通と対話ができない.両者の言語は異なるのだ.
丹下健三ですら都市からは撤退した.
この日本的な全体主義的風土の中で,半世紀の後に,建築家は,敷地の中にきれいなビルを建てることに専念し,それを建築と言うことが常識となった.
渋谷スカイの約230mの遮るもののない眺望と,谷地を受け止める建築の足元の揺らぎの設計は,確かな技術に裏打ちされたものであろう.流れと流れを繋ぐ柔らかいボリュームというコンセプトも間違ってはいない.が,それは新しい空間としての企みと野心を持った都市だと,新建築だとはたして言えるのだろうか.
(五十嵐太郎の「日本建築論」によれば)岸田日出刀が,放っておけば営繕が設計してしまうところを,丹下健三にしたから,多くの若手建築家が五輪(1964年東京オリンピック)で起用された.
その頃から,五輪が建築をメディア型へと変質させた.ロンドン五輪の聖火台を設計した(3Dネイティブな)トーマス・ヘザーウィックが,情報とイメージのプールに解き放たれ,五輪プールを設計したザハが,北京大興国際空港を設計し,中国のまったく新たな都市像を演出している.
その先に,建築家の先に何が待っているのか?
署名も,リツイートも,実空間も建築も自動走行も,ボルツマンマシンで正規化された特徴量になれば,デマゴーグ化を経て,設計はモンテカルロ木探索で情報空間と一緒に制御可能な枠組みに放り込まれることになる.
それが今,建築が,都市が置かれている状況と言ってよい.
都市が国家を変える
プリツカー賞章の授賞式において,(イエローベスト運動とノートルダム大聖堂の焼失に揺れる)フランス大統領のエマニュエル・マクロンが磯崎新を前に40分の大演説をしたことは記憶に新しい.
都市が国家を変える.フランスは,都市文化の創造をそのひとつの力として強く認識している.だからこそ,マクロンは,
「私たちは,カフェという空間を,図書館という空間を,広場という空間を,都市は発明してきた.今,私たちは危機に際して新たな空間の発明を求めている」
と磯崎新に述べた.
マクロンが磯崎新を通じて自国の建築家たちに語ったように,カフェという空間も,図書館という空間も,広場という空間も,人間がつくったものだとするなら,都市は,静かに次のイメージを待っている.
パリを,深圳を,上海を,シンガポールを,雄安新区を,そしてすっかりきれいになりつつある渋谷という大地を歩く時,次の何かを私たちは見つけることができるだろうか.
月評の存在を始めて知ったのは,磯崎新と内藤廣と鼎談をやった時だった.
内藤廣は,昔月評で,磯崎新を批判した因縁について説明してくれた.その時,建築が批評という文化を大切にしていることを知り,若者が,泰斗の建築の出来とそのよし悪しについてのあらゆる議論を尽くすことのできる大らかさについて,素晴らしいと思った.
批評することそのものが批判され,自ら批判を自制するか,せいぜい炎上目当てのデマゴーグが跋扈する息苦しい時代を,私たちは生きている.
1年間月評を書くことで見えてくるものに期待したい.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

