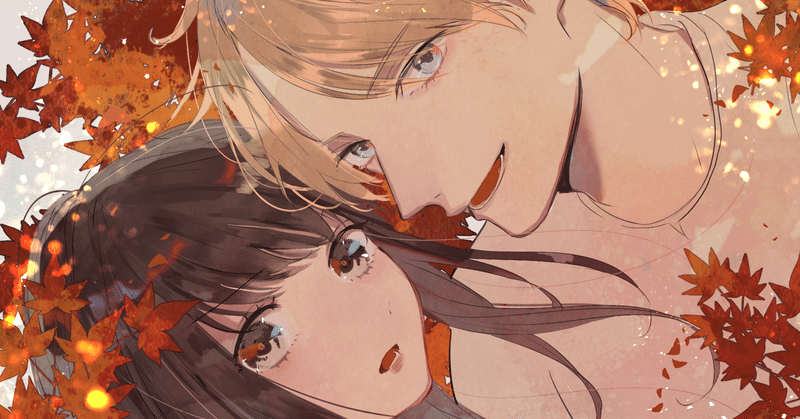
ヒーローじゃない16
とんとんとん、と包丁で刻む規則正しい音が鳴る。
使い慣れた包丁にまな板だ、怪我をすることなどほとんどない。しかし、今のアマネはいつ指を怪我してもおかしくないくらいにぼんやりとしている。
それがいけないことであるのはきちんと自覚しているので、重苦しいため息を吐き出して手を止めた。まな板には小口切りにされたネギが積まれている。味噌汁の具としてであれば、これくらいで十分だろう。
残ったネギをラップに巻き直して冷蔵庫に戻してから、鍋に水を入れて火にかける。同時に魚焼きグリルも点けておいた。
昨夜は夜勤ではなかったし、早めに自分のベッドに入った筈。それなのに、殆ど眠った気がしない。いつの間にか眠りに落ちて、いつの間にか目が覚める。そんな調子をずっと繰り返して、ついに堪らなくなっていつもよりかなり早く起床したのだった。
その為、リビングにいるのはアマネ一人だった。静かな部屋に料理をする音だけが鳴っている。こんなに静かな朝は久しぶりだった。夜勤の時もそうでない時も、大抵食事の前後はいつもチアキが近くにいるからだ。まだ起床には大分早いので、彼は部屋から出てこない。それが今のアマネにはありがたかった。
痛々しい傷跡、触れただけで分かる大怪我の名残、それなのに彼は穏やかに笑っていた。その光景が、今も目に焼き付いて離れない。全てがちぐはぐで、どう考えてもおかしいのに、彼はそれが当然だと言わんばかりの顔でそこにいた。ほんの少しだけ知った気になっていた彼という存在が、また分からなくなってしまったのだ。
「……馬鹿みたい」
小さく呟いてから魚焼きグリルを開け、解凍しておいた鮭の切り身を並べて再び閉める。本当は何も知らなかったくせに、自分は何をこんなに悩んでいるのか。それすらも、今は分からなくなっていた。
暫くして起床してきたチアキは、拍子抜けするくらいに普通だった。顔を合わせて、それから何を言おうかと考えてたアマネに彼はいつも通り「おはよう、アマネさん」とにこやかに挨拶して、いつものように朝食を食べて、後片付けも手伝ってくれた。
昨日のことについてあれこれ悩んでいたアマネを意に介してもいないその様子が、心の内に燻っているわけの分からない焦燥を煽っていく。あんなに重い話をしておいて、本人がこんな調子ではむしろこちらがどうしたら良いのか分からない。
「ね、ねえ、チアキ」
皿洗いが済んだ所で、午前巡回の準備をしていたチアキに声をかける。剣の簡単なメンテナンスをしながら彼は声だけで応じた。
「ん、何?」
「その……えっと」
呼んだは良いものの次の言葉が見つからない。珍しく歯切れが悪いアマネを不思議に思ってか、チアキは目線を上げてこちらを向いた。
目線が合う。いつも通り綺麗な銀の虹彩の中には、困惑する自分の顔が映っていた。
「アマネさん? どうかした?」
「……ごめんなさい、なんでもない」
俯くと、チアキは「変なアマネさん」と笑いつつ、剣を背負って立ち上がった。
巡回についてくるか否かを聞かれたが、首を横に振っておく。一種であるチアキは別にアマネがいなくても支障はないし──何より、ほんの少しだけ冷静になる時間が欲しかった。昨日の夜あれだけ時間があったくせに、それでもまだ足りないらしい。
出かけていくチアキを見送って、また深いため息を吐き出す。雨が降っているわけでもないのに、今日は朝から憂鬱な気分だった。
午前中の当番は、アマネとチアキが巡回または待機、力也が休憩だった。昨日の魔獣騒ぎを力也に引き継いでから彼は一睡もしないで事後処理をしてくれたようで、町は既に落ち着きを取り戻している。付近の町でも鳥型魔獣の警戒捜索が行われたが、今の所見つかってはいないらしい。アマネの所には鳥型魔獣に良く効くオイルの調合を求める声が既にちらほら来ているので、当面の仕事はその辺りを詰めることになりそうだった。
なんとなく昨夜のことが気になって、チアキに宮前家に行く旨を書き置いてから家を出た。空は相変わらずの秋晴れで、とても昨日あんな騒ぎがあったとは思えない。
宮前家に到着して扉を開けると、リビングからひょこりと小さな頭が顔を出した。
「アマネちゃん!」
「あ、ひめのちゃん」
来客が良く知った人物だということに気付いたひめのは一目散に駆けてくる。逃げている時に足を捻ったかもと聞いていたので、アマネはぎょっとした。
「ひ、ひめのちゃん足痛いでしょ? あんまり走っちゃ」
「もう大丈夫! ぜんぜん、いたくないよ!」
走った勢いそのままに抱きつかれて若干よろけながらもひめのを受け止める。良く良く見ればひめのの足には湿布が貼ってあるし、膝や腕には絆創膏も見える。どれも小さなものなので重症ではないようだが、それでもアマネとしては心配なことには変わらない。一歩間違えれば彼女は死んでいたかもしれないのだ。
「幼稚園は? お休み?」
「うん。わたしだけじゃなくて、みんなお休みなんだって」
「そう」
靴を脱いで上がりつつ頷く。妥当な所だ。あのバスの損傷具合では暫く通園は難しいだろうし、子供達のケアを考えると少なくとも二、三日は休園になるだろう。
ひめのと手を繋いでリビングに入るが、中には誰もおらずがらんとしている。いつもはテーブルで仕事をしている七都子も、ソファでだらけている力也の姿もなかった。
「あれ、二人は?」
「パパは寝てる。ママは、えっと、きんきゅーちょうないかい? でちょっとお出かけ」
なるほど、昨日の事後処理はまだ残っているというわけだ。力尽きた力也に代わって、今度は七都子が町の情報収集と説明にあたっているようだ。
どちらかと会えたら手伝うよう申し入れをしなければならないな、と考えているとソファに座ったひめのに隣に来るよう促される。
「チアキくん、大丈夫だった?」
「えっ?」
一体なんのことを言われているのか分からず戸惑うアマネに、ひめのは自身の腕を指差す。
「ケガしてたから。いたくないかなって」
「ああ、それね……大丈夫。手当てしたし、大したことないから」
「本当? よかったあ」
ぱあっと安心したように笑うひめのにつられて微笑みつつ、頭を撫でてあげる。彼女は随分とチアキに懐いているので、殊更に心配だったのだろう。
この様子だと、下手したら初恋辺りも奪っていそうだ。もしそうであれば随分と罪作りな男である。
「パパとママにはいっぱい怒られたの。かってにバスから出ちゃったから……アマネちゃんも、しんでたかもしれないんだぞって。ごめんね、アマネちゃん」
「ううん、良いよ。いきなり襲われてびっくりしちゃったんだよね。仕方ない」
ヒーローの娘としてある程度教育は受けているひめのだが、それでもまだ小さな女の子だ。パニックになれば正常な判断をすることはどうしても難しくなる。酷な話だが──それでも、彼女には慣れて貰うしかない。いつ魔獣に襲われるか分からないこんな世界で恐怖や脅威に慣れろということがどれだけ残酷なことか。それすら、もうこの世に生きる人間には理解出来なくなっているのだろう。
「わたしも、つよくなりたいな。アマネちゃんみたいに」
ぱちり、と目を瞬く。自分にはおよそ繋がらない単語で、理解するまでに少し時間がかかったのだ。
「チアキみたいに、じゃなくて?」
「チアキくんはかっこいいよ。アマネちゃんはつよい」
「そう……?」
補足されてもやはり上手く飲み込めなかった。小さなひめのがヒーローに一種二種という違いがあるということを知っているかどうかは怪しいが、それでもアマネは自身が[強い]と形容されるようなことをした記憶がなかった。
仕事に対して手を抜いてはいないが、魔獣を倒したことはただの一度もないし、大きな功績を挙げたこともない。
ただ、彼女の真っ直ぐな言葉はきちんと届いた。アマネは確かに心が温かくなるのを感じている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

