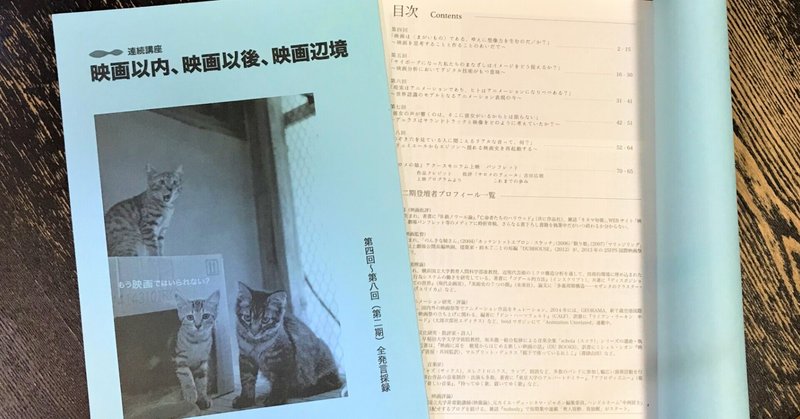
第二期 全発言採録について
2021年の秋。今の社会状況で、改めてこの連続講座の記録をひも解くに、隔世の感があります。簡素な冊子の文字の向こうから立ち上がってくる、熱の記憶。密という言葉に昨今のことさらな意味もなく、むしろ、それが歓迎されることですらあった、あのころ。小さな会場ではありましたが、目の前までぎゅうぎゅうに埋まった客席の圧を感じながら、必死に話し、聞き、考え、見せた、あのような体験は、もう永遠に帰ってこないとすら思います。
実際、渋谷のUPLINKは、すでに存在しません。「Room」という30席足らずの一番小さな部屋でスタートした第一期から、第二期は「FACTORY」という50席強入るライブスペースへ鞍替え。それでも入り切らないときもあり、細い通路から登壇者脇の壁際まで補助席を置いて、へとへとになりながら毎回2時間越え。よくも、あんなハードコアな内容で人々が集まってくれて、終演後も毎度、酒場へ会場を移して。関係者もお客さんも、終電まで。いやはや。
ZOOMというネット上のツールが普及して、トークもオンラインで配信されることが、いつのまにか一般的になり。それは、移動いらずで安全でスマートで。遠方からの参加や、録画で何度も再生できたり、便利で、楽で。表面的には議論も交流も、活性化しているのだろうけれど。何か大切なものが抜き取られた、抜け殻であるような。いや、それは元々、本当に大切ではなく、ただ面倒なだけのことだったんじゃないかと。思ったり、思わされたり。「場」というものの価値が、だんだん希薄になり、軽んじられ、それに慣らされていく世の中に。あれ? これって、映画が、“映画のようなもの” にすり替わっているような違和感。あのころ感じていた、あの嫌な感じと似てやしないかと。考えたりもするわけです。
第二期も全発言採録を作ろうということになり、青本と呼んでいた表題写真の冊子を編集していたのは、2015年の春から夏にかけてだったか。前回の黄本から倍の分量になった、この文字起こしや校正の作業も、ボランティアの方々の尽力のたまものでした。手分けして起こしてくれた部分を合わせて、表記を統一したり、誤字脱字をチェックしたり。編集の井上君にレイアウトまで担ってもらい。夏の終わりにカフェで缶詰になり、ゲラに赤入れした晴れた日のことを、何故か不思議とよく覚えています。
ところで、表紙の猫の写真。これは確か、講座の打合せというわけでもなく、豊嶋さんに最近撮った写真をいろいろ見せてもらっていたとき。どこかの捨て猫保護団体で写したという一枚に、「これ、使わせて!」となり。三匹の猫が、どれがどれだったかは忘れましたが、「以内」「以後」「辺境」だと大ウケしながら、決ったのでした。
最後に改めて、感謝とともに以下、スタッフのお名前を記載します。
編集:井上遊介
文字起こし:永井里佳子 海部淑江 豊嶋希沙 家田真也 菊地泰子 栗原亮 降矢聡 川崎恵 則定彩香 原竜之介 藤森陽子 藤田観 宮田克比古
写真:豊嶋希沙

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
