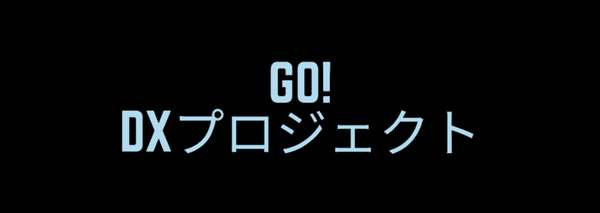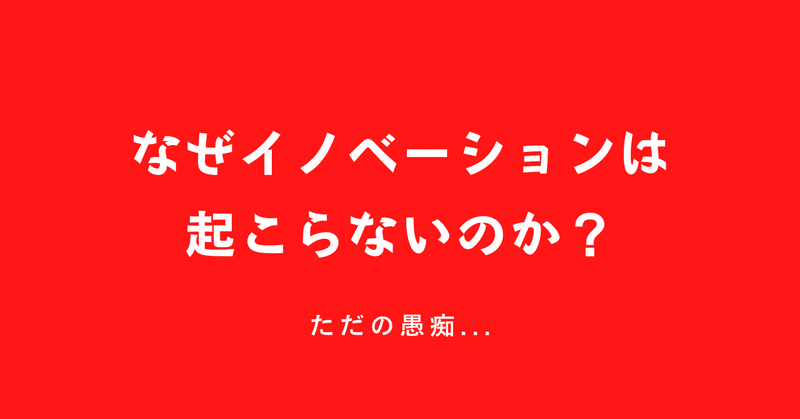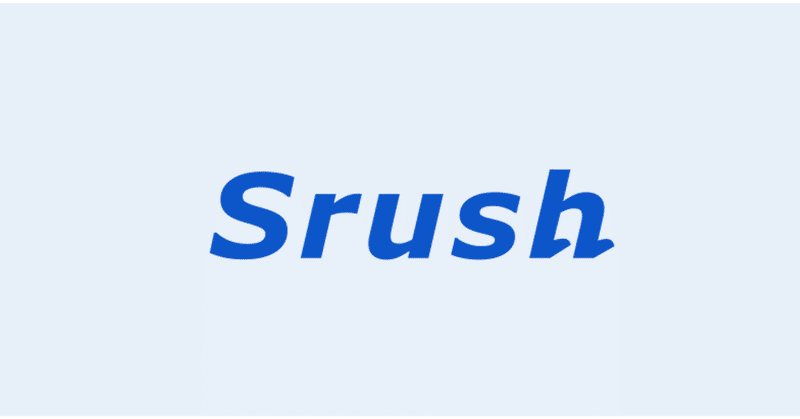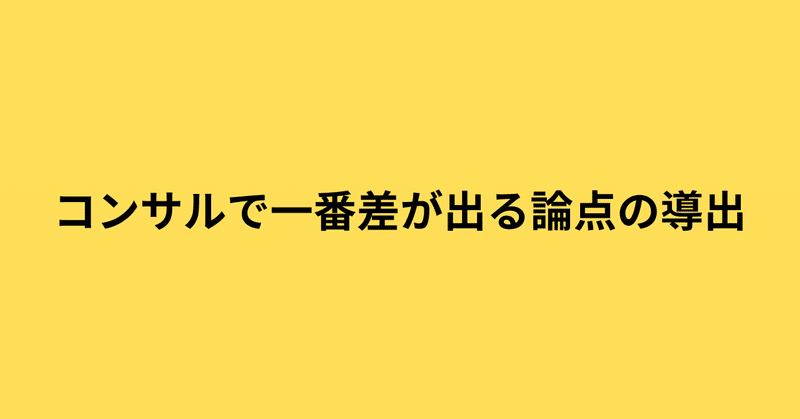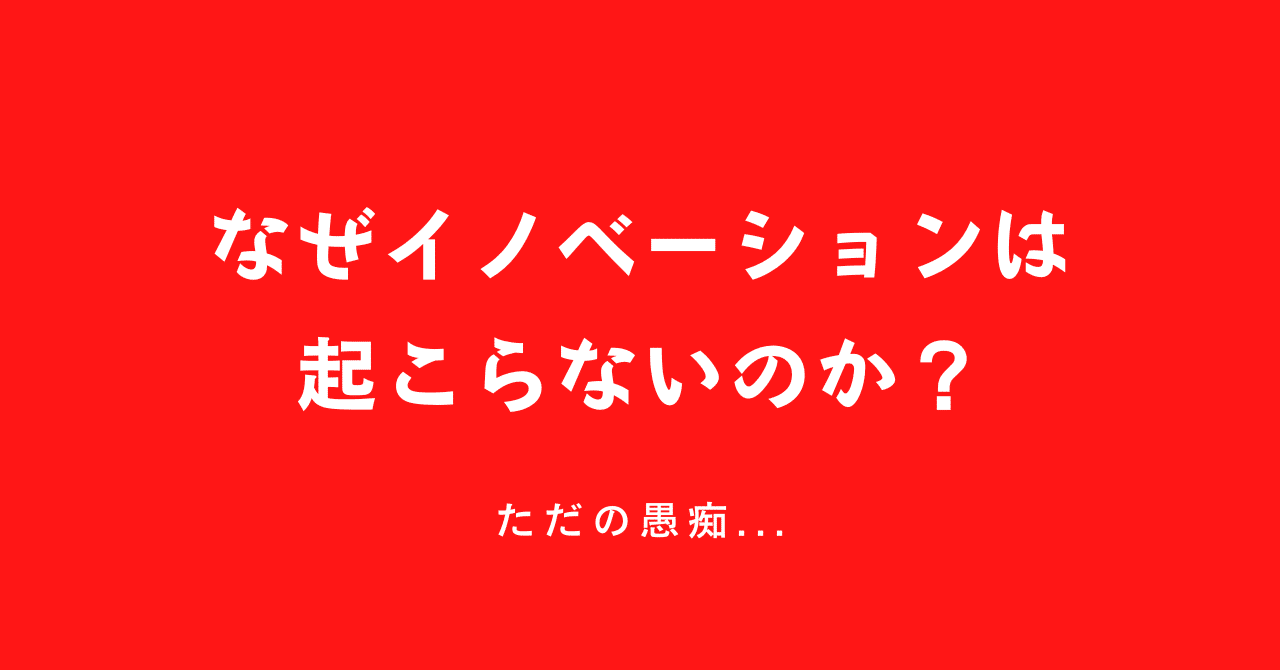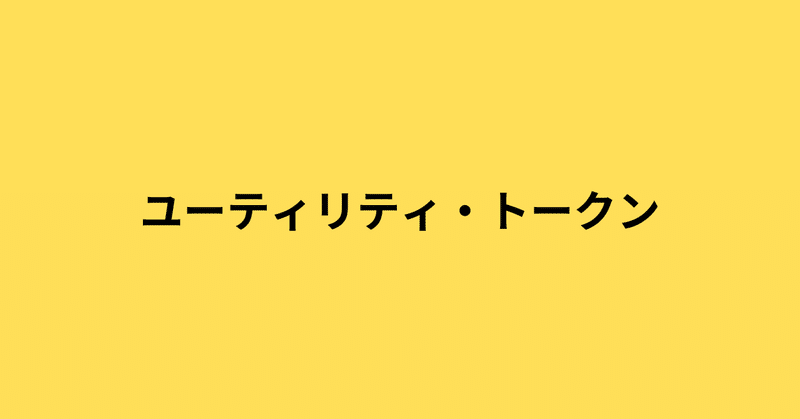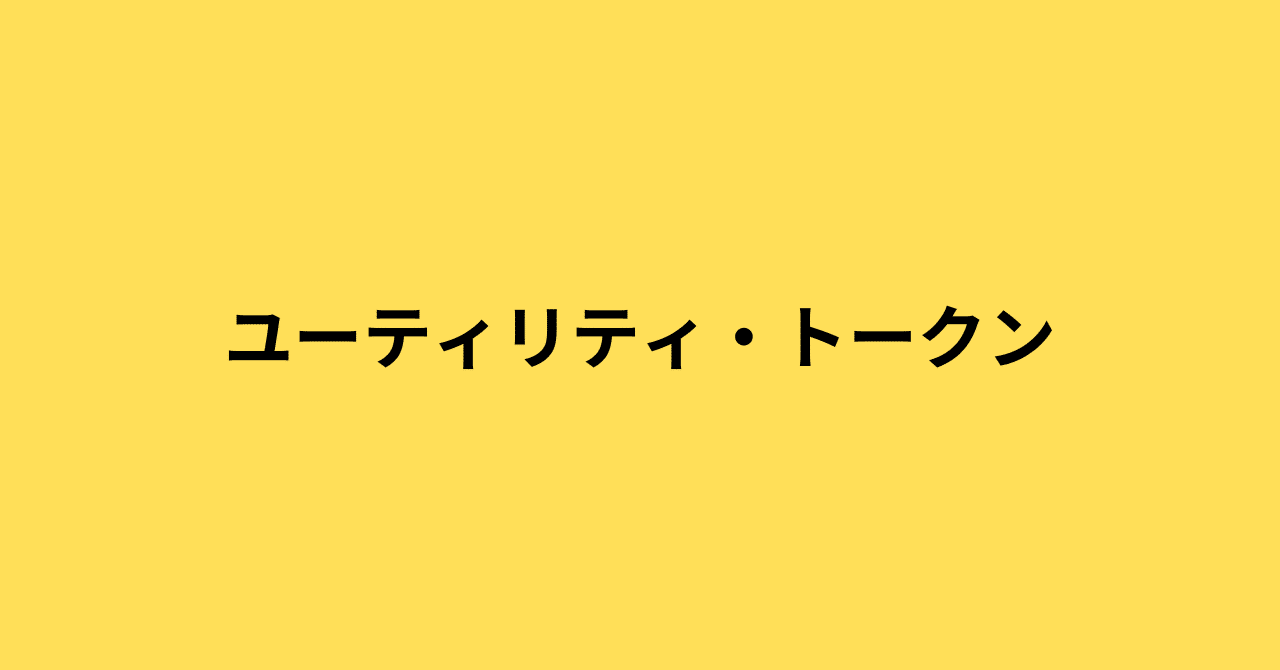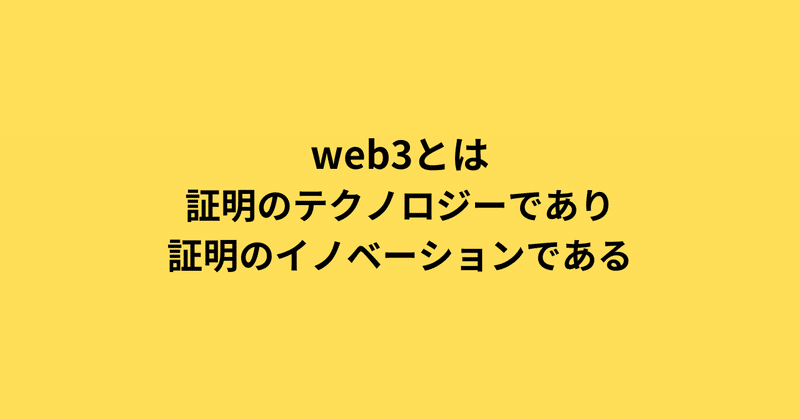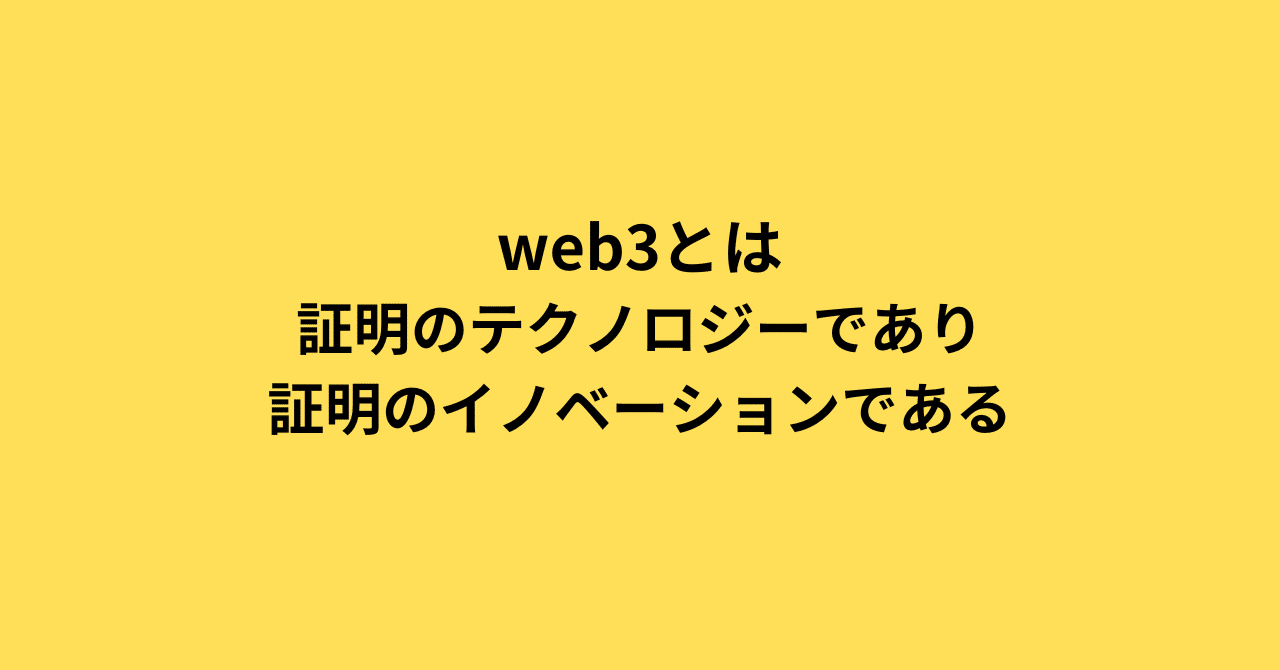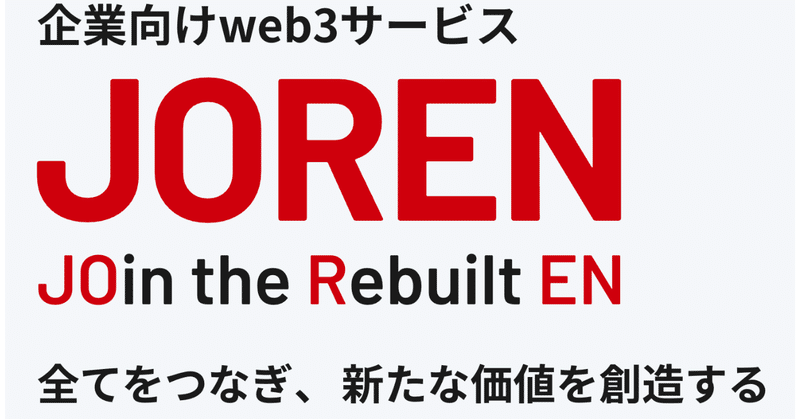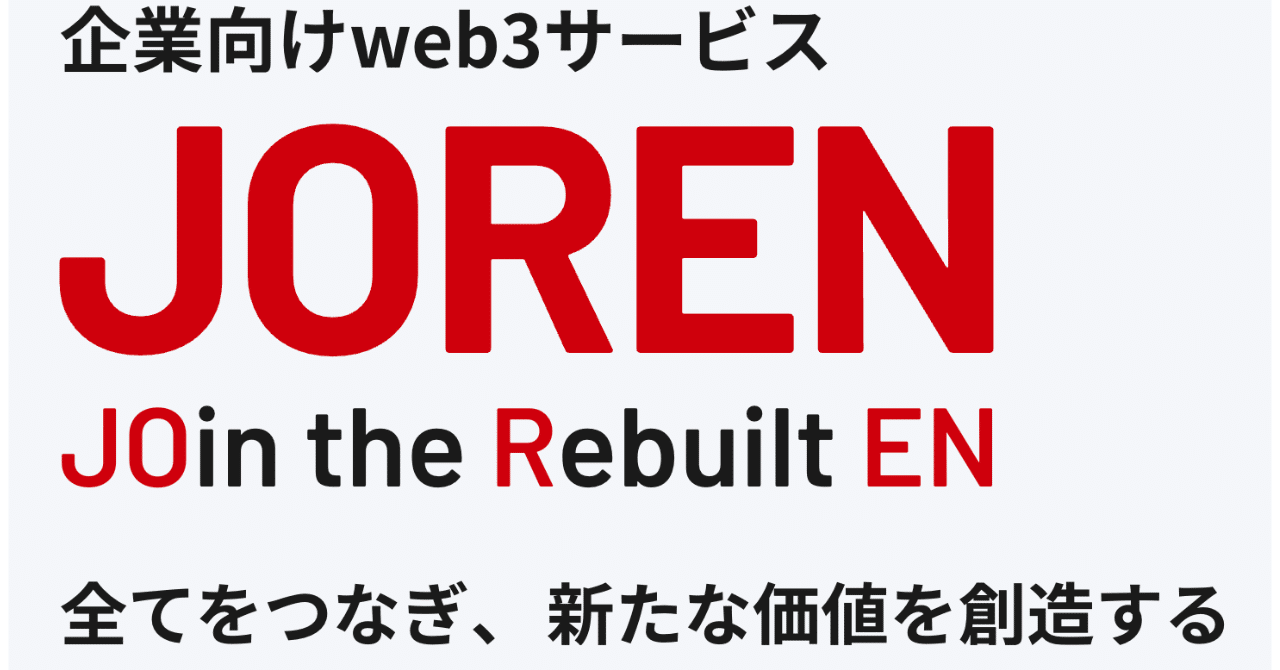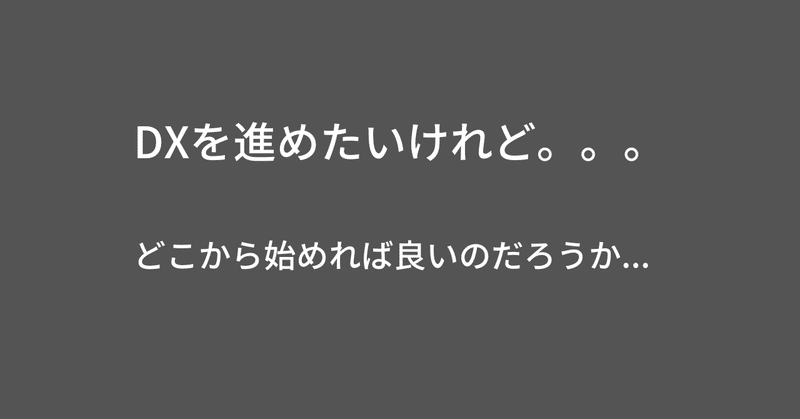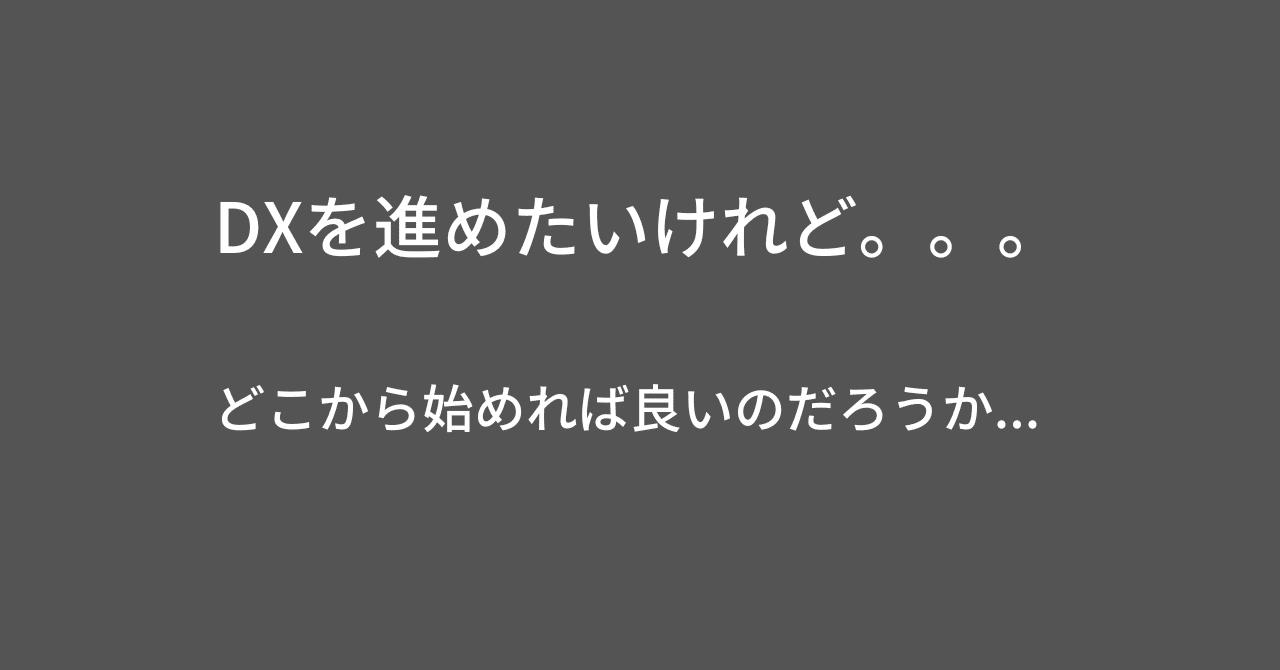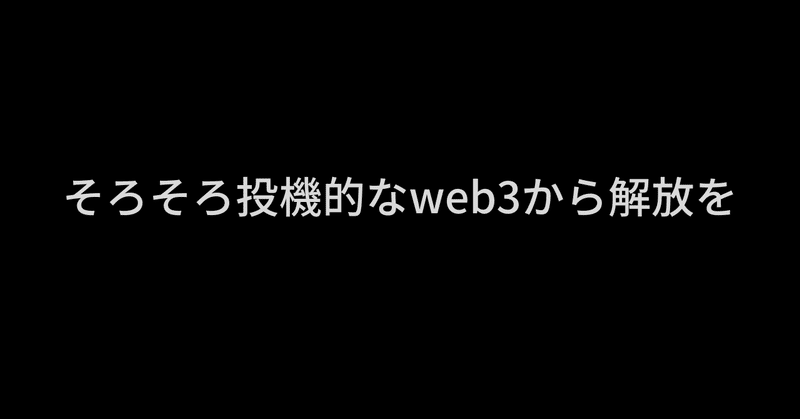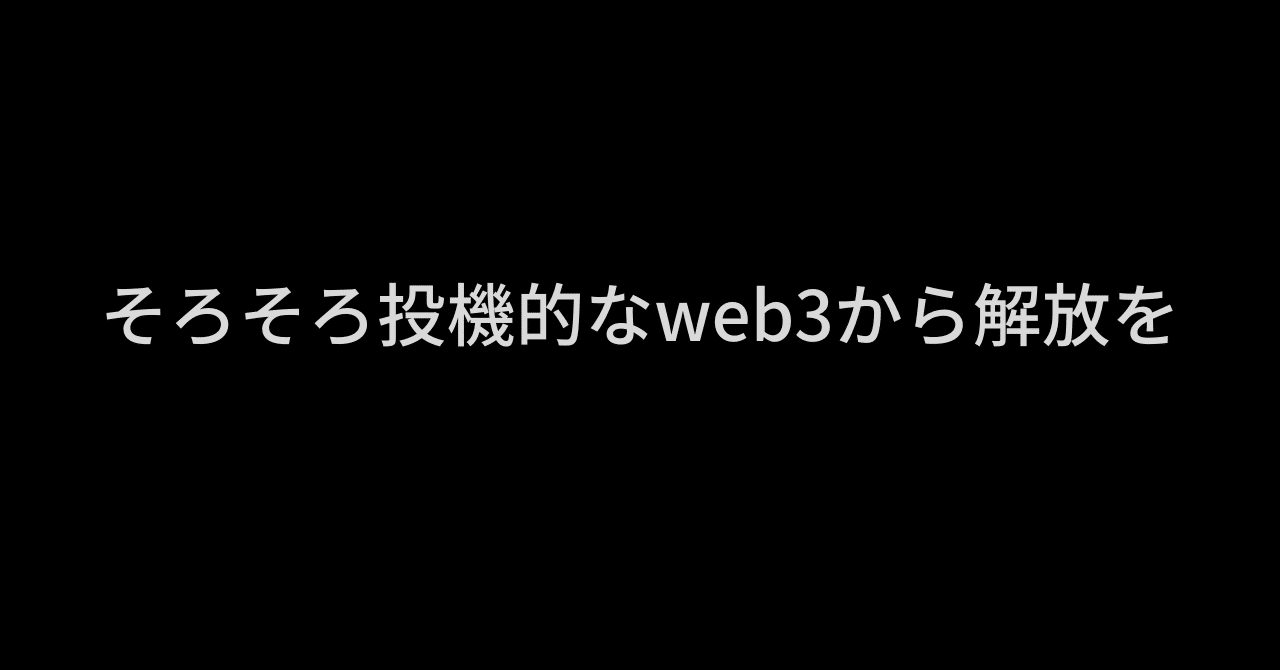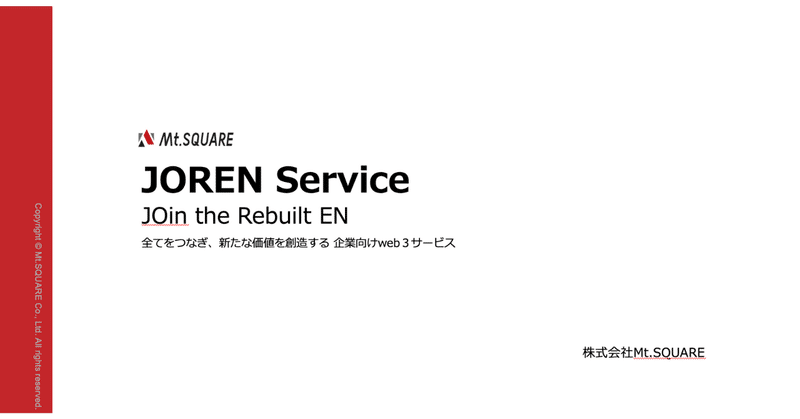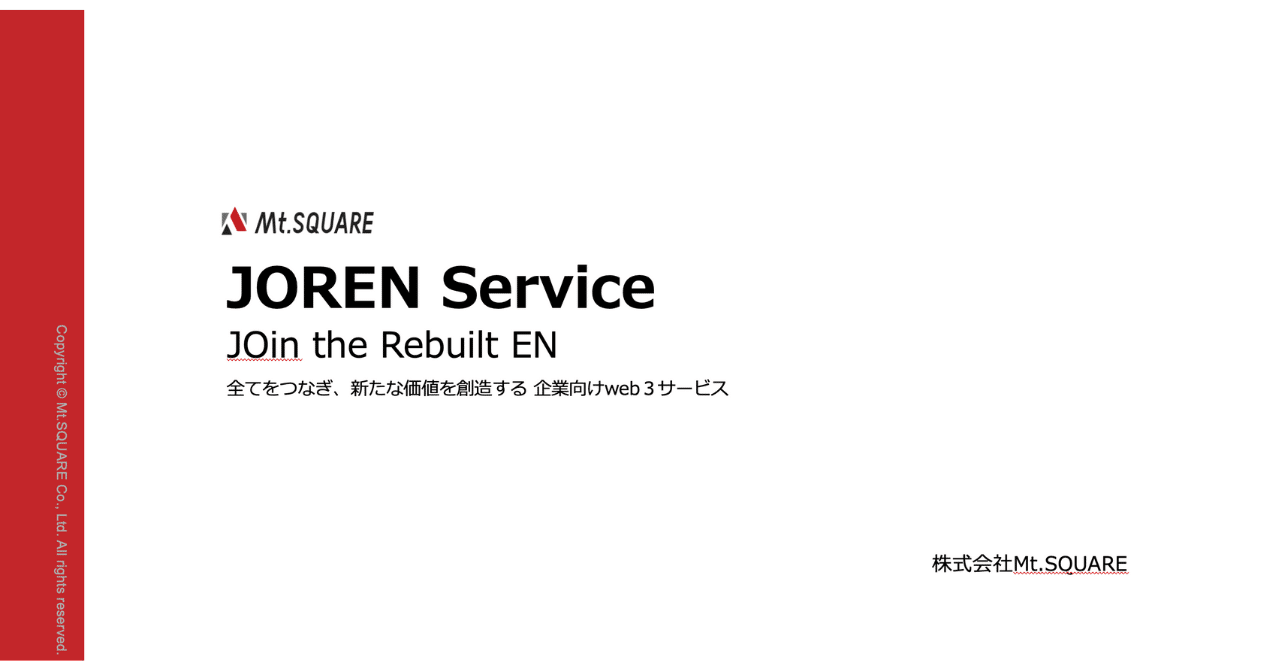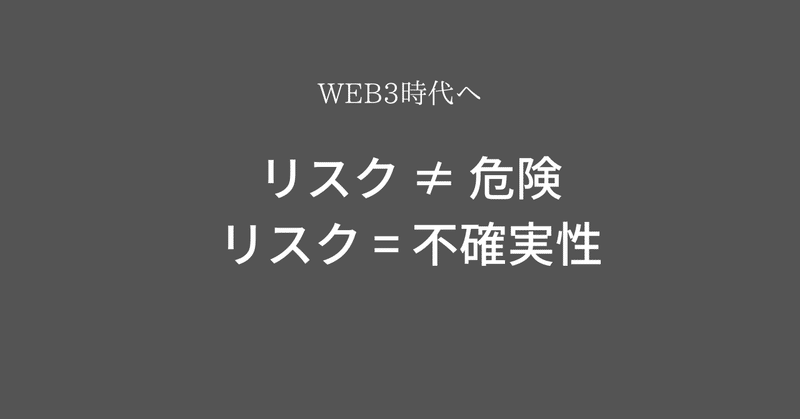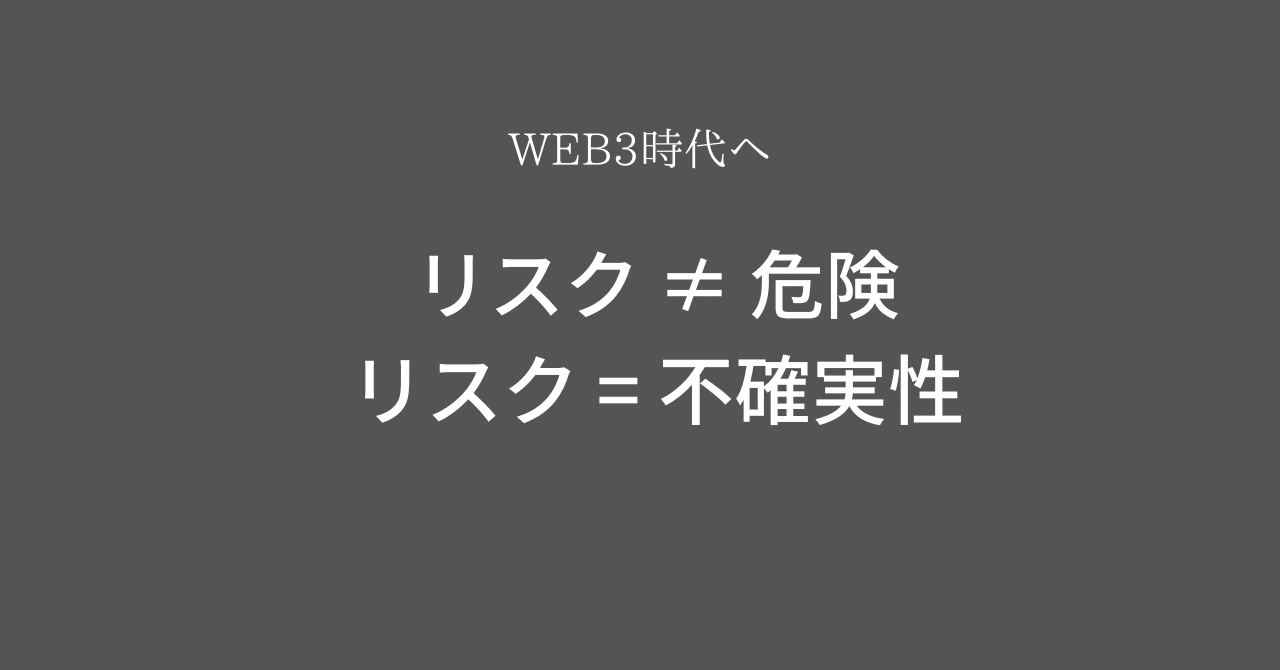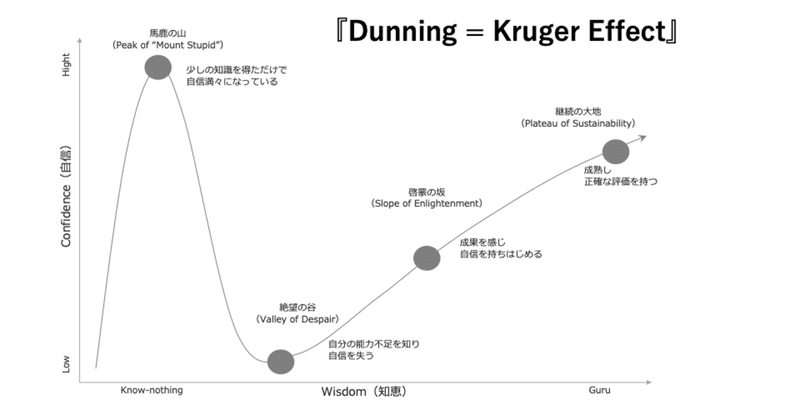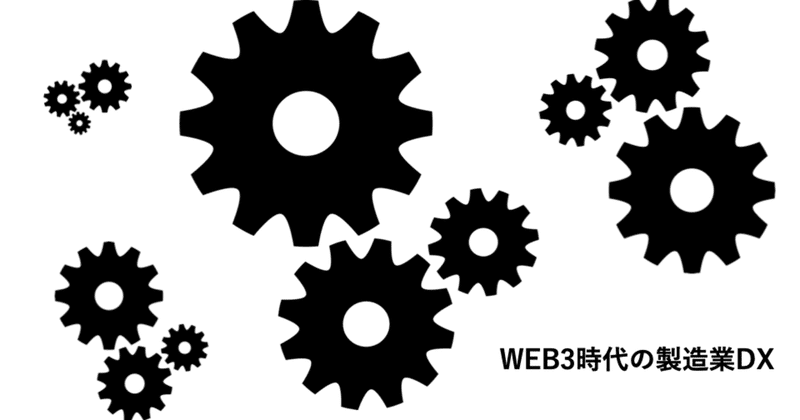最近の記事
- 固定された記事
マガジン
記事
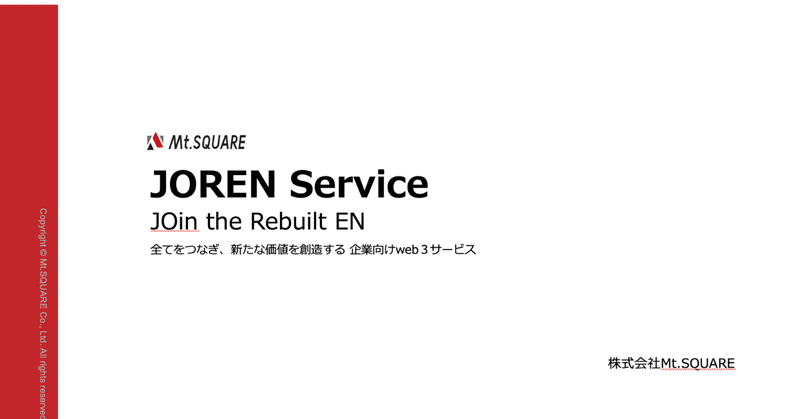
ロイヤルホールディングス「天ぷら x web3 x AI」で外食産業の課題解決を目指す 天ぷら専門店「TEN Labo」 4/27(木) 錦糸町にオープン
ロイヤルホールディングスDX プロジェクト ロイヤルホールディングスは、「中期経営計画2022~2024」において「時間や場所にとらわれない “食”&“ホスピタリティ”の提供」をビジョンとし「既存領域の深掘り」と「事業創造領域への投資」を 進めてまいりました。事業創造領域の一環であるDXプロジェクトにおいて「天ぷら x web3 x AI」で 外食産業の構造的課題の解決にチャレンジするDX店舗として「TEN Labo」を2023年4月27日(木) 錦糸町にオープンいたします。