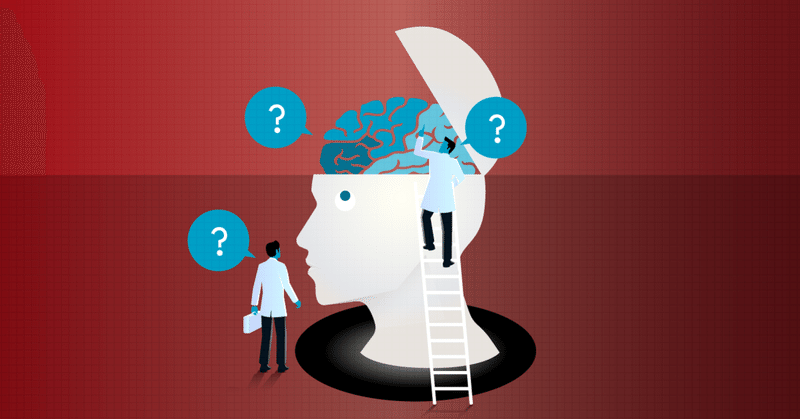
「市民感覚」「科学は人を幸せにしない」前世紀のステレオタイプがいまだ蔓延る日本 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.656
特集「市民感覚」「科学は人を幸せにしない」前世紀のステレオタイプがいまだ蔓延る日本
〜〜「20世紀の神話」は今こそ終わらせるとき(第1回)
21世紀になって20年余が過ぎました。もうすぐ世紀の4分の1、つまり四半世紀になろうとしています。しかしながら日本社会にはいまだに、20世紀の古い神話があちこちに頑として残存していることに驚かされます。
「20世紀の神話」とは、決して「日本はいまだ封建社会」「戦前に回帰したいウルトラ保守がのさばってる」というような話だけではありません。というか、そういう「封建的」「保守的」というのはどちらかといえば19世紀の神話です。もう少し引っ張ってみても、せいぜい「20世紀前半の神話」ぐらいでしかありません。
では「20世紀の神話」とはどのようなものか。それは端的に言ってしまうと、20世紀後半にテレビや新聞によって形成されたステレオタイプなモノの見方の数々です。本メルマガではこれから数回にわけて、それらのステレオタイプ神話がどのようなものだったのかを振り返りつつ、それらの神話が今ではまったく無効になってしまっていることを検討していきましょう。
(1)「市民感覚」は最善だったのか
新聞やテレビではいまだ、政治や社会の問題を論じるときに「庶民感覚からかけ離れてる」「市民の目線を取り戻せ」などの言い回しがさかんに使われています。しかしこのような「庶民感覚」「市民の目線」は本当に正しいのでしょうか?
庶民のほうが政治家や官僚、経営者よりも「健全である」という幻想は、20世紀にはまじめに信じられていました。この背景には、20世紀後半の長い自民党政権時代、これは1955年からスタートしたので「55年体制」と言われていますが、この時代に政権と官僚、経済界のトライアングルががっちりとできあがって、富の分配もこのトライアングルの中で行われていたことへの反発があったのです。
だから歴史的に捉えれば、権力のトライアングルに対抗するかたちで「市民目線」「庶民感覚」を盾にするというのは、当時としては間違いではなかったとわたしも思います。
しかしその対立構図を、半世紀以上も経ったいまも大事に抱えてしまったままで良いのか。
市民目線の怪しさのケースを、ひとつ取りあげてみましょう。1991年に映画化された三谷幸喜さんの『12人の優しい日本人』という戯曲があります。まだ裁判員制度がなかった時代に、「もし日本にアメリカのような陪審員制度ができたらどうなるか?」という仮説のもとにつくられたストーリーです。
タイトルから分かるとおり、1957年のアメリカ映画『十二人の怒れる男』のパロディになっています。父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、陪審員の大半が有罪と確信する中でたったひとりの陪審員が少年の無罪を主張し、他の陪審員を説得していくという骨太な物語です。ひたすら密室での議論を描き続けるという地味な作品ですが、「公正さとはなにか」を考えさせられる素晴らしいストーリーで日本でも大ヒットしました。
これに対して『12人の優しい日本人』では、陪審員である12人全員が最初から「無罪」に賛同し、ひとりの陪審員が反論するのにもかかわらず、「いやでも被告が可哀想ですし」「たぶんやってないんじゃないかなあ」といったあやふやで曖昧な理由や付和雷同で、なかなか議論に進んでいかない。「どうして無罪なんですか?」と聞かれた陪審員の中年女性は、「人を殺すような悪い人に見えなかったから」って答えるのです。
「殺意はあったかも知れないけど、かわいそうだから無罪」みたいなあいまいな意見がたくさん出てくる。これが当時の日本人の自己イメージにあっていたのでしょう。1991年ごろの日本社会では、「日本人は調和を愛する」「日本人は遠慮がちで優しい人たち」という自己イメージがあったから、このような映画が成立し、それを多くの日本人が「日本人ってそうだよなあ」と受け止めたのです。大ヒットし、評価も高い映画でした。
さて、ご存じのように日本の裁判員制度は2009年にスタートしました。映画『12人の優しい日本人』からおよそ20年後のことです。そして裁判員はみんな「優しい日本人」だったかというと、とんでもない。まったく逆の「厳罰化」が起きています。
たとえば、検察官の求刑よりも少し軽い判決になるのがこれまでの裁判官の裁判の常識でしたが、なんと裁判員裁判になってからは、求刑よりも重い判決をくだしてしまうことが増えています。殺人事件の裁判では「被害者が1人の場合、よほどの事情がなければ死刑にできない」という「永山基準」と呼ばれる暗黙のルールがこれまでありましたが、裁判員裁判では、検察が無期懲役の求刑をしている「一人を殺した」被告に、死刑判決を下すような事例も出てきています。
『12人の優しい日本人』を書いた三谷幸喜さんも、まさか日本人の本心にこんな苛烈さが潜んでるなんて思ってなかったことでしょう。結局のところ、わたしたち日本人は見知らぬ他人に対してはとても残酷だということなのです。
90年代までは企業やムラなどの共同体が生き残っていて、その中では他者をいたわっていると私たちは信じていた。しかし共同体の外の人間に対しては、いちじるしく苛烈であるということには気づいていなかった。そういうことではないでしょうか。
そしてこれが、もちろん「これだけ」とまでは言えませんが、わたしたちの「市民目線」「庶民感覚」の真実の一つであるということなのです。盲目的にその正しさを信じて良いものでは決してないということが、おわかりいただけるのではないかと思います。
(2)「テクノロジー/科学は必ずしもは人を幸せにしない」は「公害」報道の名残でしかない
いまだにこういうことを言う新聞やテレビは少なくありません。変種では「合理性ばかりを追い求めていいのか」ってのもありますね。
日本の戦後は電機や重工業、自動車などのテクノロジーに牽引されて経済成長してきたのにもかかわらず、メディアの反テクノロジーがここまでこじれてしまったのは不思議な感じがしますね。しかしこれは実は不思議でもなんでもなく、日本がテクノロジー立国だったからこそ、そのアンチテーゼとしてメディアが「テクノロジーにばかり傾斜するのは危険」と警鐘していたということなのです。
この言説が浮上してきたのは、1960年代の「公害」問題のころだったのではないかとわたしは推測しています(すみません、実地にはまだ検証できていません。この時代の新聞記事はデータベース化されていないので、調べるのがたいへんなのです)。
1950年代から60年代にかけての高度経済成長では、工業化が一気に進むいっぽうで、環境保護の対応がまったく追いつきませんでした。工場は有害物質の混じった廃水を河川に垂れ流し、水俣病や田子の浦のヘドロ害などを生みだした。大気汚染もひどく、四日市ぜんそくや光化学スモッグなど各地で公害が広がっていたのです。
これに対して当時のメディアが「経済成長の一方で、人々の健康が害されている。このままでいいのか」と批判したことはとても正当だったと思います。ちょうどこの時期の1970年には大阪万博が開かれ、「人類の進歩と調和」というスローガンのもとに科学の未来が高らかにうたいあげられたことも、科学万能主義への疑問を訴えるきっかけになっていました。
しかしこれはあくまでも、1960年代から70年代にかけての話です。半世紀以上も前なのです。
この時代からさらに遅れて、1990年代に入るとバブルが崩壊して経済は失速し、日本は底知れぬ30年不況の時代に入ってしまいます。自慢のテクノロジーも2000年代には失速し、電機・エレクトロニクスは総崩れになります。「電子立国・日本の自叙伝」というNHKの番組が1991年にありましたが、今は昔。現在の日本産業界は、部品やモジュールなどの中間財供給国としてはいまだ大きな存在ですが、最終消費財として生き残れているのは自動車ぐらいでしょう。
産業界だけではありません。わたしは総務省の情報通信白書のアドバイザリーボードを長年務めていますが、毎年のように白書の世論調査で問題になるのは、日本人が情報通信テクノロジーやシェアリングエコノミー、AI(人工知能)などに後ろ向きであるということです。
それなのに、いまだテレビのワイドショーなどではコメンテーターが「テクノロジーは人を必ずしも幸せにしない」とか「合理性ばかりを追い求めてていいのか」とやってる。いまこそ日本はもう一度テクノロジーで挽回し、テクノロジーで駆動して行くという社会をつくり直さなくてはいけない段階なのに、いまだに「テクノロジーけしからん」を言っていれば、なんとなく「言った気になる」ということがまかり通っている。はっきり言って、半世紀ぐらい古すぎるのです。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
