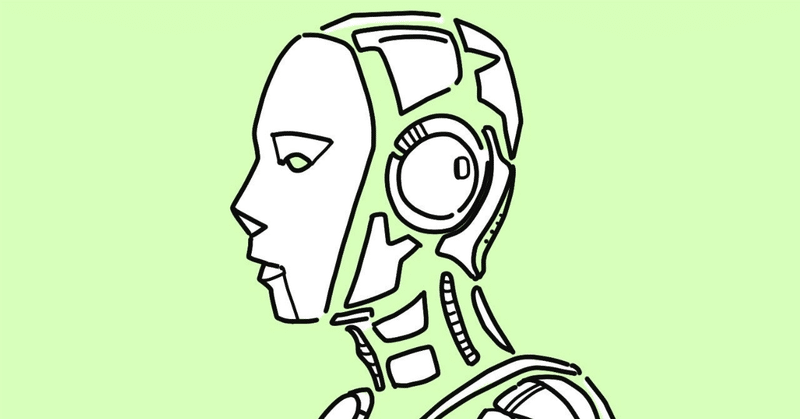
コンテンツとコンテキストの関係から、生成型AIと人類の未来を考える 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.747
特集 コンテンツとコンテキストの関係から、生成型AIと人類の未来を考える〜〜〜クラシック音楽はコンテキストなしには市場が成立しなくなった
ジェネレーティブAI(生成型人工知能)が急激に進化し、画像や動画のみならず小説や記事などさまざまなコンテンツが生成できるようになってきました。いずれは人間に近いレベルの作品が登場してくるでしょう。このテーマについて本メルマガは、744号の「AIだけで文化を創造し、それを私たちは楽しめるようになるだろうか」で論考しました。
今回はこのテーマについて、「コンテキスト」の面から考えてみたいと思います。
コンテンツとコンテキストはつねに一体として語られます。コンテンツが作品そのものであるのに対して、コンテキストは、その作品が持っている背景事情や文脈のことを指します。コンテキストはコンテンツに付随する、副次的なものと考えられがちですが、必ずしもそうではありません。
たとえば有名タレントが書いた本なら、その本の中身そのもの(コンテンツ)よりも、そのタレントの知名度や愛され度(コンテキスト)によって売れ行きが大きく変わる。コンテキストがコンテンツを上回っています。そしてこれは例外的なケースではありません。出版不況が長く続き、読書を純粋に楽しむよりは何らかのツールとして本を読む(たとえば自己啓発目的、あるいは推し活の一環など)という行為が普通になっている現状では、コンテキストがコンテンツを上回っているのが常態と言えそうです。
だいぶ以前の話ですが、2011年にウォルター・アイザックソンによる伝記「スティーブ・ジョブズ」が日本でも爆発的なベストセラーになった時、ひとりの書店員の方が「今日、うちの本屋に『電気の人の本を買いたいんだけど』と言ってきたおばあさんがいた。聞いてみるとどうもジョブズの本らしかった」という趣旨の投稿をされていたのを覚えています。電気の人の本! これもまさにコンテキストのみで本が買われているケースでしょう。
かなり古い2011年の記事で恐縮ですが、在米ジャーナリスト冷泉彰彦さんがこのコンテキストの問題を取りあげています。
フジコ・ヘミングさんは1932年生まれで、長くヨーロッパで生活されていたピアニスト。1995年に帰国されたのですが、1999年にNHKのドキュメンタリ番組で取りあげられたのをきっかけににわかに全国的なブームが沸き起こり、デビューアルバムの『奇蹟のカンパネラ』はクラシックでは異例の30万枚セールスとなりました。
フジコ・ヘミングさんの人気について、冷泉さんはこう書いています。
「無国籍者として貧困と孤独の半生を送ったとか、今も天涯孤独でネコ9匹と暮らしているといった、音楽と無関係なファンタジックな人生物語が付随している、その点をバカにする人も多いようです。ですが、そもそもクラシックの音楽というのは過剰なまでの情報量を持っていて、何らかの人生観なり世界観に絡めて理解しないと受け止められない性質があるわけです」
「そう考えると、ピアニストのキャラクターに興味を持つことから音楽に親しみを持つというのは、一種の必然とも言えます。その点で言えば『ブレンデル引退コンサートに巨匠の人生が凝縮されている』とか、『革命と恋に生きたショパン』などという音楽ファンの言い方にしても、人生物語のファンタジーということでは変わらないように思うのです」
クラシックの楽曲というハイコンテキストなコンテンツは、そのままではマスには流通しにくい。そこで『無国籍者として貧困と孤独の半生を送ったとか、今も天涯孤独でネコ9匹と暮らしている』という人生物語のコンテキストを付随させることで、このコンテキストをフックにしてマスリーチさせる戦略だったということです。
もうひとつのケース。コンテンツとコンテキストの関係を考える上で、いつもわたしが思い出すのは2014年の佐村河内事件です。被爆二世であり中途失聴でもある作曲家として著名だった佐村河内守氏の作品が、実はゴーストライターによる代作だったと発覚した事件です。
佐村河内氏の著名な交響曲《HIROSHIMA》は、クラシックの楽曲単体としてのみ消費されたのであればおそらくヒットはしなかったでしょう。そこに「被曝二世」であり「聴覚障がい者」であるという佐村河内氏の物語がコンテキストとして付随していたからこそ、クラシックとしては異例の大ヒットにつながったのです。
そもそもそれ以前に、クラシック音楽の系譜につながる「現代音楽」と呼ばれるジャンルの音楽を聴いている人はきわめて少ないという現状があるようです。以前、あるプロの現代音楽作曲家のかたが、いまや現代音楽家には報酬は期待できず、生きていく道は親ガチャにめぐまれ親の財産があるとか、あるいは遊んで暮らせるなにかの余裕があるとかなければならない。そうでなければ、自力で何らかの形で大量に売れる作品をものにしなければならない、という趣旨のことを書かれていたのを読んだことがあります。
この「自力で何らかの形で大量に売れる」というのを体現したのが、まさに佐村河内さんだったということです。音楽そのものの価値に加えて、被曝・聴覚障がいというコンテキストを加えて販売するという手法が成功したのです。
ここでもうひとつ注目したいポイントは、佐村河内さんの音楽は難解な現代音楽ではなく「昔風のわかりやすい交響曲」というコンテンツだったということ。
クラシック音楽は、貴族社会の時代には、宮廷で少人数の特権的な人たちだけに聴かれる音楽が、大きな報酬を伴って作曲されていました。特権的な人たちはハイコンテキストな文化を共有していたので、芸術的に高度なコンテンツも受容し楽しむことができたのです。いっぽうで一般の人たち何百万人が楽しんでいたような民謡や俗謡は、だれが作ったのかもわからず著作権もなく、どこにも対価は払われていませんでした。
ところが音楽が特権階級のものでなくなり、広く一般の人に大規模な演奏会やさらにはレコード、CD、そしてネット配信で聴かれるようになると、立場は逆転します。何百万人もの聴衆がいる音楽が莫大な報酬を生みだし、いっぽうで少数の特権階級にしか聴かれない音楽は報酬を得にくくなってしまったのです。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
