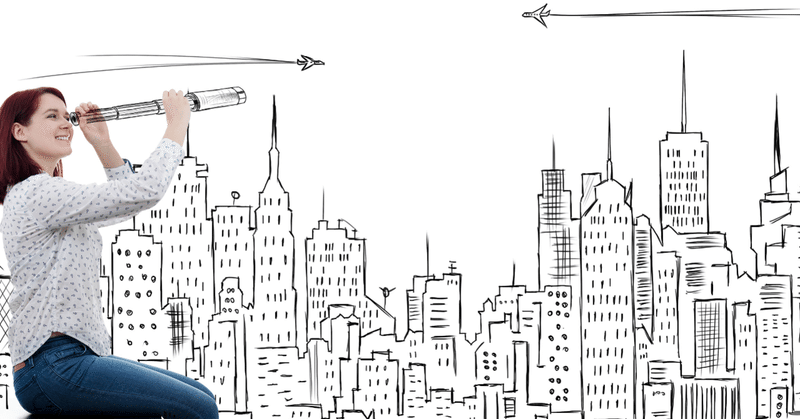
「望遠鏡的博愛」から脱却し、日本国内の貧困と格差を見つめ直せ 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.664
特集 「望遠鏡的博愛」から脱却し、日本国内の貧困と格差を見つめ直せ
〜〜ピケティもトッドもサンデルもカズオ・イシグロもこぞって訴えていること
「望遠鏡的博愛」ということばがあります。『オリバー・ツイスト』『クリスマス・キャロル』などで有名な19世紀のイギリスの文豪、チャールズ・ディケンズが発明したことばです。どういう意味かというと、遠くの人にばかり慈愛を向けて、目の前の貧困や苦難は無視してしまうこと。
ディケンズは『荒涼館』という晩年の長編小説でこのことばを使いました。ジェリビー夫人というアフリカの慈善事業にいたく熱心な女性が出てくる。なのに彼女は、自分の家のことは完全に放置で荒れ放題なのです。彼女の博愛は近くには向かわず、望遠鏡でしか見えないような遠くにだけ向けられているという意味で「望遠鏡的博愛」であるとディケンズは揶揄したのです。
このことばはイギリスではけっこう広まったようで、当時の人気風刺雑誌『パンチ』にも出てきます。風刺画をツイッターで紹介されていた方がいるので引用いたしましょう。
1865年、風刺雑誌『パンチ』に掲載された漫画「望遠鏡的博愛」。
— むっしゅ (@shohojin) July 3, 2018
足元のボロを纏い裸足の子供達には目もくれず、望遠鏡で海の向こうを覗き込む女神ブリタニア。 pic.twitter.com/sEwN1XfnDe
これって日本でもひんぱんに目にする光景ではないでしょうか。中東の難民やアフリカの飢えた子どもは強く同情されるけれど、非正規雇用で苦労して生活している日本の一般社会の人々、たとえば「キモくて金のないオッサン」と自虐的に言われる中年男性貧困層には、なかなか光りが当たらない。これはまさに望遠鏡的博愛そのものです。
19世紀イギリスの望遠鏡的博愛が、現代になってもいまだに存在しているのは、古い価値観のなごりでもあると思います。貧困にしろ格差にしろ、前世紀まではそれは「地域差」の問題でした。1960年代には「南北問題」ということばもあったのです。そのころは冷戦で、西の欧米とソ連や中国など東の共産圏の対立、つまり「東西問題」が政治的には激しかったのですが、それと同時に先進国と発展途上国の格差も大きいという経済の問題もクローズアップされた。先進国はだいたい北にあり、途上国は南に多いというので、南北問題。
日本は戦後のたいへんな経済成長であっというまに先進国入りして豊かになり、だから日本に住んでいるということは豊かであるということとイコールだと思われていました。中国や東南アジアの人たちを「貧しい途上国の人たち」と憐れみの眼で見ていたのです。いまでも年配の日本人にそういう人がいくらか残っています。もはや中国や東南アジアの都市部の方が日本よりも豊かになっているのに。
そういう「東南アジアを見くだしてる高齢者」と同じぐらいに多いのが、いまだにアジアやアフリカの人たちを「弱者」と見なしているような人たち。見くだしてる人も弱者扱いしている人も、左右の両端にいるように見えますが、根っこは同じです。世界の認識が20世紀のままアップデートされておらず、古いのです。
もちろん今でも中東ではシリアやリビアの危機があり、アジアでもミャンマーのような厳しい軍事政権があり、アフリカにもまだ飢餓はあります。しかし総体としては、飢餓や貧困は小さくなりつつあります。それどころかアフリカは経済成長も著しく、ついに「最後の人口ボーナス」地域として急激な工業化が進み、中間層が増えてきています。
「日本は貧しくなった」と言われていますが、いっぽうで21世紀のグローバリゼーションによって途上国は新興国となり、豊かになってきています。日本の地方都市にあった工場が海外移転し、日本から雇用が減ったことが問題視されていますが、それらの工場は海外のどこかの土地で雇用を生んでいるということです。それによって途上国には、かつての先進国の人たちと同じような暮らしをする中間層の人たちが現れてきました。
これは中国で考えればわかりやすいでしょう。わたしが最初に中国にわたったのはもう四半世紀以上も前の、1993年のことです。北京から上海、杭州とまわったのですが、どの都市でもぱだ人民服姿の人たちがたくさんいて、自動車はまだ少なく、自転車の群れが街を走り回っていました。1980年代からの改革開放運動で上海は建設ラッシュが始まっていましたが、わたしが取材で訪問したある企業のオフィスは、建ったばかりのビルの6階にあるのに「まだ電気が通ってなくて、エレベーターが使えないんですよ」と、社員は階段を上り下りして通勤……。街全体が実に埃っぽかったのを思い出します。
1990年代までの中国は、そんなイメージだったのです。しかしいまの中国に「人民服と自転車」をイメージする人はもういません。超高層ビルの群れ、最先端の情報通信テクノロジー、おしゃれな服装の男女。そういうイメージにがらりと変わってしまいました。
東南アジアなども同じで、地方にはまだ牧歌的な風景が広がっていますが、バンコクやジャカルタ、クアラルンプールなどの大都市はもはや日本や中国の先端都市となんら変わりはありません。
そしてこういう大都市に暮らす中間層の人たちは、日本やアメリカ、ヨーロッパの中間層の人たちとなんら変わらない暮らしをしている。H&MやユニクロやGAPの服を着て、スターバックスでお茶を飲み、おしゃれなビストロやイタリアンで食事をしているのです。東京や大阪などの大都市圏で中間層の生活を送っている日本人は、東南アジアやアフリカで同じような生活をしているアジア人やアフリカ人には共感を感じるでしょう。しかしその共感は、同じ日本の地方都市で貧困レベルの生活を送っている人たちにはつながらない。
つまり、社会階層ごとの違いの方が、国ごとの違いよりも大きくなってしまっている。それが21世紀のグローバル時代の現実なのです。「世田谷自然左翼」なんて揶揄することばがありますが、高級住宅地の東京・世田谷で「環境保護に関心あります」と言ってる豊かな人たちは、同じような階層のインドネシア人やルワンダ人には共感しても、同じ日本で暮らしているはずの「キモくて金のないオッサン」(非正規で貧困な中年男性を指す自虐的なネットスラング)には決して共感しないのです。
これは「水平の分断」ではなく、「垂直の分断」です。20世紀の世界は「水平の分断」ばかりが問題視されていましたが、しかし21世紀の世界はイギリスの産業革命時代のように、国内の「垂直の分断」も大きな問題になってきている。だからこそわたしたちは「望遠鏡的博愛」ではなく、もっと足下をみなければならない段階に来ているはずなのです。
残念ながらこの考え方は、日本のマスメディアや社会運動では驚くほど共有されていないと思います。「弱者」といえばアフリカやシリアの難民、「マイノリティ」と言えばLGBTや在日や障がい者や女性問題ばかりが取りあげられ、貧困層に陥っている国内のアンダークラスにはあまりにも眼が向けられていません。
しかしこの状況については、欧米の知識人たちがこぞって声をあげはじめています。トマ・ピケティ、エマニュエル・トッド、マイケル・サンデル、カズオ・イシグロ。彼らの訴えは驚くほど共通しており、同じ問題をだれもが指摘しているのです。なぜそれらの声が、日本の「リベラル」と言われている人たちの間に広がっていかないのでしょうか。わたしには不思議でありません。
ともあれ、その彼らの発信をここから紹介してきましょう。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
