
教養のエチュードTalk.1〈アートディレクター千原徹也〉
境界線を自由に飛び越える
分断された世界を軽やかに横断し、出会う人たちを巻き込みながらプロジェクトを大きくしていく〝台風の目〟のようのな存在。れもんらいふ代表、千原徹也。彼のすごさは、目の前の人の魅力を引き出すだけではない。「偶然」までもディレクションし、全てを物語にしてしまう。
2021年春公開予定の映画『最終日』。本作で初監督を務めた〝アートディレクター〟の千原徹也へのインタビュー。「ADM」というミステリアスなプロジェクト。その概念を紐解く。
*
夢
映画監督に転身するのではなく、「アートディレクターの視点から映画をつくる」ということをやれば今までに誰もやっていないことになる。
嶋津
来春公開される安達祐実さん主演の映画『最終日』で、千原さんの一つの夢であった〝映画監督〟デビューをされました。まずは、その経緯をお聴かせください。
千原
僕自身は映画監督という仕事をしているわけではなく、普段はアートディレクターとして広告やCDジャケットをつくる仕事をしています。もちろん映画は好きなのですが、映画業界のことは全く知りません。
僕は伊丹十三さんが好きで、あの人は50歳までアートディレクターやテレビ番組の放送作家として活躍をされていました。50歳の時に義父さんを亡くされて、その葬式で喪主をした体験をもとにシナリオを書いて『お葬式』という映画を監督されました。50歳での映画監督デビューです。
今では世界的に有名な北野武監督も、もとはお笑い芸人でした。最初から映画の仕事をしていなくても映画をつくれるということですよね。むしろ、僕は「アートディレクターという人生経験が映画にならないか」と思いました。
「このまま映画監督に転身します」と言って、監督として声をかけていただくことも一つの方法だと思います。ただ、〝アートディレクター〟という職業は広告や企業の商品をどのようにしておもしろく売っていくかということを考える仕事なので。映画も「ただ監督をする」というだけでなく、アートディレクターとしての素養をうまく取り入れて全てミックスさせることができれば今までにない映画監督になるんじゃないかって。
例えば、お仕事をさせていただいているウンナナクールさんであれば、映画のワンシーンをそのままCMにして広告にできたらおもしろい。そのように一つひとつの要素をミックスさせていく。それを「映画監督として邪道だ」と言われる可能性もあるかもしれません。だけど、〝新しいジャンル〟だと言い切ってしまえばいい。そこで、新しく「ADM(アートディレクションムービー)」と名付けました。
*
〈ADM〉
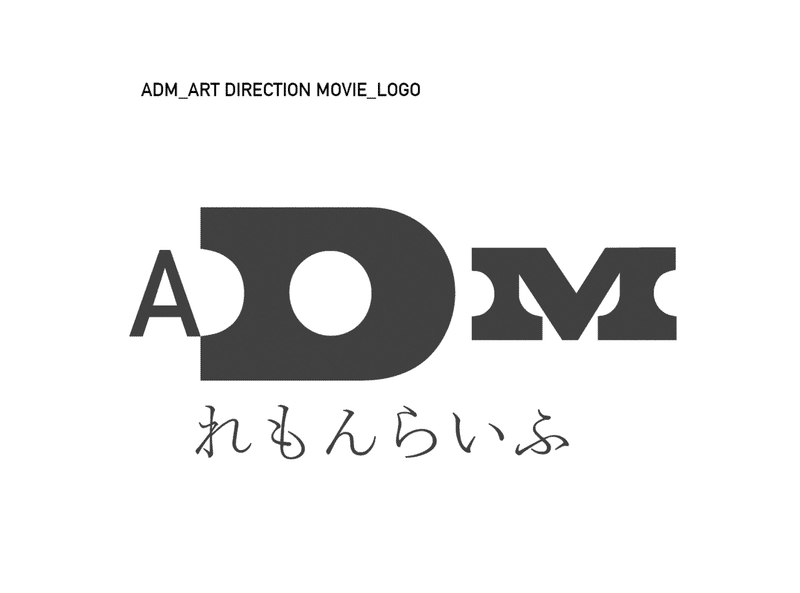
やりたいこととやりたいことを混ぜていく方が、アイデアにつながるんじゃないか。
嶋津
資金集めから、配給会社、キャスティング、広告、PRまでができる。それはアートディレクターとしての経験や、そこで生まれた出会いや人との繋がりがあるからこそ実現できることですね。
千原
そうですね。キャスティングにしても、例えば僕はCDジャケットのデザインをたくさんつくっていますが、そのアーティストの曲を主題歌にすれば双方にとって魅力的な企画になる可能性がある。
主演の女優さんにしても、僕が広告で何度も起用している方に依頼したり、そのことで両方の仕事がPRになるような企画に調整していく。
嶋津
映画とはまた別の話ですが、千原さんがクリエイティブディレクターを務めているウンナナクールでは、下着のPRのために『トーキョーベートーヴェン』としてレコードデビューもされています。「レコードを出す」という行為に「下着のPR」という新しい意味を加えることによって、意外性や世の中へのユニークな広がり方を感じました。
千原
田中知之(FPM)さんと一緒に音楽ユニットをつくりたいと考えていたことを、ウンナナクールのプロモーションと結びつけました。そうしたらパルコさんが、「ウンナナクールさんはパルコに入っているし、レコードデビューということであればライブができるのでぜひやってください」という話に展開した。
ウンナナクールのイベントは、今までは下着を配ったり、がんばってもトークイベントを開催することが精いっぱいだったのですが、音楽へと枠組みを広げたことによってプロモーションの可能性が増えました。

*
「サザンが好きならいいじゃん、両方出しても」
千原
一昨年、『勝手にサザンDAY』というサザンオールスターズを勝手に盛り上げるというイベントを開催しました。サザンオールスターズは出演しないのですが、若いアーティストたちがサザンの曲を歌うという無料イベントに5000人くらいのお客さんが集まってくれて。
その時、いろんな企業に協賛してもらうためにたくさん営業に足を運びました。その中で競合する二件のコンビニに話しに行ったんです。普通だったら「競合相手と一緒に出すことは難しい」となると思うのですが、「同じ地域に二つのコンビニがあることは普通のことだし、サザンが好きなら両方が協賛してもいいんじゃないの?」と話をした。すると「確かにそうだ」とお互いに納得してくれた。
普通なら、企業は「うちの専属でやってください」という話になります。自動車業界であれば「日産をやっているなら、ホンダの仕事はしないでくさい」というように。抱えている案件が少ない方が企業にとって良いと多くの人は思っています。たくさん抱えている人より、時間をかけてしっかりと見てくれそうな気がする。ただ、他に多くの案件を抱えていることでそこに相乗効果を生めば、「たくさんある」ということが逆に良い仕事につながる。
ウンナナクールで下着のプロモーションをしたり、Zoffでメガネの広告をつくったり、桑田佳祐さんのCDジャケットをデザインしていたり。「一点に集中する」ということではなく、「こっちとそっちを繋げればおもしろくなるよね」と。
*
〝武器〟としての企画書
全ての想いを乗せる。その人が他の人に渡しても僕の想いが薄まらないように思える企画書をつくることが重要なポイントだと思います。
嶋津
千原さんのユニークな考え方はとても興味深く、同時にその提案を柔軟に受け入れる企業も魅力的ですね。そこで気を付けなければいけないのは、同じようにしても上手くいく人といかない人がいます。千原さんのお話を聴いて「確かにそうだ」と強く頷くのですが、他の人がやろうとしても実現できるとは限りません。僕には〝千原徹也〟というパーソナリティが可能にさせている領域が大きいと思っています。その辺りはいかが思われますか?
千原
確かにそうかもしれません。僕自身、自分のことなのでどこまで分析できているかわかりません。ただ、説得する上で重要なことは「真実味があるかどうか」です。「これとこれを結び付けたらおもしろいよね。なんとかなるでしょ?」ということでは誰も振り向いてくれません。
僕はいつも何十ページに渡る企画書を必ず作成しています。ただ声をかけて「一緒にやりましょうよ」という話ではなく、そこには自分のエモーショナルな想いから、ロジカルな説得材料までを言葉にした分厚い企画書があります。そういう企画書があれば武器を持っているような感覚で、相手により強い意志をもって話すことができるし、相手もその企画書を見れば伝わり方が変わってくる。
企画書の良い点は、その場にいた人が持ち帰って社内で回したり、他の人に見せたりできるところです。伝言になるとうまく伝わらないこともありますが、これがあれば自分の想いが曲がって伝わるようなことはない。
*
〝生き方〟は全てのものへと繋がる
勝手なイメージで決められているけれど、それで良いのだろうか?
嶋津
この記事を読んだ方からの質問です。「女の子の人生を応援する」というテーマはウンナナクールを通して千原さんご自身のものになっていったとのことですが、そこに至るまでどういった過程があったのでしょうか?
千原
れもんらいふのスタッフもほとんどが女性です。女性が多い社会で生活していると、世の中の仕組みってほぼ男性中心にできているなぁと思うんです。
作家の川上未映子さんとの出会いも大きいですね。彼女との会話の節々に気付かされることがたくさんあって。一緒に電車に乗っていて、「痴漢注意」という看板を見て「これ千原くん差別だと思う?」と聞かれました。「ちょっとわからない」と答えると、「痴漢をする側に〝痴漢はダメだ〟って書かないんだよ。女性に注意しろと言っている時点で男社会なんだよね」って。そういう〝気付き〟をくれるんですね。
嶋津
表面的な部分ではなく、もっと深い部分を考えさせられる問題提起ですね。
千原
多くの場合、「社会に女性が入って来て、平等にやりましょう」と言いながらも、根本的なところでは変わっていないんですよ。戦後、東京では新橋という街が仕事の中心地になっていて。男性が働いて、女性が家庭を守るという時代でした。それはパワハラでもなんでもなくね。
今でもあの周辺には風俗があったり、その周りにはキャバクラがたくさんあります。女性が社会に入っているけど、街自体が男性中心の地理になっている。「その場所に女性が入り込んでくる」ということではなく、男性と女性が普通に生活ができる地理に変えていかなくちゃいけない。そういうことを一つひとつ考えていくと、「今」というのは男性社会に女性が入っただけなんですよね。これは平等になったということでも何でもないんです。
嶋津
上辺だけで根本的な解決に至っていない。今のお話で納得したのですが、千原さんのお仕事ではアーティストさんや女優さんを「性別で見せる」というよりも、フラットに「その人の魅力を引き出している」という印象を受けます。「男性だから、あるいは女性だから」という見方がないから、そのように自然と引き出せるのかもしれない。
千原
広告の中では普通に代理店と「男性に向けて、女性に向けて」という話になると思うんです。そこは俯瞰して見なきゃいけないんですよね。「男性向けにはこのアイドルを起用しましょう」とか「女性向け位にはイケメンを起用しましょう」とか、そういうことではなく、その商品の魅力を引き出す上で性別関係なく、どういう人物像がベストかを考えていく。
嶋津
数々のお仕事だけでなく、プライベートも、映画も、根本は人生における哲学───千原さんの〝生き方〟が全てのものへと繋がっているのですね。
千原
『最終日』では安達祐実さん扮する女性を「何もない女」というとても失礼な表現をしています。世の中の女性には「結婚することが幸せという戦い方の人」と「結婚はしていないけれど仕事がすごく楽しいよという戦い方の人」がいる。「じゃあ、そのどっちにも当てはまらなかったらどうすればいいの?」という女性の幸せの先ってあると思うんですよ。それを安達祐実さんをベースに描いていくことができたら。「別に何もなくても、生きる道があるよね」と。
ウンナナクールで「女の子の人生を応援する」という定義をいただいて、今僕がつくっている広告や映画全てに紐づいています。「ミッションとしてやらなきゃ」というよりも、自然な形として。

*
おわりに
千原さんのバースデーパーティーを取材したことがある。そこには千原さんと所縁のある人たちがボーダーレスに集まっていた。〝千原徹也〟がプラットフォームになっていて、それこそ「競合なのでは?」というような人もお互いに同じ空間にいて、真ん中に千原さんがいる。それはまさしく、〝千原徹也〟だからこそ成立すること。
千原
僕はどこの業界にも所属していない感覚でいるんですよ。デザイン業界といえばデザイン業界なのですが、ラフォーレの件などで業界の批判を書いたりもする。デザイン業界の人にいっぱい呼び出されたりもしたのですが、それも良いきっかけにもなったし、結果的に良かった。ファッションの仕事も多かったり、映画を撮ろうとしていたり。意外とそれぞれの業界は分断しているんですよね。僕はそこを渡り歩いて、こっちの人とあっちの人を繋いだり、これからもしていきます。
千原さんのこの言葉を思い出す。境界線を自由に飛び越えて、あらゆるものを繋ぎ合わせ、物語へと仕立てていく。それは映画として、そして「人生」という一大プロジェクトとして。
今後の千原徹也の動向に目が離せない。
***
公開インタビュー参加者による感想レポート
「ダイアログジャーニー」と題して、全国を巡り、さまざまなクリエイターをインタビューしています。その活動費に使用させていただきます。対話の魅力を発信するコンテンツとして還元いたします。ご支援、ありがとうございます。
