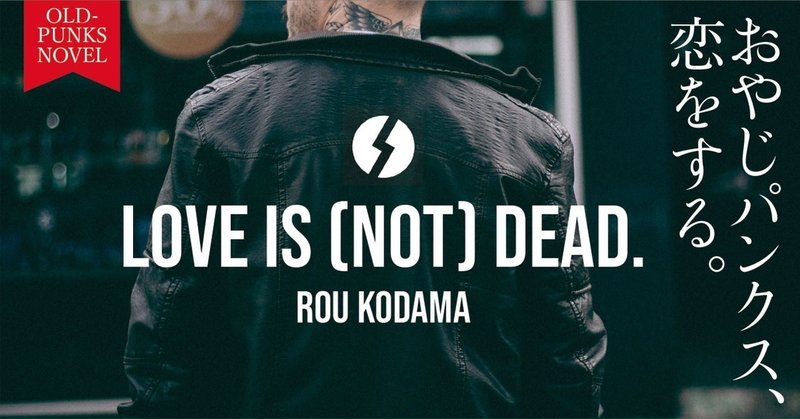
おやじパンクス、恋をする。#142
次の日、梶さんを見舞ってから会いに来るという彼女を待って、俺は馴染みの店でリッチなハンバーガーを遅い朝飯として食い、コンビニでコロナの六本入りを買って、中央公園のベンチに陣取った。
いつもの公園。見慣れた風景。でも、たった一日で世界が様変わりすることもある。
二本目のコロナを飲み終える頃、彼女から電話がかかってきた。昨晩の、色っぽく湿った声とは随分違う、さっぱりした口調(つまり、いつもの彼女の口調ってことなんだが)で、どこにいるのかと聞く。
中央公園でコロナ飲んでると言うと、オッケー、すぐ行くと言って電話は切れた。
本当に数分で現れた彼女は、秋の午前、キラキラした太陽を背負って輝いて見えた。
公園つうのは、何もねえ。
申し訳程度にベンチやトイレや遊具なんかが置いてあるが、基本的には何もねえ空間だ。
遮るものがないから、俺は遠くに豆粒くらいの大きさの彼女を発見してからずっと、少しずつ近づいてくる彼女を見つめてた。俺がじっと見てんのに彼女も気付いたんだろう、苦笑いを浮かべて、近づいてくる。
「見過ぎだよ」
彼女は俺の前に立ちはだかって言うと、一本ちょうだい、とコロナを抜き取った。
そして、コロナの箱を挟んで、俺の隣に座った。
うまく言えねえけど、彼女のこういう謙虚さというか、気遣いできるところが俺は好きだ。
反対側、つまり間に何も挟まねえ俺の隣に、何の躊躇もなく座ってきたとしたら、それもピッタリくっつくみたいに座ってきたとしたら、俺は少し驚いて、少しだけ寂しくなるような気がする。
随分勝手な理屈だとはわかってるんだが、男っつうのは、そういうもんさ。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
