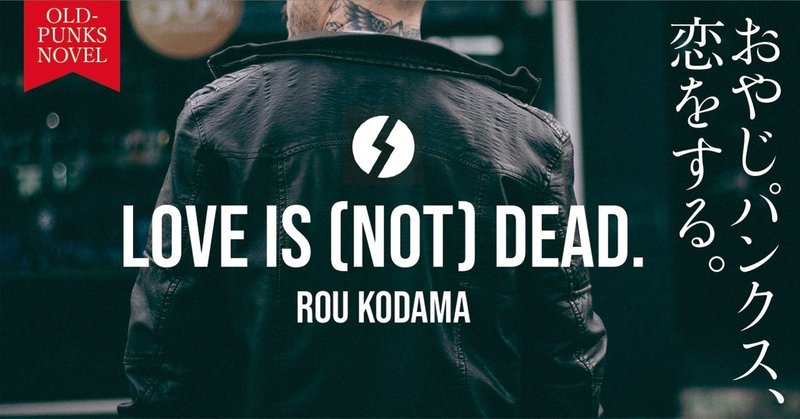
おやじパンクス、恋をする。#120
しつこく鳴る携帯の音に目が覚めた。
画面を見れば、なんてことはねえ、タカからだった。
「おお、どうしたよ」寝起きの掠れ声で言い、レースカーテン越しに外を見れば、オレンジ色の夕日。おいおい、もうこんな時間かよ。
「いや、生きてるかなと思ってよ」
「なんだそれ。勝手に殺すな」言いながら身体を起こして、壁にもたれて座った。
「どっかで飯食わねえ? おごるぜ」
タカと飯を食うこと自体は全然珍しくなかったが、それはライブとかの流れでそのままっつうか、涼介やボンとかもだいたい一緒だったし、こんな風にわざわざ電話で誘われたことは今まであんまりなかった。
それだけになんか俺、嬉しくなって、「ああ、いいよ」って了解したんだ。
パパっとシャワー浴びて、洗濯機を回して、その間に散らかっていた部屋もざっと片付けた。ちょうど明日の朝がゴミ出しだったんで、ちょっと早いが、出させてもらった。
待ち合わせの駅前までぶらぶら歩きながら、俺はなんだか気分が良かった。
タカと飯を食うことが楽しみだとかそういう気持ちの悪い意味じゃなくて、なんとなくここ数日間、俺は寂しかったんだなってのがよく分かったっていうかさ。
ほら、ほとんど隙間なく建っているビルとかあるだろ。壁と壁が五十センチくらいしか離れてないようなやつだよ。その隙間には道なんてねえから誰も通らねえしそもそも意識を向けたりしない。綺麗な花が咲いていたってそれに誰も気付かない。
そういう寂しい場所に自分の生活が落ち込んでいくような感じ、わかるだろ?
俺は毎日大勢の客に囲まれながら、何時間も鳴りやまない笑い声の中にありながら、一人で酒作ったりジョッキ洗ったりしてるばっかで、寂しかったんだ。
プライベートで、つまり損得なく誰かに誘われるってのは、悪い気分じゃねえ。
金髪リーゼントに革ジャンに革パン、サングラスって出で立ちでベンチに座っていたタカは、俺を見つけるとガキみてえに手を振り上げて「おーい、おーい」と俺を呼んだ。
まったく、見た目とのギャップがありすぎるぜ。
俺達は馴染みのハンバーガー屋に行って、コロナとバーガーセットを頼み、しばらくは無言でがっついた。店内に客はまばらで、ギター一本の気怠いカントリーが流れている。
「それで、なんか話でもあったのか?」俺は聞いた。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
