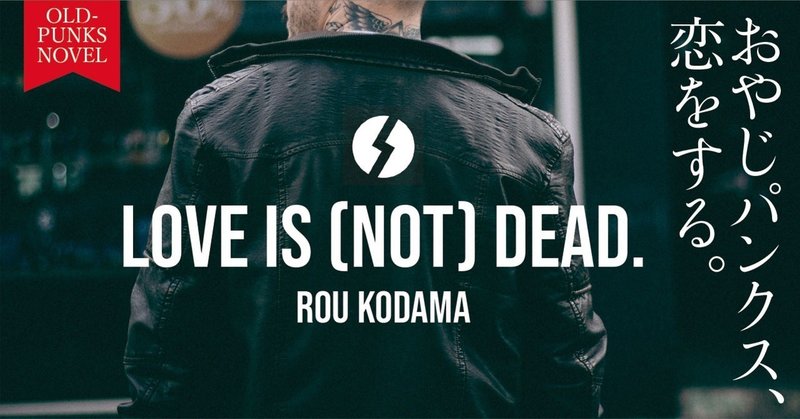
おやじパンクス、恋をする。#154
自分で言っといて照れる俺。けど、彼女は笑わなかった。俺を見定めるみたいに真顔になって、やがてゆっくり頷いて、「うん、そっか」と言った。
俺は笑った。
いや、なんでって、安心したんだ。つうか、逆に言えばこの瞬間までどこか緊張してたとも言える。
――うん、そっか、か。
俺はその言葉を、そしてそれが発せられたこの状況を、この先ずっと忘れないだろうと思った。これは、俺の告白に対する返事、彼女が俺の気持ちを受け入れてくれた瞬間なんだから。
心配症で疑り深い俺は、彼女の雰囲気からこれで俺が振られるわけもねえと必死で言い聞かせながらも、どこかで、彼女が「俺の彼女」になってくれるその確信が持てないまま、悶々としていたわけで。
まあ、その悶々がさっきの俺の、ガッついた童貞中学生のごとき行動に、つながってないとは言わねえよ。
けど、安心した。これで、安心したよ。それにしても、「うん、そっか」か。まるで他人事に納得するみたいじゃねえか。
けど、うん、彼女らしいや。彼女らしくて、逆に安心だよ。
俺はもう、ウキウキしちまって、ああやっぱ性欲つうのは良くも悪くも汚えなあ、こういう、すっきりと相手を愛おしく思える感覚のほうがずっと前向きだ。
「どっちにする?」彼女が聞いて、俺は「あ?」じゃなくて「ん?」と言う。
言って、すぐ恥ずかしくなる。
「どっちにするって、何だよ」
「だから、明日か明後日か」
「いや、だからそれが何だよ」
「祝勝会」
「はあ?」
「ミッションが完了したから、皆でお祝いしようって、涼介がさ」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
