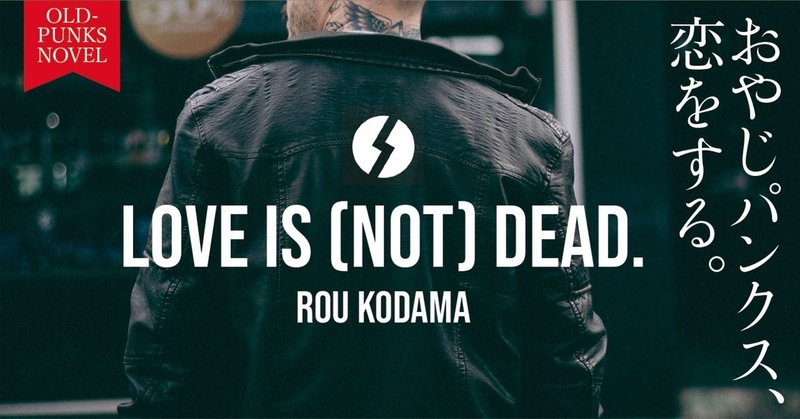
おやじパンクス、恋をする。#056
そんな風に思えば思うほど、俺のイメージの中の彼女は余計にセクシーに、艶かしく笑い、それだけに留まらずそのタイダイ染めのTシャツのシャツの裾を捲り上げ、でっかいでっかいオッパイをモミモミしながら俺を誘ってくる。おいおい、勘弁してくれ。ババアのくせに。
でも俺のアソコは情けなくも硬くなってきてしまう。クソ、なんてこった。まるで童貞のガキじゃねえか。ああ、この風呂に溜まってんのが透明の湯じゃなくてよかったぜ。
そして俺はそんな自分を戒めるために、閻魔の吐いたゲロみてえな黒々した湯にズブズブと潜っていった。
うわあ、臭い。それに妙な圧迫感がある。毛穴全部からその滋養成分が染み入ってくるような感じ。だけど我慢だ。四十三歳にしてそんなリビドーに満ちた妄想をしてしまう自分を罰するのだ。
それも対象は年上のオバハン、胸も尻もダルダル垂れているに違いねえオバハン、いや、そこいらのオバハンに比べれば二回り半くれえは綺麗だし、多分胸もピンと張っていて背が高くて尻も尖っていてスタイルもいいけど、長い髪の毛はオイルを塗ったみてえにしっとりとしていて肌は白くてサラッとしていてソバカスが魅力的で、ガハハと豪快に笑うし酒も強いし肝が据わってて格好がいいし、それでいて気配りもできるっていうか、掃除洗濯料理もソツなくこなしそうだし、とにかくどこにでもいるオバハンとは一線を画すっていうか、たぶん三線くらいは画しているわけだけど、でも、でも、オバハンに変わりはねえ。
そんなオバハンを想いながらチンポ硬くしている俺はもうそれだけで犯罪者だ。反社会的な存在だ。熟女趣味の変態だ。店に来て好き好き言ってくるガキンチョとヤッてる方がずっと健全だぜ。
まあ、そんなこんなで悶々としながら薬湯に浸かって、その後もああでもねえこうでもねえと考えながら炭酸風呂とか寝湯とかに入って、調子に乗ってなんか怖え電気風呂ってやつにも挑戦したら色んな所がビリビリピクピク動いて、つうかすげえ痛くてああもうクソ、水に電気なんか流すんじゃねえよ感電するだろとか文句言いながら水風呂に移動して、上がった。
わざわざ来ておいて全然リラックスできねえでやんの。はは、笑える。笑えねえけど。
まあとにかくそうやってひとっ風呂浴びた俺は、レンタルの浴衣を身につけ、酒臭えTシャツとブラックジーンズを丸めてビニール袋に突っ込んで、食堂街に戻った。
ジェルが落ちてしんなりとなったオレンジ色の頭に、店のロゴ入りの白い浴衣。手には真っ赤なクリームソーダのビニール袋、いやクリームソーダって飲みもんじゃねえぞ、イカしたガイコツマークのファションブランドさ。
とりあえずビール、じゃなくて、百円玉ひとつで買える濃ゆい黒酢ドリンクを買って、それを一気して、でっかいゲップをした。で、さあ飯でも食おうと食券マシンの前でメニューを考えているところに、ちょうど勤務を終えたカズが革ジャン着て登場した。おいおい、銭湯に革ジャンはねえだろう、若旦那。
「よお、相変わらず浴衣似合わねえな」
カズはポケットから数枚のコインを取り出して、ガシャンガシャンと食券マシンに入れた。るせえバカ、てめえだけには言われたくねえよ。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
