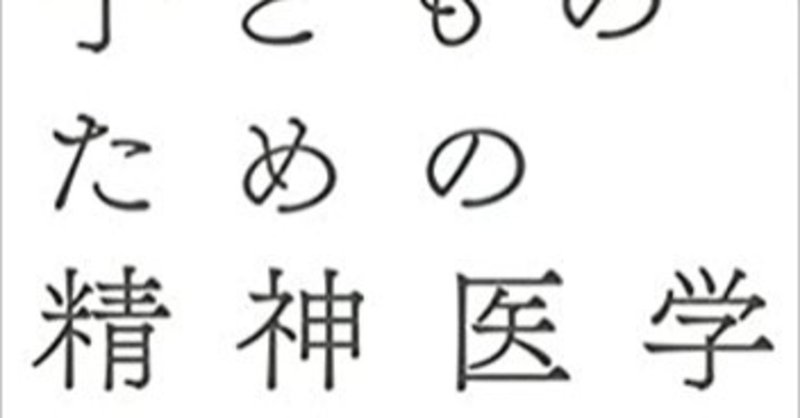
市民文庫書評『子どものための精神医学』滝川一廣著
〇「ボランティア情報」2018年8月15日号発売(とちぎボランティアネットワーク編)
「市民文庫」
『子どものための精神医学』滝川一廣著 医学書院 定価2500円+税
評者 白崎一裕 那須里山舎
文句なく名著!
その理由をまとめると以下のようになる。①、「精神医学」と書名にあるが、狭い意味での医学を超えて、哲学、心理学、社会学、教育学などの人間諸学を横断する知見に満ちている。②、①の諸学の知見は断片的で難解な学術用語ではなく、著者の文学的素養を背景にした世界観で総合化されている ③、あらゆる心の問題に悩む子ども達への支援の「方法論」が明確に提示されている。④、したがって浅薄なマニュアルではない支援者の実践的思想を育む手掛かりを得られる。⑤、すべての子ども達への温かいまなざしに満ちている。以上である。
具体的に説明しよう。本書では、ピアジェとフロイトという人間の心の発達を問い続けた巨人思想家の考えをベースに、子どもたちの心の問題を考える座標軸を明確に設定している。ピアジェは、人間の「認識の発達」について考えてきた。これに対してフロイトは人間の「関係の発達」について考えた。著者は、人間の精神発達は、この二つの軸で考えると明確になるという。この二つの軸が本書の大きな方法論の柱である。また、「認識発達」(理解のあゆみ)と「関係発達」(社会性のあゆみ)はお互いに独立したものではなく、互いに支えあい、からみあい、相互に促しあいながらすすんでいくという。知的障害や自閉症スペクトラムなどの子ども達が、いま、どこにいて、どのよう状態にあるのかを、上記の方法論(二つの軸)で考えるとスッキリ明確になる。たとえば、言語の習得についてであるが、言語には対象を指し示す機能(指示性)=「認識」と自己の認識・情動を表現する機能(表出性)=「関係」がある。たとえば、子どもが「赤い夕焼けだね」と発語するとき、それを母親が「そうだね、赤い夕焼けだね」と応答するとしよう。子どもは、「赤い夕焼け」という認識をその見た時の感情を含めて母親に伝える。このとき、母親が応答することで、子どもの認識は、言葉として「共同化」され、同時にその感情も「共同化」される。子どもの認識と情動は母親との「関係」によって定着・強化されるわけだ。このプロセスは「定型発達」の子どもの場合だが、知的障害や自閉症の子どもたちの場合、上記のプロセスが一方の軸に偏ったまま発達の困難性を抱えることになる。そして、こうした方法論から多様で具体的な支援の方法のアドバイスが語られている。
また、本書は、子どもの大人になる過程の困難さ=子どもの社会化の困難さにも目をむけ、「虐待」「不登校」「いじめ」「ひきこもり」「うつ」などの諸問題の解決にもむかっている。基本的認識は、戦後社会が高度成長から消費社会に向かうなかで、過去の共同体意識が崩壊して、豊かな社会への適応問題が前面にでてきているということである。一例として、増加しているとされる子どもの「うつ」の場合、高度成長期以前は、社会的役割の押し付けが心の「負荷」となる「うつ」となった(主に大人)が、高度成長期以降は、個人の私性が重んじられ、それを守るための一種の人間関係疲れのような「負荷」がかかり「うつ」となるという変化があるという(これが子どもにも波及)。加えて、また、「いじめ」問題については、統計上、「いじめ」と闘った子どもたちの割合が一定数存在するのに、その社会的報道的評価が低く、子どもたちの社会的経験の芽をつんでいるのではないか?と注意を促している。ここでも、子どもたちの社会化の困難さを自覚しながらその社会的成長を促すアドバイスがなされている。
最後に、著者の温かいまなざしに関わる点について。本書の333ページに『「虐待」という言葉』というコラム的文章がある。著者は「虐待」という言葉は、一方の「加害・権利侵害」の側面からの言葉で当事者への支援への共感のまなざしがないという。非道な虐待者(親など)が存在することは認めた上で、それでも虐待をうけてきた子どもたちを「被虐待児」としてレッテルを貼ることが、子どもたちの自尊感情を護るだろうか?と疑問をなげかけている。このように支援する側が陥りやすい盲点についても明確に指摘している。安易な専門家主義を戒めているともいえよう。
評者は、初期の著作である『家庭のなかの子ども学校のなかの子ども』(岩波書店、1994年)から著者を注目していた。なんといっても、児童文学批評を用いて子どもたちの心の困難さを乗り越えようとする精神医学者らしからぬ逸脱感に敬意をもっていたからだ。本書は、著者の現段階での到達点として、多くの人々に読んでもらいたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
