
【小説】『日の名残り』考察ーー描かれることのなかった「母」と「歴史」の存在について(全文無料公開)
はじめに
『日の名残り』は、戦後のイギリスを舞台にしたカズオイシグロの小説で、著者の出世作であると共に、この日系ノーベル賞作家の最も愛された作品と言って良いだろう。
この小説の楽しみは幾つもあるが、中でもストーリーの主軸となるものは二つある。
その一つがスティーブンスとかつて彼の下で働いていた女中頭のミス(ミセス)ケントンが互いに好意を持ちながらすれ違いを続けるラブストーリーで、それをもう一つの主軸である、スティーブンスが主人であるダーリントン卿に仕える中で垣間見た、第一次世界大戦以降の歴史物語が支えている。
今回はこのエッセイで、上記の二本の主軸の中に提示された「描かれることのなかった二つのモノ」について書きたい。
描かれなかったモノとはすなわち、タイトルに示した通り「母」と「歴史」である。
その二点について説明する前に、まずは簡単にストーリーをおさらいしよう。
Story
主人公である執事のスティーブンスは、ダーリントンホールの新しい所有者で雇い主でもあるアメリカ人のファラディ卿から長期休暇を貰う。その休暇を利用してイギリスの美しい自然を見て周ることにするが、最大の目的は、旅の最後にかつて自分の下で女中頭として働いたミス(ミセス)ケントンを訪ねることだ。
道中で様々な人々と交流すしながら、スティーブンスはかつての主人ダーリントン卿との、そして亡き父との、さらにはいつもそこにいたケントンとの数々のやり取りを思い出す。
さて、本論の説明に移ろう。
まずここで使う「描かれることのなかった」という言葉の意味は「母」と「歴史」、それぞれで全く異なる。
「母」については(これはスティーブンスの母であるが)、この母については文字通り、作品中一切登場しない。その面影も、存在を感じさせるものさえ一切えがかれていない。
むしろこれは、描かないことによってその存在の影響を描こうとしたのではないかと思わせるものがある。
もう一つの「歴史」についてであるが、歴史そのものについては作中でスティーブンスの口を借りて大いに語られており、字義通り「描かれることのなかった」などとはとても言えない。
とはいえ、スティーブンスによって語られている「歴史」とは通り一般のよく見聞きする歴史物語ではない。
スティーブンスが語るのは、世界史で我々が習うメインストリームの歴史ではなく、恐らくイギリス人が自国の歴史を学習する際にまず教えられるものでもないだろう。
この作品でスティーブンスによって語られる「歴史」とは、第一次世界大戦が終わり、その後イギリスがナチスドイツの空爆などにより大きな被害を受けて衰退する原因となった第二次世界大戦が始まる前の、第一次大戦直後からのイギリス国内での政治闘争の歴史であり、スティーブンスによって語られるのはそこで敗者となった者(=ダーリントン卿)の言い分である。
つまり、ここでの「描かれることのなかった」とは、勝者の物語でありメインストリームの歴史とは異なる、通常描かれることのない「敗者の言い分」を表現した、という意味だ。
この「敗者の言い分」こそが、歴史(政治の)の面白さ、難しさをストーリー上に見事に顕わしたものと言えよう。
またそこにある悲劇はスティーブンスの人生と重なるものでもあるのと同時に、著者の後の作品『忘れられた巨人』につながるものでもある。
この作品が主人公で語り手であるスティーブンスの一人称で書かれていることはこの作品にとって非常に重要だ。「信用できない語り手」としてのスティーブンスの心情は二本の主軸の背後に透けてみえてくるように作られている。
前書きが長くなった。
本論に移りたい。
まず第一章で、スティーブンスとケントンとの関係、そして父との関係からみえる、描かれる事のなかった「母」の存在について、つまり「母の不在」について論じることにしよう。
1、描かれることのなかった「母」の存在
−1スティーブンスとケントンの関係
作中で、ダーリントンホールに勤めていた当時のケントンのスティーブンスに対する態度は、以下に示すように、単なる仕事仲間への態度とはとても思えない。
ケントンのスティーブンスに対する特別な態度について幾つか挙げたい。
1、ケントンのスティーブンスの父親への態度について
スティーブンスの父親も執事であり、しかも高名な執事であったらしい。
スティーブンスは、かつての主人も亡くなり勤め先の無くなった経験豊富な父親を、ダーリントンホールの新しい召使として招く。
当初スティーブンスから見ると、ケントンはあまりにも父親を軽視するような態度をとっているように感じたが、後に父親が職務中に階段を踏み外して派手に転倒したところをみると、父親の衰えをいち早く察知していたのはケントンだったと言える。
これは職業人としてのスティーブンスに対するケントンの尊敬の裏返しとして顕れた態度なのだろう。いつも完璧な仕事をするスティーブンスが父親を前にすると目が曇る、ということに耐えられなかったのかも知れない。
2、ユダヤ人女中二人をクビにするという取り決めについて
このユダヤ人女中に対するダーリントン卿の取り決めに驚き、心苦しく思いながらも職務として受け入れたスティーブンスと比べると、ケントンのスティーブンスに対する「信じられない」「間違っている」「そんなお屋敷では私は働けない」という反応はあまりに苛烈だ。
これは次の「3」に続くものだが、職業上の繋がりで怒りを覚えた、という範疇を超えているように見える。
3、ケントンは誰に怒ったか?
「2」の出来事から時間が経ち、ダーリントン卿がユダヤ人女中二人を辞めさせたことについて過ちを認め、二人に償いがしたいと話したことをケントンに告げると、ケントンはスティーブンスが当時の彼自身の気持ち(スティーブンスもケントンと同様に気が進まなかった)を自分に伝えてくれなかったことに酷く憤り、どんなに失望し、どれ程までにダーリントンホールを去ろと思ったかを訴える。
ここで明らかになるのは、ケントンが怒りを覚えたのはダーリントン卿ではなかったということ、そしてケントンがスティーブンスに持っている感情は、単なる職業上のものだけではないということだろう。
ケントンは最初「そんなお屋敷では働けない!」と怒ったが、この怒りはダーリントン卿に対するものではなく、どうやらそれに何の抵抗もなく(とケントンには見えた)従ったスティーブンスに対してのものだったのだ。
これについても、「1」と同様にスティーブンスへの失望に違いないが、職業上の問題としてではなく、この時はスティーブンスの人間性に対して失望を抱いている。
このような態度は、スティーブンスという人を単なる上役、職業人として見ていたのではないということなのではないだろうか。
他にもまだある。
ケントンは、若い女中を雇うことになった時に彼女自身がしっかりと監督すると言ってスティーブンスに雇う気にさせた癖に、その後スティーブンスが若い女中の目覚ましい成長ぶりを褒めると、ケントンは見た目が可愛いからに違いないとヤキモチを焼くし、スティーブンスが図書室で恋愛小説を読んでいるのをからかったりもする。
このように並べるとケントンの気持ちは明らかであるが、対する「信頼できない語り手」であるスティーブンス自身の口から語られる彼の気持ちは殆ど語られておらず、何とも素っ気ないものだ。
しかし、ケントンが度々ダーリントンホールを空ける許可を貰い外に出るようになり、さらに信頼する執事仲間にケントンの結婚願望について諭されると途端に不安を感じるようになったようだ。
それまで特に聞かなかったにも関わらずケントンに次の休みにも出かけるのか、と尋ねたのだ。
その時ケントンは、待ち兼ねたように、時折屋敷を空けるのは、かつて務めたお屋敷で執事を務め今は別の仕事に就いている人と旧交を温めているかだとその理由を話す。
ケントンはそのままの流れで、そのかつての仕事仲間が執事をやっていた当時彼は大きな夢を持っていたが、スティーブンスの仕事ぶりと比べるととても及ばないと褒めると、スティーブンスは良い気になって「誰にでも向く仕事ではありません」と自慢する。
ここでスティーブンスはあまりにも不適切な態度を取る。
この時、ケントンが人生の目的を尋ねると、スティーブンスはダーリントン卿と一心同体であるかのように答え、ダーリントン卿が全ての仕事を成し遂げ完全に満足しきった時にこそ、「自分を満足しきった人間と認める認めることが出来るでしょう」と答えたのだ。
ケントンはこの時絶望的な気持ちになったに違いないが、スティーブンスはそれに気づかなかった。
それから間もなく、スティーブンスは後々まで後悔するある決断をする。
それは、毎晩就寝前のケントンとの「ココア会議」と呼んだ打ち合わせを取り止めたことだ。
ケントンはココア会議最後となった晩に、疲れているらしく集中出来ていなかった。
スティーブンスはそれを咎め、ケントンが必死に宥め、謝っているにも関わらず聞き入れる事はなかった。
スティーブンスはその事を思い出し、さらにココア会議を再開しようというケントンのほのめかしにも応じなかった過去の自分の対応を反省し「もしかしたら二人の関係は変わっていたかも知れない」という明らかな後悔の思いがあることを告白している。
ここではじめて、スティーブンスは「信頼できない語り手」から脱して本心を吐露したのだ。
このように、ケントンの思いは明らかであるが、スティーブンスの態度は煮え切らない。
その理由はなぜか。
その点については、まずスティーブンスが執事の仕事に生涯を掛けた仕事人間であるということがありそうだ。そしてそれと共に、スティーブンスの父親との関係にヒントがあるのではないか。
ちなみに、この父親も執事である。
この父親との関係をみていると、登場しないスティーブンスの母の存在(=母の不在)がみえてくる。
ー2、父との関係にみる母の不在
スティーブンスの母親が登場しないことの不自然さに気付かされるのは、スティーブンスと、やはり執事でもあった父親との別れのシーンだろう。
スティーブンスは偉大な執事に必要な品格というものについて、この父親の「主人の重要な客と言えど媚び諂うことはしない」という執事としての態度を例に出している。
また、年老いた父親をダーリントンハウスに招いて重要な役割を任せ、さらに衰えの見える父親に気を遣い、優しく諭している。これは同じく執事を生業とするこの親子の関係の一面を表していると言えるだろう。
スティーブンスが父を執事として尊敬していることは間違いない。
であるにも関わらず、スティーブンスは転倒事件以来みるみる身体を弱らせ死の床にいる父親の「私は良い父親だっただろうか」という問いかけに答えられない。それが死にゆく父親の最後の頼みであり、そのことを理解していたにもかかわらず答えられない。
父親自身も、スティーブンスは自分を執事として尊敬してくれていることは気付いていたのだろう。
だからこその質問だった。
ここで一旦立ち止まって考えてみるとおかしなことに気付く。
この父親については多くが語られているが、それはあくまで執事としての父親の姿であって、家庭人としての父親の姿は一切描かれておらず、さらに、母親についてはその存在自体が一切語られていないのだ。
これは小説として普通余りにも不自然だろう。
しかし父親は、だからこそ「父親としての自分」に限定して尋ねたのだ。
この質問と、それに答えられないスティーブンスの関係こそが、二人の関係について、また「母親の不在」について何よりも雄弁に語っていると考えて良いだろう。
なぜスティーブンスは母親のことを語らないのか?
可能性としては幾つか考えられる。
生まれてすぐ、または生まれると同時に亡くなる、あるいは何かの理由で離れ離れになってしまうなどして記憶に残っていないからなのか、或いは父母の関係に語ることの憚られるようなものがあったからなのか、スティーブンス本人にとって思い出したくもないような酷い母親だったからなのか。
何にしろこれは想像するしかないが、「母親について語られない理由」についてもまた、「私は良い父親だっただろうか」という問いに答えられないというところに見出すべきだろう。やはり「母親の不在」の責任は恐らく父親にあり、この点はスティーブンスの中にある結婚観の希薄さや、継続的な男女の関係に自信が持てない理由となっているのではないか。
スティーブンスとケントンとの奇妙なすれ違いは、著者が敬愛するチェーホフの戯曲『桜の園』のロパーヒンとワーリャのそれを思わせる。
この作品でもロパーヒンとワーリャの関係性を解く鍵は乏しいが、ロパーヒンが農奴の家系にあること、そしてワーリャが、かつての女主人の養女であるということが問題だったようにも思える。
とはいえ、『桜の園』の二人のようなものはこの『日の名残り』には見えないから、やはりこの父と母との関係にこそその理由を見出すべきなのだろう。
スティーブンスとケントンとのラブストーリーと共に、この小説を支えるもう一本の柱が(次に論じる)スティーブンスが心底敬愛して仕えたかつての主人ダーリントン卿の名誉回復語りだ。
ダーリントン卿は、ドイツへの宥和政策を支持したことによってまるでナチスの協力者であったかのような見られ方をした。
この点について、スティーブンスは自分の執事としての存在意義とダーリントン卿の名誉回復が同義であるかのような熱烈な弁護を見せる。
スティーブンスによって語られるダーリントン卿の逸話は、歴史の裏側を考える上でとても面白いものだ。
次章で、そして歴史をみる上で重要な媒体と視点について、そして歴史の見えざる裏側について解説したい。
2、描かれることのなかった「歴史」の存在
この章における「描かれることのなかった歴史」とは、メインストリームの歴史とは異なる、一般にはあまり知られていない「裏の歴史」とでも呼ぶべきもののことだ。
また、この章では、スティーブンスがその時代に対峙した「政治」の話と、それを我々が後の世からみる「歴史」の話をわけていない。
後の世の我々から見ると、スティーブンスによるダーリントン卿の話は歴史の裏話でしかない。
しかし、ダーリントン卿と、卿を敬愛し、卿が生きた時代と空間を共にし、現在的な時間との連続の中でその当時を捉えていたであろうスティーブンスからすると、卿の名誉回復は自分の使命であると同時に、世論への抵抗であったに違いない。
以下に、まず「歴史」というものを体感する上で重要だと思われる、「媒体」と「視点」の問題について考えたい。
「歴史」において「媒体」は歴史の質と量に、「視点」は内容そのものに直接的に関わり、そしてそれらによって歴史認識や世論が形成される。
ここではまず、歴史というものを見る上で重要な媒体と視点というものについて考え、そして次にダーリントン卿とスティーブンスが置かれた立場と彼らの視点について考えたい。
−1、歴史にみる「媒体」と「視点」
学問的な意味における「歴史」とは、時間の経過の中で起こった様々な出来事を記録するための記述されたモノを意味する。
既述されてきた媒体の主なものは「紙」だろう。
話が飛ぶが、この「歴史」を綴る「媒体」について考えさせられたある経験について書いておきたい。
丁度一年前、18年ぶりに思い出の地であるカンボジアのシェムリアップを訪れた時のことだ。
改めて見るクメール遺跡の数々に新たな感動を覚えたが、また同時に、ある疑問を抱いた。
それは「なぜこれ程の巨大文明なのに残された歴史は乏しいのか」というものだ。
※クメール帝国は、最盛時は現在のカンボジアだけではなく、タイ、ラオス、ベトナムに跨る大帝国だったが、クメール帝国における「歴史」は、神殿(遺跡)の石に彫り込まれた少量の文字でしかなく、それは戦争や王朝の変遷についてのごく簡単なものでしかない。
その疑問は遺跡を見れば分かることと思う。繊細で美麗な彫刻、大きな石を積みた建てた宮殿は目を見張るばかりだ。これらを作るには測量等の技術が必要と思われる技巧が施されている。
これが記述されずに達成出来るものなのか?記述する手段があったのなら、それはなぜ残されていないのか?

それは事前にカンボジアの歴史書(通史)を読んで旅をしたからこそ生まれた疑問だったが、その疑問は帰国後に周達観『真臘風土記』(13世紀に当時のクメール帝国を訪れた中国人による記録)を読んで納得した。
この頃のクメール帝国で使用された媒体は、紙ではなく(確か鹿か何かの)獣皮紙だったらしい。そして、周達観はこれを「書いてすぐ消せる優れモノ」というふうに評価をしている。
しかし、すぐに消せるとは、すぐに消えるということだろう。
これは書いて消してを繰り返すメモ帳代りとしては便利だが、書いたものを後世に残していくという意味では酷く不便に違いない。
我々現代の日本人からすると「後世に残すこと」は、歴史というものの目的であり役割であることは自明だ
しかしカンボジアのように、歴史を残す媒体に恵まれなかった地域における歴史は、多くの空白を残したまの穴空きの歴史になる。
勿論、イギリスのような国の歴史は古いし、近代から現代にかけて書かれた史料の類など数えきれない程に多く残されているに違いない。
ここで「視点」の問題に移ろう。
古代ギリシャから生まれた現代の学問の多くは、たった一つのまごうことなき真理(真実)に近付いていく作業ということが言えるかも知れない。しかし、こと歴史においてはそれは異なるように思う。
「歴史」とは、様々な視点が同時並行して成立する学問であり、それぞれにそれぞれの正しさ、(真実ではなく)諸事実が併存して形成される学問と思う(勿論これは政治も同様)。
よく「歴史は勝者によって書かれる」と言われる。
極端な例で言えば、戦争に勝利した一方が他方を根絶やしにするようなことがあれば、普通に考えれば残されるのは勝者の言い分ばかりになる筈だ。
これは「勝者の視点」に他ならない。
「勝者の歴史」であり「勝者の視点」であるというのは、勿論日本史もそうだ。
「日本史」というが、我々が通常学習する古代の日本史などは殆ど近畿地方の歴史に過ぎず、これは日本史的な勝者の拠点でしかない。古代にあった筈の別の勢力、小文明などは一般においては敵役として登場するか、ほぼ無視されていると言って良いだろう。
同様の例で言えば、タイの学校で教えられる「タイの歴史」は現在のタイの国土の歴史であって、タイ族の歴史だけではなく、現在のタイ国土を支配した近隣の別の文明の歴史が含まれているそうだ。
カンボジアの歴史について言えば、それは媒体の問題もあり酷く簡素なものでしかない。とはいえその簡略化された歴史でさえ、為政者の視点による偏ったものである可能性を考えるべきだろう。
こういった「視点」は一般的な世論の形成に影響する。
小学生の頃に読んだ「マンガ日本の歴史」では、ヤマトタケルが征伐したクマソなどは、酷く野暮ったい、未開人を思わせる見てくれで描かれていたと記憶しているが、(大和朝廷の人々と比較して)本当にそうだったのだろうか?
前書きにも書いたように、スティーブンスが語る歴史は「敗者の言い分」としての歴史であり、メインストリームの歴史ではなく、多くの媒体で扱われ教科書に載るようなものでもなく、通常はあまり語られることのない、一般においては恐らく、見たことも聞いたこともない類のものではないだろうか。
そのような歴史を知らない人にとっては、「そのような歴史はなかった」ことに他ならず、世論を形成することはない。
次に、具体的にスティーブンスが語る歴史(敗者の言い分)とはどのようなもので、どのような意味があるのか考えてみたい。
−2、ダーリントン卿の側から見た歴史
スティーブンスが生きたのは如何なる時代で、何を目的にダーリントン卿の立場を代弁したかったのか。
つまりスティーブンスが語るダーリントン卿の視点について考えたい。
この小説に書かれているような歴史の裏側を僕は不勉強で知らなかった。とはいえ、書かれていること自体は誰でも理解出来るし、中学や高校程度の世界史的な知識だけでも十分に歴史的視点を持つことも出来るようになっている。
ダーリントン卿は、第一次大戦で敵国のドイツ人でありながら尊敬し合える友人となったブレマン卿が、戦後ドイツに課せられた過大な賠償金から困窮して自殺したことを切欠にドイツへの宥和政策を推し進める。
しかしその結果としてナチスの台頭を許してしまい、政治的な敗者と記憶されている。
憎むべき対象が明確にドイツであった時代を通過したばかりの世論にあって、ダーリントン卿は政治的敗者であることには間違いない。しかし、スティーブンスは敬愛するダーリントン卿の言い分を残し、単なる敗者として記憶させておくことにはさせたくないという気持ちがあったのだろう。
スティーブンスによるダーリントン卿の名誉回復語りは、丁度ジョーライト監督の映画「ウィンストンチャーチル」と対を成している。
この映画では、変人扱いされながらも早くからナチスの狂気の正体を見抜いていたチャーチルを英雄として描き、チャーチルと対立していたドイツへの宥和政策の支持者がその敵役となっている(この敵役にダーリント卿のモデルがいたのだろう)。
これはチャーチルであり、ドイツとの戦争に勝利したイギリス国民という一方からみれば当然と言える。
しかし、歴史ともう少し距離をとって俯瞰してみると、そこに第一次世界大戦の過大な賠償金からくるドイツの貧窮があり、そこから新たなる敵ナチスドイツが立ち上がってきたことがわかる筈だ(祥伝社新書『ヒトラーの経済政策ーー世界恐慌からの奇跡的復興』[武田知弘]を読むと当時のドイツ国民がナチスを支持した理由が分かる)。
また、一般的には、第二次大戦終結後に日本とドイツに過大な賠償金を課さなかったのはこの第一次大戦終結の際の失敗を反省してのことだとされている。
これを踏まえると、やはりナチスドイツの勃興の要因の一つは、賠償金を設定した連合国側にもあると言うべきだろう。
ダーリントン卿は間違っていた。
しかしその全てを否定することは出来ない。
「敗者の言い分」にしろ、ダーリントン卿の意見もその動機は正しい、或いは結果的にはナチスの台頭を招いてしまったが、これ自体は第一次大戦後の過大な賠償金がまず最大の問題なのであってそのことへの反省からドイツの貧窮に過剰な責任感を抱いてナチスの正体を見誤ったことには同情の余地がある、くらいには言っても良いのではないだろうか。
そういった視点、そういった正しさもある。
このスティーブンスによるダーリントン卿の名誉回復を図るエピソードも、歴史解釈というものの難しさに面白さついて考えさせられる興味深い設定と言えるだろう。
まとめ
まず第一章は「描かれることのなかった『母』の存在」と題し、スティーブンスとケントンのすれ違いの理由について考察した。
ケントンとの関係で適切な対応を取れないスティーブンスについて、彼の母親との関係に問題があるのではないかとの課題を立て「母の不在」が問題なのではないかと論じた。
スティーンブンスの態度はこの作品におけるミステリーではあるが、実際にスティーブンス自身が、理想の男女の関係というものを両親の関係から経験出来ておらず、ケントンに対してどのような態度を取って良いのか分からない、というところがあったのではないか。
ちなみに、執事仲間にケントンの結婚願望について諭された際にスティーブンスは「ミスケントンは正真正銘、本物の女中頭ですよ。今更家族を持ちたいなんて、そんなふうに考えるわけがありません」と答えている。
これはスティーブンスの結婚そのものに対する意識の希薄さも表すものだろう。
続いて、第二章の「描かれることのなかった『歴史』の存在」では、スティーブンスによって語られるかつての主人ダーリントン卿の「敗者の言い分」について、まず「媒体」と「視点」という観点から論じ、その言い分を残し、記憶することの意味について論じた。
敗者の言い分という視点が残される媒体の量は多くなく、そういった視点は一般の目に触れられる機会は自ずと少なくなるだろう(歴史の最前線である現在的な時間の中ならばなおのことだ)。
勿論、そのような「敗者の歴史」は学問レベルでは研究対象とされているものも多く、研究者レベルでは当たり前に知られていることかも知れない。
しかし一般ではそうではない。
多く残され、語られるのはやはり「勝者の歴史」だ。
「歴史にifはない」と言われる。
とはいえ、歴史をつぶさに観察して「if」を見出さないことには歴史の未来への貢献はないだろう。
『日の名残り』を読む多くの人の頭に、いつかみた世界史のテキストに掲載されていた、リヤカーで札束を運ぶ第一次大戦後のドイツ人の挿絵が浮かんだことだろうと思う。
そして、その挿絵の向こうに、スティーブンスを介して、実際にそこで暮らす人々を感じることが出来たのではないだろうか。
スティーブンスのダーリントン卿擁護論にも、やはり価値はある。
これは、歴史の裏側、歴史というものの多面性を理解出来る非常に優れた題材と言えるのではないだろうか。
また、この作品の二つの主軸であるスティーブンスとケントンのラブストーリー、そしてダーリントン卿の名誉回復は、スティーブンスからみると共に失敗していると言える。
しかし、かつてスティーブンスがケントンに語ったように、ダーリントン卿がその目標の全てを成し遂げることこそ自分の人生の目的だったのだから、むしろその執事としての目的を失ってしまったからこそケントンとの選ぶことのなかったもう一つの人生が浮かび上がってきたということなのだろう。
これはケントンの側から見ると、かつて自分を散々失望させた男が自分を求めて会いに来たわけで、現在の幸せを見せ付けるのは、ささやかな自己陶酔と共に、小さな怒りや失望やその他の記憶がないまぜになってどうしようもなく芽生える復讐心を満足させた面もあるのではないか。
とは言え、お互いを思い合う二人の別れはとても美しいものだ。
最後になるが、この作品と著者の『忘れられた巨人』の関連について書いておきたい。
著者は『日の名残り』で、戦争の熱狂の中で捨て置かれ忘れ去られる「敗者の言い分」を扱い、やはり同じテーマのもとに『忘れられた巨人』を書いたように思うが、この作品は前者よりももっと広い視野をもって「歴史」そのものに挑んでいるように思える。
「歴史」とは、何者かによって書かれ、喧伝され、忘れ去られ、思い起こされ、といった過程を経験し、世論を形成し、争いや平和を作り出す。
『忘れられた巨人』はファンタジーの様相を呈しているが、高度に寓話的でもある。
(あとがき的なもの)
さて、これでやっと終わりです。
正直に言って、書きたいことを頭から取り出してきちんと説明するには、大学で史学の基礎を学んだだけで、肝心の歴史そのものについては一般レベルの僕が参考文献も使わずに書くには少々難しかったです。何度も読み直し、書き直しをしたせいもあり、とっ散らかって分かり難いところは多かっただろうし、恐らく間違いもあるだろうと思います(間違いがあれば指摘であれば有難いです)が、でもまあ書きたいことは書けたかな、と思います。
最後まで読んでくれた方には感謝します😊
※ちなみにトップの写真はラオス🇱🇦のシーパンドン地区のデット島の夕陽で、中程の遺跡の写真は、左のバイヨンと呼ばれる女性の顔のレリーフが週達観も訪れたカンボジア🇰🇭のシェムリアップにあるアンコールトムというクメール遺跡にあるもので、右の二つ、上の牛に乗る人が中心になったものとアプサラという踊る女性のレリーフはラオス🇱🇦のプラサートワットプーというクメール遺跡で撮影したものです。
そして下の写真は地元のイオンモール内のタリーズです☕️
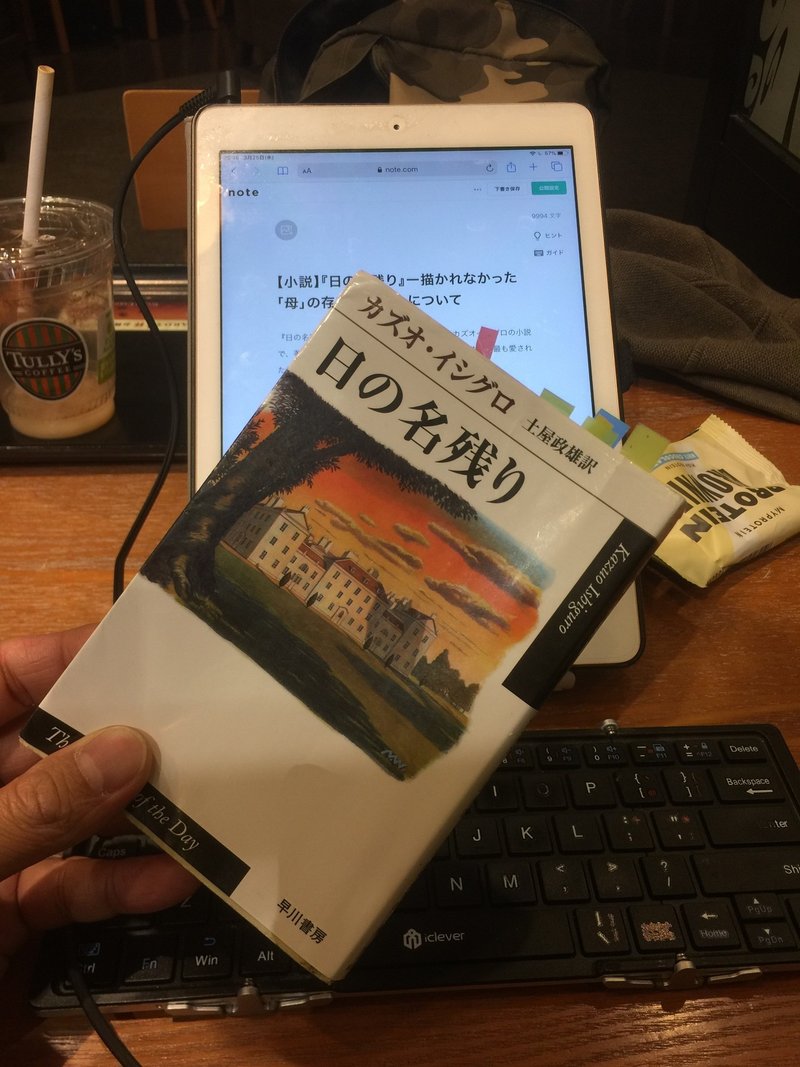
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
