
『はちどり』(韓国/キム・ボラ監督作品)ー14歳、少女を取り巻く「暴力」と、その世界に。気付きながら、もがきながらー確かに歩き出すためにー
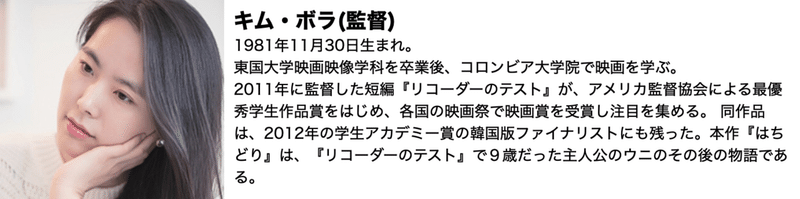
わたしは、父に殴られた記憶はないーいや一度だけある。何がどうしてだかは忘れたが、小学生の低学年だったと思う。何かしらしつこく逆らったかして、蹴られたことがあった。後にも先にもそれっきり。
親からの暴力の記憶といえば、母である。幼児期に、叩かれた記憶はない。小学校の3年くらいだったか、子どもからすれば、母は「突如として暴力的」になった。家の向い側にある郵便局で記念切手の発売日。当時、小学生の間で切手の収集が流行っており、わたしも便乗して、使用済み切手を集めたりしていた。記憶は曖昧だけれど記念切手を買いたくて、母に一緒に行ってくれと頼んだと思う。
引っ込み事案で、一人では買い物やお使いには、まだ行けない子どもだった。確かに小3にしては、おっとりしてただろうし、いつまでも幼く依頼心の強い娘について、何か周囲に言われていたのかもしれない。
母は、一人で買いに行きなさいと命令した。一人では不安だと訴えると、欲しいなら自分で買いに行けとさらに命令する。嫌だ嫌だと抵抗すると母は、わたしを叩いた。子どもは叩けば泣く。泣いたらさらに怒りが増殖したのか、どんどん叩いて、果ては玄関の三和土に蹴り出され。頭を殴られ。「何でもいいから自分で買いに行け!」とお金を持たされ、号泣するまま家を追い出された。
泣きながらとぼとぼと歩いて郵便局に並ぶ人たちの後ろに並び、生まれて初めて郵便局で一人で切手を買った。嬉しくもなんともなかった。ただわたしは、それ以来、母についてきてくれとは、言わなくなった。母の「スパルタ教育」が、子どもを自立へ促したことになるのだろうか。
わたしは、全くそうは思わない。その「暴力」を分岐点にして、母と娘は、断絶していくー本当の気持ちを隠すー素直に感情的な交流ができなくなった。互いの気持ちはこじれ、思春期の始まりから、母の暴力は、さらにエスカレートし、中学生になると止まった。おそらくは、その娘は、母にとっては、ほとんど理解のおよばない行動や態度を示すようになったから。
母が娘に歩み寄り「理解しなければならない」と悟ったときには、もう遅かった。少女のわたしは、母を信頼できなかったし、「暴力」によって断絶させられ、身に染み込まされた態度は「人に頼ってはいけない」「自分でできることは自分でする」ことで。何かしら物事を人に頼んだり、協力することは、過剰に苦手になり、逆に協調性を失い、集団の中で孤立するようになってしまう。
そして人生において最大のマイナスになったのは、「暴力」によって屈服させられた結果ー「卑屈」な精神が、わたしの根底に宿ってしまったことだ。無意識に自分より強そうな人に媚びてしまう。本心を言えない。高い自尊心と卑屈な精神が、自分の中に鬩ぎ合って、いつも苦しかった。いや今も同じかもしれないー年齢を重ねて鈍感になっただけで…。
長々と自分の話になってしまったけれどー「暴力」によって人を支配するとは、こんなに小さな個人のことでも、大きな社会の問題でも、実は同じなのではないか。
「暴力」に晒された人間は、屈服させられることで自尊心を傷つけられ、卑屈になり、自己を表現できなくなる。屈辱的な立場に自ら止まってしまうー被支配者のままになる。逆も同じ。「暴力」によって屈服させた側の人間は、支配者のままでい続ける。「暴力」が、間に立ち塞がる限り。互いの関係を変えることはできない。
韓国で異例の大ヒットと話題になった映画『はちどり』は、14歳少女ウニの思春期物語であると同時に、ウニを通して描かれる韓国社会が抱える「暴力」ー支配と被支配についての映画でもある。
韓国社会の問題、背景については、リンクした映画批評に詳しいので、是非、こちらを読んでみてください。
1994年のソウル。一見して可憐な少女ウニ。母と父は、商店街で餅屋を経営している。兄と姉、五人で集合住宅に住んでいるのだが、その風景も家の中も、まるで日本の団地と変わりない。ウニの通う中学校も同様で、男女に分けられているようだったが、校舎の作り、教室の中、教師の態度、何の違和感もない。
韓国語とハングル文字がなかったら、日本映画と言われたってわからないかもしれないくらい。映画の中の韓国と日本は相似している。しかし、映画が進むにつれ、そこにはだんだんと相違が浮き出されていく。
ウニの家では、父親が大きな声を出して子どもを叱り付ける。妻を怒鳴りつける。子どもたちは、父に対して敬語を使い。母には、そうでもない。(日本語字幕は、言葉使いについて、非常に繊細に表現していた)
目上の人には等しく敬語で、教室でも教師は威嚇的で、一方的に授業を進め、命令する。(わたしの中学時代は、1970年代だが、そっくりだなと思った。教師はまだ暴力を振るっても全然許されてたし、どんなに理不尽な校則でも黙って従うしかなかった)
礼儀に厳しくー礼儀とはルールでもあり、守れば良い子で、守らない子は不良ーとされる。上からの暴力は黙認し肯定され、下からの反抗は、完全に否定される。
14歳のウニには、何の権利もなく。自由な発言もできない。兄の命令に逆らい「バカみたい」と呟けば、兄は、ウニの部屋に侵入し暴力を振るう。漢文教室の友達も兄に殴られて顔に青痣を作っている。
少女たちは、抵抗できないまま、心に憤りと悲しみと諦め、を抱えている。
「わたしが自殺したら、あの人たちは悲しみ、謝ってくれるだろうか」
映画館のシートの上で、わたしは、拳を握り締めた。怒りが、怒りが、腹の底から湧いてきて。たまらなかった。なんでだ。なんで女の子だからって、こんな目に合わされ続けなければならないのかー
そうして、わたしの暗黒、少女時代に戻ればーそこには「マンガ」があった。
ウニの「好きなもの」も、マンガだ。ウニは、何かにつけマンガを描いている。最初に描いていたのは、日本の『ベルサイユのばら』にそっくりな絵だった。少女マンガ風の絵は、日本の女の子が描くものとなんら変わりがない。
現実の生活の中で、無力な立場に置かれたものは、空想の世界で自由を得るー『赤毛のアン』の昔から、変わらない。「少女」でしかいられない誰かを助けるものー
ウニの描くイラストマンガの世界には、「暴力」の陰りは見えない。明るくふわふわしていて、優しく、可愛いものでいっぱいだ。
そういう世界が、欲しいーどこにもない。だから空想するー
この痛みを
この悲しみを
わかる人にしかわからない。世間知らずの女の子。ただの少女趣味だと、あなたは鼻で笑う。
しかし、でも、その空想の力こそが、彼女を助ける根源となるー
「生きてみたい」と願う世界が、存在することーそれだけが、少女をこの世に生かす縁なのだからー
ウニの身体の中には、力が、宿っている。
生きてみようとする力ー握り締めた拳を広げ、指先を見つめるー
掌は、指先は、動かせるー自分の力でー
「もう殴られないで」「抵抗するの」
ウニを助けた女教師言葉が、胸に響くー
映画館が明るくなるときーわたしも、握り締めた拳を開いた。
「暴力」に争うために必要なのは、拳=暴力ではないはずだ。あの頃、母が「暴力」に頼ったのは、なぜなのか。わたしは、すでに知っている。母の上には、父がいた。非暴力的で教養があり、民主的で優しい父ー母にとっては夫ー男ーが。
学童保育の指導員、新婦人の会で書記局員もしていた母は、忙しかった。小学校の頃から中学にかけて、家に母がいた記憶があんまりない。高学年からは家事もわたしがやっていた。公務員の父はマイペースで自分の趣味や好きなことを自由にしていた。父は父で「君は君の自由にすればいいよ」スタイルだったのだろうけれども。子どもの学校や近所の人間関係のことなど、父が介入していた記憶もこれまたない。
おそらく、母は子どもや地域での出来事をほとんどを丸抱えして、疲れていたんだと思う。曖昧で優柔不断な父に対して不満があったはずだが、口に出せないプライドや事情があったんだろう。そこで思う通りに「良い子」に育っていかない子どもに鬱憤が、出る。子どもは母親にとって支配しやすい対象だから。でも、彼女が本当に殴りたかったのは、父だったのではないのか…。叩かれる時は、かならず母と二人きりの時だけだった。母自身が、自分の心を表現できない人になっていた。
40年前、男女平等をうたう夫婦でいながら、実態は歴然と違う社会で、母はきっと必死で生きようとしていた。子どもの人権運動に熱心で教育者でありながら、子どもを殴ってしまった自分に打ちひしがれていたかもしれない。年老いた母は「わたしは子どもを叩いたことなんか一度もない」と言い張っているように。
「子どもを叩いたことはない」人生。それは彼女にとって「生きてみたい」世界なのだと。58歳になった娘は、想像できる力を持った。(だからといって叩かれた子どもの感情が消えるわけでもないけれど)
家の中のー男ーが、必ずしも「暴力」を振るわないからといって、社会的な支配と被支配の関係が変わるわけではない。抑圧は、様々な形で現れ、結局は、最も弱い立場へと向かっていくーたった今も。
そこへの想像力を、決して失わないことー
『はちどり』というタイトルは、ごくごく小さな鳥の羽ばたきー小さく震えるような羽ばたきでもー生きて行こうするー力を表しているという。
2020年、ウニは、どんな大人に成長しているのだろうかー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
