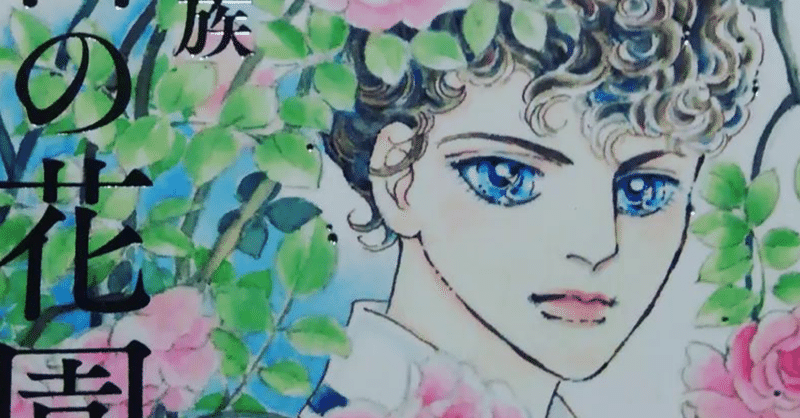
『秘密の花園』萩尾望都(小学館) エドガーは、眠りの中から飛び出す。目を見開くためにーその1
萩尾望都は、夢を見るー
1979年発刊『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』橋本治による萩尾望都論「眠りの中へ…」は、この一言から始まる。
1972年、わたしは10歳、小学4年生のとき『ポーの一族』とその主人公エドガー・ポーツネルに出会った。橋本治の言葉を借りれば、「世界は滅びてしまった」瞬間。萩尾望都が目を瞑るとき、世界は、金色に輝くーその時、子どもにとっての現実世界は滅び、萩尾マンガがつむぐー夢ーが「リアル」に転換される。ここでないどこか「もう一つの世界」が、自分(子ども)の生きるべき世界へと。
10歳から14歳になるまでの間、わたしは、本当に信じていた。外から見れば普通に日常生活を過ごし学校に通う、ただの子どもでありながら、でも固く心に抱いていた。
(エドガーは、必ずこの世界に生きている。必ず迎えに来てくれる)
1970年代「少女マンガ革命」と呼ばれるムーブメントがあった。少女マンガは、それまで世間一般低俗扱いのマンガ出版の中でもさらに最下層の、いわく「女子どもの少女趣味」取るに足らない存在とされていた。
そんな中で、一躍脚光を浴びたのが、『ポーの一族』萩尾望都、『ベルサイユのばら』池田理代子、『ジョカへ…』大島弓子、『風と木の詩』竹宮恵子、『アラベスク』山岸凉子…『ガラスの仮面』美内すずえ『はみだしっ子』三原順…書ききれない、あまたきらめく1970年前後から出現する新たな少女マンガ家たちだった。
わたしは1962年生まれで、ちょうどもの心がつく時期であり、もろにそれらのマンガ世界から影響を受けることになったし、さらに大人になって自らマンガ評論も書くようになっても、ずいぶん長いこと、その時代の少女マンガは、それこそ革命的に「世界を変える力」があると考えていた。
多くの名作が生まれ、マンガ文化全体への大きな転換期だったのも間違いない。しかし、21世紀を20年も過ぎた頃になって。もう一度70年代少女マンガを振り返るとき、果たしてそれは本当に「革命」だったのか?と疑念を抱くようになった。
きっかけは、昨年放送されたNHK「100分de萩尾望都」という番組だった。番組中で70年代まで少女マンガには画一的で幼稚な作品しかなく、萩尾らの登場によって高度な物語が描かれるようになったーかのような紹介がされていた。かつては、わたしも同様の認識だったが、80年代以降、多くの人々の努力により発展深化してきたマンガ研究によって、そのような評価は、すでに覆されているのに。
天下のNHKで、著名人の萩尾ファンの皆さんが語る中、70年代以前の少女マンガは滝の下に落とされてしまっている。どうしてそうなるのか、それこそがまた「萩尾望都が目を瞑る時」ーと同期するのだけれども。
真実に具体的に「少女マンガに革命が起きていた」のは、1960年代だ。戦前も含め50年代までは、内容に関わらずマンガの描き手は男性マンガ家が大半を占めていた。少女マンガも『リボンの騎士』手塚治虫を筆頭に、ちばてつや、赤塚不二夫、松本零士…。黎明期のわたなべまさこ、水野英子から女性マンガ家への転換は、60年代に本格化する。
西谷祥子、里中真智子、大島弓子も萩尾望都も60年代の後半にデビューするが、その頃少女マンガ誌では、ちまたにイメージされているような「でっかいキラキラ目玉に花を背負ってお涙頂戴している」マンガばかりが載っていたわけではない。この時代の最大の変革は「男女が対等な人間関係にある恋愛マンガ」の登場だったし、それに伴って性愛や妊娠に関するもの、社会問題を扱うもの、多様なマンガ作品が出現していた。
それはもちろんのこと現実の日本社会における60年安保、70年安保運動へと向かう、現実の社会ー世界を変えようとする「若者の時代」と折り重なっている。
橋本治の言う「世界が滅びる時」「子どもの時代の終わり」とは、70年安保の終わり、全学連の敗北、浅間山荘事件での終幕ーのことだと、わたしは考える。戦後社会に生まれ落ちた「子ども」たちが「若者」という「子どもの変形」として既存の大人社会と向き合い、戦って、敗れ去ったとき。
彼らは、子どもであることをやめるー長く伸ばされた髪を切って「大人になる」道を選ぶか、目を閉じて、子どもの時を止めようとしたのか。
「少女マンガ革命」という言葉が生まれる。その意味を、本物のただの子どもだった者には、わかるはずもなかった。革命に挫折した年上の若者や大人の男たちが「少女マンガ」を見つけるーそういう事情を。
60年代にあった少女の現実や社会的問題を描く試みー政治性ーは、少女マンガ誌から(もちろん少年マンガもだが事情は違う)忽然と消えていき、入れ替わりに高度に発達した物語性と表現力を持つ作品群が大量発生する。
取るに足りない少女マンガは、取るに足る「社会人=大人の男」も論じるに足る表現として格上げされる。とりわけ独自のコマ割り、心理描写への傾倒。それは社会全体が、大大衆消費社会へと向かっていく時と同じくするのだったが。
萩尾望都が目を瞑るとき、世界は、金色に輝く ー眠りの中へー
もう43年も前の橋本治の言葉は、あまりにも克明に時代と世界を捉えてしまっていて、わたしが今更付け加える必要もなんにもないのだけれど。
つまり、当時10歳のわたしは、そのすでに破滅されてしまった現実社会に置かれながら、萩尾マンガが描くー金色の世界ーに生きていたことになる。
1976年『エディス』で物語は止まった。アランは炎の中に消え、エドガーは行方知れずとなる。その時、永遠の14歳の彼らと、わたしは同い年だった。ちょっきり14歳だったんだよ…。
14歳。エドガーが時を止めた年に。わたしは、時を動かし始める。もう『ポーの一族』は描かれない。だってアランがいないのだから。エドガーにとってアランのいない世界は、誰もいない破滅された世界。
エドガーは、目を瞑る。眠りの中へ…。
わたしは、目覚める。現実の世界の中へ。14歳の向こうへ。辿々しく、生きてきた。なんとか生き延びてきた。マンガにしがみつきながら。延々と現実に目を瞑りながら、現実を生きる。その矛盾を矛盾とせず。結婚して子どもを産んで、大人になり中年になり、50を過ぎ、初老の女になるまで。
そんな頃になって、エドガーは、再び、目の前に現れた。
2017年。萩尾望都は、突如として『ポーの一族』を再開する。40年ぶりの新作。世の中は信じられないように騒然とした。その昔はマニアックで教室の少数派であったはずの萩尾マンガは、いつの間にか「少女マンガの神様」へと祭り上げられていた。
果たして、今も萩尾望都が目を瞑る時 世界は金色に輝くーのか
再開された「ポーの一族』は、永遠の時を生きる少年、エドガーの心の旅(目を閉じた内面の)を描く物語ではすでになくなっている。
40年の時を経て、萩尾望都が自らノックした、眠る小部屋から呼び戻されたエドガーとアランの旅は、「破滅された世界」それ自体を描く試みへと転換する。かつては描かれることのなかったエドガーとは何者か。ポーの一族とはいかなる一族か。彼らが生きる世界とは、いかなるものか。
70歳を過ぎたマンガ家の視点は、遠い天から世界を俯瞰し、その片隅から時を刻み、歌を歌い、小さい網目から布を織り上げ、時間と空間をつなぐ。
全てを! 全てを! 全てを見よ。目を見開いて!
「紙の上のインクの滲み」
マンガとは、結局ただそれだけのものだと、マンガ批評の先輩、阿部幸弘さんが放った言葉は、わたしの頭に張り付いている。
そうマンガは、どこまでもどう思い込もうとも、ただの「紙の上のインクの滲み」に過ぎない。印刷物ー今なら電子物?
『ポーの一族」も同じくだ。40年前も今も紙の上にあるだけの。だからこそ、この奇跡の物語を奇跡というしかないように。
最新作『秘密の花園』は、1975年作『ランプトンは語る』に繋がるお話だが、『ランプトン〜』では、エドガー自身が、バンパネラを探す人間を燃やしてしまおうとするーマンガ世界の中でエドガーを求める人たちにとっても、読み手のわたしたちにとっても主役は、あくまでも「エドガー」であり、彼らの生きるー夢の世界ー眠りの国、それ自体だ。
しかし『秘密の花園』は違う。エドガーは、「破滅された世界」に同着する。主役は、顔に傷を負ったアーサー・クエントン卿であり、お金持ちと結婚して「夫の所有物」と言われるパトリシアであり、死んでしまった吃音のドミニクであり、「自己実現」を目指す看護師のセスであり、彼らの生きる<現実>だ。現実の中に、エルフ=幻想であるはずのエドガーは、実存として混在し、同等にあるいは対等に生きている。
彼はもうそこでー夢ーではない。「異質な何者か」ではあったとしても。眠りの中にはいない。目覚めたまま。そこに「在る」ことの意味とは。
そうして、実のところ、戦後社会に生まれたわたしたちは、2021年に至るまで、ずっと皆、全員、眠りの中にいたのではなかったか。誰も現実のことはよく知らない。というより現実に興味がない。70年代からずっとリアリティ(あるいは共感性)があるのは、テレビの世界、ラジオから聞こえる声、マンガ。21世紀からは、パソコン、インターネット。ツイッター。このnoteのように。
同時にまた、世界は、破滅したままそこにあり続け…現実に気候変動、地殻変動、戦争の前哨…破滅へ向かっている。
再び、橋本治が「眠りの中ヘ…」で述べたように。自身が「現実を心から信頼し家庭を信じていた」からこそ、萩尾望都は、目を瞑り、眠りの中へ、金色の夢を見続けることができた。
しかし、時を経た今、現実を信頼することは、難しい。たった今、マンガ家は、力の限り、目を見開いている。『秘密の花園』の必死のペンタッチよ!
『エディス』の最期。消し炭になってしまったアランを再生させる旅とは、つまり彼らが、再び目を瞑るー眠りの中へ、帰ることを意味する。
その時こそ、世界は、金色に輝く ために。
もう一度、鳥は歌うー。
その2に続く(文中敬称略)
『秘密の花園』萩尾望都 小学館 フラワーコミックススペシャル
参考文献 『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』前編 橋本治 河出文庫(1984刊)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
