
再生されゆく舞台 スペースノットブランク『フィジカル・カタルシス』評
形式面の諸特徴については、すでにイントロダクションで触れました。以下の評はそちらを前提に読まれることを推奨いたします。ここでは記録映像を参考に舞台上での展開を具体的にたどりながら、少々踏み込んだ解釈を展開したいと思います。
スペースノットブランクは同題の作品を形を変えながら幾度もクリエーションしていますが、ここで扱うのは2020年8月15~24日にこまばアゴラ劇場で行われた公演です(なお、同様の内容が8月7~9日にかけて京都のTHEATRE E9 KYOTOでも上演される予定でしたが、コロナ拡大のあおりを受けて中止となりました)。
出演は荒木知佳さん、古賀友樹さん、花井瑠奈さん、山口静さん。演出は小野彩加さん、中澤陽さんです。
なお、写真は公式サイトにアップロードされた月館森さん撮影のものを使用させていただきます。
PHASE 1: JUMP(前) パターンとズレが生むリズム
開場時間。舞台奥左側には小さなモニターが、右側には電子ドラムが簡素に置かれていて、黒で統一された無機質な劇場の殺風景さを強調しています。アゴラ劇場の舞台は上手側に突き出ていて、そのスペースはエレベーター乗り場として機能しているのですが、そこには机が置かれ、控えとして使用されていました。開演10分前になるとモニターの画面が切り替わり、そこではイントロダクションの原稿を握り締める東京はるかに主宰の植村の身体が舞台に合成されています。顔が見えないほどその姿は小さく、宙に浮いた感じがあり、また実際読まれるイントロダクションの音声と映像とは正確に同期していません。
イントロダクションが終わると、しばらくして、開演です。エレベーターが開き、縄跳びを身体に巻き付けた花井さんが入場、舞台中央でしばらく周囲をまなざします。視線に巻き込まれることで、観客は舞台と客席との場の同一性を強く喚起されます。服装は動きやすそうなオールブラックで、ダンスのための装いといった風情です。
モニターも花井さんの同じ動きを捉えますが、そこにはディレイがあります。以下、映像にはディレイが続きます。
花井さんはそのままこれといった動きを見せることなく控えに戻ります。その間に、白のスニーカーに黒いジーンズ、Tシャツというラフな格好をした古賀さんを乗せたエレベーターが到着していて、花井さんと入れ替わるように舞台に立ちます。しばらく観客を眺めていますが、右半身を軽く引いたのち、右腕を強く足元につきだし左手でそれを打ち鳴らして押さえ、姿勢を戻し去っていきます。
次に入れ替わるのはバスケのユニフォームに包まれた荒木さんで、まず観客から見て斜めに立ち、横に向き直って、息を吐き右手を突き出しつつ上半身を前方に倒し、すぐに右手を今度は高く上方に持ち上げながら大きく息を吸います。退場。
最後に山口さん。右ひじを上げ、下ろします。すぐ同じ動きを繰り返したかと思えば、そのまま右手を素早く接地させ、姿勢を戻す際には持ち上がる右腕を左手が打つように押さえます。同じ行為が再び繰り返され、そして再びさらなる展開を見せてゆきます。
いささか丁寧に記述しすぎてしまいましたが、ここで確認していただきたいのは、観客に向かい合い見回すという基本形をパターンとして反復しながら、徐々に大きくなる動きや衣装の相違がそこにリズムをもたらしていることです。エレベーターの振動音や開閉もこの構成に加わります。リズムは舞台上の身体と映像上の身体とのずれによってさらに補強されます。そうした律動の中では、呼吸や足音といった聴覚情報も同時に強く意識されます。動きがミニマルに抑制されている分、さまざまな差異が際立つのです。
花井さんが再び舞台へ進むと、彼女は身体にくくりつけられていた縄跳びをほどいて、緩やかなリズムで飛び始めます。ここで、これまでゆるやかに組み立てられていたグルーヴに明快な形が与えられます。花井さんの足踏みと床面にしたたかに打ち付けられる縄とが劇場に反響しますし、かつモニターからも音が遅れてやって来て、目の前の跳躍とうねるようなリズムで絡み合いますから、花井さんは縄跳びという楽器を用いて即興演奏を提示しているかのようです。こうして『フィジカル・カタルシス』では冒頭から聴覚情報に集中する知覚のモードが自然に促され、音をも身体表現の一つとして見る素地が用意されていました。身体表現からテクストの発話へと次第に重心を移してきたスペースノットブランクのこれまでの展開をも想起したいところです。ジョン・ケージは演奏時間中沈黙を保ち続ける『4分33秒』で知られますが、その間観客の意識は演奏者の姿へと注がれるわけで、これを音楽が聴覚から視覚へと移行した契機と見るならば、『フィジカル・カタルシス』の経験をその反転として考えることもできます。
やがて獣のように身をかがめた古賀さんが上手から現われ、ゆっくりと呼吸しながら花井さんめがけて歩いてきます。一度撤退しますが、同じ軌道で再び歩みを始めます。ここにも反復が、パターンがあり、リズムがあります。今度は古賀さんは花井さんのもとに到達し、と同時に花井さんは床へと倒れてしまいます。古賀さんは倒れた花井さんの頭とお腹に手を添えます。やがて手を持ち上げると、古賀さんの手から下りる見えない糸で操られるかのように花井さんの身体も起き上がり、二人はハケてゆきます。それは蘇生の儀式のように見えます。
演出の中澤さんが電子ドラム用のいす(ドラムスローン)に座り、足元にテープレコーダーを置き、ドラムをたたき続けるうちに舞台は暗転し、モニターの画面がいやにくっきりと闇のなかで浮かび上がります。
PHASE 1: JUMP(後) 「再生」される過去
モニター内での舞台はそのまま暗転することなく、人物が現れさえします。ここで、モニターは目の前の舞台を遅らせて映していたのではなく、事前に録画された映像を流していたのだということが(おそらく)初めて了解されます。おそらく、というのは、映像内にはモニターとドラムは置かれず、したがって勘のいい観客であればこの事実には最初から気づけただろうからです。
明転。荒木さんがバスケットボールを持って中央に立っています。中澤さんは依然ドラムの前にいて、荒木さんのことを見つめています。稽古場での「見る」身体を舞台上でも継続するとともに、そのような自身の姿を「見られる」身体として観客に供するのは、スペースノットブランクの作品にしばしばみられる姿勢です。『フィジカル・カタルシス』の場合、出演者も「見られる」身体でありながら、相互に「見る」ことで動きを作り出す主体であり、そうした能動性と受動性の交錯する場として舞台を位置付けることができます(詳しくは後述します)。
荒木さんはドリブルを始め、中澤さんもドラムをたたき、花井さんが舞台へきて、荒木さんと向かい合うようにしてまた縄跳びを飛び始めます。こうして三つの「打楽器」が演奏されますが、映像は素知らぬ風でまったく異なるゆったりとした動きを映します。
しかし、画面は小さく、誰がうつっているのかさえ判別できません。おそらく荒木さんと花井さんが映っているのでしょうけれども、そのことさえ確証はできません。ちなみに私が鑑賞したのは千秋楽下手側の最前列で、おそらくは最もモニターに近い座席でした。映像はこの場合、それ自体として見られるためのスペクタクルの機能をはたしてはいないのです。そこで展開される動きに注目しようにも、モニターは客席から遠くに置かれ、しかもサイズのゆえに見づらいですから、注視したところで美的な感動がただちに享受されることはありません。それはこの年の春に一般化した、小さなディスプレイで見つめる舞台との距離感を、強く連想させます。そしてその距離は、いつ撮られたのかもわからない風化した映像との時間的な距離とも相似です。
しかし、映像はただの到達不能な「距離」の表象として置かれているのではありません。いまや映像内には二人の人物がいて、踊るでも見つめ合うでもなく舞台を漂っているのですが、それが荒木さんと花井さんとの関係性にだぶることで、やはりここに共通のパターンとズレが生み出されています。場のグルーヴの生成に関わることで、映像には確かな役割と審美的価値が与えられるのです。これを裏返して言えば、空間全体が織りなすリズムの一パターンとして動性を付与されることで、不動の遠い過去が現在形の舞台から新たな「生」を授かっているのだとも考えられます。そしてその動きは、環境にダンサブルに充満する諸々のリズムを通じて観客たちにも感染してゆきます。
荒木さんと花井さんはボールのパスに移行し、中澤さんのドラムもパスに同期します。上手から現れた古賀さんがパス途中のボールを奪うと、荒木さんと花井さんは右手を斜め下に差し出して向かい合います。しばらくの沈黙ののち、中澤さんが足元のレコーダーを止めると、「キャリー・オン……ファイッ、オーファイッ、オーファイッ、オー……」と小声で荒木さんと花井さんが声の掛け合い(キャリー・オンとは「続行する」の意ですが、これは昔荒木さんが所属なさっていたバスケットボールチームの実際の掛け声です)。二人は「おねがいします」と口にしながら四方に頭を下げると、バスケの試合を思わせる動作から、数分間の「運動」に移行します。
その「運動」は通常ダンスと呼び表されるべきものですが、息を切らしながら争うようになされる一連の動きは、鑑賞者を意識した美的なものというよりはスポーツを思わせるものです。ジャンプを軸とした動作が続くので、身体への負担は実際大きいのです。汗をかき呼吸を乱すリアルな形而下的身体を舞台に載せる点で、ポストモダン・ダンスの伝統のうちにこれを位置付けることもできるでしょう。
二人は様々な振り付けを展開しますが、同じ振りを互いに向き合って行うために互いが互いの鏡像であるかのようで、それだけに一層身体差が強調されます。ここでもやはり、パターンとズレの論理が働いているのです。荒木さんの動きには力強く勢いがあり、メリハリが効いていて直線的なのに対して、花井さんはどこかゆったりとスムーズで曲線的です。映像中の二人の動きは緩慢なままで、舞台のスポーティーな激しさとは対照を描いていました。
暗転。
PHASE 2: REPLAY ヴァーチャルな二つの身体
舞台中央に荒木さん。ドラム前には依然中澤さんが控えています。荒木さんは、
①左手を起点に左半身を後方に捻る運動
②右手を右足に沿わせすっと引き上げる運動
③都度振り返りながら曲げた腕と足を左右交互に前に突き出す運動
をそれぞれ数十回反復します。すると中澤さんが、レコーダーを再生。PHASE 1終盤での三つの「打楽器」の演奏が蘇り(REPLAY)ます。山口さんも舞台にやって来て、荒木さんとモニターとの中間地点を定位置として動き始めます。二人の動きを追っているうちに、いくつもの動きが順序を変えて二人の間で反復されていることがわかります。ここでは、特定の動き――パターンが、タイミングを変えて別々の身体で繰り返される(REPLAY)ことで動的なズレを孕み、ミニマルなリズムを構成しています。以下、その動きを荒木さんが行った順に列挙します。
④三度に一度左足を曲げてケンパーパーのジャンプ
⑤右手を起点に大きく伸ばして上半身を前方に畳んでは起こす運動(冒頭と同じもの)
⑥都度振り返りながら曲げた肘を、胸の筋肉を伸ばすように大きく数回開く運動
⑦腰を大きく落としソーラン節の要領でものを引っ張るかのような運動
⑧肩を大きくいからせ腕を前後に振りながら小刻みに下方へ突き出す運動
⑨左足のみでたち、右足で前方後方へ軽く蹴り出す運動
⑩都度振り返りながら両手を前方に大きく伸ばし、なにか持ち上げるかのような運動
一方、山口さんの動きの展開は以下の通りです。
⑩→⑨→⑥→④→②→①→③→⑤→⑦→⑧→定位置を離れあちこちへ移動し様々に踊る
⑧は二人同時に行われます。そして、山口さんは同期の直後に持ち場を離れていくわけです。⑧は山口さんが現れた時から数えて荒木さんにとっては五個目、山口さんにとっては十個目の動きですが、山口さんの動きは俊敏で勝つそれぞれの動きの反復回数も少ないので、荒木さんの動きには追い付いているのです。山口さんがちょうど倍速で動いているのだとも言えます。
倍速。ここでの山口さんの身体は実際、映像的な非実体性を感じさせるものです。荒木さんは一貫して大きく呼吸し、その呼吸に合わせて動きに抑揚をつけていますが、山口さんのそれはメリハリを捨象したなめらかなものです。荒木さんはPHASE 1からそのまま舞台に立っているので、息は軽く切れていて汗もかなりかいています。こうして、重力を感じさせる現実的な肉体を曝け出す荒木さんと、無重力的な優雅さと素早さで淡々と動きをこなしていく山口さんとの対比が強調されます。山口さんの身体のヴァーチャルな両義性は、モニターと荒木さんの肉体とを結ぶ線の途上に置かれることでいっそう意識されます。
映像には二つの身体が並んでいて、どちらの動きも舞台上のそれとはやはり異なっていますが、それだけに両者の間の関係性を探ろうという姿勢が促されます。
レコーダーからは「打楽器」の演奏が複雑なリズムで鳴り続けていますが、聴覚を身体表現の一つとして感受する知覚に慣らされた私たちは、そこにPHASE 1での三つの身体の写像を感得することにもなります。映像、録音、山口さん、そうした様々のヴァーチャルな身体が相互に関係を結んで、荒木さんの肉体を鑑賞者の知覚の中で多重的に開いてゆくのです。こうした多重反復構造のうちでは鑑賞者の身体も動的に揺さぶられ、場に引き込まれていきます。
暗転。映像では一人の人物が残され、佇んでいます。
PHASE 3: FORM(前) 動きという形の思考
明転。古賀さんが紙を持って現われ、床においてなにか参照した素振りののち、急に後ろに引きさがってスライディング、ダンスへと移行します。次の動きを確認するかのように古賀さんが紙の方へ戻ると、シュタタと山口さんもかけてきてひとしく紙を見つめます。
ここで、紙が動きを指定するカンペのようなものだろうという察しが付くわけですが、しかし紙から離れて展開される二人の動きは全く異なるものです。けれども両者の動きを注意深く見つめていると、向かう方向や描く軌跡といった点で両者の身体が共振する瞬間があります。
二人は共通の抽象的な記号をもとにして別の振り付けを作り出しています。ここではその形が共通パターンとして共有され、形を「解釈」した身体へのあらわれがズレとしてもたらされています。ところで、ここで舞台に持ち込まれた形の描かれた紙は、舞台上で再現されるべく書かれたものであるという点で、演劇の戯曲を想起させます。『フィジカル・カタルシス』という言葉自体、古典悲劇を語る上で重要なタームを含んでいて、本作のジャンル区分を曖昧化しています(本作が演劇的な知覚のコードを要請することはイントロダクションで論じています)。しかし、ここではその「戯曲」の内容はそれ自体としてはっきり舞台に現れることはありません。内容は二人の身体の描く軌跡を綜合し、抽象することで断片的にもたらされるものです。
ジャドソン・ダンス・シアターを設立したトリシャ・ブラウンはしばしばドローイングに取り組みましたが、伊藤亜紗さんは「身体を運動させる空間――トリシャ・ブラウンのダンスとドローイング」でブラウンのドローイングと即興との関係を論じています。
ブラウンの方法論にしたがえば、ダンスの動きは動くことによってうまれるのではなく、先にも述べたように、ポイントからポイントへ移動するときに、その「あいだ」に残されていくものである。別の見方をすれば、生身の身体をそのまま見せるダンスにおいては、ドローイングにおける「ペン先を紙から離す」に相当する操作が不可能であるために、すべての運動が取捨選択なく見る者のまえにさらされる。「最初に左下の点、次に右上の点を示す」ことが、不可避的に「左下から右上に手をのばす」運動になり、「二つの点」が「二点間の軌跡」へと変換されてしまうのである。
この「点から軌跡へ(1D→2D)」という議論を、「軌跡から立体へ(2D→3D)」へと並行にスライドすれば、ただちに『フィジカル・カタルシス』論としても読める箇所でしょう。
ここでは描かれた形を再現し観客に届けることが問題になっているわけではありません。しかし、観客の方では、そこに秘めたる共通パターンとしての「テクスト」が潜んでいるという事実が姿勢を前のめりにします。そこにある形を「読む」ことへの希求が生じるのです。そうした抽象化に向かう知覚のモードの中で、二人の身体は統合的かつ破裂的なものとして現れてきます。具体的な身体の多様はそのような抽象に抵抗するからです。
ダンサーが踊りを通じてなんらかの役割や意味を帯びることはしばしばですが、そこでは俳優の身体は内容伝達のための透明な媒体と化してしまいます。このイリュージョンの問題はしかし、到達不可能な記号という形而上的地平が示されながらそれが物語やメタファーの形をとらず、あくまでダンサーたちはどんな言語的な意味をも再現しない自身の身体それ自体として舞い動く点で、『フィジカル・カタルシス』では回避されています。個別具体的な形而下の身体とそこから「読まれる」べき形而上の身体とが舞台上で明滅するのです。
マクシーン・シーツ=ジョンストン「動きという形の思考」(『芸術としての身体』所収、瀧一郎訳)は、身体と精神を二分する発想を否定した上で、「思考は動きという形で進む過程でありうる」ことを唱えることで、即興舞踏家の身体感覚に肉薄しています。そのような「思考」においては、「行動は、それ自身を超えた意味を指向したり指示したりしているのではなく、それ自体において自ずから知性的かつ可知的なもの」なのだといいます。
テクストの単なる再現を離れ純粋演劇を追求したアルトーが、バリ島の演劇の「言葉ではなく記号に基づく新たな身体言語」(「バリ島の演劇について」鈴木創士訳)を讃え、「身振りの形而上学」を唱えていることも注記しておきましょう。そこでは「俳優たちは命ある象形文字のように見え」るのです。
PHASE 3: FORM(中) いくつもの関係と対話
舞台に荒木さんと花井さんも加わり、四者が一斉に動き始めると、そこで示される彼らの間の関係性をあまねく把握することはほとんど不可能になります。わたしの場合、複数の俳優によって異なる動作が行われる場合、同時に確認できるのは経験から言って最大四名です。それも、特定の動作に目を奪われれば失敗に終わります。拾いきれない豊穣が舞台に展開するわけです。
この段に入ると、舞台上での出演者たちの身体に共通パターンとしての形を見出すことはできなくなります。しかし、特定の二人が対でデュエットをしているかのような動きのリンクが時折現れます。
この箇所は稽古場ではコンタクト・インプロヴィゼーションによって作り出されていました。これは身体間のふれあいの中で動きを作り出す即興形式のことで、超絶技巧を離れた平等主義・民主主義的な振り付けの潮流とも関係があります。このシーンではコンタクトと言っても物理的な接触はなく、二人並んで互いの動きを目で見て確認しながら、一つ一つ、古賀さんが動きを提案したら山口さんがそれに応じ、今度は古賀さんがそれに応じ、といった風に動きは生み出されていました。
しかし、四者の並ぶ空間の中で、デュエットのペアは自明ではなくなっています。稽古場ではもともと二人が隣り合って作られていた動きを、舞台ではバラバラの位置で一人一人で行っています。ですから、動きの対応するタイミングのズレもそこには孕まれています。こうして空間的・時間的にそれぞれのペアの間に「距離」を持ち込み、その繋がりを目に見えなくすることで、今度は共通パターンとしての「関係性」が観客の能動的かつ参加的な想像力によって幻視されることになります。動きを作った本人がその動きを行う必要はないので、作られた形は出演者間でシャッフル的に編集され、分け持たれていました。したがって、彼らの間に引かれる関係性も刻一刻と移り変わる流動的なものだったと言えます。
映像中で踊っているのは実は演出の小野さんで、彼女は昨年の12月に発表された別バージョンの『フィジカル・カタルシス』で、まさにこのFORMの制作論でのパフォーマンスを豊橋での滞在制作の成果として公開しています。モニターで披露されているのはまさにその際の振り付けです。ここでも映像と舞台との関係が問題になることはもはや言うまでもないでしょう。実際には、今回なぞられる形は山口さんが考案したもので、小野さんとは形が共有されてもいないのですが、舞台と映像との間になんらかの響き合いを求める思考が働くことの方が重要なのです。
読み取るのが形であれ関係性であれ、包括的に把握し得ない仕方でめくるめく展開される身体同士の「対話」を前に、観客は鑑賞体験の一回性のなかで独自のイマジネーションを築き上げることになる筈です。それはここまで論じたような形式レベルでの想像にとどまらず、時に人物間の物語の創造をも促すかもしれません。実際、男性一名女性三名という構成はさまざまな解釈を誘発するものですし、作品全体はタンツ・テアター的な物語の気配を感じさせもします(この点についてはPHASE 4以下で詳述します)。
コンタクト・インプロヴィゼーションの舞台上での再現として興味深いのは、出演者が時折動きをやめ、ただ周囲での動きを視線で追っていたことです。これは相手の動きを目で追い鑑賞するというこの箇所の制作契機をダイレクトに舞台に持ち込むことで、稽古場での身体を現在に蘇生させる企てであると同時に、それまで「見られる」ものでしかなかった身体が「見る」ものとして、観客たちの相似形として現れることで、観客の「見る」という動作をも作品世界を生成する「ダンス」として場に巻き込むものでした。出演者は客席に目を向けこそしないけれども、観客たちは創造的に「見られ」ている自分の身体を意識することになったのではないでしょうか。
ところで、この箇所をクリエーションした終盤の稽古には私は参加していないので、ここで指摘していない別の方法で作られた動きが混入している可能性もあります。実際PHASE 1,2での動きに対応する箇所もあり、全体で1時間の上演時間の中で15分ほども続いたこのシークエンスは、さまざまなメソッドを集約した過剰な絢爛さを示していたのです。
PHASE 3: FORM(後) 編み直される主体
ここで、演出の二人は指示のみを与え、具体的な振り付けは出演者の自発的な主体性に委ねていました。こうしたいわゆるタスクの手法は、完成された指示ではなく、したがって即興的な現在形の具体性を主体的に生成しうるところに特徴があります。しかし、形が与えられる場合にせよ、他者との関係性を意識して動く場合にせよ、なんらかの空間上の制約を受け取りながら身体が動いているのもまた確かです。これを「ルール」と見れば、『フィジカル・カタルシス』はスポーツにも接近するかもしれません。ここまでのPHASEや荒木さんの衣装などにも、作品をスポーツ的なものとして提示する意向は表れています。そこでは能動性と受動性との対立は止揚されています。
『フィジカル・カタルシス』での「即興」が特異であるのは、動きの生成に際してゆったりとした時間がとられ、したがって出演者は自ら考えながら主体的に振り付けに参加することができたところにあります。いくらか客観的に冷静に自分自身を見つめながら、選択的に振り付けを行うことができたのです。そこでは即興の偶然性と出演者の主体性とが手を取り合っています。
『フィジカル・カタルシス』の公演が行われた2020年8月はコロナの閉塞感が強い時期でした。メディアでは新自由主義的な自己責任のポリティクスが暗黙裡に喧伝され、しきりに対立の感情があおられ、ソーシャル・ディスタンスや自粛の風潮のなかで他者との関係性はつぎつぎに切断されていきました。あるのはディスプレイを介したヴァーチャルな関係ばかりです。全体から遊離して弱められた孤在がいくら主体性を叫ぼうとも、所詮はシステムの掌中から逃れることはできません。
『フィジカル・カタルシス』はこうした社会状況下においてさまざまに「距離」を編み直し、出演者や観客の主体をいくつもの制約や関係性のうちに置き入れることで、個と全体との健康な関係性を回復しようという試みだと解釈することもできると思います。
荒木さんは足まわりのトリッキーな自由さと体幹の安定性に支えられたメリハリのある動きに、古賀さんは男性的な直線性や力強さ、ダンスの訓練を受けていないが故の動きの独創性に、花井さんは四方に伸び縮みするかのような身のこなしのしなやかさ、自由さに、山口さんは安定した姿勢から繰り出される挙動の正確な印象やキレの良さに、それぞれ魅力を感じました。
ここで改めて『フィジカル・カタルシス』のステートメントに立ち返ると、それぞれの文章が多義的な含みを持って見えるはずです。出演者の方々のインタビューは、そうした含みを実感を伴った言葉を用いて展開しています。
それは多様な選択ができるものとする。
それは躰の内在と外在から構築される。
それは作家のためだけのものではない。
舞台から荒木さんと山口さんはハケて、古賀さんと花井さんが接触を伴う動作を行います。互いに寄りかかり合い続ける挙動はしかし素早く、なにかを争っているようにも見えます。その身体の寄せ合いには重力が感じられます。さまざまに編まれてきた関係性はここにおいて現実的かつ物理的なものへ結晶化したのです。やがて古賀さんの上半身は接地し、花井さんが彼の足を静かに床へ下ろして、暗転です。
PHASE 4: MUSIC(前) 展開説明
ドラムに照明が落ちます。椅子には花井さんがついていて、ドラムをたたき始めると、華やかな電子音が鳴り響きます。数分の演奏の後、しばらく間をおいて、通常のドラムセットのような素朴で乾いた音にシフトします。映像からは気が付けば小野さんは立ち去っていて、空間だけが取り残されています。中央の闇には依然として古賀さんが横たわっています。
ドラムはきまったビートを刻み、そのリズムに呼び寄せられるかのようにして、荒木さんがゆっくり歩いてきます。下手側にはいつしか黄色い照明が落とされていて、荒木さんはその光の中へ入ってゆくと、古賀さんを見下ろすようにして立ち止まります。光は絞られてゆき、代わりに白い照明が荒木さんにピンスポットで当てられます。
ドラムのビートが止みます。
荒木さんが、ささやくように歌を歌い始めます。瀧腰教寛さん作詞・作曲の「真フィジカル・カタルシスのテーマ」です。
間違い すれ違い 奪い合い 触れ合い
溶け合い 未知なる 誰かに 出会う……
ひとしきり歌い終えると、花井さんが再度スティックを握り、荒木さんを促すようにドラムを打ちます。再び歌が歌われ始め、ビートと声量とは相乗的に高まっていきます。そのクライマックスで二人の照明もふっと消え、古賀さんを照らす光だけが残り静寂が包みます。
しばらくして、荒木さんが高音で言葉のないメロディーを口ずさみ始めると、舞台のあちこちにスポットが落ちてきます。なにか穏やかで神秘的な音楽が流れています。歌声は次第に大きさを増していき、照明もはげしく変化してゆきます。その極限で花井さんの苛烈なドラムが入ると、古賀さんがついに起き上がり、荒木さんは控えへと戻ります。あちこちをやたらめったらに照らす光と花井さんのドラムが激しく場を満たすうちに、ギューーンと電子音。
古賀さんが上手側の舞台奥で壁に向かい合って立つと、時代のかった音楽が流れ始め、花井さんはドラムを離れ、マイクを手に舞台手前下手側で歌を歌い始めます。いやにカラフルなミラーボールがディスコティックに舞台を彩り始めます。さあ、古賀さん・花井さんが作詞、花井さんが作曲を務めた「新フィジカル・カタルシスのテーマ」です。花井さんのヴォーカルに、舞台奥の古賀さんが合いの手の茶々を入れます。
覚えている形
(いろんな形があるけれど大好きな形でっけえシャチ)
同じ線を描いては消えてゆく
(せつない!消えてゆく、大事な人、忘れたくない人、忘れちゃダメな人、誰だ、誰だ、、、誰だお前は!あー不安。不安だわー。もう消えたい。消えちゃいたい。早くこの場から消えちゃいたい。あちょっと待って、、、スー。)
見たことのない体内で
(あそぼ!)
繋がった点と点
(松本清張)
見えることを見るしかできない
(そういう部活)
来た道を思い出して
(フワフワフワフワ)
並んだ記憶が
フィジカル・カタルシス
(素知らぬ顔をして デカめの蟹を食う)
(アメリカのメジャーリーガー
出てくる時の音楽に似てるけど
メジャーリーガー出てこない ha...)
いまここで見たものすべて
(はい、すべすべ〜)
本当じゃなくてもいいから
(偽善の塊)
いつか見つける、正解はなくても
(見上げた根性)
触れた手を忘れないで
(はいサビいきまーす 3・2・1 Fire!)
そして通過する
フィジカル 語る 死す
(基本的に柚子胡椒 何にでも合う)
覚えている言葉
(いろんな言葉があるけれど、大好きな言葉でっけえシャチ)
同じ線を描いては消えてゆく
(あーい あーい あーい あーい
長い長い長い旅の時間 乗りこなすサーファーライカ湘南
グラサンかけたらNO PLAN レッドゾーン 深夜のウッチャン
意味ないことに意味を見出だす アイデア一閃、常にミニマム
デゴイチじゃないけど走りだす 拾って食べちゃうマキシマム
からだが熱を帯びてるからそろそろスピードを緩めよう
やがて呼吸が落ち着いたなら話の続きを始めよう)
これまでパターンとズレを用いて様々な動的「リズム」をつないできた『フィジカル・カタルシス』ですが、言葉がふんだんに使用され、ユーモラスな雰囲気の中、ノリのいいダンサブルな音楽に身を揺らすことができる点で、音楽的快楽へと突き抜けたのがこの箇所だったようです。実際SNSでもこちらのシーンは大変評判を集めていました。
モニターではいつのまにか古賀さんが床に寝そべっていますが、合いの手パートではカットが切り替わり、壁に取り付けられたビデオカメラがにこにこ踊る彼をリアルタイムで捉えています。古賀さんは終始この壁とカメラに向かって踊り歌うので、客席からはモニターを通じてでないと彼の表情を正面からまなざすことはできません。
このシーンは往年のバラエティー番組『学校へ行こう!』内で話題になった軟式globeという音楽ユニットのパフォーマンスをパロディしたものです。

PHASE 4: MUSIC(後) 古賀さん概念化説&古賀さん液状化説
ところで、このPHASEのあまりに儀式的な装いはどうしたことでしょう。荒木さんと花井さんが音楽によって古賀さんを起こす一連のプロセスは、なにか降霊術や蘇生術めいた神秘的な雰囲気に包まれています。そして、こうした印象と突き合せたとき、寝そべる古賀さんの姿勢は明らかに死を表象するものとして受け取ることができます。
だとして、なぜここで死者が扱われなければならなかったのでしょうか。感染症被害の象徴という解釈にも当然作品は開かれているでしょうけれども、死者は昨年の『フィジカル・カタルシス』の時点でも登場しています。
わたしはここで、「古賀さん概念化説」と「古賀さん液状化説」という二つの解釈を提示したいと思います。
まず、ここまでのPHASEの展開を確認しましょう。
PHASE 1:縄跳び、バスケットボール、ドラム、映像のディレイ等が生むミニマルなパターンの重層構造
PHASE 2:映像、肉体、それらに挟まれたヴァーチャルかつ物理的な身体と聴覚的な空想上の身体の重層構造
PHASE 3:形および関係性を主とした不可視のパターンと身体の過剰かつ多様な展開
PHASE 4:二つの「フィジカル・カタルシスのテーマ」による蘇生劇
こうして見ていくと、PHASE 3まででは、観客に要求される想像力の程度と、与えられる知覚可能な対象の量とが増大していくのがわかります。対してPHASE 4では音楽を軸として舞台上の要素はすっきりとまとめ上げられ、またその鑑賞体験もおそらくは与えられる歌詞という言語的概念的な意味によってそれまでの全体を構造化するよう働くと思われます。そこでは詞の強制力から自由な想像の行使の契機は薄弱です。そうしてこれまでの舞台上のファクターを「再認」する思考が働くだけに、ポップな音楽が持つ求心力が際立ち圧倒的な「カタルシス」をもたらすのでもあります。また、パターンとズレを基調とするダイナミズムの生成という原理もPHASE 4では共有されていません。
「古賀さん概念化説」というのは、身体の奥にあるなんらかの抽象的な次元に到達せんとする志向性が強まっていくのがPHASE 3であることを指して言ったものです。そのような抽象は現実的物理的な身体を捨象、つまり捨てて象ることで初めて可能になります。寝そべる古賀さんはまさに捨てられた身体としてそこに置かれているというわけです。前言語的で具体的なものをいくら愛そうとしても、人はすぐそれを抽象性や意味に還元してしまいます。言葉や概念の暴力的な規定性は、これまでのスペースノットブランク作品でも幾度か対象化されています。わたしの批評では2019年の『ささやかなさ』を「囁か無さ」と読み替える評でこれを扱っています。「新フィジカル・カタルシスのテーマ」の歌詞に「フィジカル 語る 死す」とあることも、身体が語られることで死へと堕するというテーマの縮図と読むことができます。その概念化の極点として、言語的な意味に満ち溢れたあの線型的ポップスシーンへの移行を読むこともできます。
ただし、ここで断っておかなければならないのは、『フィジカル・カタルシス』は作家という特定の個人の統一的な意図によって構成されたものではなく、一定の構成原理をもとにクリエイションメンバーそれぞれの思考や身体が集合したそのプロセスや結果を提示するものであって、こうした解釈を展開したところでその是非を判定する審級はどこにも存在していないということです。
ですから「新フィジカル・カタルシスのテーマ」の意味ありげな歌詞も、あくまで作品に対する制作者側からの一つの解釈の呈示にとどまるものであって、作品の「真意」を開示するエクスキューズのようなものではありません。実際、花井さんの詞とそれを茶化すような古賀さんの合いの手は、存在の身分の上では等価です。加えて、この「フィジカル→語る→死す」という構図はわたしが公演期間よりも前にウェブサイト用のイントロダクションですでに示していたものですから、それがここでの歌詞に反映された可能性も否定できません。しかしそのことは、私のここでの解釈の「正当性」を何ら傷つけるものではありません。さまざまな解釈と関わり方がさまざまに許容されながら場に蓄積されてゆくのがスペースノットブランクのクリエーションなのです。
さて、しかしPHASE 3においてこうした概念化に抵抗するに十分なほどめくるめく展開された身体の多様を、この解釈は捨象しています。実際、こうした解釈が許容されるとすれば、作品を言葉の次元に置き換えてしまうまさにこうした批評の還元性においてのことでしょう。
「古賀さん液状化説」は逆に、古賀さんの死をそうした具象的要素の過剰が空間を飽和させたことの帰結と見ます。このようにまったく正反対の解釈を一人の論者がとりうるという事実自体が、作品の様々な理解への開かれを立証しています。
PHASE 1は鑑賞者の知覚が追うことが可能なレベルにとどまった諸ファクターは、PHASE 2において想像上の身体が複数置かれることで知覚の容量を超え、PHASE 3ではその情報量の飽和を前に、能動的積極的な鑑賞の停止さえ危ぶまれます。動き続ける身体はたどり切れない情報の波へと液状化してゆくのです。飽和する情報が無意味へと接近すること(白いキャンバスに黒点を無数に打つイメージを想像してください)もまた、しばしばスペースノットブランクの作品に現れる現象の一つで、2020年の『ウエア』評ではこれをエントロピーという物理学の概念をモチーフに説明しています。
情報過剰の帰結としての無意味化と、帰結としての鑑賞停止とは別の問題ですが、実際に後者のケースが観客側からの自然な反応として見られただろうことは中西理さんの批評が如実に示しています。
下手奥にはあらかじめ同じ場所収録されたと思われるパフォーマーの動きがモニターの映像で提示されるが、最初の方はそれがほぼ同じような動きをしているのに次第にずれていったりと単純に現前での演者の動きを提示するだけではない情報が同時進行し、受け取る情報の多さについての負荷が高く、一方で物語性や娯楽性はほぼないためマスクをして息苦しいなかで作品に集中するには難しい作品と感じた。
(中略)
この作品では後半の「MUSIC」で音楽が使われ、ここでは音楽に合わせて生でラップと歌唱を行う。(中略)この「フィジカル・カタルシス」という作品では「音楽との出合いによるダンスの誕生」をひとつの仮想の物語として提起した作品のように思えた。作品の表題はそういう意味ではないのかもしれないが音楽の出現にはある種のカタルシスを感じた。(2020年10月6日確認)
理解不能なまでの情報の過剰=身体の液状化。液体になるというのは死ぬことと同義でしょう。けれども、構造化された言葉とメロディーが荒木さんによって付与されることで古賀さんは蘇生し、意味のクリアで豊かなめくるめく色彩の世界へと突入していくというわけです(作品はモノトーンを基調としていて、舞台がカラフルに彩られるのはこの「新フィジカル・カタルシスのテーマ」のシーンのみです)。
ただし、蘇った古賀さんの身体は、あくまで寝そべる過去の自分の身体に重ね合わされる形でのみ正面的に開示されます。思えば映像や録音など、戻ることのできない過去というメタフォリカルな形で「死者」の存在は初めから問題にされていました。蘇生を経てもなお古賀さんはそうした死者の存在格から逃れることができていません。
思えば、作品は倒れた花井さんを古賀さんが立ち上がらせることから始まっていました。花井さんのドラムによる古賀さんの蘇生と二人のデュエットは、輪廻転生のサイクルを完結させる行いと見ることもできるでしょう。上演は公演期間中繰り返され、『フィジカル・カタルシス』自体形を変えてまたいつか再演されます。そうした円環構造の中での生死のだぶつきが最も祝祭的に謳歌されるのがこのMUSICのPHASEだったのです。
浅田彰『構造と力』では、メタ・レベルとオブジェクト・レベルという、「二つのレベルに足をかけているという事実を笑いとともに肯定する」ニーチェとドゥルーズの姿を、今日の社会において真に遊戯を体現する示唆的な存在として紹介しています。この二つのレベルとは、まさにここまでで重ねられてきた超越的主体と経験的主体、見る者と見られる者、概念化or液状化された死者と現実に身を置く物理的生者、カタルシスとフィジカルに対応するものです。スペースノットブランクの舞台とは、こうした二つの地平を不断に往還する楽しい反復横跳びなのです。
PHASE 5: TRACE 「再生」される現在
舞台中央には荒木さん。PHASE 2での動きを一つ一つ確かめるように反復していて、やがて山口さんもそれに加わります。両者の位置関係には変化はありません。映像は依然古賀さんの死を殺風景に映しています。やがて二人の動きはPHASE 3でのものに移行、立ち位置の固定性も崩されます。作品の展開が再度TRACEされてゆきます。映像の方にも、中央に古賀さんを残したまま荒木さんと山口さんの二人が加わり、動きを展開。
けれども時間が経つと、舞台には山口さんだけが残されます。様々な時間、様々な身体の姿が山口さん一人に集約されます。ここでもやはり、個を没した集合的な地平でなされる「再認」を通じた「カタルシス」の論理が働いているのです。映像の方では二人が去り、やがて古賀さんも去って、誰もいなくなります。山口さんだけが独り舞台で踊りを続けています。真っ赤な照明が舞台の全体を包んでいきます。長い駆け足の動作の後、ひざを寄せつつ足は開くという大変歩きづらい姿勢で足踏みを繰り返すうちに暗転。終幕です。
実は、舞台上に展開された様々な動きを山口さんの身体に集約させるというこの展開は、2019年5月の『フィジカル・カタルシス』の終盤の展開をTRACEしたものでもあります。そのバージョンは、花井さんをロープで持ち上げるという首つりのメタファーで終幕しました。それは、一つ素直な解釈を提示すれば、動きを特定の個人に集約した結果捨象されてしまったある別の身体を例示しているかのようでした。わたしがイントロダクションの時点で死について取り上げたのも、そちらの公演のことが念頭にあったからです。
真っ赤な照明のどこか非現実的な雰囲気、舞台に一人残されるという孤在の感覚、そして駆け足の末進む先をなくしてしまう行き詰まりの感覚を表象するかのような最後の振り付け――こうした終盤の要素も、孤独と停滞の観念、ひいてはある種の「死」を具現しているように思われます。
音楽はそれが時間芸術であり、基本的に終わるものであることにその本質があります。刹那的な享楽を超えた先に持続する反復の日々を、このTRACEのチャプターは体現しているのでしょうか。
実は、今回の舞台から私が受け取った印象は、寧ろその対極にありました。なぜなら、複数のパターン、複数の身体の折り重なりのうちに生まれ出る生き生きとしたリズムを追いかけてきたわたしは、空白となった空間にも、舞台上の山口さんと呼応し動きを舞う生者の姿を幻視したからです(スペースノットブランク)。他者との関係性を切断され動けなくなるかのような山口さんに、死者の表象であり続けていたはずの過去が、わたしのイマジネーションの中で、今度は生を与え返していたのです。メタ・レベルとオブジェクト・レベル、幻視される空想上の身体と現実的物理的肉体、生と死とは、複雑に多重化されながら、あくまでそのだぶつきを保持し続けるのです。
暗転ののち、「真フィジカル・カタルシスのテーマ」が再度流れます。今度は作者である瀧腰さん自身が歌って録音したものです。モニターはバスケットボールのボードゲームを映し出しています。作品とスポーツの先ほどの類比を思い出していただければ、これが作品自体の縮図を成していることがおわかりになるでしょう。ゲーム盤はエレベーター前の控えに置かれていて、遊んでいるのが手元で映し出されています。盤上にはクリエーションへの参加者たちが持ち寄った小さな人形や置物が「プレイヤー」として並べられています。プレイをしているのは古賀さんだそうで、PHASE 1でボールを奪い去った彼の身体が、これまで人体を小さく映し出してきた映像の中でシームレスに極小のゲーム盤へと地続きに引き継がれていることになります。映像という概念的な地平においては人体とミニチュアとの区別も霧消するのです(この点については中澤さんから示唆を頂きました)。
こうした入れ子的な循環構造によって作品は閉じられてゆきます。退屈と停滞と死と別離と孤独とがズレを孕んだダンサブルなパターンとして編み直されていくのは、そうした無限の円環においてのことなのです。
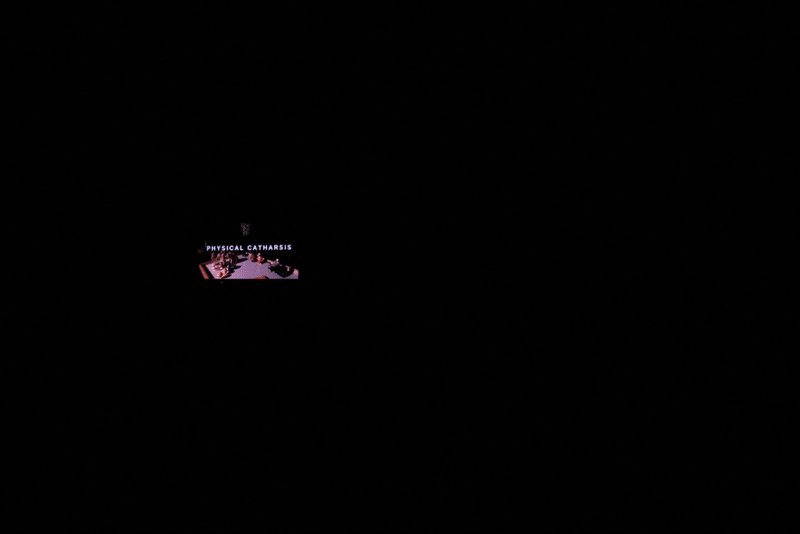
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
