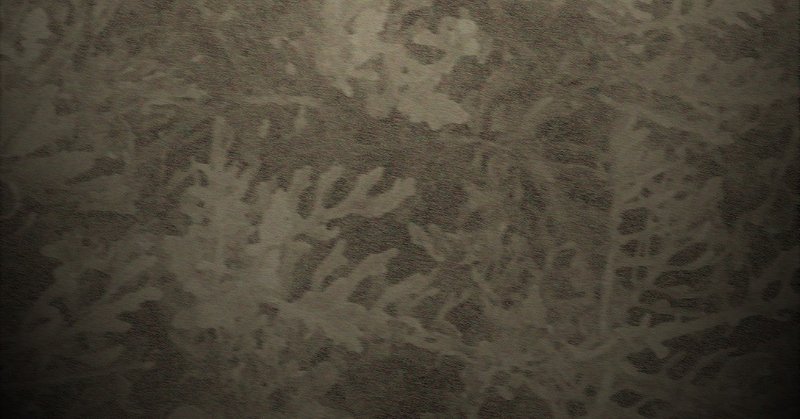
中編小説【白の添え歌~後編】(文字数16637 無料)
いくつかの謎
今日のように晴れた朝のことでした。バーマンという牧師が中庭を通りかかると、とっくにお祈りの時間は終わっているのに、塩の上に誰かがうずくまっているのが見えます。熱心に祈りを捧げているようにも、あるいは眠っているようにも見えます。
中庭で祈りを捧げることができるのは大高師か副高師、あるいは彼等に許可をもらった者だけです。
見ると、その人物は真っ赤な法衣をまとっているようです。赤い法衣は副高師が祭事に着ることがあります。
バーマンは焦りました。大高師であっても副高師であっても、いまから行事があるので急いでその準備をしてもらわなければなりません。塩の敷いてある箇所にバーマン自身は立ち入ることはできないので人影に呼びかけようと思ったとき「そろそろ時間ではないのか」と背後から聞き慣れた声がします。
振り返ると他ならぬ副高師が立っています。バーマン牧師は驚いて中庭の人影を指さしました。副高師も気がつき「さて、大高師様ではないのかな」と塩の上に一筋残された足跡の横を歩いて近づいていきます。歩きながら副高師は不思議なことを口にしました。「さて、おかしな話だ。高師様はあのように鮮やかな色の法衣を持っておられただろうか」
その声を聞きながら、バーマン牧師は行事が予定より遅れることを伝えるためにその場を離れました。
唐突にフィルマンは話を止めた。
感情が激して平静な口調を続けられなくなるのを感じていた。
ひどく詰まらないことに思えた。
「こんなことを話してもしょうがない。どうせ実際に起こったことではありません」
そしてまた無言で歩く。さすがに探偵も驚いたようだったが、なにも言わずフィルマンの横を歩き続けた。
しばらく二人は無言だった。どこまでこの男はついてくるのだろうとフィルマンは思ったが、訊ねないことにした。
「あの、一つ聞いてもいいですか」
双一郎の言葉もフィルマンは黙殺した。
「あなたは北へ向かっていますね」
ため息をつく。無視するのも疲れる。このしつこさも、人の秘密を探る探偵という職業の資質なのかもしれない。
「その通りです」
「どうして北を目指すのですか」
「個人的なことです。答える必要はないと思います」
「僕のような眼鏡もしていませんよね。土地の人は塩の光で目をやられないんですか?」
詰まらないことに気がつく男だと思った。
「……それも個人的なことです」
「そうですか。失礼しました。では僕もしばらく北へ向かいます。もちろん、個人的な理由でね」
探偵がフィルマンの横で歩きながら伸びをする。
「ところで、いまの話って結局あれでしょう、きっと大高師は殺されているんですよね。法衣を赤く染めているのは彼自身の血。それなのに、塩の上には犯人の足跡がないんですよね。いや、そういうパターンの謎がありますよ。足跡なき殺人ってね」
探偵は楽しそうだった。フィルマンの返答を待たずに先を続ける。
「うーん、足跡がないっていうのは、僕が先ほどあなたに訊ねたことと同じですよね。あなたは塩に触れるのも危険だと言った。教会の中庭の塩もやっぱり危険だったということですか。でも、普段は祈りを捧げているんだから、そのときだけ危険な塩になったということか……それにしても、高師はどのような方法で殺されたんでしょうねえ。それがわかるとさらに真実に近づくと思うのになあ」
実際には起こっていない事柄だと言ったにも関わらず、よく喋る男だった。
「高師は……体中に穴が開いて死んだ」
その言葉に探偵がひどく驚いた声を上げる。
「ちょっと待ってください。そんなことが塩によって引き起こされるわけないじゃないですか」
「でも、そういうことが起こったんだ。しばらくしてバーマン牧師が中庭に駆けつけたときには、副高師も同じように死んでいた。足跡は大高師様と副高師のものしかなかった」
「へえ……そりゃ不思議だ、と驚きたいところですが、どうも決定的な手掛かりが僕には与えられていないようですね。それが多いに不満です」
結局、この辺りの者はこの塩の湖やそこで起こっていることについて、余所者に詳しく話したがらないのだ。塩の上を行こうというこの好奇心旺盛な旅人に、この場所の恐怖の原因を教えなかったというのは確かに公明正大とは言えないやり方に思えた。
フィルマンは立ち止まり、振り返る。
「彼等は日光が苦手なので、昼間は決して姿を現しません。だけど、ほら」
後方の、先ほど自分が投げ捨てた水筒を指さした。それは彼と探偵の足跡から離れた場所にあった。放り投げた場所から少し東へ移動しているのだ。
「あの水筒は羊の胃袋でできています。よく見てご覧なさい」
探偵が目を凝らして見つめている。と、風もないのに水筒が転がった。しばらくしてまた。少しずつ動いている。
「うわ、すごく不思議なんですけど。でも、あなたは当たり前のように言う。ちょっと考えさせてくださいよ……」
双一郎が俯いて目を閉じた。一瞬だけ。そして、顔を上げる。
「何か生き物ですね」
と言った。フィルマンは改めて詮索好きの男の能力に驚いた。
「その通りです。塩の表面に衝撃があると、何が起こったのか確かめようと下から管々蟲(くだくだむし)という鋭い歯を持った親指ほどの太さの細長い虫が上がってきます。彼等は鉱物以外にも動物性の蛋白質を好んで食べます。もともとはこの湖にまだ水が満ちていた頃には普通の肉食生物だったものが、塩の堆積と共に体の仕組みを変えていったのだという話ですが」
「じゃあ、いまも地下から食いついているわけですか。でも、いまあの水筒の下には穴もないようですよ。素早く穴を埋めて逃げることができるのですか」
「逃げていません。ほら、ちょっと左の方に表面に開いた穴が二つあるでしょう。もともと水筒はあの辺りに落ちていました」
そう言っている間に、また激しく水筒は転がった。穴から遠ざかっていく。
「おそらく数匹は水筒の中に入っているでしょう」
「その、管々蟲がですか……」
「その通り。そして、それがあなたが先ほどから気にしていた疑問に対する答えなのです」
「ええっと、確かこの塩の道に足跡がないのが何故かということをお聞きしました」
「夜の間は虫の活動が活発になります。それで消えてしまうんですよ」
「虫の活動で?」
「この塩湖の北側では、表面の塩が常に乾いています。それが川の流れ込む南の方と大きく違う点です。南では一般の業者が塩の採掘を行っていますが、品質は確実に落ちます。しかし、品質の良い北では塩の採取が厳しく制限されているのです」
「なぜですか」
「ここが遠い昔に賢者が悟りを開いたという聖地だからです」
「で、それが足跡が消えることと関係あるのですか?」
「ここで採れる塩は南部のものと違って粒がとても細かい。とても高価なものです」
「……それほど場所が離れているわけでもないのに、塩がそんなに違うのですか」
「塩湖の中央から北部の表面にある塩は管々蟲の吐き出したものなのです。毎晩夜明け前にこの塩の下の方の層で動き回っているたくさんの管々蟲が地表に出てきて、表面にうっすらと積もる程度の塩を吹き出します。そしてこの表面のどんな痕跡も次の日にはほとんど消えてしまうのです」
「ははあ。だから足跡も翌朝には消えている、とそういうわけですね。なるほど。奇妙なことをする虫ですねえ」
「湖の北部では、下の方に虫が好む鉱物をたくさん含んだ泥の層があります。虫はその泥を食べて、硫黄分など吸収して生きています。そして、なぜか夜明け前という決まった時間に不要なものを排出しに上がってくる。そのほとんどが塩分であり、虫の体内を通った塩は独特の風味を持ったものになる。ここの塩が他の塩湖のものと決定的に違う理由です」
「えーっと、つまり、この辺りの塩というのは、早い話が虫の糞ですか」
「まあ、そうです」
「なるほど……」
探偵を名乗る若い男が改めて塩の大地を見渡す。フィルマンもそれに倣(なら)った。この辺りの塩を採取できるのは教会の許可を得た者だけだ。
「それを思うと感慨深いものがありますね」
「人がこの地に触れようとしないことにより、虫はその数を増やす一方です。この上を横断することは禁じられていませんが、命がけであるというのはそういうことなのです。中には密かに管々蟲を捕らえる輩もいるようですが、その連中も基本的にこういう、筒状の罠を投げつけて、入り込んでくる虫を捕まえるという話です。もちろん、いまあの水筒をわたしかあなたが拾おうものなら、今度は腕に食らいついてきますからやめた方がいいでしょう。密猟者はもっと安全な仕掛けを使って捕らえるんでしょうね。でも、管々蟲はこの辺りの塩産業を支えている貴重な生物ですし、教会の命令に背いているわけですからね、見つかったら間違いなく死罪です。いまの我々も裏に毛皮を貼り付けた靴を履いているから平気なんですよ。彼等は動物の毛を極端に嫌いますからね」
「塩はともかく、虫をどこへ売るのですか?」
「この環境以外でさほど長くは生きられないでしょうが、愛玩用に買う人がいるみたいですね。あと、食べると変わった味がするという話や、いろいろな病気を直す薬になるという話も聞きます。そういったわけで、かなりの値段で取引されているようですよ」
「では密猟に命をかけるだけの価値はあるということですね」
双一郎が我が意を得たり、という表情でフィルマンを見た。背負っている荷物にも好奇の目を向けている。フィルマンは苦笑する。
「期待を裏切って申し訳ないけれど、わたしは密猟者ではない。虫に興味はありませんよ」
そう言えばあきらめて帰るかもしれないとフィルマンは思っていたが、意外な返答が返ってきただけだった。
「まあ、そうでしょうね。もう少し僕も北へ行きます。でもあまり行き過ぎると日が暮れるまでに東へたどり着けなくなってしまうので、適当なところまでです」
「それがいい。それ以上わたしについてきても、何も得られるものはないですし」
「ということは、あなたは日のあるうちに戻る気はないということですかね」
なるほど。探偵とはこういうものか。もっと出会いが早ければ何らかの意味はあったかもしれない。
視線を落として歩き続ける。
日差しは元々それほどきつくはなかったが、塩の表面での照り返しもあり、額には汗が浮かんできた。見ると、探偵の額にも頬にも大粒の汗が浮かんでいる。
足下を見つめながら進む。探偵は何も言わない。
自分の影。塩を踏みつける感触。
前方には広大な白の大地が広がり、蒼穹との境に山脈を挟む。
右手を見る。ほぼ真横に黄誠団の聖地が見える。
注意深く、もう一度前方を見る。
そして、探し求めていたものと思われる小さな影を見つけた。
フィルマンは目を閉じた。
大地が傾く気がした。
倒れ込みそうになった。
悲鳴を上げそうになった。
荷物を放り出して走りたくなった。
それら全てをこらえて、彼は背中の荷物を揺すって肩に食い込む帯の位置をずらすと、また一歩ずつ歩き始めた。
「あれ、なんだろう」
それが次第にはっきりと見えてくると、隣で双一郎がつぶやいた。答えは期待していないようだった。
やがて、堅い塩の上に横たわっているものの細部が見えてくる。
見覚えのある濃紺の布と柿色の生地。
フィルマンは歩を速めた。荷物がますます肩に食い込む。揺すって帯の位置をずらす。
ようやく、隣の男にもその正体がわかったようだった。
「うわ、これはもしかして……」
フィルマンと、旅人はようやくそこへたどり着いた。
塩の大地に横たわる、女の亡骸の元へ。
白と赤
風はすっかりやんでいた。
何の音もしない。
まだ顔はきれいに残っていた。
穏やかな表情をしているのが意外だとフィルマンは思った。
亡骸とフィルマンを交互に見ていた双一郎がいきなり「管々蟲が塩を吹くのは夜明け前だけですか」と訊ねてきた。
「そうです。夜の間は地表近くにいて、日の光が塩の表面に当たると一斉に塩を吐き出して深く潜ります。次に出てくるのは明日の早朝になる」
「だとしたら、これって不思議ですよね」
言いながら双一郎が塩の表面を指さす。
亡骸の足跡は北から続いていた。右足と左足。五十歩ほどもあるだろうか。つまり、最後に南へ向かっていたということだ。町のある南へ。
少し離れた場所からきれいに残っており、死体に近づくにつれて赤くなっていた。
彼女の血。
「これを見てどう思います」
「別に」
それは嘘だった。
だが、自分が思っていることを説明することなどできそうになかった。
探偵が喋る。
「まず最初に気がつくのはね、この人、女性ですけど、裸足だということですよ」
足は、特に膝から下は血まみれで、あまり原形を留めていないため、わかりにくいが、塩の上の足跡にはいくつか指の形がはっきりと残っており、片方だけ伸ばされた足にも靴は履いていなかった。
「それがまずおかしいんですよ。この塩の上を歩くなら、毛皮を貼り付けた靴にしないと。ねえ、それはこの辺りでは常識なんですよね」
「そうだ」
「湖を渡ることのできる橇なども、見る限りどこにも存在しない」
「そうだ」
「なのに何故ここでいきなり力尽きているのか。足跡の始まりは塩の湖の真ん中だ。あなたの話だと、夜明け前には虫がはね回ってとても人が歩けるような状態じゃないとのことですよね。だとすると、この女性は今日、日が昇って虫達の乱痴気騒ぎが終わった後で、この塩湖の中心にいきなり現れたことになる。靴も履かずに。そして、南へ裸足で少し進んで、案の定、虫にやられてしまった」
「なるほど。確かにそんなふうに見えるかもしれない」
「でもそれだとかなり無理のある状況ですよね。そもそも裸足でここにたどり着けるはずがない。だから、この死体はこんなところにいられるはずがない」
「夜が明けてから歩いてここにきて靴を脱いだということも考えられる。いまわたしや君が同じことをすれば同じような目にあうだろう」
単に探偵の意見を否定するための言葉だと自分でもわかっていた。
「靴はどこへ消えましたか。毛皮のついている靴なら管々蟲は嫌って食べないんじゃないですか。よしんば靴を履いていたとしても、その足跡はどこに消えましたか。僕等の足跡はご覧の通りずっと残っています。明日の明け方にまた虫達が騒ぎ始めるまでは残っているでしょう。だけど、彼女の場合はこの数十歩分の足跡しか残っていない。そんなことはあり得ないでしょう」
探偵がうなって塩の上の足跡を見ている。
ああ、これが彼の言っていた謎というやつか。真相を知っているものには不思議でもなんでもない。探偵が何をどうしようとここにはもう取り返しのつかない風景があるだけだ。
「あ、前言の一部を撤回します」
探偵がいつの間にか取り出した鉛筆で彼女の足の裏を指して「靴ではないようですが、何かが貼り付いています」と言った。
フィルマンは血と塩にまみれたそれを見た。
薄い毛皮の一部がかろうじて残っていた。おそらくは虫膠(むしにかわ)のようなもので足に付けたのだろう。
丈夫な毛皮の靴は、当たり前だが持つことを許されなかっただろう。こんなもので、塩の上を渡りきることなどできるはずがない。
だが、何もなければ、一歩も進めない。
「えーっと、つまり、この毛皮を足の裏に貼ってあれば、ある程度は安全に渡れることができると、少なくともそう思ってやってみたけど、駄目だったと。この足跡を見る限り、数十歩しか動けなかった。最後は歩幅が乱れながら大きくなっている。血の跡も混じっているから、虫にやられながら走ったんでしょうね」
「そうだろうな」
声が震える。返事を短くしないと、耐えられそうになかった。
「かわいそうに……それ以上は何がわかるかな。手がかりが少なすぎるけど……まあ、ここは証言をしてくれそうな人に直接聞いてみるとするかな」
探偵がフィルマンの顔を覗き込んできた。
「あなたの恋人ですか? あるいは家族」
顔を上げる。驚きを悟られまいとする。
「どうしてそう思う」
「ここが道もない塩の上だからです。なにも目印を持たない塩の大地の上だからです」と探偵が答えた。
「理由になっていない」
「僕があなたと出会ったのはそれほど驚くような偶然ではありません。僕が歩いていた東西へ伸びる道は日に何人か通う人間がいるそうですから。遮るものが何もない塩の上を、東西に横切ろうとしている僕に、南北を縦断しようとしているあなたが気がつく、あるいは僕があなたに気がつくのは容易なことです。時間は全く同じである必要はない。かなり離れていても塩の上を歩いていれば目立ちますからね。そういう行動を取っている二人が存在する時点でなんの苦労もなく起こりうることです。僕は自分の行く先の様子が知りたくて、道筋の合流地点であなたを待ちかまえて話しかけることができました」
探偵が笑ったが、フィルマンは表情を変えなかった。
探偵が鉛筆で南をさした。そこには二人が歩いてきた足跡がまっすぐと残されていた。
「ところが、いまここであなたがこの亡骸を見つけたのはわけが違います。ここから四方を見回しても他の死体などどこにも見あたりません。なのに、あなたは最初からこの死体へと向かう道をほぼ一直線に歩いていた。それこそ、最初に僕があなたを見たときに、すでにここへ向かっていたということです。あなたは最初からこの死体のある場所を目指してここへ来ていた。それしか考えられません」
そしてフィルマンを見た。
「僕の言うことは間違っていますか」
フィルマンは答えなかった。
「まあこれも他人の要らぬ干渉かもしれないですね。あなたがここを目指していた理由に関しては置いておきましょう。だけど、どうしてここにこのようなものがあるのを知っていたのかという問題は残る。見たところあなたは磁石も地図も持っていないようです。それなのになんの目印もない広大な塩の上の一点にたどり着いている。まあ、手っ取り早く思いつく可能性はあなたがここでこの女性を殺した本人であるというものですが、まあ、あなたが今日ここへ二回来たと考えるのも不自然ですよね。僕も町を朝一番に出てきて、いまようやく昼近くになって湖の半ばまでたどり着いたくらいですから。僕とあなたが出会った地点から考えると、南の町の方が遠いと言ってもいいと思う。あなたはいつ町を出ましたか?」
「夜明けと同時に出てきた」
「そんなところでしょうね。そこから休まず歩いて、いまようやくここにいる。どう考えてもあなたが犯人であるとは思えない。だけど、犯人しか知りようのない凶行の現場を知っている」
双一郎が亡骸の顔を指した。
「亡くなってからまだそれほど時間は経っていないように見えますよね」
手を伸ばしかけていたが、その言葉が終わらないうちに、亡骸の衣服が、胸の辺りで不自然に動いた。探偵がおびえたような悲鳴を上げて手を引っ込めた。フィルマンは目を細めた。
「迂闊(うかつ)に触らない方がいい」
服の袖から伸ばされた亡骸の白い腕が動いた。皮膚の下が瘤のように盛り上がり、そのまま手首へと伸びていく。一部が裂けて新たな血が流れる。
「管々蟲だ」
フィルマンの言葉に、探偵は後ずさった。
「うわー、怖いなあ。でもね、恐らくは最初に被害を受けたであろうこの足を見てください。まだ血液が完全に乾ききっていない。ね。とても不思議なんです。足跡が残っていることからこの女性が亡くなったのは夜が明けてからだということは確実です。この傷口の新しさからいうと、それこそ僕とあなたが出会った頃にはまだ彼女は生きていたのではないかと、そんなことさえ考えてしまうんですけど……僕は間違ってますかね」
フィルマンは黙って荷物を下ろした。筺を開ける。早速、筺の底を叩く音が聞こえ始める。毛皮は貼っていない。管々蟲が新たな獲物かと思って分厚い紫檀黄金(したんこがね)の板を食い破ろうとしているのだ。もちろん、歯の鋭い彼等の攻撃をもってしても、丈夫な筺の底板に穴を開けるのには相当時間がかかるだろう。
彼はセロを取り出す。探偵の驚いた表情がおもしろかった。筺の蓋を閉めるとそこへ腰掛けて楽器を両足で挟み、折り畳みのネックを伸ばす。簡単な音合わせを終えると、足を大きく振り、天気を占うように履き物を飛ばす。両足とも。そして弓を一度空へ向けてから、ゆっくりと弦をこすり始めた。
朗々と低い響きが風に混ざる。筺の底の振動が消えた。
「セロのね、この楽器の独特の音色は管々蟲が嫌いなものの一つです。風が鳴らすこの辺りの音は、我々の耳にはセロに似ているようにも聞こえますが、虫には違うものとして聞こえるのでしょう。毛皮とセロの音、そして氷。彼等が手を出そうとしないものです」
フィルマンは運指練習用の単調な旋律を弾きながら話を始めた。
わたしの父は町の南中地区にある小さな虫機器工場の技術者で、主に縫い取り機や機織り機の修理をしていました。町では一番の腕前だと言われていましたが、そもそも技術者自体が珍しい存在となっていました。
最近では金属を使った製品が安く出回るようになったので、それに比べて腐りやすいという致命的な欠点を持った虫機関はいずれ消えていく技術だろうと、これは父親自身がいつも言っていました。
わたしも子供の頃から父の手伝いをしていたのですが、別の職を見つけるように何度も言われていたので、跡を継がないことを当然だと考えていました。
貴重な技術を持った父は教会が所有する越境船の修理も任されていました。五百年も前に造られたとされる物で、この辺りでは塩や砂漠を渡ることができる唯一の機械でした。虫の騒ぐ夜間でさえ塩の上を走ることができるのです。わたしもその修理を手伝うために、教会の広い敷地内にある、塩湖に面した船置き場へ何度も訪れたことがあります。
越境船は最大八人乗りで、巨大な湯船にきれいな装飾を施したような形をしています。動力部の虫機関は大きな推進力を得るために幾匹も虫を重ねた作りになっており、絡み合う虫達の脚部の連動を統率する仕組みは複雑かつ繊細で、それを触ることができるのは父だけです。船の下部には丈夫な毛皮が貼り付けてあり、管々蟲に食べられるのを防いでいました。当然、修繕のためには船の内部構造を把握していなければならないので、何度も船のキャビンに入ったこともあるのですが、中に桶というか檻のようなものがあることにも気がついていました。
それを副高師が説明してくれました。近頃になって大神の啓示があり、塩という聖なるものの中で暮らす管々蟲を捕獲し、その研究を行うようになったと。それは間違いなく教会のためになっているのだと。
まあ、早い話が教会ではその船を使って管々蟲を捕獲しては好事家に売り払っていたのです。密猟者達が一番問題にする『いかに教会の連中に見つからずに塩の上を移動するか』という問題を、彼等は最初から気にしなくて良いのですし、こんな便利な船を持っています。月に一度の小祈祷のために船が数日間は塩湖の上をさまよいますから、きっとそのときにでも虫を捕まえているのでしょう。
父が死んでから、教会では慌てて次の虫職人を探したのですが、いまさら簡単に見つかるはずもなく、しばらくはわたしが簡単な保守をすることになりました。もともと祭事に使うだけだったので、本格的な修繕が必要になることは滅多になかったのです。まあ、いまさら父の技術に到達できるわけはありませんけどね。
わたしは学校を卒業すると町の楽器屋で働き始めました。ヘレザグルートという、ヴァイオリン造りではかなり名の知れた職人がやっている店です。まだ楽器には虫を加工したものが多く使われていましたから、いままで学んできた技術が役にたったのです。
去年の聖盤節の日に、一人の女性が店にやってきました。彼女は教会の音楽隊でセロを弾いており、その楽器の調節をするためにわたしの働いている店を訪れたのです。彼女が持ってきたのは黄金鈎爪虫(こがねかぎつめむし)のボディを使った美しいセロでした。引退を決意した先輩の楽器を譲り受けたのに、どうも音が変わってしまったような気がするということで相談に来たのです。
指板には夜蛍(やぼたる)の硬い羽が貼られ、弦止めには銀七節が使われていました。弦は太紐蟲ですが、全体的に音の伸びがなくなってしまっているとしか思えないというのです。もちろん、こちらとしては元の音を聞いたことがないので、それが本当かどうか客観的に判断することはできません。ただ、楽団の人達も同じことを言うというので、彼等の耳を信じるしかないのです。
ヘレザグルート親方はわたしにその調節を任せると言いました。おそらく経験を積ませるためなのでしょうが、いったいどのようにして楽器に以前のような音を蘇らせればよいのか、まだ駆け出しの楽器職人としては途方にくれるしかありませんでした。
来る日も来る日も楽器を眺めていて、あるとき突然気がついたのです。弦の根本にある太紐蟲の目の色が赤いということに。ご存じかもしれませんが、この太紐蟲というのは環境によってその成長の早さがずいぶんと異なります。気候や環境に恵まれて早く成長したものの目は赤く、遅く成長したものは微妙に橙になります。さっそく、持ち主に確認をしましたところ、確かに弦を張り替えたというのです。
店にあった橙の弦に張り替えたところ、わたしにもはっきりとわかるほど音に艶がでました。親方にそのことを報告すると、よくやったなと言われました。おそらく彼は最初からそれを見抜いていたに違いありません。
楽器を取りに来た女性に店の中で試しに音を出してもらったら、とても驚いていました。彼女がいままで使っていたセロでは、弦によってそれほど差が出るのを感じたことがなかったので、ついつい安い弦を買うのが習慣になっており、譲り受けた楽器にも特に疑問も持たずに使っていたというのです。お互いに自分の携わる世界の駆け出しだったということで、なんとなく親近感を抱いたのかもしれません。それから何度もお店に顔を出すようになり、わたし達は親しくなったのです。
彼女はチルダという名前でした。
彼女が出ている演奏会には必ず足を運びましたし、歌劇の演奏もやっていたので、慣れない観劇までしました。
わたしは楽器の演奏はからきし駄目だったのですが、チルダが一つだけ簡単な曲を教えてくれて、なんとか弾けるようになりました。『雪添(ゆきそ)え言(ごと)』という曲をご存じですか? セロの初心者用の曲で、運指がとても簡単なのですが、緩やかな旋律を持った美しい曲なのです。来る日も来る日もわたしはそればかり練習していました。
彼女の両親に会う機会がありました。二人とも熱心な教会の信者で、娘が教会の楽団に入っていることがとても自慢だと話していました。ただ、日頃からチルダは両親の信仰の度が過ぎて困るとこぼしていたので、わたしは彼等の話を聞いても素直にうなずけませんでした。
彼女が練習用に借りている郊外の小屋で『夢降り』や『風吟(ふうぎん)』を聞いていたときの幸せなひととき。黄金色のセロを抱き、目を閉じて『情熱のための赤』を弾く彼女の横顔。古びた小屋の中が光り輝くようでした。
彼女の事ばかり考えていました。わたしの毎日は彼女のためにありました。
これは誰にでもあるような、さして珍しくもない出来事でしょう。
だけど、わたしには一度きりだったのです。
ところが、そんな幸せは一瞬にして終わりを告げました。
五日前、わたしは仕事を終えた後、いつものように彼女の練習小屋を訪ねました。
二週間後の定期演奏会を前に、ここのところ同じ曲ばかり演奏していたのですが、その日の音は少し乱れているようでした。
練習が終わった後で、そのことを指摘すると、驚いたことにもう会いに来ないで欲しいとわたしに言ったのです。まさに青天の霹靂です。わたしの言葉が気に障ったのかと聞いたけど、彼女は首を振るだけでした。
まるで意味がわかりません。それでも、なにか彼女が一時的に機嫌を損ねただけなのだと思っていました。まあ、いままでにも何度か些細なことがきっかけで小さな喧嘩をしたことはありましたし、わたしはちょっと鈍いから原因が自分でわかっていないだけで、重大な失敗をしでかしたということも考えられます。とりあえず、その日は帰ることにしました。ところが、玄関を出るときに、彼女が突然後ろから抱きついてきました。そのまま、しばらくわたし達は身動きをしませんでした。
彼女は半ば突き放すようにわたしを小屋の外へ追いやり、泣きながらありがとうと言ってドアを閉じたのです。
わたしはしばらく呆然としていました。もう何がなんだかわかりません。
部屋の中からは雪添え言の曲が聞こえてきました。わたしが練習するならともかく、いまさら彼女がこの曲を弾くのは珍しいことです。
まだわたしは迷っていましたが、その曲に背を向けて、とりあえず、その日はおとなしく家に帰りました。
もちろん、ずっと彼女のことが気になっていました。二日ほど黙って働いていましたが、彼女が来る様子もないので、練習小屋へ行きました。壁際には彼女の立派なセロが立てかけられ、主を待っていました。小屋のオーナーに訊ねましたが、ここ数日は来ていないとのことでした。
気が進みませんでしたが、彼女の家に行くことにしました。
緊張しながらドアを叩くと、彼女の母親がにこにこしながら出てきて、チルダが遠くへ引っ越したのだと言いました。
わたしは呆気にとられました。とにかく母親は何を聞いても具体的なことを言わずに、彼女がどれほど幸せになれるかということを嬉しそうに話すだけなのです。わたしはその目の輝きが気味悪くなって、結局その場は納得した振りをして帰ることにしました。
ところが、家から離れてすぐに町角で呼び止められました。チルダの父親が立っていました。
近くのパブでわたしは彼から話を聞きました。
今年の聖地の祈りの儀に、チルダが神子(かみご)として選ばれたというのです。
もう会うことができないと言われました。
彼女のセロを聞くこともできないし、わたしのセロを聞いてもらうことも、二度とできないのです。
フィルマンの話はまた唐突にとぎれた。
探偵が肩をすくめる。
「いったい、その神子というのは何をやるんですか? お祭りの準備のためにどこかで修行でもするのですか?」
「わたしも最初は神子がどんなことをするのかよくわからなかったのです。教会で聖職に就くのかと思っていました。祈りの儀は昨日の夜から今日の朝にかけて行われることはわかっていましたが……わたしは昨日の夜からずっとお酒を飲んでいました。明け方に酒場の女将がどうしてそんなに荒れているのか訊いてきたので、わたしは全てを話しました。すると女将は溜息混じりに神子となった者の運命を話してくれたのです」
「えーっと、いやな予感がするんですけど」
「聖者であるヌエイエが塩の上で悟りを開きました。その塩の地に神子は捧げられるそうです。神子を差し出すことはとても光栄なことであり、その親族までもが死後の神の祝福を約束されますが、これを拒否すれば、親まで地獄に堕ちると、半ば脅しのようなことを言われるそうです。十年に一人。熱心な信者の娘だけを選んでいるそうです。もちろんそうでなければ生け贄として娘を差し出すわけがありません。夜のうちに越境船で運ばれた神子は、氷で作られた捧げ台の上に乗せられ、塩の上に置き去りにされます。夜間騒いでいる虫達も氷は嫌って手を出してきません。しかし、氷はやがて溶けてしまいます。つまり、彼女はそういう目にあっているということです。わたしはそれを聞いて教会へ向かいました。もちろん、船を使って彼女を助けに行くつもりでした。幸いドックの鍵はあずかっています。彼女を救うにはなんとかして船を奪うしかありません。まだ船が戻ってきていない可能性はありましたが、帰還を待って、すぐに奪えばなんとかなるかもしれません。教会の門番は船のメンテナンスに呼ばれたのだと言うとあっさり通してくれました。船を使う儀式があることを知っていたのでしょう。
回廊を歩いていると、背後から呼び止められました。見ると年老いた牧師が立っています。牧師の知り合いなどほとんどいないはずなのに、奇妙なことにその顔には見覚えがあるような気がしました。
「さて、迷われたかな、お客人」
その話し方を聞いて、一瞬にして思い出しました。以前学校の先生をしていたバーマン牧師です。
「そちらは滅多なことでは立ち入ってはならぬ区域ですぞ」
どうやら彼はわたしを覚えていないようでした。それも無理はありません。
「船の修理をするために呼ばれたので、ドックへ行く必要があるのです」
「ああ、そうでしたか。ご苦労様です」
背を丸めて立ち去ろうとするバーマン牧師にわたしは声をかけました。
「この教会は床の減り方が激しいと聞いたのですが、どうしてでしょうか」
彼はいぶかしげにわたしを見ていましたが、一言「神に近いところだからでしょうね」と応えて去っていきました。わたしはその答えを聞いて吹き出しそうになりました。そして、牧師の姿が見えなくなった途端に悲しくなりました。
ドックへたどり着くと塩湖に面した出航ゲートが大きく開いており、なぜか越境船がドックに入らず、その少し手前の塩の上で泊まっていました。甲板にいた牧師がわたしに気がつき手を振りました。どうやら、機関が突然停止してしまったらしいのです。岸に近い場所では塩が固くなっており、それだけエンジンにも負担がかかるので、時折起こる事故です。父の死後、本格的な調整を行ってこなかったツケが回ってきたのでしょう。
わたしは言われるままに船を固定するための板を塩の上に敷いて船までの橋を作りました。すぐに船内から大高師と副高師が出てきました。この辺りでは管々蟲がくる可能性はほとんどなく、この位の距離なら歩いても危険はありませんが、それを試みる者はいなかったようです。船を渡りきった彼等は口々にわたしに礼を言いました。後に残ったのは儀に同行した若い牧師一人で、彼はいわば雑役夫として乗り込んだらしいのです。わたしは船の内部を見せてもらいながらどのように停止したのか詳しい話を聞きました。エンジンの様子を見ながら、儀式についていろいろと質問をします。もちろん、こんな時間に船を動かした理由になんとなく興味を持った、という風を装ったつもりでしたが、なんとしてもすぐにこの船で彼女を救いに行かなければと焦っていたので、芝居をするような余裕はありません。それでも、若い牧師はさんざんこき使われた後ということもあってか、不満混じりにいろいろと今夜行われたことを教えてくれました。
エンジンの故障は思ったよりも深刻で、機関部に詰め込まれた虫は大半が干からびていました。力なく動く脚を見て、わたしはため息をつきました。これを直ちに修復するのは、わたしの技術では不可能でしょう。替わりを注文して運良く見合った大きさの虫がいたとしても、十日以上はかかるはずです。これで船に乗って彼女を助けに行くのは不可能であるという結論があっさり出てしまったのです。せめて船の故障が出発する前であったら、また運命は変わっていたはずですが。
とりあえず今すぐは修理ができないと言うと牧師はあくびをしながら去っていきました。わたしは為す術もなく船内をうろつきました。あるいは父ほどの腕前であれば、例えばハッチの動力の一部をエンジンへ回してとりあえず船を動かす、という荒技も可能なのかもしれません。しかし、間違いなくわたしの技術では無理な話です。
そのとき、気がつきました。船内に微かな音が響いているのです。ブラシをこすりあわせるような音の元を探すと、船室の片隅に陶器の壺を見つけました。目の細かい金格子がかぶせてあります。蓋を開けることはしませんでしたが、薄暗い壺の中になにやら白く濡れた細長いものが絡み合っているのが見えます。管々蟲であることは容易に想像できます。この高価な虫を捕まえては売っているというのは本当だったのだと思いました。エンジン停止で恐慌を来した彼等は値打ちのある虫の存在を忘れてしまったのでしょう。
わたしは家に戻ることにしました。空はすでにうっすらと明るくなっていました。いま、同じ空を彼女が、おそらくは氷の上で見ているのだと思うとやりきれない気持ちになりました。
途中で練習小屋に寄り、彼女のセロを持ち出しました。鈎爪虫でできたこの手の楽器はこうして折りたたむことができるので、楽器を入れる筺も、それほど大きくはないのです。
牧師の話では神子の下に敷かれる氷はさほどの厚さはないそうです。聖者ヌエイエが夜が明ける頃に一人きりで悟りを開いたという伝説にちなんで、神子は誰もいない塩の上で夜明けと共に神に供されなければならないので、その時間には溶けるように調節されているそうです。
荷物をまとめて家を出て教会を避けて北の外れから塩湖に出ました。もうそのときには最初の日差しが町に射し込んでいました。
「なるほど」
探偵は深くうなずいた。
「それが答えですね。越境船もおそらく何らかの痕跡は残しただろうけど、夜間の虫がすべて消してしまうわけだ。あとには真っ白な塩の上に氷と神子が残される。氷が溶けた時点で神子である女性が塩の上を歩き出し、虫にやられるまでの数十歩が塩の上に残ると」
「もう間に合わないとわかったので、わたしはここへ彼女のセロを持ってきたのです。場所がわかったのは、目印として大きなモニュメントが二つ、北のカセツ山脈と東の黄誠団の聖地があるので、その辺りが聖地だと若い牧師が教えてくれたからです」
フィルマンは運指練習の曲を終えた。尻をずらしてセロを抱え直す。素足の足の裏が塩の下からつつかれる感触があった。すぐに彼女から教わった最初の一小節を始める。この曲を教えてくれた時の表情を思い出していた。
「これは『情熱のための赤』という曲です。わたしはこの曲を八小節しか弾けないのです。もう少しうまくなったら、残りを教えてくれると言っていました」
あっという間に弾ける部分は終わった。一瞬だけ休んで、指板を押さえて弓をすべらせる。再びセロの筐体が震え、雪添え言の緩やかな旋律が塩の上に響き渡る。太紐蟲の細かく重なり合った殻から生まれる複雑な音色。
「わたしが最後まで弾けるのはこの曲だけです。これ以外には運指用の練習曲をいくつか覚えていますが。こんな単純な曲を、彼女の情熱に届くように弾くことが可能でしょうか」
目を閉じて大きく弓を動かす。虫にこの曲の美しさがわかるだろうかと思った。この無念がわかるだろうかと思った。
目を開けると探偵がまだそばにいた。
「もうお話することはありません」
曲を続けながら告げると探偵はうなずいた。
「では、僕はもとの道に戻って東を目指すとします。南の町であなたが望んだような事件が本当に起こっているのか興味がありますが」
「さきほどの話は……わたしの想像です」
「教会で不思議な事件が起こっているかもしれないんでしょ? 中庭でなんとか教の偉い坊さんが血にまみれて死んでおり、周りには誰の足跡もないという事件が。あなたが越境船から持ち出して中庭に放った管々蟲のせいでね」
「虫にはすぐに誰かが気づくはずだ」
「そりゃそうでしょう。管々蟲のことをよく知っている人達がいる場所ですからね。まあ、気がついたところで、危険すぎて普通の人は手を出せないんでしょうけど」
探偵が踵を返し、立ち去るのをフィルマンは見ていた。
塩の上の死体。彼女の首から血に染まった虫が飛び出してきた。塩を赤く染めて潜っていく。
そこに転がっているのはもうチルダではない。ただの死骸なのだと思ってしまったことに戸惑った。
彼女と過ごした時間。彼女がここで横たわっていること。二人が出会ったこと。その時間の意味を教えてくれと、問いたかった。
牧師にではなく、探偵に。
白が広がる大地の上を、頼りない足跡が続いている。その先端に小さな点がある。
探偵は時々振り返り、己の足跡を見る。もう人影を判別することはできなくなっていたが、まだ穏やかな音色が風の中に聞こえる。
しかし、それ以外の笛のような音が、幾重にも探偵を包んでいた。虫によって塩の表面に穿たれた穴が、風を震わせる。
ようやく塩の上に杭が並ぶ場所まで戻ってきた。
南へ手をかざす。話に聞いた町が小さく見えた。その一段と高い建物から黒い弔旗が揚げられているのがわかった。
探偵は振り返り、北の彼方に目を凝らした。あの男に旗は見えるだろうか。
やがて探偵は小さく首を振り、杭を頼りに東へと歩き出した。
風に混じって空耳のように、もの悲しいメロディーが響いていた。
いつまでも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
