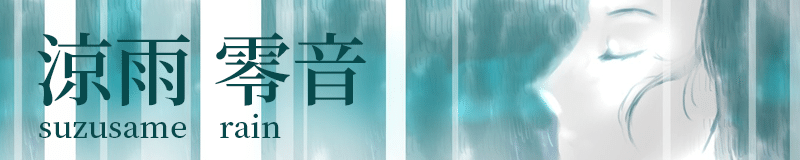カフェとハンダごて
しゃれたカフェスタンドの窓際の席で、用意された電源にハンダごてを挿して使っている女性というのはいったいどんな風に見えるものだろうか。いや、まさにこんな風に見えるのだ。窓越しにその光景を見たオレは思わず足を止めてしまった。通りすぎる人々もみんな冷ややかな視線を送っているように感じる。心なしか、足を止めているオレにまでチクチクと浴びせられている気がする。言葉を失って見ているとハンダごてガールがオレに気づいて顔を上げ、重そうなメガネの向こうからオレを見上げて「おう」と口を動かしながらハンダごてを掲げた。オレは曖昧ににやけて見せてから入口へ回って店に入った。
コーヒーを受け取って窓際の席へ向かう。窓の方を向き、こちらへ背を向けた状態でハンダごてを動かしている奇妙な女は月海(つきうみ)みなも。通称くらげ。くらげは本当は海月と書くのだが、誤解が定着してくらげと呼ばれている。くらげはオレと同じ大学に通う変人だ。妙な縁でオレはこの変人に目を付けられ、こうして休みの日にカフェで待ち合わせとしゃれ込んだりすることになった。念のために言っておくとデートとかそういうんではない。もう一人、これまた妙な女が合流する予定だ。両手に花だって? 花は花かもしれないがきっと食虫植物かなんかだ。
くらげの手元を覗き込むと、なにやら派手な色をした物体のねじを締めているところだった。ねじを締め終えてボタンを押すと、翼の生えたポリスカーらしきそれはサイレンを鳴らしながら回転灯をビカビカさせた。「すごい、なおった」と横にいた小さな男の子が手を出し、くらげは「はーい、なおったよー」と言いながらビカビカカーを渡した。少年の横にいたその母らしき女性が礼を言いながら何度も頭を下げている。
少年が喜んでボタンを押すとおもちゃは「フョンフョンフョン。宇宙パトロール、出撃せよ」などと言いながらビカビカ光った。「それは魔法の道具?」と少年がハンダごてを指さす。くらげが「そうだねえ。きみももう少し大きくなったらこの道具を使えるようになるよ」と言ったら少年は「ほんと」と目をクリクリさせた。
「おまえは、こんなカフェでいったい何をしているんだ」
「ん。この少年のおもちゃがね。壊れて音が出なくなっちゃったんだって聞こえたもんだからさ。どれ、おねえちゃんが見てあげるよ、ってなことにね」
オレがくらげの隣の席に腰を下ろすと、反対側に座っていた親子は立ち上がった。お母さんらしき女性は去り際にも何度も頭を下げながら出て行った。
「で、おまえはそういう道具をいつも持って歩いてるのか」
「あたりまえでしょ。イオタは持って来てないの、ハンダごて」
イオタってのはオレのあだ名だ。そんな風に呼ぶのはこいつらだけだが、オレの名前は西庵(にしいおり)太一(たいち)で、苗字と名前をまたいで略したらしい。
「あのな。千円賭けてもいいが今この店にいる客でハンダごてを所持しているのはおまえだけだと思うぞ」
「ほえぇ。みんなよく不安じゃないな」
くらげがそんなことを言いながらハンダごてのプラグを抜いたところで、親子連れのいた席に狂った風貌の女がやってきた。鮮やかなオレンジ色の髪は左半分が刈り上げで右半分はボブというなにかの間違いみたいな形だ。左の瞼に目立つピアスをしている。女はそこら中の視線を集めながら登場し、コーヒーと小脇に抱えていた機械をテーブルに置いてから腰を下ろした。
「くらげといるとハンダごてってのはスマホ並みに日常的なデバイスなのかなって気がしてくるよね」
風貌にまったく似合わないアニメキャラみたいな声でそんなことを言いながらヘッドフォンを外したこの極端な風貌の女は水無川(みながわ)雫(しずく)。通称はそのまましずく。こいつも同じ大学に通う変人だ。
「ハンダごてってデバイスなのか」とオレが聞くとしずくは「じゃあガジェットでもいい」と答えたがたぶんそういう話でもない。
しずくの持ってきた機械は何やらシンセサイザーの一種で音楽を作る道具だ。前に説明してもらったがオレにはよくわからなかった。しずくはミス・カオスとかいう名前でテクノをやっているらしく、日頃からこういう電池で動くタイプのシンセサイザーを持って自分で作った音を聴きながら歩いている。
「しずくのそのグルーヴマシンも日常的なデバイスに見えてくるよ」と言いながらくらげはハンダごてに手の甲を近づける。ポーチにしまえる温度に下がったかどうかを確認しているのだろう。
「え、まさかみんな持ってないの? みんなよく不安じゃないな」
「おまえらといるとオレはだんだん不安になってくるよ」
ストローに唇を寄せてアイスコーヒーを吸うと、グラスの表面を水滴が一つ滑り降りた。
《了》
--1936文字
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。