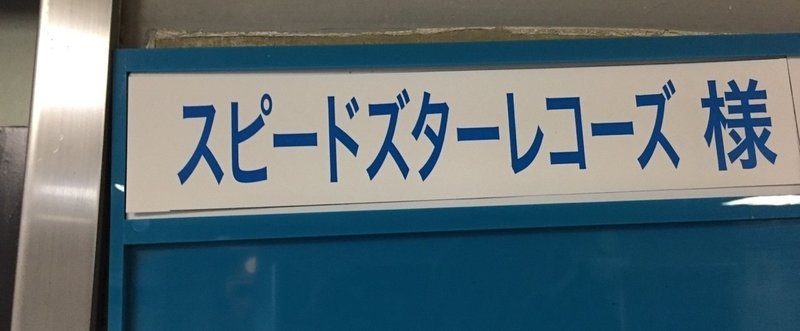
「春を待つ」セルフ・ライナーノーツ
ちょうど20年前、俺や佐藤、くるりオリジナルメンバーだったもっくんこと森信行はまだ大学生で、来るべき同年秋のメジャー・デビューに向けてレコーディングや曲作りに追われる毎日だった。
追われる毎日、なんて書くとなんだかしんどそうだと誤解されるかもしれないが、未来への希望あふれる21歳の若者達にとって、こんなに楽しい時間を過ごすことができる喜びが、ほかの何にも勝っていた頃の話。
音楽的文脈で話すと、1990年代後半はUSオルタナ/グランジブームの末端。衝撃的なデビューを飾ったBECKの「Loser」よろしく、恵まれた時代の「負け犬」が結果を出すことが出来る時代。ブリット・ポップ・ブームに留まらず、オルタナティブ英国産音楽が世界的に再び巨大なものになり、ここ日本においてはバブル崩壊とともに塗り変わりつつある音楽業界に生まれつつあった「ガチのインディーズブーム」到来。我々のような「田舎の非ヤンキーバンドマン」にとって、妙に肌の馴染みがいい時代だった。
話をくるりに戻そう。
メジャー・デビューが決まっていたくるりは、デビュー曲「東京」そして「虹」のレコーディングをその後に行うことになるのだが、他はいかにも当時の大学生バンド風の、ジャンクで完成度の低い、言わばアングラ趣味全開の楽曲がレパートリーの大半を占めていた。そういうのは今でも嫌いじゃないけどね。
洋楽至上主義(つまり当時の米英オルタナティブ音楽至上主義)だった当時の我々やその周囲のコミュニティは、いわゆるJロックと呼ばれていたロック風サウンドの歌謡曲を必要以上に忌み嫌い、メジャー行きに必要となる「売れるサウンドや雰囲気」との剥離が課題だとスタッフから言われていたように思う。
大学生だった我々は、当時のA&R高橋太郎氏、藤井寿博氏と常に意見交換やデモ製作をしながら、様々な音楽性の新曲を数多く試作していた時期だった。その時には既に「ワンダーフォーゲル」や「ばらの花」、「春風」や「飴色の部屋」などの雛型も出来上がっていた。
京都のライブハウスで青春時代を過ごした我々や周囲のバンドマンたちの中には、1960〜70年代の古典ロックやR&Bも一応下敷きとして存在していた。そして、その時代のサウンド・テクスチュアを唯一無比のものに作り上げた日本のバンド「はっぴいえんど」が、日本語で歌うロックバンドにとって、ひとつのロールモデルでもあった。そういった参照点は、同時代的な洋楽サウンドの真似事よりも、少しばかり音楽の中身や技術、センスの問われるもので、当時の我々にとってはハードルが高いものでもあった。
「春を待つ」と題したこの楽曲のデモを録り終えた時、そのような参照点を心の隅に持ちつつ作ったものであるにも関わらず、とても自然に気負うことなく、いい曲が出来た手応えを持つことができた。しかしその後くるりは、より同時代的なアレンジやサウンドの方向性へ向かったこともあり、結局デモを録音しただけで、ライブで演奏することもなくこの曲はそのままお蔵入りすることになった。
録音したデモを聴くこともなく、まるまる20年寝かせた「春を待つ」だが、ちょうどその頃取り掛かり始めていた「その線は水平線」のプロダクションとのリンクを感じ、急遽録音候補曲に浮上した。幸いにメロディーも歌詞も、ギターのコードも頭の中ですぐに再生することが出来た。自分の中では、この曲はとても普遍的(不変的)で、よく出来た曲だということを確信したのは、この録音を始めた昨年末頃である。
ギターのコードもよく知らなかった20年前に書いた曲ではあるものの、殆どオリジナルのアンサンブル構成のまま弄ることが無かった。この曲はもともとよく出来ていたのだ。
中間部の間奏部分のみ、昨年末に新しく書き足したパートである。個人的なテーマは「ノスタルジックなもの」。
どうも、この「ノスタルジックなもの」という価値観は、くるりにとって足枷に映ってしまうことが多いみたいで、どうしても「新しいもの」や「現在進行形の価値観」を中心に置いて考えようとすることが多い。多分、放っておくとノスタルジック過剰に見えてしまう要素に溢れているからだろう。我々は周りが思っている以上に保守的なタイプなのである。
20年も前の楽曲は、ノスタルジー以外のなにものでもない。もし俺が漬け物屋さんで、漬け物だけを使い定食を出す、としたら、こういう風に出す、と考えながら作業を行った。
エンジニア/プロデューサー小泉大輔氏所有の京都にあるSTUDIO SIMPOと自宅で再びデモ製作とヴォーカル録音を開始。最終的に使用したローズ・ピアノ風の音色も俺がMIDIを使ってプログラミングしたもの。そのへんが、20年経って出来るようになった進歩(SIMPO)です。あと、ガットギターも録音した。
その後京都精華大学内のmagi sound studioに移り、ドラム、ベース、ギター類の録音を行う。ベースは「その線は水平線」同様5弦ベースを佐藤が弾いた。エンジニアは谷川氏、ドラムは屋敷豪太さん。
年を跨ぎ、谷川氏のスタジオ、ファーストコールにてリード・ギターのダビング。アンプ、ギター、歪み(トーンベンダーを使用)ともに谷川氏のヴィンテージ楽器と機材をお借りした。ノスタルジック風ではなく、リアルに1960〜70年代の空気を感じるサウンドに仕上がったと思う。
2018年1月末、ファーストコールにて谷川氏の手でミックスダウン。20年寝かせた楽曲は解凍され、ようやく巣立つことが出来るのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
