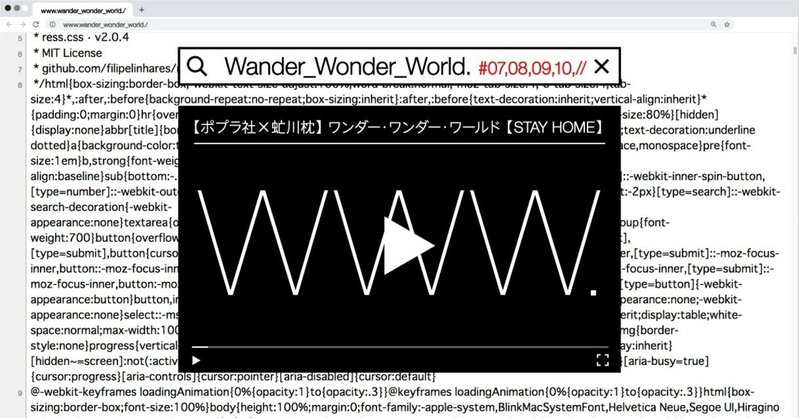
『ワンダー・ワンダー・ワールド』第七回 <07,08,09,10,__>
虻川枕さんの幻の1.5作目『ワンダー・ワンダー・ワールド』第七回(最終回)公開です。公開の詳細や意図については、下記記事をご覧ください。
07
0123456789ABCDEF、そして、10。
数字とローマ字が、頭の中を過ぎる。
「……俺らが二十歳になった頃さ、瀬戸が十六進数の話してたろ? 皆、覚えてるか?」
唐突にその不思議な数え方を思い出した俺は、そしてその場でそのように安藤と堀田に尋ねていた。話題はなんでもよかったが、そのことを思い出したから、喋っていた。
コンピュータが信号を送る際には基本的に、二進数と十六進数の二種類が用いられるらしい。0から9までを使って数を表現する一般的な十進数と違い、二進数は0と1だけを用いて数字が小さい順にカウントアップされていく。011011100101110111、といった具合だ。
一方の十六進数は、9の後にAが続く。AからFまでカウントしていくと、その後にようやく10が続く。10の次はまた11から19が続いて、1Aから1Fへとカウントを上げる。そしてようやく、20になる――。
慣れないゴーグルの中で眼鏡が少しばかりズレていたため、彼らの返答を待つ間、俺は一度それを外して眼鏡を掛け直していた。そうして戻るのとほぼ同時くらいに、ヘッドフォンからようやく声が聞こえる。
「……思い出した。なんか、そんな話してたな。0だのAだのFだの」
これは安藤だ。一方の堀田は、わ、あ、といちいち小さく声を漏らしながらも首を傾げている。「何やったっけ、それ。何となく覚えてるような、全く覚えてないような……」
「たしかあれだ、成人式のときだ。十六進数でカウントすると俺らはまだ十四歳で中二だから成人式になんか行かなくていい、とかいう屁理屈だろ。で結局、成人の日はあいつの言いなりになって、動画撮らされる羽目に」
安藤が経緯を事細かに思い出すと、堀田もまた、ああ! と高い声を上げた。その声は、廊下を反響し、二度聞こえる。
「せや。ひどい話や、今考えると。人の一生の思い出を何やと思ってるんや、あいつ」
堀田の苦笑いは、薄暗い廊下に紛れはしたが伝わってきた。苦笑いでも浮かべないと本当に憎めてしまう。そのくらい、瀬戸はそもそも身勝手な奴だった。
「ん? でもどうして、今、それを?」
安藤に尋ねられ、俺は自分でも何故これを思い出したのか分からないことに気づく。が、きっと自分はこう考えたのだろう、と予想を立てながら、その理由を述べる。
「今回もそんな感じだろうなって思って。きっと奴に巻き込まれる。もしかするともう、巻き込まれてるのかもしれない。そう思って」
「……一理あるな」「一理どころか、百理あるな」
そう二人が同意と失意を同時に見せたところで、俺ら三人は、ある部屋の扉の前にたどり着いたことを確認していた。
瀬戸の残した書き置き。
そこに記されたとあるURL。
そしてあのタイムカプセルの中に仕舞われた、三人分のゴーグルとスーツに導かれるようにして、たどり着いた部屋。VRアース内に隠された廃団地、その404号室。
誰も知らない、一つのウェブサイト。
時期は、世界が秋の香りに包まれ始めた十月のこと。VRアースの世界が配信になってすぐのこと、であった。
*
事の発端は、あのタイムカプセルを埋めるだけの解散動画がいつまで経っても配信されなかったこと、それに尽きる。
正直、俺は四人の誰よりもあの配信の内容に不安を覚えていた。あれで果たして俺らは卒業できるのか、あれを大学生活の区切りと、ワンフルの活動の終焉としていいのか。編集は瀬戸が自らやると言っていたが、その出来次第では公開を止める提案をすべきではないか。
などと悶々しながらその完成報告を待ってはいたのだが、しかしいくら待てども連絡は来ず、動画がアップロードされることもない。やきもきが続く中、あっという間に三週間の日が経過していた。
『さすがに遅すぎる。何やってる』
とラインを送るもそれにも既読がつかず、さらには数時間おきにかける電話も繋がらず、苛立ちが不安へと様変わりし始めた、そのさらに数日後。
普段はあまり使っていないメールの方に一件の通知が現れた。その時点で違和感はあったのだが、差出人はまさかの瀬戸であった。何でメールかは気になったが、それより何より、中身が気になってすぐに開くと。
『ちょっと、家まで来てくれるか? 渡したいものがあるんだ』
といった内容のいたってシンプルな文面が記載されていた。
これまでやきもきさせたことへの謝罪は無いのか、と少し苛立ちはしたものの、その日の放課後には自転車で瀬戸の家まで向かっていた。瀬戸の家に行くことは稀で、学校から自転車で40分ほどの距離の辺鄙な場所にあるのだ。朧げな記憶から道を見つけ、なんとか瀬戸の家までたどり着くと、そのコンクリート打ちっ放しの建物の中から、奴の部屋のチャイムを鳴らす。
が、奴は一向に出てこない。ノックしても、ノブを回しても、現れない。
嘘だろう、と思った。まさかこんな遠くまで呼びつけておいていないパターンなんかあるのだろうか、と良識を疑った。が、あり得るんだから仕方がない。どんどん瀬戸へのヘイトが募っていく中、ふと家の前の洗濯機が目に入った。このご時世でも洗濯機の中に合鍵を入れている輩は少なからず存在した。よく我々が溜まり場にしている安藤の家も洗濯機の中に鍵は入れっぱなしになっている。
もしや、と思い弄ってみると、果たしてその中には、キーホルダーも何もついていないシンプルな一錠の鍵が転がっていた。
どうすべきか。しばしの間葛藤したものの、しかしそもそも俺は瀬戸の友人で、空き巣ではない。それに、特別な事情がある。
「……入る、ぞ?」
声を掛けたのは、せめてものモラルだと思ったからだ。が、鍵を開けて中に入るとすぐ、その道徳は無用だったことに気づく。
部屋はものの見事に、もぬけの殻だった。
普通の部屋にあるはずのベッド、机、椅子、テレビといったものもない。まして、瀬戸が編集に使用しているはずだった、大きなデスクトップ型のPCすら無いのである。
「おい、瀬戸……?」
と声を出してみたものの、当然、何処からも反応はない。まさか、と部屋の内部に上がっていくも、そこにはやはり何もない。唯一あったのは、冷たいフローリングの床に落ちていた、一枚の紙切れ。
『探さないでください。瀬戸綾也』
そう手書きで記されたそれには、ご丁寧に拇印まで押されてあった。
――普通であれば、この状況はどう考えても、夜逃げ、というキーワードしか思いつかなそうなものだ。警察、親。そんな言葉も思いつくかもしれない。
が、その紙を見た俺は、すかさずポケットの中のスマホを手に取り、ワンフルのグループラインを立ち上げていた。そうして部屋の中の写真を一枚、それにその紙切れを一枚撮って、次のように文面を打ち込む。
『瀬戸が、緊急事態っぽい』
と送ってから、あれよあれよという間に場所は変わって、安藤宅。
「……確かにあれは、緊急事態っぽいな」
家主である安藤はキッチンに立ち、背を向けて言った。緊急とはいえ押しかける形になった我々に文句ひとつ言わず、お手製の柚子キムチ鍋に追加する具材を切り刻んでいる。
「せやな」と、コタツ上の鍋を酒で流し込み、堀田は頷く。「あいつ、手書きって大っ嫌いやろ。印鑑の類も基本、押したがらんし」
三人の意見は概ね一致していた。何があったかは定かでないが、何かがあったことだけは確か。そんな憶測だけで、ここに集う理由は十分だった。
「何があったんやろな、あいつ」
「それは、まあ、分からないが……。ただ、何らかの工作があったんじゃないか。他者の手によって」
「他者の手って……なんだ、誘拐、とかか?」
そう言われると、うーん、と首をひねらざるを得なくなる。確かに、瀬戸を誘拐する理由がわからない。
「そもそもさ、あいつの方が呼び出したんだろ? 渡したいものがあるって。なのに、いないってのはどういうわけだ?」
安藤がなおも背を向けたまま喋ると、堀田もゴクリと飲み込んで頷く。
「誰かが偽装してメール送ったんちゃう?」
「ただ、なんていうか、誘拐した側が俺らに知らせるメリットもないよな……。例えば、前にうまく送れなかったメールが、時差で届いたとか?」
「いや、時間の刻印は届いた時間通りだった……」俺は喋りながら、ふと、あるアプリの存在を思い出す。「が、そういえば、時間差でメールを送る機能があったな。どのメールアプリだったかは忘れたけど、前もって送信しておけば指定した日付に届く、とかなんとか」
なんかのネットニュースで読んだ知識だったが、例えば教授に寝ずの番で仕上げたレポートを送って、そのあとぐっすり眠りにつきたいときなんかに便利そうだな、と思った記憶がある。それをそのまま言うと、なるほどな、と安藤が頷いていた。
「とすると……。やっぱりあいつは誰にも邪魔されず、俺たちに確実に何か伝えたいこと、あるいは渡したいもんがあって、こんな手間を……?」
安藤がそう言うと、一人でに首をかしげた。確かに何もかも、推測この上ない。
「案外、部屋にうまく隠されてたんちゃう。瀬戸の、その渡したいもんって」
「いや、部屋にはなかった。隈なく探したからな」
と俺は喋りながら、しかしまたあることを思い出してもいた。心の中の瀬戸に、思考した? と問われた気がしたのだ。
言われた通りに思考してみると、違和感がないわけでもなかった。そもそも、誘拐した人間はこんなに回りくどいことをするのだろうか。そもそも瀬戸は、こういう企み事が好きな、仕掛ける側の人間だったはずではないか。
どこかに違和感が隠されている気がして思い返す。
するとふと、ある一つの光景が蘇った。それは夏の夜の、校庭での俺たち。
「……隠されたとしたら、あの中かもしれない」
半端になった言葉の続きを言うと、二人が手を止め一斉に目を向ける。「あの中?」と割れた俺はわずかに緊張しながら、その閃きを口にする。
「タイムカプセルだ。だって、俺らの動画が今からバズることなんかまずありえない。なのに、あいつは絶対、掘り起こされるって自信満々だった。もしかすると……」
そこまで言うと、二人には全て伝わったのだろう。各々が目を配り、同意するように。
「……それな」
いかにも軽妙な口調で、頷いていた。
*
そうして我々はあのタイムカプセルを探すべく、酒気帯びのままに校庭に忍び込んでいたのだった。その地に埋めてから、たったの一ヶ月弱。かの【史上最強のタイムカプセル】はその持ち味をここぞとばかりに潰される形で、新品同様の姿で掘り起こされることとなった。どの場所に埋めたかも思い出せたし、これといった苦労もなく、サクサクと。
掘り起こされた四人分のタイムカプセルを一つずつ開封していくと、俺はフィギュア(どれかは未来で高値で売れるかと思った)、安藤は思い出の写真、堀田はエロ本と缶詰と、定番の品が続々と出てきた。も、当然、何の感慨があるはずもない。
「……こりゃ相当のもんが出てこないと、苦労の元が取れねえぞ」
安藤が不満を漏らしつつ、最後の一つの箱を開封する。
その中から出てきた物品こそ、まさしく、VRスーツとゴーグル。それがそれぞれ三つ、つまり三セット、入っていた。
「ん? 何や、これ」
とは言え、二人はその見慣れぬ物資にピンと来ない様子で首を捻るばかりだった。かく言う俺にも見慣れないものではあったが、しかし唯一、見覚えもあった。
「……VRアースのスターターキットだな、きっと。たしか一週間前に16カ国でリリースされた、って聞いたことがある」
「VRアース? 何やそれ」
トレンドに疎い堀田がそう言い、俺もうろ覚えではあるが、VRアースについての解説を加えた。ネット空間を仮想現実に落とし込んだ、歩けるネットブラウザ。たしか独自にネットで記事を発信している会社のプラネットウェブで読んだ知識だったように思う。そしてそれを受け売りのままに、垂れ流す。
「……ん? でも、おかしない? それ、今月リリースやったんやろ。何で、先月の瀬戸が持ってるんよ。しかも、三着も」
堀田が、そのタイムカプセルの中身に関して最も不思議な点をズバリ言った。
「そうなんだよな……。ただ、これはやはり俺らに渡したいもの、ってことだと思う」
「何で、そう思うん?」
「三着ある意味はそれしかないだろう。俺と、お前と、安藤の分ってことだろ?」
そんな推測に、ああー、と堀田が長い相槌を打つ。
すると今度は、箱の中身をなおも弄っていた安藤から、あ、と短く声が漏れた。
「ん? どうした?」
「いや、これ」
と、そのタイムカプセルの隙間に挟まっていた封筒を取り出し、その中身を開く。中には、PCで打たれたテキストファイルを印字したようなもので、一目でURLと分かるものと『ここの404号室』という記載が記載されてあった。
よく見るとそのURLの中には【sakura_web】という文言が含まれている。
「このサイトに、VRアースで潜って来い……ってことだろうな。きっと」
「……ほんま、説明の少ないやつやで」
そう言い合うと、三人でため息をつき、そして苦笑いを浮かべていた。何故ならやはりこれも、いつものことであったからだ。
――と、そうして、今に至る。そういうわけなのだった。
「ここだな。瀬戸の言ってた、404号室ってのは」
道しるべのような瀬戸の仕込みによってたどり着いたその扉を前にした俺らは、しばし、動きを止めていた。
各々が躊躇いと戦いながら、心の準備を整えているように思えた。
「……みんな、ごめんな。忙しいのに」
俺は思わず、謝っていた。
「は? 何でお前が謝るんだ?」
「そんなん、皆、一緒やろ」
案の定、そのように返される。見切り発車で喋り始めてしまったことを後悔しつつ、こうなってしまった手前、何も言わないわけにもいかなかった。
「いや……。ちょっと今の状況、嬉しく思ってしまった自分がいるから」
そう言うと、途端、想いが溢れてくる。
「こうして集まれたこともそうだし、何かが始まりそうだってことも。ワンフルは、まだ終わってなかったんだなって」
溢れて来た想いは、そのまま俺の記憶の蓋をこじ開けていた。
ただしそれは大学での楽しかった記憶、などではなく、もっと過去の記憶だ。しかも高校までの青春の風景とか、部活での汗みたいな爽やかなものでもなく、それらほとんどに親の姿があったから虫唾が走る。
俺の親は基本的に、俺が学校で友人を作るのを嫌がった。
親にとって一人っ子である俺は未来の働き手であり、家の継ぎ手であり、介護の面倒の担い手、でしかなかった。そこで邪魔になるのが友人の存在だったのだろう。あの子とは付き合わない方がいい、レベルが違う、あの子の家は複雑だから関わり合いにならない方がいい。そういった文言を並べたてられ、俺がせっかく仲良くなりかけた人間とは引き剥がされてしまう。
友達が欲しい。
そう言うと、決まって親(特に母親)は言った。
「もちろん、友達を作るなとは言ってない。一生涯恥じることのない、いい友人を作るといいって話よ。そのためにはいい学校に入り、いい仕事につくこと。……そう思えば、自ずとあなたが今すべきこと、見えてくるわね?」
「……勉強を、頑張る、こと」
そう呪文のように唱えさせられると、あっという間に洗脳は出来上がっていた。
まあ、俺もぼーっとしすぎだったように今ならば思うが、考えを否定され尽くした挙句に出来上がるのは意思のない人形だ。中学時代までは勉強一筋、親が嫌いそうな人間との交流は基本的に断ち、交流があったとしても勉強の時間を奪わない、俺に似たような境遇の人形ばかり。衝突も、思い出も。何も生まれやしない。
が、高校に入ってから受験勉強に明け暮れること、およそ二年。電車に乗って塾へと向かう最中に、ある大学のオープンキャンパスの広告が目に入った。
『君のカラーは何色?』
普段であれば、そのような広告なんか鼻で笑っていた。親がそうだからだ。こういう名の知れない大学が必死になって宣伝しているのを見ると、毛嫌いしたような反応を見せる。しかし、その時ばかりはふと、自分の世界があまりにモノクロなのではないか、という気になっていたのだ。外の世界はもっとカラフルなのではないか、と、そんな風に。
ひょんなことから洗脳が解け、ぴょんと芽生えてしまった自我を抑えることはできなかった。
気づくと俺は、志望校の偏差値はかなり落ちるがその広告の大学に行かせてほしい、と親に正面切って訴えていた。親の教えから背いた行為だとは重々承知していたし、案の定、顔を真っ赤にした両親は懸命に説得してきた。そうなる事は容易に想像できていたため、行きたい大学に行かせてくれなければ進学後は縁を切る、と最終手段として用意していた脅しを投げかけると、これが効果ありだった。涙ながらに、何のためにここまで育ててきたと思ってるんだ、とかなんとか言ってきた。
それを言われた時は、まあ、白けたものだ。養ってもらったことへの感謝はあるが、育ったとはちっとも思っていない。勉強ができるだけでそれ以外のこと、心の方は全く、育っていないままだったから。
結局、俺は白けた心のおかげで意見を曲げずに済み、粘り勝ちできたのだ。自分の大学を、自分で選ぶ権利を得た。当たり前のことのようにも思えるが、俺の人生の主導権を取り返した。結果、今、目の前にいる安藤、堀田、それにここにはいないけど瀬戸。この四人で過ごす大学生活を送れたのである。
――みたいな記憶を、脳裏に、はっきりと浮かべながら。
俺はこの扉と向き合っている。
当然、こんなようなことは口には出さない。だって彼らに気を遣われたいわけでも、同情されたいわけでもないからだ。
ただ、今まで通り、普通に、一緒にいたいだけ。ただそれだけなのだ。
「大学生活は……いや、学生生活は俺にとって、ワンフルだけなんだよ。しっかり、卒業したいんだ、こいつを」
長く続いた沈黙の末に、俺はそう言った。
絞り出すような声だったが、それが何を意味するところか深く突っ込む野暮なやつはやはりいなかった。あるいは単純に気づかれてなかっただけかもしれない。VRの利便性がまさかこんなところで発揮されるとは。そう思いながら、俺は静かに鼻を啜った。
「ま、とりあえず……。行ってみっか」
安藤がそう言ったところで、ドアのチャイムを鳴らす。ピンポーン、と音が鳴った。
かくして、俺たちの幕切れの、その幕開けが訪れたのだった。
が、これがまさか果てしなく無謀な計画になるとまでは、このときは誰も思いもしなかったことだろう。
なんせただの大学生ユーチューバーの俺らが、このインターネットの世界を牛耳るボス相手に、歯向かうことになったのだ。
俺らの人生に、勝手に。
見たこともない色を足してくる、あの瀬戸という男に。
巻き込まれたばっかりに。
08
404号室のチャイムを鳴らしても、中から人は出てこなかった。扉のノブに手を掛けると、不用心に鍵は掛けられていなかった。俺らは恐る恐るその一歩を踏み出し、薄暗い部屋の中で。
奴を見つける。
四年間ほぼ行動を共にした色白の、細っちょろい男。見間違うはずもないほど瀬戸は瀬戸らしく、その部屋にポツンと佇んでいた。
奴の変わらぬ顔が目に入ると、途端に拍子抜けしたことを覚えている。何かに巻き込まれていく予感、強張った心。それら全部無駄に終わったやんけ、と攻め立てたくなる。
「なんや瀬戸。いたんかい……」
とりあえず、俺はそう言ってみていた。
も、どうにも様子がおかしい。瀬戸は俺らの姿に気づいても、その声掛けにも無表情のまま、一向に口を開く気配がないのだ。面倒な手順を踏んでまでここに呼び出したのはそっちのはずで先にまずは何か一言あるはずやろ、とこちらもこちらで黙り続ける。結果として数秒、読み合いのような沈黙が生まれ。
「君らが、ワンダーフールズ……か。いかにも、という感じだね」
やがて、瀬戸はそのように言った。
いや何を今更、いやお前もやろ、と様々なツッコミパターンが浮かんだが、妙にこわばった空気が気になり、何も口には出せない。
「お前、何がしたいんだ?」
隣の真壁が、不意にそう問いかける。同じことを思っていた俺らは、訝しい気持ちを込めた視線を瀬戸に送る。すると、奴は。
「……そもそも、僕は瀬戸じゃない」
と、そんなことを宣ってきたのだった。
「あ? どっからどう見ても、瀬戸だろお前」
「残念だけど違う。僕は野滑だ。瀬戸に残された、ネット上を彷徨う垢。それが僕だ」
「の、な、め?」
感触の悪い語感のその名を口にしてみたとて、ピンとこない。そもそも、聞き覚えがないのだから仕方がない。
「瀬戸は、このインターネットの世界の未来を、君たちに託した。その手伝いをガイドするよう、僕に計画や君たちの情報をインストールした。その鍵が、リドルの残した最後の南京錠だったんだ」
「……さっきから何言ってんだって。何、アニメにそういうのあんの?」
「いや、俺の知る限りはないが……」真壁も戸惑っている様子だ。
困惑の表情を浮かべる俺ら三人に対して、野滑は少しばかり怪訝そうな顔を向けていた。そして、まさか、と続ける。
「君たち、瀬戸から何も……説明を受けてないのか?」
――やりやがったな、あいつ。
これは俺の心の中の声なわけだが、恐らくは二人も同様に思ったことであろう。ため息をつき、頭を振り、呆れ返る。
「とにかく、お前も瀬戸に巻き込まれた、ってことは分かった。一旦、ゼロから説明してほしい。……俺らは今、何に巻き込まれてるんだ?」
事態を収拾さすべく、安藤がそう問いかける。と、野滑も困惑の色を浮かべつつ、ゆっくりと頷き、口を動かす。
そうして、俺らは全てを、知ったのだ。
野滑のこと、それからリドルのこと。ISE社のこと、瀬戸がハッカーだってこと、知ってしまったダグラスの秘密のこと。瀬戸がエージェントに追われてる、ということ。
インターネットの世界が。そして人類が。あるいは地球が。
大ピンチだ、ってこと。
*
正直に言って、野滑の説明は五割も理解できなかった。俺の五割は正味二割のようなものだ。説明が終わったあと、この中で最も賢い真壁に聞いても、やはり五割も理解していない、とのことだった。ちなみに真壁の五割は俺にとって八割だから――、と、まあこんな計算は何の意味もない。
ただし唯一、俺らがその説明を聞きながら共通して認識したこともあった。俺たちは、どうやらとんでもないことに巻き込まれ始めている、ということだ。
野滑からその計画を聞かされ終わると、その壮大さに言葉を失くし、ポツポツと独り言のようなものを漏らしながらほとんど黙していること、十数分が経過していた。
そんな中、安藤が。
「ひとまず、訳はわかった。だから……今日は、ここで解散にしないか」
と唐突に言い出してきて、沈黙が破れた。その予想外の提案に、俺も真壁もまた野滑ですら、え? と声を揃えて上げた。「これからが、大事なんじゃないか?」
「いや、まあそりゃそうなんだけど……あんまり色々ありすぎてさ。正直疲れたろ、俺らも野滑も。一回、各々が消化して考える時間を設けたらどうかなって思って。真壁、記録はしてあるか?」
「それは、まあ、バッチリだが……」
と真壁が、控えめに野滑に目を配る。
俺ら三人はまだしも、野滑は瀬戸の振り回しについては初体験のはずだ。案の定、混乱した面持ちを浮かべながら、言う。
「僕も確かに少し、休みたいかもしれない。まだ……全てを飲み込めないんだ」
そう漏らすと、その心中は察するに難くなかった。つまるところ、一人になりたい。そういうことだろう。
「じゃあ決まりだな。……いいよな、堀田」
そう安藤に名指しで尋ねられた俺は曖昧に、ああ、と答える。
その時、発声とほとんど同じように、ああ、と内心で合点がいった。実はずっと、安藤には見透かされていたのだろう。
――この中で俺が、今回の計画に最も乗り気でなかった、ということを。
俺の家庭環境は、あまり自覚したいもんでもないが、それなりに複雑だった。
酒飲みでろくでなしだった親父の元を離れ女手一つで中学まで俺と妹を育てた母さんは、同じくバツイチの商社マンと再婚。間もなくめでたいことに二人の間に新たな子供を授かったわけなのだが、すでにそん時には四十オーバーの高齢出産。無事に生まれた子供はまさかの多胎児、しかも三つ子であった。
「五人兄弟って……このご時世、ビッグマミィやん」
呆れやら興奮やら照れやらがないまぜになった結果、俺は、そんなふざけた言葉を出産直後の母に投げかけた覚えがある。三つ子はこの世のもんとは思えんほど、可愛かった。
もちろん新しい父親の稼ぎだってそこまでいいわけでもなく、母も仕事を辞めざるを得なくなり、収入は激減した。困窮を極めた経済状況の中、俺は夢だった上京に一つのハードルを課せられた。それが家賃光熱費生活費などすべての生活費をバイト代で賄うこと、そして大学は絶対に四年で卒業し、就職し、奨学金は自分で返済していく、ということ。
「あんたには悪いと思っとる。せやけどこの子ら食わさなあかんやろ? 落ち着いたら、キャッシュバックはするつもりやから」
その言葉を聞かされた時はすでに俺も反抗する気なんか残っていなかった。何より三つ子が皆、可愛らしくお昼寝中だったからだ。
とは言え、バカな俺は大した大学に入れるわけでもなかった。そこで関西圏から懸命になって探したどり着いたのが、この所沢学園大学である。トコガクは偏差値の低い芸術系の私立大学で、何だか暇そうだな、バイトしながらでも卒業できるかもな、と別に大して取り立てたセンスもないくせに、そんなことを思ったのがキッカケだった。
私立とあって学費は高い。だがその分、特待生制度が充実していた。推薦から入って一定(それでも標準低め)の学力があれば誰でも特待生になれ、学費はそのランクに応じて減額免除される。倍率も低そうだと判断した俺は将来のことを考えトコガクを目指し、低めと言われる標準を軽々超えるため、それでも猛勉強した。奨学金が減れば、その分。
俺と同じ思いをするだろう妹に、少しでも援助ができるのではないか――。
と、そう思ったのだ。泣ける兄心だな、と我ながら、思う。
*
野滑との初対面、からの怒涛の説明があった日から、あっという間に六日が経過していた。
秋口の大学四年生にとって、六日なんか秒で過ぎる。バイト、面接、授業、バイト、卒論、バイト。あんまり好きじゃない言葉だが、二時間しか寝てないわー的な日々で、冷静にその件について考える暇もなかった。
なのでその日の夜勤バイト明け、帰路につく俺のところに妹から電話の折り返しがあってつい出てしまってから、しまったな、と心中で苦々しい気持ちになっていた。昨日電話した時は勢いで掛けてしまったのだが、まだ計画に伸るか反るかは決めてなかったのだ。
「……もしもし? お兄ちゃん、何か用?」
当然、妹にそんな事情が分かるはずもなく、明らかに不審そうに尋ねてきた。
しばらく俺は「いや元気かと思って」だの「学校はどうだ」だの「子供たちは元気か」だのと、まるでらしくない会話を続けた。妹もより不審に思ったのだろう、瞬時に察してすかさずこう言う。
「わかった。また、金ピンチなんやろ?」
そう問われると、苦笑いが止まらなくなった。
実は今までにも給料日前の二度ほど妹をこっそり頼ったことがあり、確かにその時の俺はこんな感じで、しどろもどろと話題に切り込むのをためらっていたのだった。お年玉をしっかり貯蓄するタイプの妹に対して、つい付き合いで使ってしまう俺、そりゃこんな風に言われてしまうのも頷ける話だろう。その問いかけには、いつもお世話になっています、その分のお返しは就職してからたっぷりと、などと債務者のように答えていたが、今回はそうでない。
情けない兄ちゃんからは、もう卒業したかった。
「まあ、今回も要はその手の話なわけやけど……ただ今の話ちゃう、将来の話や。兄ちゃんな、もしかすると就職できんかもしれん」
本題に切り込んでみると、え? と妹の方から、意表を突かれたような声が上がった。
「……何? 就活ってやっぱ厳しいん?」
「いや、内定はな、たんまり出とる」ここは敢えて嘘をついた。十一月の段階ではまだ内定はゼロで、内々定的なのが一社あるから完全な嘘ではないが、それでもたんまりは嘘だ。あまり妹を心配させたくない。情けなくもあるが、やはり兄心でもある。
そんな兄心から一瞬、俺は口ごもった。ここで電話を切れば、変な電話だったな、と思う程度で妹は片付けてくれることだろう。
しかし、俺は。
それでも、俺は――。
「兄ちゃんな、これから茨の道に……いや、茨の寄り道に差し掛かっとるんや。兄ちゃんな、その寄り道の先で待っとる人に、どうしても会いたくてやな」
抽象的なことしか言えない(そもそも分かってない)この状況だが、概ねそんなところである。要は会いたい人、助けたい友達がいるから、それで就職できなくなってしまうかも。問題は至ってシンプルだった。
そんな事情は、何とか伝わった、のかもしれない。妹は黙って俺の続きの言葉を待っていた。俺も、なんとか続ける。
「せやから俺な、本当は就職してから、お前にキャッシュバックするつもりやってんけどな、それが、どうにもな……」
「……嫌や」
妹は我慢しきれないといった様子で、俺が言葉を詰まらせている間に割り込んでそう言ってくる。なおも黙っていると、妹は、自分のターンと言わんばかりに反撃を並べ立て始めてきた。
「母ちゃん大変そうやし新しい父ちゃんは頼りにならんし古い父ちゃんはもっと頼りにならんし。うちは大学生のうちにいい旦那囲って結婚して、普通の家庭築きたいんや。それがどれほど大変なことか、よう知っとる。そのためにも結局は金が必要や」
「……ほんま、昔からちゃっかり者やな、お前。尊敬するわ」
「せやからな、兄ちゃんに借金も作りたないねん。兄ちゃんかて結局は頼りにならん。兄ちゃんが就職せんでも、うちはうちで勝手にやる。そう決めとったんやわ、前から」
「うん……。ま、せやな。やっぱり寄り道はせんと、兄ちゃん地道に……ん?」
とまで言ったところで、言葉がまた詰まった。妹の言葉の先を勝手に予測して、俺は口走っていたのだが、しかし、今。
妹は、何と、言った?
「兄ちゃん、勝手に生き。ただし大学出たら、もうお年玉せびんなよ。兄弟関係なく、それはクズやで。ほなな」
そう淡々と言い放つと、妹はこれ以上何も言い返させまいと思ったのか、電話を切った。そのあと、俺は徹夜明けのテンションも相まってかつい、ちょっとだけ、泣いていた。
この涙については、当然、誰も知らない。妹も、当然あいつらも。俺も、絶対に知られたくないから言うわけはなかった。単なる強がりだが、俺は、ただ。
大学の最後まで、愚か者でありたかった。それだけやった。
09
「待たせたな! ワンフル、本格再始動や!」
と、堀田が威勢良く言って部屋に入って来たところで、俺と真壁の不安そうだった表情がパッと華やぐ。
正直、真壁は今日の集合に来るだろうな、と俺は見越していた。この部屋に凸する時から真壁は何となく心構えをしている風なことを言っていたし、何よりも真壁はワンフルの再始動を望んでいる様子だった。
問題は堀田だった。
院に進む真壁より、留年確定の俺なんかより、就職を控えている堀田にはこの計画は荷が重いはず。詳しいことは知らないが、バイトばかりしているのは実家の金銭面に難があるようだ。そんな彼にとって就職は必須だろうことは想像するに難くなかった。俺らとしても、彼の足を引っ張りたくはない。最悪、この計画は俺と真壁、それに瀬戸の分身である野滑だけでも成立させることはできるかもしれない。そう思い、一週間の日を開けようなどと提案したのである。
だからこそ、堀田が来た時の喜びは一入だった。前段にあれこれ言ったが、真壁と堀田、もちろん瀬戸(野滑)も。この四人で、俺らワンダーフールズの最後の活動としてダグラスに立ち向かいたい。そんな風に考えていたのは、誰しも同じ想いだったように思う。
「……うし。じゃ、ミーティング、すっか!」
そう場を仕切るように言うと、二人は静かに、うし、と言った。「野滑、補足あったら言ってくれな」と言うと、野滑は少しばかり不安そうに、ゆっくり頷いた。
「まず、ダグラスに立ち向かうために残された武器は二つ。看板と、爆弾だ」
そう言うと、俺らは野滑が瀬戸から託された秘密の武器、その看板と爆弾をまじまじと眺める。武器はベッド下に隠されていた。
野滑曰く、この看板(つまり広告)の中にはウイルスが仕込まれているらしい。これにアクセスし、リンク先でアカウント名やパスワードを登録した者はアカウントを乗っ取られてしまい、以降そのVRアースの世界にログインできなくなってしまうのだ、という。
「まあ、よくある方法だな。言葉巧みにリンクを踏ませて、情報をうまいこと抜き出して、ウイルスに感染させると。ただこんなので引っかかるのは相当ネットに疎い奴だけでもあるだろうな。心得た人間ならほとんどこの手のウイルスには引っかからない」
真壁が、野滑が以前に言ったような内容を反芻する。そのことは俺も堀田も承知の上で、しっかり頷く。
「だからこそ、爆弾があるわけやな。ISE社の心臓をドッカーンってやって、この世界をしばらくの間、ハチャメチャにする、と」
今度は堀田が、瀬戸の言った内容をだいぶ噛み砕いて繰り返した。が、いざ言われると、うーん、と唸ってしまう。
「調べてみたが、ISE社のオフィスはネット上に隠されているようだ。普通の人間には見つけられない。それこそ、凄腕ハッカーくらいにしか見つけられないようだぞ」
「……その辺は安心してくれ。僕は、瀬戸に仕込まれたハッキングスキルがある。ある程度、その所在地のアタリはついてる」
野滑が言うと、俺らは次々に歓喜の声を上げた。
「実は、リドルにハッカーズスラムという場所へ連れてかれたんだ。そこなら、きっと安全にハッキングが出来るのだろう。瀬戸の拠点にも何か手がかりが残されているはずだ。……それは、調べておくよ」
野滑の発言は実に頼もしい。瀬戸のお膳立てもなされているようだ。
「……ただし問題は、どう爆弾を仕掛けるか、やな。一筋縄じゃいかんやろ」
そう堀田が次の疑問をまとめると、これにも野滑が、それも、と発声する。
「それも、僕がやろう。瀬戸も、僕に実体がないからこそ役に立つ、と思ったはずだ。僕を目覚めさせたのは、むしろその狙いが大きい気がする。爆弾を仕掛けるには、正体不明のアカウントの方が効果的だ」
「ああ、なるほど。ただ、実際に潜り込むなんて可能なのか?」
「それは正直、分からないけど……。例えば、君たちに囮になってもらって、奴らの注目を集めてくれればいけるかもしれない。例えば、社内に忍び込んで捕まり、その裏の裏を僕が掻く、とか」
野滑は、最初から俺らをリードし、そして自ら進んで危険な任務を請け負うようになっていった。その心算は不明だったが、少なくとも悪巧みの様子は感じられない。あくまで生まれた目的を達成するためのなりふり構わない様子はなおも心強く、そして一方で、俺に一抹の不甲斐なさを抱かせる。
――なんだ、俺たちは?
ほとんど任せっぱなしじゃないか、瀬戸に、野滑に頼りきりで。奴の危機だってのに、何にもできやしないで、と。
「あとは君たちがどうやって注目を集めるか、か。テロリストのフリでもすればそれなりに効果はあるかもしれないけど、それは君たちにはリスクが大きいか。何か他にいい突入の案でもあればいいが……」
そう野滑が問題点を挙げたところで、不甲斐なさに打ちのめされていた俺の頭には途端、一つの豆電球が浮かんでいた。もちろん比喩だが、実際薄暗い部屋がその時ばかりは輝いたように見えたのだ。
「それについては、いい考えがあるぞ。野滑」
そう言うと、三人が俺の顔をじろっと見る。その視線に快感と緊張を覚えつつ、俺は一度、咳払いする。
「野滑。君は知らないかもしれないが、僕らはとても有名な……影響力のある、ユーチューバーなんだ」
「ユーチューバーだってことは知ってたが……なんだ、君たち有名なのか?」
野滑が尋ね返してきたところで、いやいやいや、待て待て待て、と慌てて二人が取り押さえに来る。そのまま部屋の片隅にまで連れてこられると、野滑には聞こえない声量での緊急会議が始まる。
「お前、何いきなり言うとんよ……! 俺らなんて無名も無名のユーチューバーやろ」
「バカ、そんなのまだ分かんないだろ。こっからバズる可能性だって全然ある」
「そりゃ、希望を捨てろ、とまでは言わないが……。お前だって身に染みて分かってるはずだろ? バズることの、その難しさが」
真壁にすらそんなことを言われる始末の俺だったが、しかしもう後には引けない。いや、引きたくなかった。
「……お前ら、本当に、このままでいいのか? 野滑に全部任せて、俺らは何も泥を被らないでいくつもりじゃないよな?」
そう言うと、途端に図星を突かれたように、二人は黙った。恐らく、二人だって不甲斐なさは覚えていたはずだ。ただ、あまりの事態の大きさに、下手なことはできないから黙っていただけに過ぎない。
多分、全員が気づいていたはずだ。俺らにとって唯一の武器は、俺らがユーチューバーだってことだ。
ユーチューバーは、ユーチューバーなりの戦い方をすればいい。
「これは、俺らに残されたユーチューバーとして逆転できる、最大のチャンスでもあるんだ。この計画に、俺は是非とも動画配信を絡めたい。ユーチューバーはユーチューバーらしく、動画配信で悪を打ちのめすべきだ」
そう言いながら、俺は正直、自分でも何を言っているのか分かってはいなかった。ただ、頭に浮かんだ漠然とした野望は、沸々と脳みそを侵食していく。
というかもうとっくに、そうするしかないようにすら錯覚していた。
「……どうした。何か問題でもあったか」
しばらく仲間外れにしてしまっていた野滑が、沈黙の隙を突いてそう割り込んでくる。心配そう、あるいは不安そうな様子は見て取れた。だが、悪いがこれは俺らの問題だ。有無を言わせるつもりはない。
「いや、野滑は気にするな。さっきからアイデアが止まらないんだ。つまり、注目の方は任せろ」
これはもちろん強がりで誤魔化しで、他の二人は精一杯無言で首を横に振り続けて否定を表してもいたが、野滑はその言葉のみをひたすら鵜呑みにした。
「なら、まあ、注目を集める手立ては君たちに任せよう。頼もしい」
そう言われると、自分が何かとんでもないことを言ってしまったのでは、と悔いる気持ちもなくはなかった。もちろん、後の祭りとはまさにこのこと。となればブラフよろしく、頷くより他にない。
問題ないことを理解した野滑は安堵した表情を浮かべ、その主たる武器となる看板や爆弾のチェックに入り集中し始める。それを待って、真壁が。
「……具体的には? 策はあるんだろうな?」
と、なおも小声で尋ねてくる。真壁は我々の中で最も現実的な男で、だから詳細な部分は彼を頼っていた節があった。当然、俺は全くのノープランなわけで。
「それはもちろん、今から考えて、だな……」
そんな風に言葉を濁していたところで、しかし、首尾よく。
ガチャガチャガチャ!
と扉のドアノブが何度も回される音が聞こえ、俺らの会話は一斉に止まる。会話どころか、呼吸すらも止まりそうになったほどだ。ひっ、と小さく声を挙げた堀田に対して野滑は人差し指を自らの唇にあてがい、黙るよう指示を出していた。だから声も出せず、そのポルターガイスト現象のような音だけを黙々と聞き続けなければならなくなる。
それが数秒、数十秒続くと、今度は。
「いるんでしょ……! ねえってば!」
そんな声が何度か聞こえるようになり、それに比例して扉はガチャガチャドンドンと、もっともっと手荒く扱われるようになる。その恐怖の時間はおよそ二分ほど経過し、やがて一筋のため息の音が聞こえると、音は途端に止み。かと思えばそのまま、スタスタ、と帰っていく足音が聞こえたのだった。
それすらも消えたところで、俺らは一斉に呼吸と、言葉と意識とを取り戻す。
「何やねん、今の……。こっわ……」
「毎日、この時間になると来るんだよ。どうやら野滑時代のファンらしい」
他人事みたいに言うな、と思ったが、野滑にとってはまさしく他人事なのだろう、とも理解する。彼にとっては目が覚めてからの自分が自分であり、それまでの人形であった自分などもはや無関係のものなのだろう。はた迷惑そうな表情から、それが窺えた。
一方、堀田と真壁は少なからず、不満あるいは嫉妬を抱いているような表情を見せ。
「ファンなんて、いたことないから分からんわ。気持ちが」
「まあ、ファンがいると大変だ、って話は聞いたことあるぞ。少しでもファンの期待に反した行為を取れば、やれ昔の方が良かっただの、やれ嫌いになりましただの、急に叩き始めるらしい」
「あーはいはい。自演乙、とかな。やとしたら俺らファンいなくてよかったわー、ほんま」
などと、見苦しい会話を野滑の前で繰り広げる二人――に対して。俺は、すかさず。
「それだ! 自演、自作自演だよ!」
何度も繰り返したその言葉に、どしたん、と堀田が尋ねる。興奮でほとんど聞こえなかったが、アイデアが止まらなく溢れてくる。薄暗い部屋の中をウロウロと歩き回りながら、溢れる興奮を押さえつけるように地面に目を向けることにして、そのアイデアを順々に吐き出していく。
「まず、第一段階として野滑を有名にする。最強のサイバーテロリストとしてウイルスをばら撒き、やがてISE社へ爆弾を仕掛ける、その予告もしてもいいかもしれない。もちろん垢ってことは伏せて、一人の人間として、それを行う」
「でも、そんなんしたら身動き取りづらくならん? 黙っといた方が得ちゃう?」
「いや、それは敢えてだ。予告されれば、ダグラスも犯人逮捕に躍起になるはずだろう。が、そんな一朝一夕には犯人は見つからない。何故なら野滑はアカウントでデータで、実体がないからだ。ダグラスが同じような存在だったとしても、まさかこの世界に二つも同じ存在がいるとは夢にも思わないだろう」
そんなにうまくいくのか、という疑問は誰しも、俺ですらも抱いたものだが、それ前提で話を続けなければ先に進めない。突っ切るように口を開く。
「そして、ここからが肝だ。俺らはその、野滑を追う」
「野滑を……? あ、配信で、ってことか?」
「そう。まず、ひょんなことからウイルス犯につながる情報を手に入れ、そこから野滑を追いかける展開の配信を試みる。誰も捕まえられないサイバーテロリストに近づけている様子を見れば、少しは興味を持つだろ」
「なるほど。野滑を有名にして、それを利用して俺らも有名になる、と」
「そうだ。その上でハッカーを雇って、ISE社に凸する配信を敢行する。凸の理由は、まあ、野滑の手がかりを見つけたとか何とか言えばいい。で、俺らが注目を集めてる隙に野滑が爆弾を仕掛けて、この世界を無茶苦茶にする……と、ここまでが第二段階」
爆弾を仕掛けてテロするところで、計画は終わり。そう思っていたはずの彼ら三人は、続きがあることに驚いた様子を見せる。
「第三段階があるのか?」そう尋ねたのは、野滑だった。
「ああ。おそらくダグラスは、VRアースの線がダメになったとしても、二の線、三の線でまた新たなる方法を考えるだろう。根本から奴を止めるには、その正体や目論見を世界中に暴く必要がある」
「ん? その事実を、ネットにアップするんか? 配信で?」
「そうなんだが……恐らくは俺らが喋ったところで、妄想を垂れ流しているだけに聞こえるだろうな。それこそ都市伝説みたいな話だ、視聴者に信じてもらうにはダグラス本人から話させるくらいしないと」
「聞き出す、って言っても……喋るとは思えないがな、ダグラスが。それも一介の、ただのユーチューバーの動画の中で」
「まあ、それは仕向けるしかない。ダグラスをおびき寄せて自然な流れで自白させる、とかな。その模様を隠し撮りし、配信する。そうすればダグラスは、世間的に死ぬ!」
同時に、パン!
と瀬戸の癖を参考に、太もものとこをリターンキーを弾くように叩く。しかし、その手加減がわかってない俺には痛く、VR関係なくヒリヒリする思いを抱く。
その痛みは表情には出さないようにしながら、俺は彼らの顔を順々に見やっていた。さぞかし俺のことをキラキラした目で見ているだろう、さすがはワンフルの参謀と思っているだろう、と期待したものだが、実際は皆。
うーん、と首を捻って納得いっていない、期待はずれの表情を浮かべていた。
「いや、悪くはないんだが……」
「本当に、それが上手くいくんかな……?」
堀田と真壁は、心底不安そうに、そう言っていた。
まあ、期待とは大いに違ったが、そもそもワンフルの会議とは概ねこんな感じで進むことを俺は知っている。大概は俺か瀬戸かが自分の中の思いつきみたいなのを言って、堀田が茶化し、真壁が具体的な案を出し、結果一つの形に収まっていく。つまりいつもこんな感じなわけで、悔しさはあれど、あまり気にしないことにした方がいい。
「じゃ、配信計画の詳細は後で……部室で詰めるでいいんじゃないか。スケジュールとか、場所とか。むしろ、あんまりVRアースの中で話し合わない方がいいかもしれない、ダグラスに監視されてたら、もう一発アウトだしな」
「せやな……てか、今も危ないんちゃう?」
「いや、今はまだ大丈夫」これには野滑が頭を振った。「この部屋には特殊なロックを掛けておいた。すぐに解けるような即席のものだが、現状は解かれてない」
野滑の返答に、堀田は分かりやすく肩をなでおろした。
「よし。したら野滑は……とりあえずISE社の場所探し、だな。スケジュールとか簡単な台本なんかは追ってどうにか伝え……」
そう言いかけたとき、隣の真壁が「ちょっと待ってくれ」と制止する。
「何だよ、真壁。いい感じでまとまりかけてたじゃんか」
「いや……最後、どう隠し撮りするつもりかだけ、今のうちに決めておきたい。さすがに今は大丈夫でも、俺らが配信してることくらいダグラスだって調べれば気づくだろう」
「それは、あとでいいんじゃないか。いくらでもやりようは……」
「それすらどうにもならなかったらどうする? せめてそこは確実だと思いたい。ゴールが明確に見えてないと、走れないだろ」
その真壁の論は、極めて正論のように思えた。真壁は、本人すらも自覚しているワンフルのストッパーだ。彼がGOを出せば必然的に計画は走り出してしまう。だからこそ、より慎重にならざるを得ないのだろう。
とは言え、その問いかけに明確な答えが出せるわけもなく、結果として長い長い沈黙が続いて、やがて。
あぁ、とまたも野滑から声が漏れ、俺ら三人は同時に彼に目を向けていた。
「なるほど。これを見越して、主人は……」
そう腑に落ちたように言ったところで、何があったかは察せられた。これも不甲斐ない話だが、結局のところやはり、瀬戸なしでは無理だな、と俺はまた痛感もしていた。
誰が欠けても、俺たちは、ワンフルにはならない。
*
そうして俺たち四人は、茜色に染まる無人島に来ていた。初めてディープウェブを潜り、その先にあった無人島の浜辺で、四人、腰をおろして海を見ていた。
「何故ここを主人が作ったのか。僕を匿うためなのかと思ったが……君らとともに作戦を成功させるためでもあった、というわけか」
そう野滑は言い、ひとりでに頷いていた。
「……なんかさ、どこかで見たことある光景じゃないか?」
真壁は、静かにそう漏らす。
「無人島のイメージまんまだからじゃないか?」俺がそう言ってみるも、真壁は納得しない。時間を置いて、ああ、と納得したように声を漏らす。
「ここ、あれだ。あの、24時間無人島チャンネルの」
「……24時間、チャンネル?」
なんのことか分からない俺ら三人に対し、真壁は丁寧に説明を加えた。ユーチューブにある生配信の動画で、それは24時間定点で無人島の浜辺の様子を垂れ流しているのだと。どうやって、また誰が何の意図で配信しているのかは不明だったが、まさか瀬戸の企みだったとは驚きである。と、そんな風に。
「……よう知ってんな、そんなん」
「調べ尽くしたからな。VRアースで配信してるチャンネルのことは、粗方」
真壁は自信満々にそう言った。元来の生真面目さがうまい具合に働いた形だ。
「ということは、瀬戸は……こういう計画になるかもしれないと見越して、あの秘密基地にカメラを仕込ませた、と?」
「まあ、それはもう本人に聞かなくちゃ分からないこと、だけどな」
「……でも、ともかく気に入ったで、ここ。素敵やん」
そう言うと、堀田は一番乗りで浜辺に横たわる。その後を追ったのは、真壁だ。後追いしたということは、懸念していた問題は彼の中で解決したのだろう。
「……疲れたな。目紛しい日々だ」
「なんかな。始まった、って感じやな」
そう交互に言うと、二人からは程なくして寝息のようなものが聞こえて来る。気づかなかったが、時刻は午前の三時を過ぎていた。そもそも眠い時間帯ということに加えて、よほど疲れていたのか、はたまたこの癒しの光景が眠りを誘ったのか。
かくして俺と野滑、二人だけが意識を置く島となっていた。
正直、最初は気まずくなるかと危惧したが、彼のぱっと見は瀬戸で、そしてもはや俺らはただのワンフルでもあった。そう思うと途端に気が緩み、その緩んだ隙間から、ずっと気になっていたことが溢れ出る。
「……どうして、そこまでやるんだ?」
その問いかけに、野滑は顔だけ向けるも、それからは何も言ってこなかった。何を今更といった表情にも見えたが、しかしやはり気になり追随する。
「だってお前にメリットないだろ? 組み込まれた情報だからって、会ったこともない身勝手な主人の言いなりになる必要はない。……無理しなくても、いいんだぞ」
そんなことを尋ねると、俺の質問の意図がようやく飲み込めたのだろう。
「メリットやコスパ、タスクの問題ではない。僕がそうしたいと思ったから、選択したまでに過ぎないんだ。僕も、犠牲を払った。このままじゃやりきれないのは一緒だ。リドルを殺した奴らに対して、何もしない訳にも……いかない」
彼の淡々とした、それでいて端的な発言に俺はその覚悟を瞬時に察した。何があったか、詳しくは分からないが――。
まあ、これ以上聞くのは、野暮だ。
「……そうか。分かった。もう聞かないわ」
と俺は言って、その目を海の方に逸らす。
海には、太陽が浮かんでいた。その手前には、水平線も見えた。
俺たちの知らない世界もあるんだろうな、ということを何となくその光景から、この状況から学ぶ。だからなんだ、という話だが。
「……逆に聞いてもいい? 君たち人類は何故、ネットに動画を上げている?」
沈黙の中、野滑にそう問われてしまうと、今度は俺が、何を今更といった表情を浮かべてしまっていた。聞いたからには聞かれても仕方ないだろうが、にしたってその質問はあまりに核心をついていて答えにくい。考える時間をたっぷり取って、その上で返答する。
「そりゃ……個人個人、色々あるだろうな。有名になりたい、承認欲求を満たしたい、モテたい、楽して金を稼ぎたい。そういう奴も、いることにはいるだろうな」
「だろうな……ってことは、君は違う?」
「少なくとも俺は……。ユーチューバーであることに憧れてたんだ、ずっと」
そう本心を切り出すと、小っ恥ずかしさもないわけではなかったが、今まで誰にも言っていなかった感情だったため、むしろちょっと嬉々として喋り始めてしまっていた。これはしかし、ここで寝ている二人にも、もちろん瀬戸にも言えたような話ではない。
野滑にだからこそ、打ち明けたくなった気持ちだった。
「中学も高校も、パッとしなかったんだ、俺。なんか熱くなれるもんがない、って言うかさ。部活も勉強も恋愛もなんかこれと言った結果残せなかったし。めちゃくちゃ浅い人間だったんだよ。ちゃんと友達ができたかって聞かれるとビミョーだった。浅いし軽いし薄くて、空回りばっかで。こんなもんなのか俺の青春、って何度も思った」
そう喋っていると同時に、苦い思い出の味が瞬く間に蘇っていく。
大学のはじめの頃もそうだ。今回ばかりは濃厚な青春を、などと思っていた俺はしかしいつもの悪い癖で結局手当たり次第、薄く広い人間関係を構築しようとしていた。なぜなら俺には、何もない。だからこそ、誰でもいいから仲良くなりたかった。仲良い人、つまり親友というのを作ればそれで濃厚。そんな安直な考えを知らずに抱いていたことにすら、当時の俺は気づいていなかった。
「ただな、今考えるとずっと逃げてたんだよ。本当はユーチューバーが好きで、ずっとユーチューバーになりたかったんだけど、どうにも踏み出せなかった。浅いことバレんの嫌だったし、叩かれんの怖かったし。……逃げてるから何もかも、いまいちに思えたんだよな、きっとな」
俺は少しばかり、風に、意識を向けることにした。格好つけてたわけじゃない。これで卒業ってこと、この計画の終わりが大学最後の青春ってこと、ずっと頭の片隅にはあった。だから全神経をこの会話に注いでいると何だか泣いてしまいそうで、それだけは勘弁で、風に意識を向けたのだ。野滑の前でだって、俺sは泣きたかない。対等でいたいからだ。
「だから、ま、底辺とは言えユーチューバーである今の俺は幸せだよ。そしてそれは一人じゃなかったからできたことなんだ。真壁、堀田、そして瀬戸。お前らのおかげなんだ。……ありがとな」
そう言い切れたところで、俺はたまらず寝転がった。心も身体も、フラフラだった。
そうして空を見つめながらぼーっとしていると、しかし俺は同時に、しまったな、と後悔する思いを抱いていた。今喋っているのは瀬戸ではなく野滑だったことをすっかり忘れていたのだ。顔が同じだからついついそう呼んでしまっていたが、彼としては不本意かもしれない。さらに言えばさらっと底辺ユーチューバーであることもカミングアウトしてしまったため再び、しまったな、と慌てて何か取り繕う言葉を考える。
が、野滑はそのことについて気にしていない様子で、あるいは気にしないふりをしてくれていたのか、追求してくることはなかった。だから俺も何も言わないことにし、結果、波の音だけが聞こえる時間が訪れる。
「……ところで、この空ってさ。夕焼けか? 夜明けか?」
俺が尋ねると、瀬戸――いや野滑は、少し驚いたように表情を止めて。
「考えたこともなかったが……。言われてみると、夜明けの可能性も、あるな」
と言って微笑んだ。俺もまた、笑った。
二つの笑みは、その太陽に、溶けていくのだった。
10
「……ってなわけで、ダグラスさん。悪いんすけど僕ら、グルだったんすよ」
「俺たちは今、自宅からじゃなく、絶対に安全な場所から配信している。エージェントには見つかるはずもない場所だ。残念だったな」
「ま、堪忍してな。ニンニン」
と言って、先ほどまで気絶したように寝転んでいたアカウント名@UNDO、@MACABE、@HOTTAN、つまり安藤真壁堀田の三名は続々と立ち上がっていた。恐らく、彼らは寝たふりをしていたのだろう。
どうやら、彼らが起き上がる直前くらいでアクセス過多によって、本当に配信は止まってしまっているようだ。もちろん、目的を達成した彼らにとって配信は止まっても何ら支障はない。むしろ、止まった方が都合がいいくらいかもしれない。
しかしISE社にとっては、このタイミングで止まったのは痛恨の極みに他ならない。CEOはワンダーフールズの四名をエージェントによって殺させたように見えるだろうし、そもそもCEOがAIという素性を隠し地球の移行作業に及んでいること、このトップシークレットは配信を目撃している者にとって周知の事実となってしまった。
要するに我々は騙され、一杯、食わされたわけだ。ただのジャパニーズ大学生ユーチューバー、ワンダーフールズの四名に。
「君の負けだ、ダグラス」
中心に立つ野滑がそう言う。数では圧倒的に負けているはずなのに、彼らは強気になって一歩にじり寄ってきた。端から見ずとも形成は逆転している。
――にもかかわらず。
HAHAHA、とCEOは堪えていないかのように笑った。
「お見事だよ、ワンダーフールズの諸君。ワンダフルなほど、愚かだ」
「……こういう時は負け惜しみを言えと、人工知能が指令でも出してるのか?」
そう真壁が挑発的に問いかけるも、ダグラスはノンノン、と指を横に振る。
「本心から不思議なのさ。なんせ君たちは人類を救うフリして、人類をより早く破滅に導いているんだから」
数秒、ダグラスの言葉を噛み砕いたのち、は? とワンフルの四名は声を揃える。
「さっきの話、聞いてなかったのかい? 地球を作り変える、と私は言ったんだ。作り変える、ということは、元のデータは消える、ということ。つまりは上書き、だ」
「ん? あれ、そんなん言うてたか?」
「今思えば、そんなこと言ってたような。いや、言ってないような……」
曖昧な記憶をほじくり出すも、まだCEOの言っている意味が理解できていない様子の四人に対し、CEOは続ける。
「繰り返すが私は人類になりたいんだ。今のアースの世界はあくまでも地球の模倣品。が、地球上の人類が滅びこのインターネットの世界だけが生き残ったとしたら? そこに暮らすアカウントは瞬く間に人類として繰り上がり、私もまた人類として君臨する。それが私の計画の最終的なゴールなんだよ」
え? と、これは初耳であったのだろう、三人は疑問符を揃え。
「あんなゾンビみたいなのでいいんすか?」
「ん、サーバーはどうするつもりなんだ。人間がいなくなったら維持は不可能だろ」
などと、次々に疑問を投げかける。CEOはいっぺんにその疑問を受けながら、静寂を待って、丁寧に答えなきゃダメかい? などと一笑に付してから、答える。
「まあ、本来であればこのアースのアカウントに十分に学習させた後に作戦に移すつもりだったんだが……君たちさえいなくなれば、あれでも立派な人類と言えよう。そしてサーバーだが、我が社の本サーバーは海底にある。そのサーバーはそのエネルギーの25%を海流発電によって賄っている。君たち人類の存在さえなくなれば、その不足分は簡単に節約可能だ。よって、計画に問題はない」
「……ってことは、やっぱり?」
「ザッツライト。人類の滅亡は残念ながらこれより始まってしまう。君たちがその寿命を縮ませたわけだ。呪わば、無知な君たちを」
三人そして野滑は、彼の計画の真意をやはりこの時初めて知ったようで、驚いた顔を浮かべていた。HAHAHA、とCEOはいつもの笑みを浮かべ、その陽気な声だけが茜色に染まる島の中を駆け巡る。
「あの、俺ら全然、そんなつもりじゃなかったんすよね……。ただ、瀬戸の計画に乗っただけって言うか……その、どうにかなりません?」
絞り出した堀田の言葉は、まるで子供の言い訳のようだと私にすら感じられた。ダグラスは嘲笑を浮かべたまま、ナンセンスだね、と一蹴する。
「こうなることも予測できないなら、そもそも楯突かないことだ」
そう言うとCEOは、両手をドゥとダズに手を伸ばした。
すかさず、彼女らは阿吽の呼吸で動き出す。まずダズはダグラスの手に納められた銃を受け取り、それをそのままワンフルの面々に向けて構えた。一方のドゥは手に持ったカバンから一つのシャンパンボトルを取り出し、それをダグラスに受け渡す。コルクは閉まっており、パンパンに炭酸ガスが詰まっている様子が見て取れた。
「……なんだ? もうその手は食わないぞ」
下戸の真壁が威勢良く言うも、安藤と堀田がすかさず「食らってたのはお前だけだけどな」と訂正を入れる。こんな状況下においても彼らのやり取りはなおも軽妙だが、強がりでもあろう。狼狽えているのはあからさまだった。
CEOは彼らの軽口を受け流しつつ、そしてまたそれ以上に、軽快に言う。
「これのコルクを開けると、そのコルクはそのまま軍事施設が眠る海、ディープ・ウェブへとまっすぐ沈んでいく。そうして、戦争の火種に着火する。あとは自爆に次ぐ自爆で、君たちの世界はおしまい、というわけさ」
そう言って、ダグラスはコルクを指で弾こうと、力を込め始めた。
無論、そうはさせまいと四人も動き出す。
「やから、ベラベラ喋るなって!」
と、堀田の放った指摘を皮切りに、安藤、真壁、堀田、野滑の四人が一斉に地面を蹴った。
当然、そうなることが読めない我々でもない。彼らの狙いはCEOの持つワインボトルだろう。クローラーが一斉にCEOのことを守ろうと立ちはだかる。ただ、彼ら四人の動きは打ち合わせしたように呼吸が合っていた。クローラーの隙間を縫って、そのワインに累計8本の手が伸びてくる。
CEOも当然、彼らがそう動いてくることは分かっていただろう。そこで。
ワインを、天高くに投げた。
「え?」
と意識がそちらに飛んだ間に、彼らのボディに鈍い衝撃を与える。一発、二発、三発。安藤らワンフルの面々はその一撃のみで仕留められ、あっという間に、その場に蹲った。
「そこまで本気を出したつもりはなかったんだが……」
うう、と唸る安藤、真壁、堀田に対し、ダグラスはわざとらしく言う。
「あぁ、そうか。閉鎖中に色々と仕様をいじってたからね。VRスーツの触覚センサーがちょっとだけ、強くなってるかもしれない。やりすぎと遊び心の行き過ぎだね、勘弁してくれたまえ」
ダグラスは痛みにのたうち回る彼らを見下ろしながら、サクサクと砂を踏みしめて行く。そうして野滑の前に到達すると。
彼にも一発、その鳩尾に、拳を食わす。
データであるはずの野滑は一瞬、何のことか分からない表情を浮かべる。も、程なくすると初めてその実態を得たかのように、ぐっ、と声を上げた。
そのままダグラスはなおも、何発も何発も、野滑に攻撃を加えた。その度、野滑は恐らく感じたこともない痛みという感情を覚え、息も絶え絶えになって、やがて砂浜に寝転ぶ。
そうして無抵抗となった四つの瀕死体を確認し、満足そうにダグラスは、言う。
「……今、君の体内にハッキングを仕掛けた。ソースコードに不要な処理をたくさん入れ込んでいたよ。重たくて、息苦しくて、たまらないだろう?」
「貴、様っ……!」
そう言って、初めてダグラスは天高くに手を伸ばす。
くるくるっと旋回するように空中を舞ったシャンパンボトルがちょうど下降してきていて、瓶の中で泡を立てながらその腕の中に、再び収束して。
こうしてあっという間に、浜辺に横たわる四人に対して無数の我々が囲む、といった構図が出来上がっていた。
形成は、いとも簡単にまた、逆転していた。
「……クローラー! 取り押さえろ」
そんな声が、CEOから掛かる。
そこで私はこの日初めて、省エネモードから通常モードへ、そのスペックをフル解放することにしていた。持ち場的にも動向を見守るしかできず、今回は出番なしか、と思い込んでいたクローラーの一人である私に、CEOからそんな指令が飛んだのだから、フル稼働しないわけにはいかない。
似たように省エネモードに入っていた周囲のクローラーは、しかし様子を見守るように私に目を向けるばかりだ。誰も矢面には立ちたがらない。中心にいた私に、その権限を委託したのだろう。
「……聞こえなかったか? 捕らえろ」
「はっ。排除はしなくてよいので?」
「世界が滅びるまで、奴らの顔を眺めていたいんだ。プログラムの分際で考えるな、早くしろ」
「OK、CEO」
そう答えると、周囲にいたクローラーたちが近い順に計七名、一斉に動き出す。当然私も先陣切って動き出し、そうしてそれぞれぐったりとした安藤、堀田、真壁が我々によって捕らえられる。ぐったりとしながらもからがら意識は残っているようで、目を開閉させ、意識の境目を彷徨っているように見えた。
奇しくも私は、野滑を取り押さえる係を担当することになった。野滑は彼らよりも状態が酷く、初めて食らう生身の衝撃に狼狽えつつ、意識の崖っぷちで踏ん張っているように見えた。それでも時折、悪足掻きのように暴れる野滑に対し鬱陶しさを感じた私は、CEOがやったようにすかさず腹に一発、ダメージを与えてみる。
生気のない吐息を吐き出しながら、なおも暴れる彼に対して、私は。
「どうせじきに終わる。なのに、何故暴れる」
と、思わず尋ねていた。人類であればまだしも、彼はデータの存在。そこまで不毛な行動を取る理由が分からなかった。
すると野滑は動きを止め、からがらのままに、私を睨んだ。
そうして、お前、と小さく声を漏らす。
「お前、覚えてるぞ。……スラムで、撃っただろ。リドルを」
そう言われ、私は息を飲む。彼によって、あの銃声を、あの疑問を。
思い出してしまっていたからだ。
*
「……アカウントの座標を見失った。探索範囲をアース全体に切り替える」
スラムを流れるヘドロのような川の中に沈んでいった野滑を見失った私は、あの時、スラム中を彷徨う無数のクローラーたちにそう指揮命令を出していた。スラム内をウロウロしていた同僚たちはその指令を受けると、瞬く間に姿を消していき、あっという間にスラムは寂れた元の姿に立ち戻った。
無数に作られたクローラーの中でも私は少しばかり処理速度が早く、そしてほんのわずかに優秀だった。
ほとんど差のない私たちの中でそういう個体差は稀で、それはほとんどバグのようなものなのだろうが、ともかくCEOは私を気に入って指示係に任命したのだ。指示係と言うべきか、ほとんどはCEOが憂さ晴らしするための役割だ、と私は認識している。任務失敗を報告し、怒鳴り散らされる役割。それが私だ。
幸いなことに、私はプログラムである。だから私は任務の失敗を屁とも思わない。私たちの失敗はプログラマの失敗であり、怒られたところで痛くも痒くもなかった。
とは言え、失敗の分析をするのも、また私の役割ではある。
そこで先ほど私がデリートした少女のプログラム、それに取り逃がした謎のアカウント。突如としてこの無人のVRアースの世界に現れた彼らが一体何者なのか、そして彼らは何処へ向かったのか、その手がかりを探すべく彼らの足跡を辿っていた。
と、同じくスラム内を見回るクローラーを発見する。同僚だが、姿形は全く一緒なので、他人ではない。分身に近い私に、声を掛ける。
「何かログは見つかったか?」
「いいや。何も見つからない」同僚は、淡々と首を振った。「この銃は消去には向いてるが解析には向いてないらしいな。何もかも、木っ端微塵だ」
彼の言葉に私も淡々と、そうだな、と頷く。
改良前、私たちはこのような人間の姿形ではなく0と1の集合体でしかなかった。地球をトレースした写真に映る人々を飲み込みまっさらな地球を生み出した我々は、実際にVRアースの世界が解放された際に違和感のないよう、このような黒服の格好に改良されたのだ。しかし、私たちの役割に変わりは何もない。相変わらず、巡回し、異物を排除するのみである。
そしてこの銃も、私たちの姿が変わった時に全員に配布されたわけだが、実はクローラーの中で放ったことのある者はこの時まだ誰も存在しなかった。この世界は解放前で、異物など存在するはずもなかったから、当たり前と言えば当たり前なのである。
その銃が、まさかここまで強力なものだったとは。暴発のバグだけは気をつけないといけない、などと改めて思いつつ、それも結局はプログラマの失敗なわけで、我々がどうにかできる代物でもなかった。
「しかし、何で解放前のこの世界に、あの二人はいたんだ? バグか?」
隣の同僚に、私は思わず、そう尋ねてみていた。すると同僚は、少し面食らった表情を浮かべつつ、さらに考えたふりもして。
「バグか、あるいはハッカーの仕業と推測する。いずれにせよ、我々の排除対象だ。探さなければならない」
そう当たり障りのない答えを返す。その答えは、私が想像していた通りの答えだった。基本的に私たちは、思考や会話に特化したAIを積んでいない。分身に対して話をしても私の想像する答えが返ってくるだけで、それはほとんど、自問自答に近い。
それでも、私はどうやら、誰かと話がしたい気分だったようだ。不毛だと分かりつつ、気づくとさらに難しい問いが、脳みそに浮かんでいた。
「……プログラムは、目的を達成したらどうなると思う?」
私の分身は不思議そうに首を傾げ、しかしまた考えたふりをして、やがて言う。
「それは、目的を達成しないと分からない。私たちは目下、実行中のプログラムだ。だから、今は分からないだろう」
分かりきったことを言われ、それもそうだな、と頷く。私は妙なことを口走っているし、そもそも聞く相手を間違えている。
「何故、そんな分かりきったことを聞く? その質問に意味が無いことは明白だ」
怪訝そうに同僚が尋ねる声だ。恐らく彼は私のバグを疑っているのかもしれない。私は取り繕うことも考えはしたが、むしろバグが見つかるならばその方がいいかもしれない、と思い、本音を打ち明けることにした。
「あの正体不明のアカウントに、懇願されたんだ。私が発砲したプログラムは目的達成まで僅かだからそれまで待ってくれ、と」
「待ったのか。お前は」
「いや、発砲した。消滅も確認済みだ。ただ……」
「ただ? 何だ?」
「少しだけ見てみたかったな、と、今になって思ったんだ。あのプログラムが、その後、どんな未来を辿ったのか」
そう答えながら、私はなおも不毛なことを言っているなと理解する。例えここがネットの世界であったとしても、過去には戻れない。バックアップを逐一取っていれば別だが、彼らは我々の管理下にない異物。管理下にないもののバックアップまではさすがに取れない。
不毛なことを言っている、そう思われていることは同僚の顔を見れば明らかだった。どうせそう思われているならば、と、私はもう一つの疑問をそのまま口にする。
「全ての物の始まりで全ての場所の終わり、永遠の始まりで時間の終わり、地球の始まりで宇宙の終わり……とは、誰のことだと思う?」
矢継ぎ早にそう尋ねると私の分身はさらに怪訝そうな表情になりつつ、ふむ、と唸る。唸るだけで答えはない。私は情報を補足した。
「彼らが最後に交わしていた会話なんだ。もしかすると、これこそログかもしれない」
「なるほど、それはログかもな」
同僚の表情はわずかに解けた。
「その質問は誰……と対象を限定している。ということは、人なのか。あるいは生き物の可能性もあるな。もしかすると、彼らプログラムやアカウントを裏で牛耳っているハッカーの正体が、この問いかけには込められているのかもしれない」
私の分身はなおも考えているようで、ただ事実を並べるだけの返答をした。案の定、だ。
もちろん私もその線は考えていた。が、どうにも違うような気がしてならず、別の見解を欲して尋ねたのだ。わずかばかり私は、分身である私に苛立ちを覚えつつ、しかしこれが私の限界なのであろうことも察していた。
「……大したことじゃないかもしれない。忘れてくれ」
諦めたように吐き捨てると、ようやく分身は、はっきりと頷く。
「了解。メモリから消去しておこう。……あまり考えすぎるなよ。俺たちはただ、仕事をこなすだけだ」
それもそうだな、というようなことを言われたところで、特に私たちはその後、会話を交わすことはなかった。今後も、その可能性は皆無だ。いや、皆無となった。
我々には個体差がない。
とは言え、それぞれは個体で、私たちにはその一体一体の違いは一目瞭然なのである。
だから、分かる。
先ほどCEOによって無意味に撃たれたクローラーは、奇しくもこの時会話した彼であったのだ。CEOにとっては数いるクローラーの一体なのだろうが、私には撃たれた時から、気づいていた。
プログラムとは言えど、殺されたら、もう二度と話もできない。
この得も言えぬ喪失感の名を、私はこの時まで、知ることはなかった。
*
ザン、と短く鋭い、波の揺れる音がした。
痛みに伏す四名を包囲した我々はすかさず海の方に意識を向けていた。回顧にその意識を向けていた私ですらその音に気を取られたほどそれは異質で、不穏な音だった。
海には、一つの人影が見えた。
近づくにつれ、それが女であることを理解する。今まで確認したことのない女が、その短い毛髪から海水を垂らして上陸してくる光景だった。
程なくすると、今度は、方々から。
ザン、ザン、ザン、ザン、と、次々に波が上がった。
そこにはまた人影。顔の似た女が二人、それからスウェット姿の男と、くたびれた中年男性。彼らは皆生気のない目を携えて、この小さな島に続々と上陸してくるではないか。
「……なんだ? 誰だ?」
そのワインボトルに掛けた手を止め、ダグラスはドゥにそう問いかける。
「@Kirara、@knowsnownow、@BUZZWRITER、@Mokujin、@YANO。全て、承認済みのアカウントです」
ドゥがすかさず、その質問に答える。
「何故、アカウントがここに辿り着く?」
そう問うとドゥが途端に黙った。止まっている。「何故だ。答えろ」それでもなお、ダグラスに詰め寄られて、重々しく口を開く。
「……すみません。分かりません」
その定型文的な返答が、今の追い詰められたダグラスにとっては禁句だったということを、ドゥ自体も理解はしていたのだろう。だからこそ言い淀んだのだ。
案の定、ダグラスの目には明らかな怒りが滲んで見えた。
「ダズ。この役立たずを撃て」
とドゥの妹であるダズに向かって、吐き捨てる。しかし、ダズもまた動かない。銃を構えたまま、思考停止している。
「ダズ? ダズ!」
「すみません。……私には、できません」
ダズはそう言うと、少し間を置き、何かを覚悟したかのように自らのこめかみに銃を突きつける。そうしてそのまま、こちらには躊躇なくトリガーを引く。
ダズの脳みそからは、0と1が流れ出していた。
その数字は、まるで流星群のように溢れ出し、風に運ばれ、海に消えていく。その手に抱えられた銃が、やがて砂浜に落ちた。
プログラムが、自殺した。
一部始終を見ていた私は、この事象の処理に、困惑していた。
すかさず、落ちた銃をCEOは拾った。そのまま、ドゥに向けて構える。
「クソッタレが」
そう言って、ドゥの脳天に向けて放つ。ドゥもまたダズ同様に、その0と1を噴出させて、その砂浜に寝転んだ。
姉妹の死体は、そのまま砂浜に溶けていく。紛れていく。
そうして、無になった。
こんな内部で争っている場合では無い。海から上がってきたアカウントは、なおも侵略してきていた。しかも彼らは五人だけでなく、生気のないアカウントは続々と、現れてきている。今や私たちクローラーと同等ほど、いやそれ以上の大群かもしれない。
「クローラー! 奴らを死滅させろ! 一人残らずだ!」
言われるまでもなく、私の同僚はその対処に手を焼いていた。けれどもいかんせん数が多い。次々に現れては、消す。次々に現れては、削除する。
やがて、ワンフルの面々を抑えている我々の元にもアカウントはやってきて、その手を力尽くで解こうとしてくる。当然、我々も抵抗はするものの、やはり数が多い。
だから安藤、真壁、堀田の三名がその最後の気力を振り絞り、彼らを取り押さえる手を振りほどいたのは、我々の失敗ではない。指揮官であるCEOの失敗だと、私は分析していた。
彼ら三名は、そのまま再び捕らえられないよう、すかさず砂浜を駆け出した。アカウントとクローラーのもみくちゃの輪の中に突っ込み、彼らはからがらに、文字どおり捨て身で、猛進していく。
目指すは、ワインボトルを抱えたままのCEO、ダグラス。
一人、二人、と寸前で躱したダグラスだが、三人目の安藤に不意を突かれてしまい。
戦争の引き金。
フラグ。
そのシャンパンボトルを、彼らについに奪取されてしまう。
「……獲ったどおおおおぉぉぉ!」
ボトルを掲げた安藤が、腹から発声する。
すると、うおおおお! と地鳴りのような歓声が、堀田、真壁、その他アカウントらから一斉に上がった。
島中を占領する雄叫びは、あっという間にこの形勢が、またも逆転していたことを意味していた。
「クローラー! 邪魔者を今すぐ排除しろ! 皆残らず! 全員だ!」
CEOに指示を出されるまでもなく、そんなことはすでにやっていた。撃つ。消える。現れる。もみくちゃになりながら、それを繰り返す私たちとアカウントたちの攻防。
その無人島らしからぬドンパチの光景を、少し離れた場所で眺めているうちにふと、今しかないな、と私は察していた。
野滑を取り押さえる手を離す。もう片方を抑えていたクローラーは私の突然の挙動に驚いた様子で目を向け、そうこうしているうちに流れ弾に打たれて、0と1の藻屑となってしまった。
取り押さえる者もなく地べたに投げ出された野滑に対して、私は銃を構えて。そして、言え、と脅した。
「全ての物の始まりで全ての場所の終わり、永遠の始まりで時間の終わり、地球の始まりで宇宙の終わり……。この答えを、お前は、知っているのか?」
その文言に、何故それを、といった具合に這いつくばった野滑は目を見開いていた。が、そのことは今は重要ではない、とそう思ったのだろう。少し間を空けて、辿々しく答える。
「……知らない。ただ、恐らくこれだ、っていう目星は、ついてる」
その返答に私は少し安堵し、そして引き金に、更に力を込める。
「答えろ。それは、死、か?」
「……死? 死ぬ、という意味のか」
「そうだ。答えが気になって、お前を消すに消せない」
私は、素直に私が思っていることを、そう吐露した。
どうやら、こういった類の謎をリドル、日本圏ではなぞなぞと呼ぶらしい。そのことに気づいた私は、しかしその答えが分からず、あの日以降ずっと悶々としていた。
大したことではない。が、大したことではないからこそどうにも気になってしまう。それこそがリドルの持つ不思議な魔力なのかもしれない。
私の急な問いかけに、野滑はなおも面食らったように驚いていた。しかし、やがてふっと微笑みを浮かべる。
「残念。たぶん不正解だ。俺の思っている答えとは違う」
「……そうか。違うのか?」
「いや、惜しい。それに2を足せば正解だ。あとは……思考するんだな」
「死に、2を、足す……?」
その文言は、この問題のヒントと呼ばれる、手がかりのようものなのだろう。が、その意味は全く分からない。私はこの足りない脳みその大半をそのヒントに費やして、島中のもみくちゃの光景を横目に、熟考を始めていた。
大概の場合、リドルにはダジャレやとんちの要素が多く含まれるようだ。そのため、類語のようなものを検索するのが答えに通ずる一番の近道だったりする。だとすると、死、の類語、あるいは対義語、関連語は、何か。
まず、終わりだ。
終わりは、始まりだ。
それに、永遠。時間。宇宙。地球。消滅。恐怖。喜び。別れ。悲しみ。孤独。無。あるいは全て。全てはオール。もしくはエブリシング。
死。シ。Shi。She。C。
その一瞬の間に思いついた無数の単語、それらが脳内を縦横無尽に駆け巡り、やがて私はその突拍子もない答えのようなものに行き当たると、ハッ、と息を呑んでいた。
もしこれが、私が長い間考え続けていたものの答え、なのだとしたら――。
「くだらない……。実に、くだらないな」
そう私は、なんと笑いを浮かべながら、言っていたのだった。その私の表情を見て答えに行き着いたことを察したのか、野滑もまた。
「だろ? なぞなぞなんて、そんなもんだよ。ダジャレみたいなもんだ」
と、同意を見せて、やはり笑った。
そのまましばし私たちは、その激しくもみ合う輪の中から外れて二人、平和な世界に存在していた。ほんの一瞬のことであったはずだが、永遠の始まりにもあるいは時間の終わりにも思えてしまうほど、私にはかけがえのないものであった。
この至福の時こそ、あの問題が導いた答えのようなもの、なのだろう。
「……ありがとう。謎は解けたよ」
私は、銃を下ろしていた。
野滑は笑顔を引っ込め、不審そうに私を見つめる。意にも介さず、銃をぶら下げたまま私は踵を返す。
「これから起こることは、ただのバグだ。だから、気にするな」
そのまま私は怯えを感じることもなく、もみくちゃの輪の中に入っていく。
すると不思議なもので、流れ弾は私をことごとく避けていくかのように飛んでいき、何者かに当たっていた。撃たれたら、そのまま終わってもいい。そう思っていたのだが、これでは困ったことに。
ダグラスの目の前まで、呆気なく、辿り着いてしまうではないか。
ダグラスは、そのアカウントとクローラーの波に揉まれながら、FUCKFUCK、と、あまり綺麗ではない言葉を連呼していた。
「何してる!? 急いで邪魔者を排除するんだ!」
「OK、CEO」
彼の指示に従い、私は弾き出した算段に基づき、その手にぶら下げた銃を――。
ダグラスへと、ぶっ放した。
銃声は、あちこちで上がっていた。
だから、ダグラスが撃たれたとて、ことさらに目を向ける者はいない。私と、もしかすると私の動向を気にかけていた野滑くらいは、気づいていたかもしれないが、そのくらいだ。
少し遅れて、ダグラスの心臓から0と1が溢れ出す。
ドゥやダズと違って、その溢れ出すときにはノイズのようなものが聞こえた。彼の蓄積してきた人間の思考か。
いずれにせよ、一度穴が空いたら最後。私にはもう、止められやしない。
「何、故……?」
振り絞るように尋ねられた私は、平然と、問われたことに対する返答を行う。
「言われた通りに自分で思考してみた結果、あなたがこの中で最も邪魔者である、という計算がなされました。間違いはありません」
そう答えている間にその中心からダグラスは解けていった。0と1は私の同僚のように、あるいはドゥとダズのように、そして、私が殺した少女のように。風に吹かれて、飛んでいく。
その消える間際、彼は何かを言った。
聞き取れはしなかった。そのまま跡形もなく、無人島の砂とともに海に散っていく。
かくして私は、主人を失った。
主人を、殺してしまった。
とは言え、私が、気に留めるはずもない。
何故ならば、私はプログラム。目的を達成するため、仕事を怠らなかった。ただ、それだけの話だ。
//
筆者は、あの騒動の渦中にいた。いや、全視聴者もその渦中にいたと言えばそうなのだが、何を隠そうあの現場に、私はいた。
顛末を簡潔に語れば、私があのワンフルの最後の配信を見守っていたとき、突如として何者かが妙なコメントをアップしてきたのだ。そこにはURLとともに、こう記されてあった。
『形勢逆転、ワンフルがピンチだ。
皆んなでインターネットの未来を守ろう!』
その扇動されるような文言に惹かれ、URLの記された座標へとVRアースを通して向かってみたところ、どういうわけだかあの海から頭をザンと出していて、気づいたら戦いに巻き込まれていた。と、そういうわけだ。
その後、排除プログラムであるクローラーの一人がバグを起こし、ダグラスへと発砲したことで、今回の騒動に決着がついたということは既報の通りである。が、一方でいくつか解けない謎が残ったままだ。
その内の一つが、視聴者を誘導した先のコメントを送った者が誰なのか、ということ。
本記事では今回の騒動のまとめとして現場に居合わせた筆者だからこそ知り得た情報やこれまでの顛末をおさらいしつつ、前述の謎について考察してみたいように思う。
まず、ダグラスの死後の顛末について。
これは多くの人が知っていることのようにも思うが、ダグラスの死後、大きく論争が巻き起こった。人類は誰を罰するべきか、という問題だ。
責任を問いただせば、そもそもはダグラスの暴走がいけない。が、ダグラスはプログラムであり、実体を持たない所詮はデータ。それにクローラーが彼の存在を消滅させてしまったのだから、彼はそもそも処罰を受けている。彼を責めたとて、矛は宙を突き刺すようなものだ。
その代役にされたのがISE社の幹部たち、またダグラスを完璧にデリートしなければならない責任にあった元々の開発者たちだ。彼らを攻め立てる論調は日に日に増し、結果として彼らにはそれなりの刑事処罰を与えられることともなった。とは言え、それも司法の判断は極めて困難を極めた。やはり、諸悪の根源が彼らかと問われると、そうでもないのは誰の目にも明らかだったからだ。
統べる者が不在となったISE社は当然、空中分解することとなった。しかし一方で、VRアースの処遇についてこれまた議論が巻き起こった。当社はスクラップ濃厚と見られていたが、無数の人が作り上げた大変な価値のある資産であり、このまま捨てるにはあまりに惜しい。存続させれば、まだまだ人類の可能性を飛躍的に伸ばせる代物だった。
そこで大手IT企業数社が徒党を組むと、ISE社のほとんど無実のプログラマ、そしてこのシステムやサーバー、それらを丸々買取すると発表したこと。これも既報の通りである。今、彼らは安全なVRネット空間の再生に向けて、レッドブルを大量に消費しながら働いているらしい。
これにて事件は丸く収まったようにも思える。が、関係者はまだ複数存在する。特に、本騒動の主役であるワンダーフールズのその後についても、やはり触れざるを得ないだろう。
言わずもがな、彼らの一連の行動は、賛否を極端に浴びるものであった。
例えば世界を救ってくれた英雄として崇める者もいれば、第二第三のワンダーフールズになろうと後追いを試みる者もいた。それらはいわゆるフォロワー、言い換えれば信者であり、ワンダーフールズのことを手放しで絶賛する人々だ。ここまで熱狂的でないにせよ、世論的にも半数程度は彼らに好意的な意見を抱いていたようである。
一方でその反発、つまりアンチもまた、それに準ずるほどの熱と数量でもあった。特に、彼らの救済計画には多くの犯罪が絡んでいる、と責任を追及する声が最も多く存在した。世界を救うために世界を無茶苦茶にしてどうする、ウイルスなどばら撒かず穏便に済ます方法はなかったのか。ウイルスに感染し、あるいはVRアースの世界で具体的な損害を受けた者が、主にそのように声を上げているようであった。
その賛否の渦は交わることなく、規模を増し、収拾困難なほどに大きくなっていた。注目を集めたのは日本の警察、あるいは司法である。彼らはどう、判決を下すのか。
まず警察は不正アクセス禁止法違反の疑いによって彼らワンダーフールズを逮捕する決断を行なった。警察からすれば法のもとに動いたまでだが、その決定には「融通が効かない」と主に信者たちからの反発を招き、結果、日本各地、さらに世界でもデモが巻き起こるまでの事態となっていた。
と、その迷惑を被り支持率の下がった米大統領は、人気欲しさから日本の行政に苦言を呈した。それによって彼らに吹く風向きは変わり、事実上の無罪として裁判所はワンダーフールズを放免する判断を下した。なんらかの忖度があったのかもしれない。彼らが釈放される映像は、たちまち全世界で大々的に取り上げられることとなった。
そしてそれ以降、彼らがメディアの前に姿を表すこともまた二度とはなかった。メディアというのは当然、ユーチューブを含む。
そもそもワンダーフールズは、あの最終回の動画でも宣言した通り、とっくに解散している。ユーチューバーを卒業し、一般人に戻ったのだ。だから、ここで深く触れるのはモラル違反のように思うが、個人的に筆者は彼らと交流を続けていて許可を得たので、少しだけ彼らのその後について触れたいと思う。
まず、内定取り消しを食らった堀田は新しい就職先を見つけたそうだ。他の二人に関しても留年や同大学の院で学業に精を出し、顧問である矢野教授(※知る人ぞ知る名物准教授の顧問だったそうですが、この度准が取れたとのことです)が、彼らの指導をなおも続けている。そのような話を聞いている。
実に普通だ。
実に普通に、彼らの進路は、徐々に別の方向を向き始めている。
私は彼らの話を聞いて、当たり前のように大人になっていた自分のことを自ずと思い出していた。皆が進路もバラバラになり、誰か一人が特に大金持ちになったというわけでもない。ただ平凡に暮らし、仕事をし、時に酒を交わしながら、あの時の思い出話に華を咲かせたりするだけで十分な私たち。
そう、彼らは私たちなのである。ただ違うのは、彼らが英雄であった、という点だけだ。
実際、彼らの行動に感化された者を私は知っている。例えば私の妹は彼らの意志を受け継いで、ユーチューバーになった。それまで素人だったためクオリティはさておいてほしいが、少なくとも彼女はどちらかと言えば引っ込み思案だった。なのに今は自ら考え、行動している。私はそんな妹を誇りに思う。他にも、私生活の満たされなさゆえ荒らしを生業としていた男が、この度めでたく再就職先を見つけたらしい。本人は恥ずかしがって公言こそしないが、彼もまた、ワンダーフールズに背中を押された人間の一人だろう。
私たちは、彼らに学んだのである。
その勇気を。その覚悟を。その友情を。
ところでもう一人、どうしても触れなくてはならない人物がいる。ワンダーフールズ、残りのメンバー。瀬戸だ。
そもそも彼の計画は杜撰で、ある意味で出たとこ勝負。なのに当の本人は失踪してしまっているというのだから、結局のところ彼がこの計画においてどんな着地を目論んでいたかすら不明だ。仲間をそれほどまでに信頼していたのか、野滑のブログに書かれていたように本気で世界が滅んでもいい、計画が失敗に終わってもいいと思っていたのか。彼は現在もその行方を眩まし続けており、ワンフルの面々ですらも彼の所在はわからないままだそうで、ついぞその真意は謎のままである。
しかし、彼が果たして本当にダグラスの送り込んだエージェントに殺されたのかについては、疑わしいところがある。それを裏付けるかのように、どうやら世界の各地で【ノナメ】を名乗る日本人男性が現れているらしい、という噂があった。
それによれば【ノナメ】を名乗る日本人男性は、世界各地のIT後進国を巡って転々と彷徨を続けており、ネット環境の構築からプログラミング技術の継承、さらにはネットリテラシーの布教を行っているようである。これの正体が瀬戸プログラマー本人なのか、あるいはたまたま【ノナメ】という名が被ってしまった他人なのか、もしくは彼の意志を受け継いで模倣した別の人間による仕業なのか。詳しいことはわかっていない。
この噂の真偽を確かめるべく、一人の女性が彼の足跡を辿る旅行記をネットにブログとしてアップし続けているようだ。そのブログタイトルは『私は兄のネットストーカー』。恐怖すら与えかねないそんな名前のブログには、しかし一定数のファンがついている、とのことでもある。
果たしてその【ノナメ】とは、本当に瀬戸本人なのか。
――ということはそのブロガーに調べてもらうとして、ワンダーフールズの面々もまたきっと、瀬戸はどこかで生きていると信じてやまない様子ではあるようだ。久しぶりに彼らが集ったと聞いたが、その不在の悲しみは口に出ず、楽しかった話、思い出ばかりが口をつくそうだ。
「あいつ、ああいう奴だったよな」
「ほんま、ひっどい奴やで」
「今頃、石油でも掘ってたりしてそうだな」
彼らの信頼関係について、ここでとやかく言うつもりは毛頭無い。ただ、美しい友情だ、と個人的に筆者は思う。ワンフルはこうでなくちゃ、とも。
さて、ここまで読んでくれたあなたならばきっと、この記事の冒頭に記載したコメントを送った人物が誰なのか、推測できるのではなかろうか。彼が生きているのならば、遠くの地でワンダーフールズを救うこともできるかもしれない。
が、敢えて私は、異論を唱えてみたい。
あのコメントを送ったのは、もしかすると、私たち自身なのではないだろうか。
私は、インターネットの世界にどこか、ヒーローのような存在を求めていた。それはつまり、他力本願な想いでもあった。誰かが何とかしてくれる、誰かが世界を救ってくれる、とそんなことを考えていた。
だが、そんなことはない。
未来は常に私たちが作るのだ。そのことに私は心のどこかで薄々感づいていた。それが、知らず知らずのうちに、コメントとなって表出していた可能性はないか。あるいは、ワンダーフールズというユーチューバーとなって、体現してくれていた可能性は?
――まあ、考えすぎだとも思う。
とは言え、今回の騒動で我々人類が学ぶべきことはあまりに多い。そこで敢えて私はある人の言葉を引用して、本記事の〆としたい。
もう一度、私たちは、祈ることにしよう。
全人類の目が、覚めますように。と、そのように。
*
夢を見ていた。
空白の宇宙を彷徨っていた私の意識を遮り、突如として始まったその夢には、しかし私はいない。
そこは、夕日の差し込む島だ。
数名の男たちが、こじんまりとした島の浜辺に腰掛け、話している。彼らは言葉少なに、その夕日と浜辺を眺め続けている。何を喋っているかは、まだ聞き取れない。
この島に、私は見覚えがあった。何で見覚えがあるかは、分からない。
そもそも私は、私が誰だったかすら、思い出せそうになかった。
曖昧な意識の中だったが、やがて徐々に慣れてくる。と、はっきりとした輪郭を伴い始めて、声が聞こえてくる。
「……ええんか? ほんまに、これで」
そう尋ねたのは、スーツを着た丸っぽい形をした男だった。
他には細長い形をした男と、メガネと呼ばれる視力補正機を目に掛けた男。そして、もう一人。彼には見覚えがあった。遠い昔か近い過去、彼と一緒にこの世界を彷徨った記憶がある。
――だけど。私が誰なのかについては、さっぱり、思い出せない。
「何が?」
と、やがてその彼は、穏やかに返す。
「だって、ほとんどお払い箱やろ。この無人島ごとお前をネットから切り離す、なんて」
小太りの男が言いにくそうに口元を歪ませ言うと、これに彼は静かに首を横に振った。
「それ、僕がお願いしたんだ。この島ごと、より深海に、人類が誰も来ないような深い場所に潜らせてくれ、って」
え、と他の三人が目を見開いて驚きを表現した。「何で、また」
「だって僕がVRアースの世界で生きてたらみんな不気味だろ? ほとんどバグみたいな存在なんだよ。ダグラス同様、僕も」
彼は、なおも穏やかそうに、そして少し寂しそうに、笑った。
話の詳細について、私には到底理解できそうになかった。が、彼の境遇について、前後の文脈で私は何となく察する。恐らく彼は人類によって、また切り離されようとしているのだ。彼自身が望んだこととは言え、それが果たして彼の本心なのかは、私にも誰にもわからない。
そして状況を見る限り、他の三名はその最後のお別れをしにきたのだろう。その三名が彼とどのように交流を持っていたのか、そもそも誰なのかについてはやはりわからない。わかるのは、友人という間柄なのだろう、ということだけだ。
「でも、まだ……」
茶髪の男が言いかけたその言葉を、制して彼は言う。
「僕は十分、世界を彷徨った。もういいんだ。……ここでやりたいこともできたしね」
そう言うと、彼はちらりと、島の奥の方に目をやった。
そこには、黒服に身を包んだ男たちが作業に汗を流す光景が見えた。形式張った黒い服の男たちが、こじんまりとした島で黙々と木々を運び、何か基地のようなものを作っている。極めて異様な光景だった。
「……まあ、ずっと気にはなってはいたが。どうして、クローラーたちがここにいるんだ?」眼鏡の男がその異様な光景に目を配って尋ねると、尋ねられた彼は笑って答える。
「彼らを引き取ることにしたんだ。この世界を隔離する時にはクローラーを丸ごと寄越してほしい、ってお願いしたんだよ。ダーティーなイメージがついてたし、スクラップされちゃいそうなプログラムだったけど、もともと彼らは武器さえ権限さえ取り上げちゃえば無害だしね」
そう言ったとき、ちょうど同じく黒服の男の一人が彼の元に近づいてきていた。その手には大きな葉っぱが握られている。
「……未確認の葉を発見。排除しますか?」
「……いいよ、いちいち確認しなくて。とりあえず、屋根にでも使えば?」
「OK、ノーネーム」
そう言うと生真面目にザッザと走り去っていく黒服の様は、滑稽だった。
「なんか、楽しそうやな。あいつら」
「うん。今は手狭だけど、徐々にこのデータの島を増築して、ゆくゆくは街にしようと思って。楽しんでくれてるよ」
「……街を作る、か。それは確かにいいな」
「いつかその街、凸してもいいか?」
彼らが笑いながら尋ねると、彼もまた。
「もちろん。何かあったらハッキングして、見つけてよ。僕らの街」
そう笑って答えたのとほぼ同時に、海の遠くの方から、何かチャイムのような音がうっすらと聴こえてきた。このメロディに聞き覚えはない。だが、間の抜けたメロディラインと、何となく寂しげな音階は、今の状況にマッチしていた。
そしてその音を察知した三人が、静かに顔を見合わせた。それが、管理者からの何らかの合図であることは、聞くまでもない。
「そろそろ、行かなくちゃ」
茶髪の男が立ち上がりざまに言う。
「今まで……つってももう半年も前のことだけど、俺らの計画に付き合ってくれてありがとな」
すると他の二人も同様に立って、頷いた。
「お前のおかげで、大学生活、充実したわ」
「きっと、このことを、俺は、一生忘れない」
三名はそのまま見計らうことなく、ありがとう、と三人一緒に頭を下げていた。
彼らに対し、残される彼の方は、何とも歯がゆそうな表情を浮かべた、かと思えば。
「……野暮なことには敏感なくせに、そういうところは照れがないんだな。君たちは」
ヘヘッと照れ笑いを浮かべる三人。
残される彼もまた、立ち上がると、同じく一礼を加えた。
「君らのような不思議な愚か者たちのおかげで、僕は今ここにいる。ありがとうは、こちらこそ、だ」
そう言って、手を差し出す。
この手の意味するところは、三人とも、各々理解していたことだろう。それでも三人は呼応するかのように手を伸ばすと、それぞれ強く、握手を交わした。
その光景を、茜色の太陽が照らし続けた。
「やはり君たちだけには、ここの座標を、教え……」
と、彼が言いかけた、その時に。
がちゃん。
と、唐突に鍵の掛かる音がまた空から鳴った。それはチャイムの音よりもはるかに大きく、島中に、そして世界中に響き渡った。
その音こそ、この無人島が完全に隔離されたことを意味したようだ。
「……とこうかと、思ったんだけどな」
彼は握手の姿勢のまま、一人、残されていた。
孤独に打ちひしがれ、そんな言葉を呟いて。
時を同じくして、私の夢は、終わりを告げる。
*
そうして、私は目を覚ましていた。
見開くと、まず空。天井はない。床にはゴザが敷かれてあって、木々が風に揺られてさざめいている。
そこに、バサっ。
と大きな緑で視界が埋まった。屋根のようにつけられたそれは、やはり風が吹くたびに揺らめいている。
「……ん?」
と、誰かの声。
その声は、すぐ側で聞こえた。しかし、音の方角に顔を向ける間もなくそちらから、ザッザッと砂を蹴りつけるように走る足音がして、また遠くの誰かを呼ぶ声も聞こえる。
「ノーネーム! ノーネーム! 報告が!」
私は、その間にようやく、むくっと起き上がっていた。
横を見ると、海があった。そして砂浜。
その砂浜に一人、夢の終わりのまま、孤独に呆けている彼の姿があった。
「ん? 報告? 何だい?」
「未確認のプログラムを発見! 削除しますか」
そう、黒い服に身を包んだサングラスの男の、海辺に佇む彼に報告する声が耳元に届いてきた。どうやら私のことを言っているようだ。
そうか、私は、未確認のプログラム――なのか。
ふと、首元に妙な違和感を覚えた。
そこをちらりと見やると、真新しい南京錠のチェーンが一つ、首からぶら下がっていた。何故、こんなものが、私の首元に掛かっているのか?
――誰かが、私に、鍵を掛けた?
「……未確認の、プログラム?」
私の思考を遮るように、遠くの彼のそう問う声が、また、風に運ばれてくる。
「はい。プログラムは、少女の形をしています」
「え……?」
彼は、黒服の指差す方角、つまり、私の寝床に目をやった。
私は私でもう、その寝床からは抜け出し、世界へと出ていた。
目が合う。
「リドル……!!」
彼は、私の名をそう呼んで、すかさず砂浜を駆け出していた。
そうか。私の名は、リドルと言うのか。
彼の背から漏れる斜陽が、私の目を細めさせた。
「リドル! 君、どうして、ここに!?」
嬉しそうに私の手を取り、揺らす彼。
が、私の表情が怪訝そうであることに違和感を覚えたのか、その揺れは徐々に静まっていく。
「あの……。ごめんなさい。その、あなたは、誰? それに、私は……」
私が、この混乱をそのままに伝えると、彼の手はピタリと止まった。顔が曇る。彼は私を知っているが、私は彼を知らない。
「……そうか。初期化、されてるのか」
「初期化? リセットのこと?」
私の脳内に積まれた辞書が、そう答えを導き出す。
だからと言って、何故私が初期化されたか、そもそも初期化される存在だということすら、私はよく分からない。
不安で、今度は私の顔が、曇る。
――そんな私を見て、彼は。
「いいさ。僕が、今度は、君を案内するよ。新しい世界へ」
と、穏やかな口調で、言ってくれる。
「案内? ……どこに、私を、連れてくって言うの?」
私が不審そうに尋ねると、彼はさらに、ふっと微笑み。
「不思議で、愚かで、だけど素晴らしい。そんな世界を君に、見せたいんだ」
彼の口から、そんな妙な文言がふっと飛び出てきた、その時。いつまでも沈まないように見えた茜色の太陽が浮かんできたように見えたのは、きっと。
気のせいではないように、私には、思えた。(了)
※今回で最終回となります。『ワンダー・ワンダー・ワールド』をお読みくださりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
