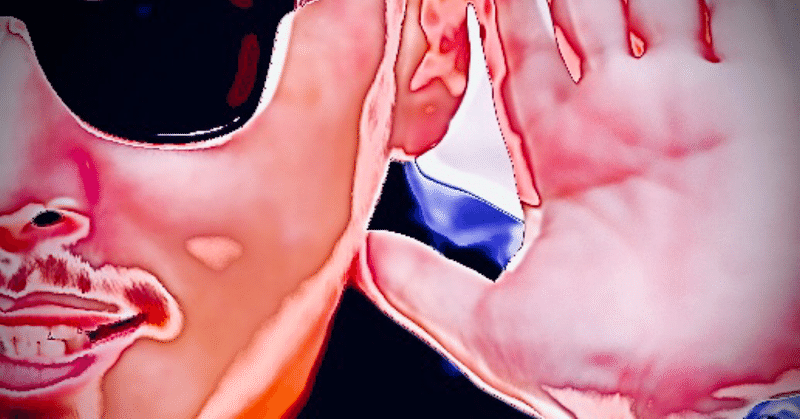
にがうりの人 #34 (注がれる毒)
そんなことが何度か続き、私は高峰の依頼人に対する姿勢を誇りに思うようになり、やがて絶対の信頼を寄せるようになっていった。
弁護士といっても、商売である。うまくやりぬくにはそれなりの経営判断も必要だろう。ただ、それを理由に法律家としての理想を易々と破棄するのはおかしいのではないか。私はそう思うようになり、そしてそれを行動に移す高峰を尊敬していた。
✴︎
私が入所してから二年ほどの月日が流れた。相変わらず小さな案件に二人して忙殺されていたが、それでも仕事にはやりがいを感じていた。その年は梅雨明けが例年よりも早く、六月の中旬にして夏が訪れていた。古い空調がやる気を出したのか、事務所の温度を必要以上に下げている。窓から見える街をゆく人の流れも予想外の夏の到来に苛立ちを隠せないのか、速く感じた。
裁判所に提出する書類がたくさんあり期限も迫っているため、私はその作成に時間を費やし、高峰は別件の書類に目を通していた。
「先生、お昼にしますか?」
壁に掛かった時計を見上げると短針と長針が十二時で重なっている。
「そうだなあ。私はもう少し片付けてからにするよ」
高峰は大きく伸びをすると再びパソコンに目をやった。
「じゃあ何か買ってきましょうか?」
その時、事務所の扉が開いた。サングラスをかけた軽薄そうな男が立っている。
「弁護士の先生おる?」
私は書類を整理していた手を止めて笑顔を投げた。法律事務所ともなると近寄りがたい印象があるため来客の際は極力表情を柔らかくしていた。
「はい、どのようなご用件でしょうか?」
男の表情を間近で見たその瞬間、私は胸が締め付けられる思いに駆られた。それは形容しがたい、ある意味郷愁に近い感覚。だが、それが何かは判然とせず、私は気を取り直して再び笑顔をつくった。
「お前はなんなん?弁護士ちゃうやろ?あ?」
私が丁寧に応対すると男はさらに顔を近づけ、居丈高に言った。よく見るとまだあどけなさが残っており、未成年なのではないかと勘ぐってしまう。
「はい。しかしご用件はまず私が承っておりますので」
「下っ端に用はないねん。弁護士出せや、弁護士」
男はそう言って私の肩を小突いた。
「私に何か御用でしょうか?」
忙しなく響いていたキーボードの音が止み、高峰は眼鏡を外しながら立ち上がった。男は私の肩を背後から掴み、邪魔だとばかりに押しのけた。
「あんたが、高峰弁護士かい?」
不遜な態度はさらに度を増し、高峰の机に尻をのせると馴れ馴れしく高峰の肩を叩いた。
「なんとか丸く収めて欲しいことがあるんや。ちっと面倒くさい女がおってな」
高峰は男をじっと見つめている。それは相手を探るというわけでも、射抜くというわけでもないが、鋭い目つきであった。
「レイプした女が俺の事訴えるいうて聞かんのよ」
男は躊躇せず言い放った。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
