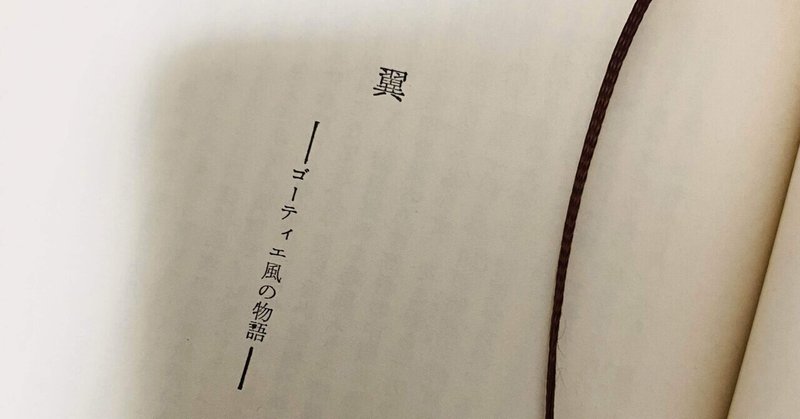
三島由紀夫の翼の正体を考察する
恋愛物において、夏から始まる関係性というのは「過失」とか「過ち」とか「勢い」なんかとセットで描かれがちな気がするのだけど、これがなんというかちょっと苦手だ。
そして季節の移ろいと共に、秋で心が離れ、冬に関係性に終わりを告げ、春がまた始まる。
なんかそういう表現を見かけることがあるけど、実際の人間関係は四季に影響を受けたりしない。
そのせいかプラトニックな恋愛物が好きだ。
そんな物語に敢えて夏に触れてみるのはどうだろう。三島由紀夫で。
三島由紀夫という作家からはそんな作風は想像しづらいかもしれない。
三島といえば「同性愛」「男色」「マゾヒズム」「耽美」「切腹」なんて、字面だけでお腹いっぱいになるような情報過多なイメージが先行するんじゃないだろうか。
でもこの『翼』という作品はとてもプラトニックで、ジュブナイル性を持った作品だという印象があって、初めて読んだ時から随分好きなんです。
タイトルにもある通り「翼」が重要なキーワードになっている作品なのですが、具体的に何を示しているのか明言されていないんです。
従兄弟同士で恋人同士の葉子と杉男は電車でお互いの背中が触れたとき、背中に翼が生えているんじゃないか、と想像します。
翼ではあるまいかと二人は思った。隠され畳み込まれた翼が、じっと息をひそめている気配がある。というのは、時折強く触れあう背中に、敏感すぎる甚だしい羞恥が感じられたからである。翼を隠しているのだとすれば、こうした羞(はじ)らいは理に叶っていた。
もう!!この文章がプラトニックさを表していませんか!
この後に葉子は「翼を信じるためには、罰せられることが必要な手続きだった。」と考えるシーンがあり、この考え方が葉子の将来を仄めかしているようにも捉えられるなあ、と思うのです。(「罰せられることが必要な手続き」ってマゾヒズムっぽくもあり、必要性をわざわざ訴えかけるところがとても三島っぽいなと思うのです。)
杉男は翼を信じるだけでなく、葉子の翼を磨硝子越しであるけれど、存在を見てしまったために葉子のような「罰」を受けなかった、その代わり自身の翼は終戦後、色あせてしまったようにも思うのです。
神様を可視化してはいけない、偶像崇拝してはいけない、という考え方がありますがそれに近い形で捉えています。
「翼」はもともと目に見えないもので、精神的に感じるものであったので「信じ切れなかった」杉男は禁忌を犯してしまった。
じゃあ、その「翼」って何を表しているの?ということになるんだけど個人的には「相手への愛慕」とか「ジュブナイル性」とか「純粋さ」みたいなものを隠喩していると思っています。ちょっと一言で表すのは難しい。
その「翼」を大人になっても背中に生やしている杉男が出世できないのは、葉子への想いを未だに抱え続けているからなのかな…と思います。というか「少年性(ジュブナイル性)」とか「純粋さ」とか含めて。
社交辞令なんかの人間関係を円滑にするような優しい嘘をつけず、仕事に忙殺されているような気がするのです。
社会人になってまで10代の頃の恋心を自ら足枷にするのは、随分重たいような気もするけれど、意外とみんなそういう部分ってあると思う。恋愛に限らず。
嫌なことがあった時、失敗したとき、褒められた時、10代の頃の記憶がフラッシュバックして、昔から何度も言われるようなことを反芻したりして「あ、これが自分なんだな」と嫌ほど思い知らされてしまうことが多々ある。
過去の経験って実は一生付き纏うものだな、と思う。本物の大人になるのは結構難しい。
お互いの翼を見る機会があったら、結ばれてハッピーエンドだったかもしれないけど、そうしたらこのプラトニックさは失われてしまう、という美しい儚さを持った、なんとも脆い物語だと思っています。
#三島由紀夫 #小説 #夏の読書感想文
