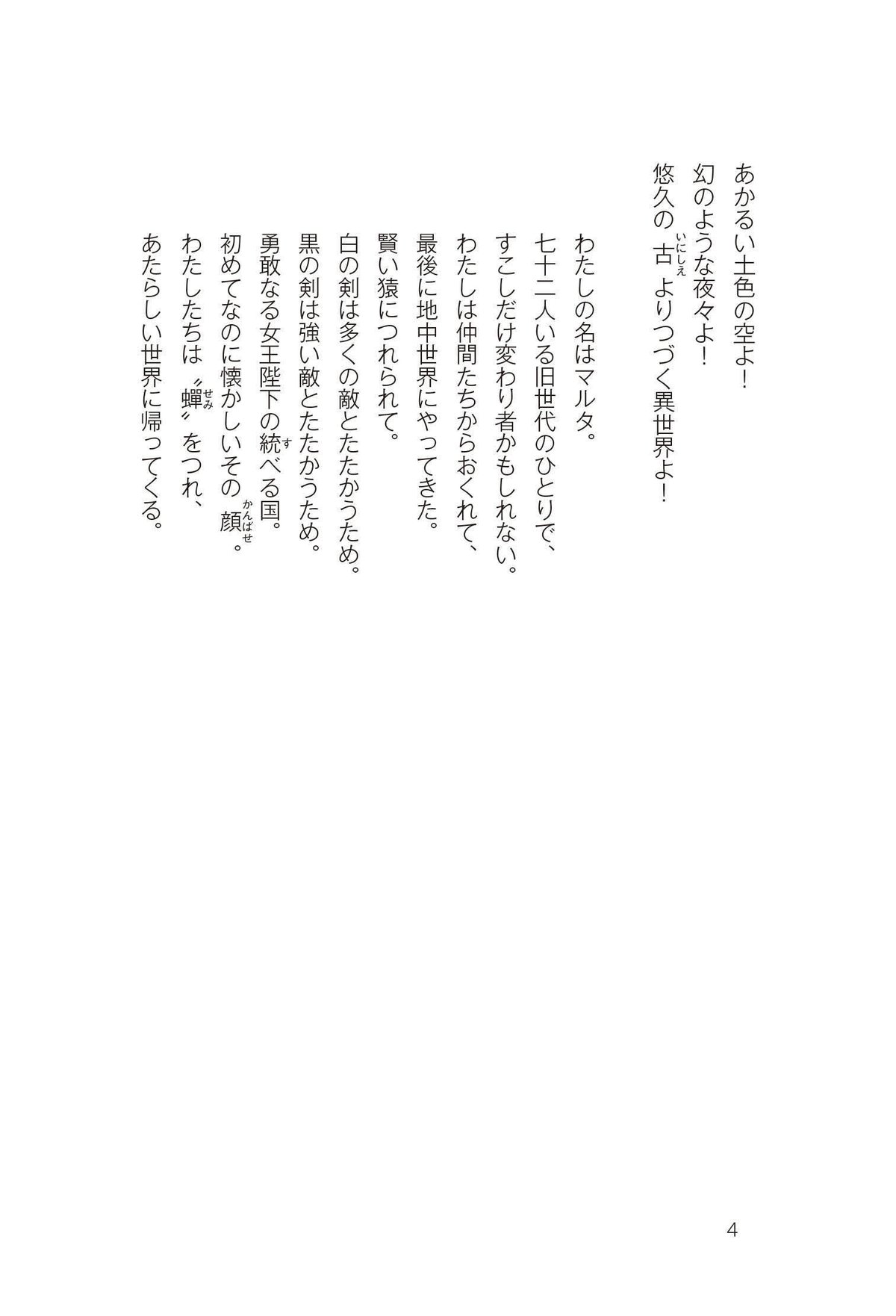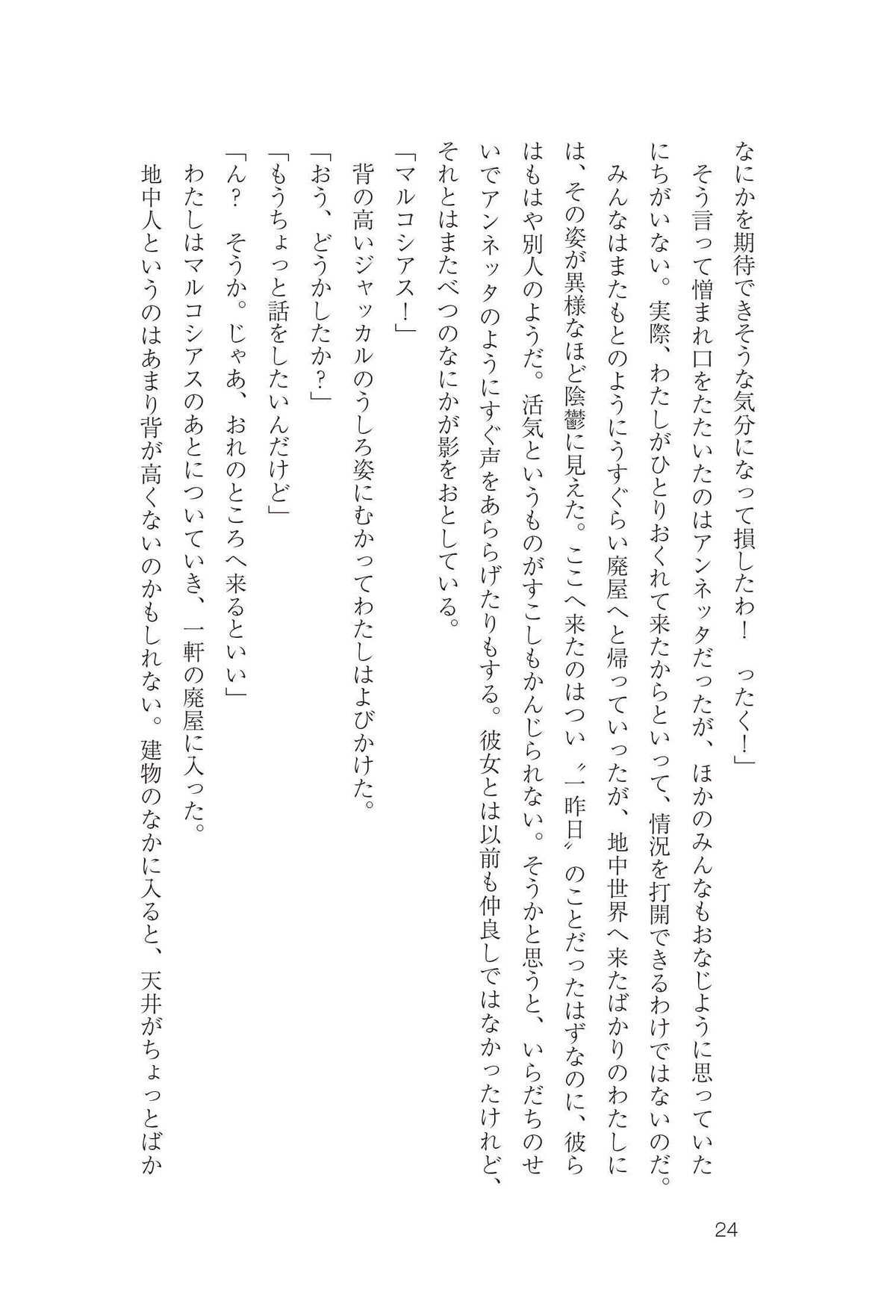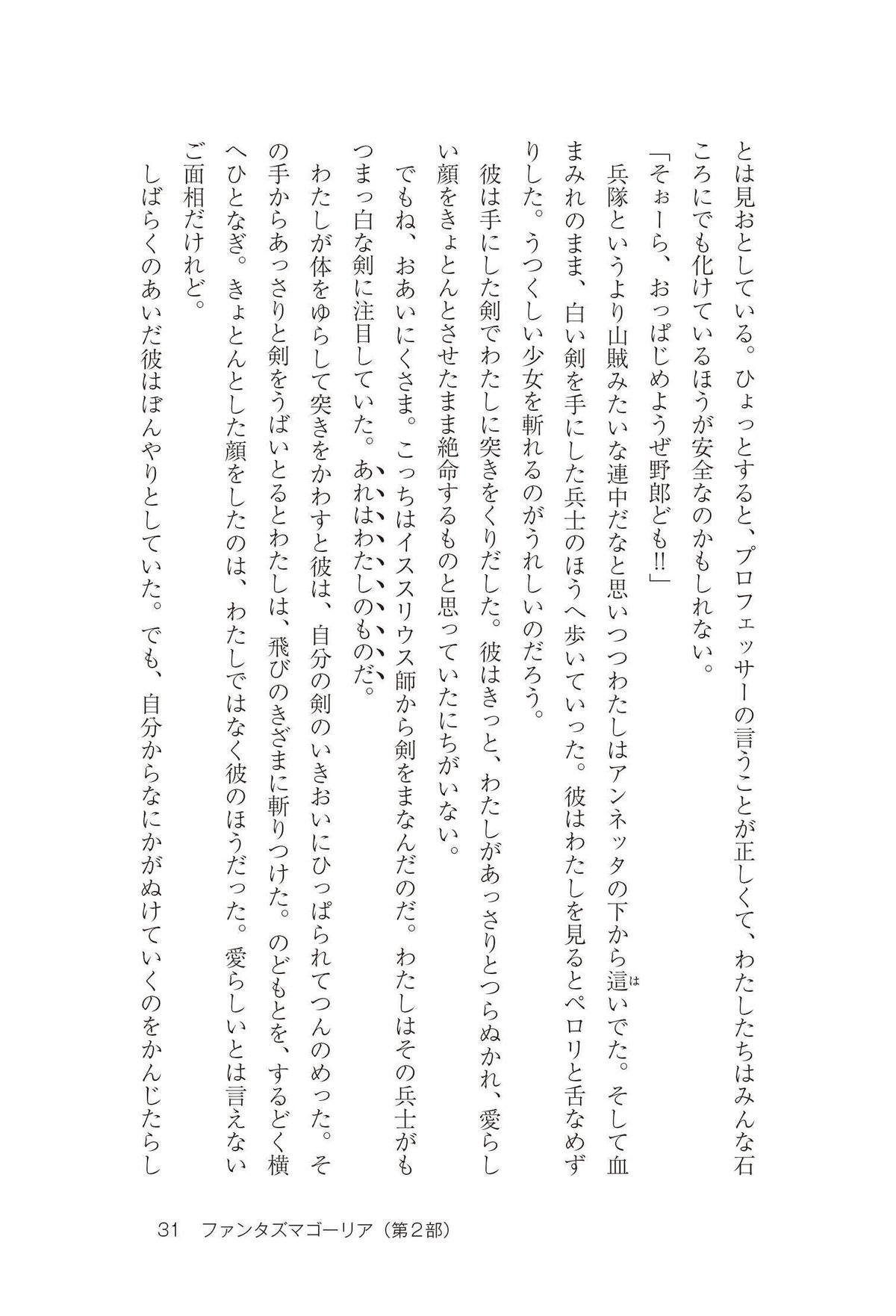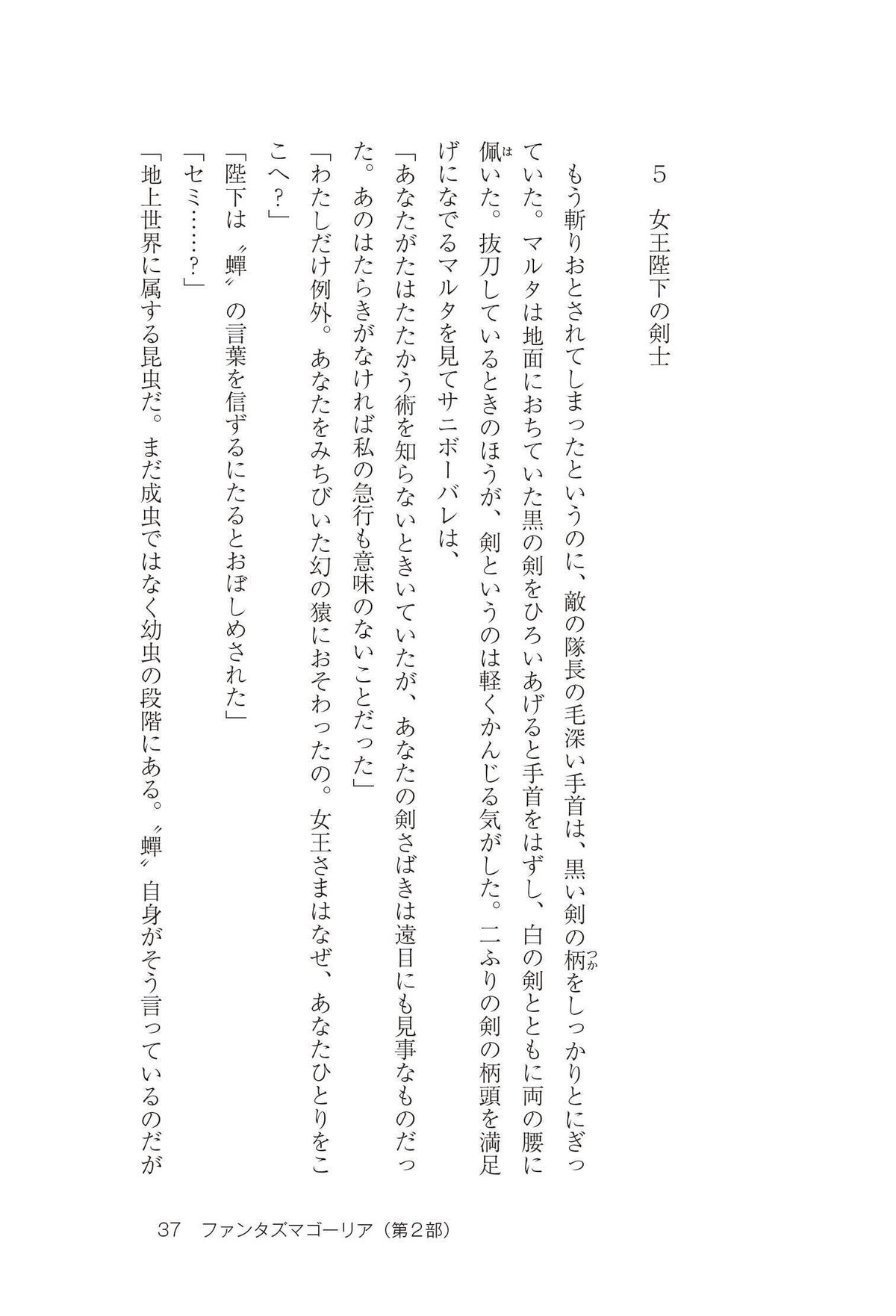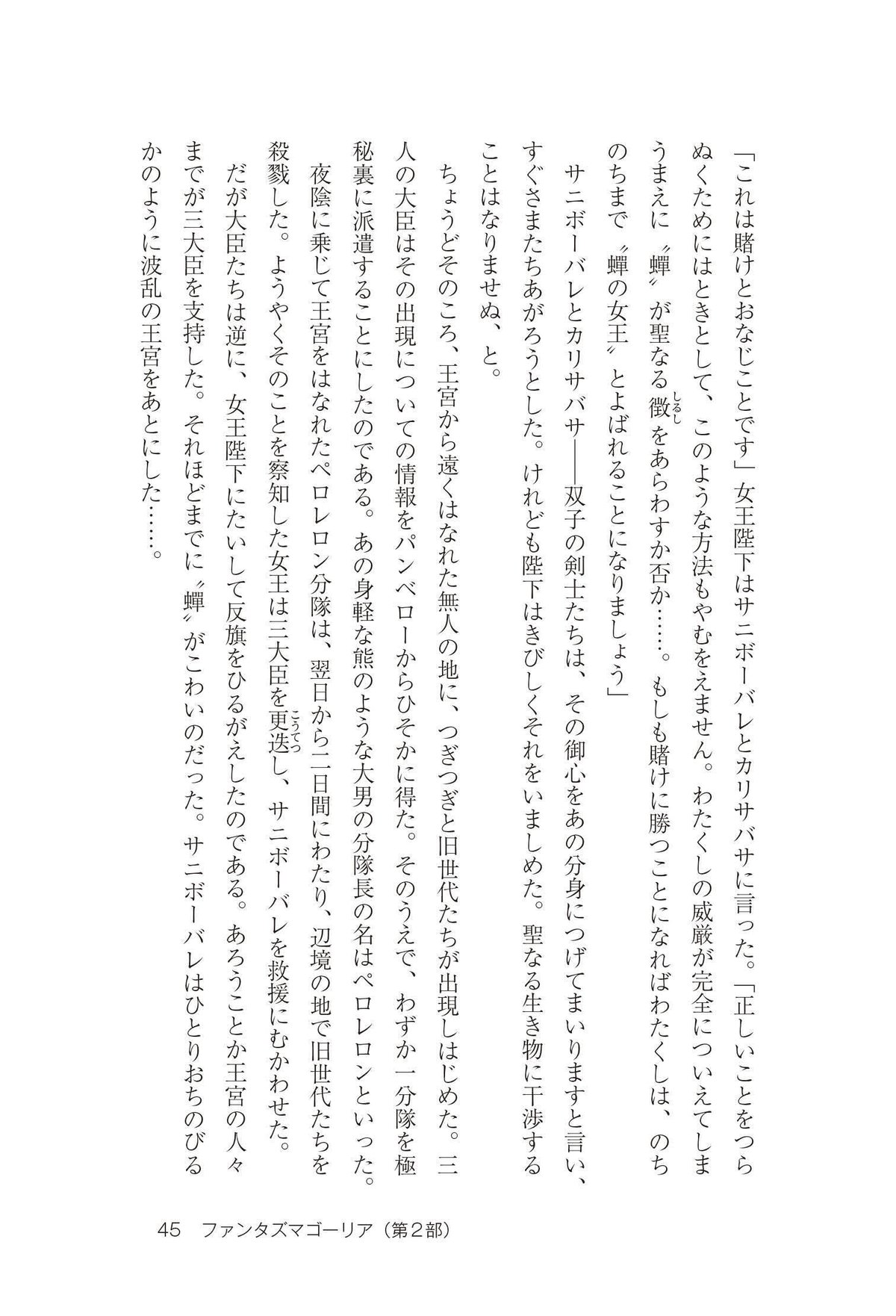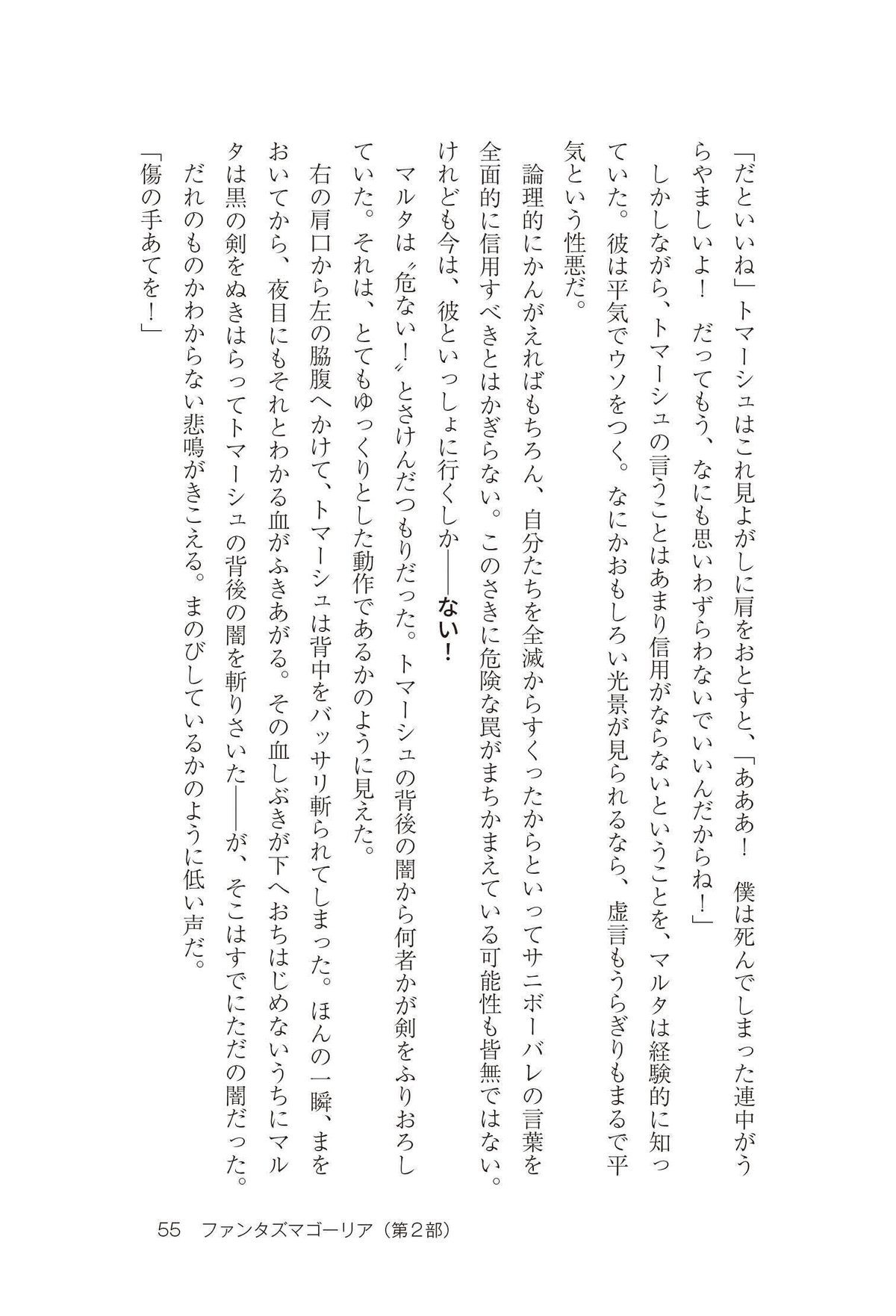ファンタズマゴーリア(第2部)
『群像』2012年10月号
『ファンタズマゴーリア』2014年9月(講談社)所収
第2部の舞台は地中世界です。地底世界でもなければ、地下世界でもなく。
生き埋めという死に方は、想像しただけでもゾッとします。四方八方を閉ざされたまま、ろくに身うごきできず(でもちょっとはうごけて)、圧しつぶされそうになりながら(でもつぶされはしないまま)、狭いところで、息がつまって(そのうえ失禁までしているかもしれない状態で)死ぬのは、かなり無惨なのではないかと。
生きながら埋葬されるとか、棺桶の蓋を内側からひっかきつづけるとか、恐怖のあまり(というか絶望のあまり)髪がまっ白になるとか、そういうのはもう、何にも増して耐えがたい、と個人的には思います。おざなりの土饅頭ぐらいならまだしも、それなりの深さであれば、そうそう掘れるものでもないでしょうし…。
というわけで、地面の下というのはかなり苦手な領域なのですが、にもかかわらず、地底旅行とか地下世界探検とか地球大空洞説などといったものが嫌いではないというか、むしろ好物かもしれず、そういった題材の作品があると、ついつい気になってしまいます。怖いもの見たさかもしれないし、フィクションなら自分が生き埋めになることはない、などとたかを括っているのかもしれません。
とはいえ、自分の作品として書くのであれば、画期的とまでは言わないまでも、ちょっとはユニークな世界観を提示せねばなるまい、いや、ぜひともやってみたいものだ、ということで、生き埋めにならない地中という、なんとも素敵な世界を描いてみたわけです。
そして、地中へ行くのであればやはり、蟬(幼虫)はつれていきたいな、と。蟬(成虫)は、小さくはないサイズの昆虫なので、怖がる人もいるでしょうし、ビックリさせられた経験がある人もいれば、鳴き声が苦手な人もいるかもしれないですけど、いたって無害な生き物というか、咬まないし、刺さないし、毒もないし、生まれてから死ぬまで(幼虫の頃も成虫になってからもずっと)口にするのは樹の汁だけ、という質素な生き物で、手の中に入れてみると、ほんのり温かみも感じます。
土の下に7年いて、地上に出たら7日で死ぬ──などと儚さ・空しさの象徴のひとつのように言われるのは、いわゆる俗説みたいなものというか、数字をきれいにしすぎてはいるものの、幼虫期間と成虫期間の長短の比率は実際かなりアンバランスなので、まあ、それはそれでいいのかな、と。
しかしそうは言いながらも、蟬の成虫というのは要するに、植物でいうなら〝花〟で、キノコでいうなら〝子実体〟みたいなものだろうから、生活の大部分は、それ以外のところにあるのではないか、とも思います。
とまれ、微に入り細に入り──というほどではないものの、その他にもあれこれ、自分なりのものを携えて行ってみた地中、という次第です。
※メンバーシップ限定になっていた『ファンタズマゴーリアの世界』をオープンにしたので、そちらもどうぞご覧ください。