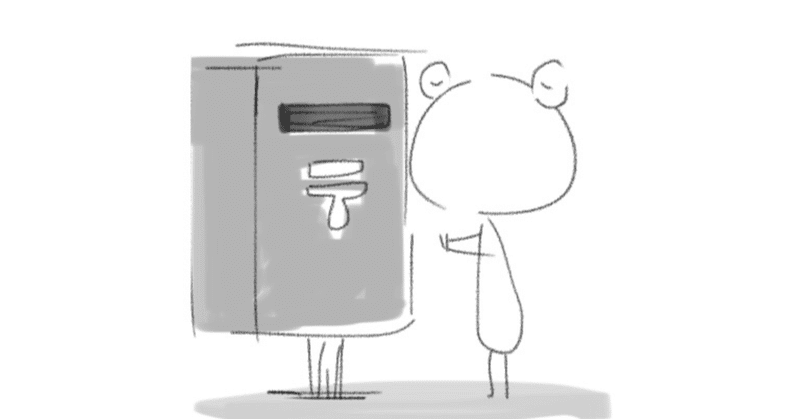
届かない手紙というヒューモア
1.『かえるくんとがまくん』の「おてがみ」
アーノルド・ローベル氏の『かえるくんとがまくん ふたりはともだち(Frog and Toad are Friends: 1970年刊)』の最後に収められた「おてがみ(The Letter)」。この可笑しくもの悲しいがあたたかい短い話のなかに込められているのは、人生についての深い洞察である。
子供の英語の教科書に載っているこのかえるくんとがまくんの手紙の話は、かたつむりが手紙を届けるのに4日も経ってしまったことで笑いを誘うし、がまくんの悩みは子供からみても大したことがないように思える。
がまくんは人間で言えば歳を取った年配の男性という設定になっている。故にかえるくんとがまくんのシリーズではいつでも自分の小さな悩みや想いを訴えたり感情的にそれを行動に移すが、特に深い思慮や反省はない。そしてそれによって本人にとって悲劇的だが読者の笑いを誘うような結末になることが多い。かえるくんはがまくんの若い友人であるが、素直で誠実であり、ときにがまくんと同じく行動し、ふたりの出来ごとはさまざまな悲喜交々の結果をもたらす。
そんながまくんの手紙の悩みは、「自分宛に手紙が届かない」ことだった。当然かえるくんはそんながまくんを励まそうと手紙をがまくんに書く。かえるくんは、がまくんのそんな悩みを自分で解決したかったからだ。
そこで不思議なのは、何故かえるくんはがまくんに手紙を直接届けなかったのか。
しかもかえるくんは手紙を書いて出した後に、がまくんに手紙を書いたこと、内容も含めて先にがまくんに伝えてしまう。話はここで終わりでも良かったのではないか。
結論から言えば、かえるくんは手紙を書くことが大事なのではなかったからだ。かえるくんが伝えたかったことは他にあったのだ。
がまくんは自分宛に手紙が届くまでの時間が、届かないという結果があると思うと、待つこと自体が苦痛で「悲しい」言っていた。つまり、未来に福音があるかどうかわからずに待つこと、そしてそれが失敗に終わる可能性を待つこと自体が悩みなのだ。
かえるくんは、その待つ時間の悩みを理解していたので、手紙が来ることを伝えた上で、かつ待つことを選択した。かえるくんは、がまくんと自分にとってその悩みをかかえる時間そのものが、ふたりであればそれが結果如何に関わらず、福音であることを知っていたからだ。
実はがまくんの悩みは、人間が死に際に悩むこととよく似ている。
死に際に後悔するのは、自分がなし得なかったり出来なかったという後悔と、まわりの家族や知人に愛されていたかどうかだ。そして前者のために後者が成り立たず、自分が役立たない無用な人間だと思い込んでしまう。これは手紙が届かないことで悲しいと嘆くのと同じである。
しかし人生の意味は届いた手紙という結果で決まらないし、その結果が良くなかったからといってけして愛されてないわけではない。
かえるくんは、そんながまくんの側にいながら、自分ががまくんを友人として大切にしていること、その気持ちは結果そのものではなくて一緒に過ごす時間にあると知っていたのだ。
だからかえるくんはまず自分の気持ちを手紙に書いた。なのでそれをがまくんに聞かれたまま答える。がまくんは驚くが、幸せな気持ちになる。これで一旦がまくんの悩みは解消されたように見える。
かえるくんが本当に伝えたかったのはそれだけではない。がまくんと同じ気持ちで手紙、つまり未来を待つこと、これまでと変わらずふたりがともに経験する時間を過ごすことが大事なのだ。だからがまくんもかえるくんも一緒に手紙が届くのを待つのである。この待つ時間は長ければ長いほど幸せだ。4日もかけてかたつむりくんはいい仕事をしたのである。
柄谷行人は、フロイトが死刑囚が冗談を言うことや正岡子規の死後について延々と書く態度について、現実の酷さについて自分を客観的に述べる笑いとしてヒューモアと呼んだ。
それは「自我の苦しみに、そんなことは何でもない」と親が子に笑って諭すようなものだ。がまくんに対するこの手紙の話はヒューモアに満ち溢れていて、かえるくんの態度は親が子にする態度によく似ている。
だから私たちはこのがまくんの悩みを笑うことができるが、本当の意味で笑うことは出来ない。自分たちには、がまくんのような自我の苦しみばかりだからだ。
がまくんとかえるくんの話は手紙であるが、そこには死や別れを連想させる。がまくんが死に際に同じことを悩んでいてもきっとかえるくんは同じことをしただろう。かえるくんからのがまくんへの愛を伝えるだけでは不十分であり、本当に伝えたかったのは共に過ごしたこれまでの時間そのものなのだとして、共に手紙を待つことを選んだに違いない。
死あるいは別れを待つ態度とは、ここに集約される。死=結果だけを考えるとひとは不安に苛まされるだけだ。
死刑囚や正岡子規がそうだったように、その現実を捉える態度を変えることが、人をその苦しみから周りの人達も含めて和らげらるのだ。ここで大事なのは、死や別れという結果は変わることなどないことだ。そんな魔法などありはしない。ただそれに対する態度の変更はすさまじく大きい。そのことがヒューモアとして当事者以外の心も動かすのである。
2.のび太の届かない手紙「さようなら、どらえもん」
がまくんのような自我の苦しみを、パートナーであるかえるくんが助けるという構図は見慣れたキャラクターの組み合わせである。この典型はドラえもんだ。言わずもがな、がまくんの役割はのび太である。
のび太はがまくんのような日々悩みに尽きない子どもであり、その解決の手助けを例のひみつ道具をもってするのがドラえもんである。たいていその結果は悩みが解決したとしてものび太には違う結果をもたらしてしまうところもよく似ている。
こののび太とドラえもんの関係性は安定していて終始変わらないように見えるが、一部のエピソードはこれが逆転することがある。
その代表作が、「さようなら、ドラえもん」(1974年初出)である。
この話は有名なエピソードだが、普段悩みを持つことが少ないドラえもんが、がまくんのように悩みを抱えてはじまる話である。この時点ですでに逆転している。
ドラえもんの悩みとは、未来に帰らなければならない、ということであり、それはのび太との別れを意味する。ここで大事なのは、のび太と別れることそのものよりは、ドラえもん自身の自我の苦しみであることだ。それは人生で多くの人が後悔するのと同じく「自分はのび太の未来を変えるほど、のび太を成長させたか」という問いだ。自分が成功していないまま去ってしまうことについて苦しんでいるのである。
がまくんの手紙と同じく、ドラえもんは成功したか失敗したか、という結果そのものにとらわれている。このような悩みは過去に対して「自分は十分に事を成し得たか」と問う時点ですでに出口がない。そしてこの過去についての後悔がそのまま現在に投影される。つまり、ドラえもんはのび太にとって意味のない存在だ(だからのび太に愛されていない)というように負のスパイラルになる。
だから本来ののび太とドラえもんの関係性なら、のび太がドラえもんとの別れがイヤで、いかにしてそれを逃れようかと行動し失敗して、それをドラえもんがなだめる、というのがお決まりなのだが、これが逆になっている。では、ひみつ道具も持たないのび太はどうドラえもんの悩みに立ち向かうのか。
のび太はドラえもんの悩みをよく理解していた。かえるくんのようにがまくんに直接伝えることはしなかった。かえるくんが「手紙を書いた」ようにドラえもんにわかってほしかったからだ。それは、言い換えれば、のび太がドラえもんには価値があることを伝えるには、自分自身の価値をドラえもんに見せることが大事だと思ったからだ。
のび太は、そうして勝てそうもないジャイアンとのケンカに挑む。読者にとっては何のひみつ道具の助けもなく、また何の努力もしていないいつもののび太なら勝てる訳がないことを知っている。
しかし、のび太はドラえもんも読者も気付いてないことを知っていた。それはこのケンカに勝てなければドラえもんにのび太の成長を示せないこと、つまりドラえもんの苦しみから解放されない、それはドラえもんに価値がない、ドラえもんは愛されてないと認めてしまうことだからだ。
のび太がどんなに殴られてもジャイアンに必死でくらいつくのは、のび太自身の苦しみから解放するためだからではない。それはドラえもんのためだからである。ジャイアンがのび太を最後に恐れるのは、のび太自身にケンカを止めるように殴るという苦痛を与えても、それが一向に効き目がないからである。他人のために自身の苦しみを耐えるのび太に心底恐怖したのだ。このような相手に勝てるわけがない。
のび太はボロボロになりながら、迎えに来たドラえもんの背中でジャイアンとのケンカに勝ったことを伝える。この作品が感動的なのは、こののび太のヒューモアにある。自身がボロボロなくせに、悩んでいたドラえもんに対して「そんなことは何でもない。安心していいんだよ」と、のび太が親のようにドラえもんに言っているかのようだ。そしてドラえもんは初めて気づくのだ。
のび太はドラえもんが出会ったときから変わらずだからと言って、ドラえもんが成功したか失敗したかに悩むのはバカバカしい。のび太がドラえもんのことをこれほどまでに大事に思って自分のこと以上に気にかけている。結果が自分の価値を決めるのではない。のび太からのドラえもんへの愛情がそれを決めるのだ。
愛という概念は男女の恋愛のことだけを示すのではない。特に親子のような愛情は、他人からの見返りを期待せずに奉仕することだ。親は赤ん坊からの見返りを期待して世話するのではない。だがここに愛の逆説がある。のび太がドラえもんに対して愛情があるから、自身の苦しみを乗り越えられたように、他人のために行動していることが結果的に自身を成長させるのだ。親は子のことを想い尽くすことによって、自ら成長するのである。
自分自身のためだけに行動すると、がまくんやドラえもんのように自分で成し得た事が何かという成功や失敗に囚われ、文字通り一生後悔する。もしくは結果だけが全てであり、自分も他人も結果でしか判断できなくなり、愛することも愛されることからも遠ざかってしまう。
さようなら、ドラえもんは、思いのほかドラえもんの台詞が少ない。これは作者が意図的に、いつもののび太を裏切って、読者にドラえもんの側から感じてもらいたいからだろう。
最後の一コマは、のび太のモノローグで終わる。それには再び「心配しないで」とドラえもんに語りかけるのだ。これは、かえるくんががまくんに書いた手紙の内容と同じである。のび太はここで自分の気持ちを届かない手紙に託している。
この話はこの後も延々と続くドラえもんの話のなかでは異質だ。だか今でもこのエピソードが愛されるのはいつか読者が体験するであろう別れや死について、この話を思い出してもらいたいのだ。
別れそのものは悲しいが、それに意味があったか価値があったかを結果だけから判断するのは難しい。そこには必ず後悔があり、それによって残された人は一生苦しみ続ける。だからこそ、今はいない誰かのことを思うならば、彼らのためにも未来に向かって「手紙」を書き続けるのだ。
3.死ではじめて伝わる想い『ごんぎつね』
『ごんぎつね』(1932年初出)は、新美南吉の代表作で、こちらも子どもの教科書の常連である。
新美南吉は動物を題材にした物語が有名だが、彼にとってのごんきつねのような動物は物語上の便宜的な設定のように感じる。なぜならごんぎつねは、まるで人間のように考えるからである。
この物語は、兵十とごんぎつねのすれ違いについての短い話である。ごんぎつねとは、確かにいたずら好きのきつねではあるが、悪意があるわけではない。ただ自分のためだけに生きている動物だ。ただし、ごんぎつねが孤独であるからと言って、人間への関心や想像力がないわけではない。兵十の母が死んだことに同情もすれば、自分ではなく神さまの仕業だと決めつける人間にも嫉妬する。
人間ときつねは本質的に分かり合えるわけがない。この物語は、そこから出発する。きつねが人間のことを気にかけて行動するわけがなく、彼らはただ勝手に振る舞っているだけだ。
新美南吉は、そこでふと考えたに違いない。だが、それが通じ合うことがあるとすれば、どんな形で可能だろうか、と。
ごんぎつねはウナギを逃したり、いわしを投げ入れたりしたことで、人間の行動を学んでいくが、人間にはそれは分からない。きつねは人間のことばを話すことが出来ないからだ。
だとすれば、ごんぎつねの行動を人間に見せるしかない。
ただし、それには人間がいかにごんぎつねのことを理解していないことを示さなければならない。だから栗をもたらしたのが神さまだと誤解したりするのである。
そして、人間がごんぎつねの姿を見れば、悪いきつねとして行動せざるを得ない。兵十が火縄銃をごんぎつねに向けるのはそのためだ。
もしここで仮に兵十の前からごんぎつねが逃げていたら、兵十は栗を持ってきたのがごんぎつね理解したかもしれないが、ごんぎつねには兵十の思いは伝わらない。
兵十は撃って驚いてごんぎつねにその思いを言ったからこそ、ごんぎつねの死に間際にそれが伝わったのだ。
ごんぎつねは、ずっと最初からごんの主観の視点での語りだったのに、この最後の場面では兵十の視点に切り替わっている。それはごんと兵十のすれ違いが顕著だったことを示すためである。
ごんぎつねというキャラクターは、兵十の苦しみに対して、かえるくんやのび太のようにその苦しみを和らげようと食べものを届け続けた。だが、きつねだからこそでもあるが、その気持ちは直接伝えることが出来ない。それは行動で示さなければならない。
ごんぎつねは、兵十に対して想いが通じるのはその死を通してである。そして兵十は自らの行動を後悔するに違いない。ごんぎつねがもし生きていたら、この後も兵十に栗を届けていただろうか。それとも思いが伝わればそれで良かったと、二度と現れないだろうか。そのような手紙を、兵十はごんぎつねの死を通して受け取ったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
