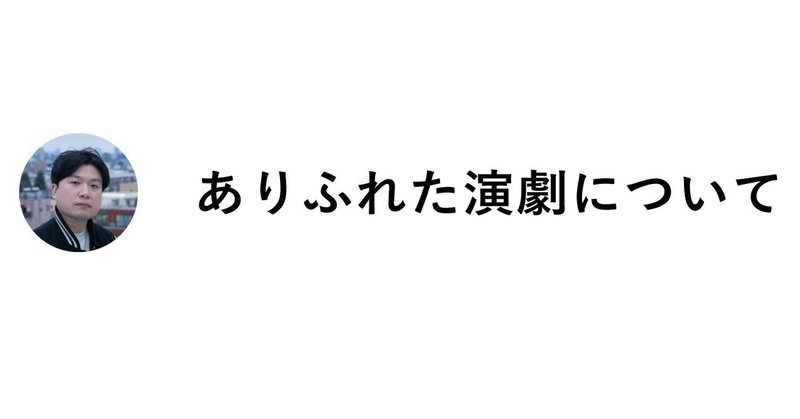
「ありふれた演劇について」31
先日、円盤に乗る場でイプセン『幽霊』を声に出して読む読書会を開催した。
当日はZOOM参加も含めた数名の参加者で役を振り分け、演技を重視せずにただ声に出して最初から最後まで「通読」した。数年前に一度読んだことのある戯曲だったが、同時代の人間でないと理解がしづらそうな場所も多く、当時はそこまでピンとこなかった(放蕩息子オスヴァルが罹患したのは梅毒と言われているが、直接的な言及はなく、予備知識がなければ何の病気かわからないだろう)。むしろイプセンで言えば『人形の家』や『野鴨』の方がまだわかりやすかった。それでも、将来に絶望したオスヴァルが虚ろな目で「太陽。――太陽。」とつぶやくラストは印象に残っていたし、どこか気になる作品としてずっと意識をしていたように思う。
今回改めて読んでみて、ここで言われている「幽霊」という存在、古い因習や思想、父親や母親からの遺伝といった、どうしても追っ払えないものの存在はリアリティをもって感じられたし、それと同時に「幽霊」に行く手を阻まれた登場人物たちの閉塞感や絶望感をまざまざと感じとることができたように思った。声に出して戯曲を読むことによって、その言葉が否応なく現在を生きている我々と関係してくる。その言葉はどこか、かつて我々の身体を通じて発されたことがあるようにも思えるし、その言葉の響きの感覚を覚えているような気もする。そして言葉の対象は、どうしても現在の我々を取り囲む状況に向かう。このオスヴァルの絶望は、アルヴィング夫人のやりきれなさは、まさに今の我々の状況なのではないか? と思えてくる。
アルヴィング夫人は、夫の不義によって汚れた家の空気を吸わせまいと息子のオスヴァルを外国へ留学させた。オスヴァルは自由思想に触れ、芸術の道を志した。進歩的であること、古いものから脱却することは、確かに希望のあることなのかもしれなかった。しかし結果として、オスヴァルは父から遺伝したと説明される病気(=梅毒)によって精神に異常をきたす。保守的な社会はアルヴィング夫人の価値観を受け容れることはできないし、名士とされる亡き夫の影(幽霊)から逃れることはできない。実際の歴史はさておき、少なくともこの戯曲の中では、これより先の進歩は存在しない。完全な行き止まりだ。ここより先には未来はない。戯曲を通じて、我々は「そこからの未来がなくなった世界」を疑似体験する。これは世界の終わりを描いた聖典でもないし、ましてやSF小説でもないが、しかし間違いなくここに描かれているのは終末であり、時間の最果てだ。
円盤に乗る場での読書会はこれで2回目だが、1回目はエウリピデスの『トロイアの女たち』を読んだ。これもまさに、これ以上の未来のない世界を描いた作品だ。あらゆる希望は絶たれ、戦争に敗北したトロイアは崩壊する。男たちは殺され、残された女たちには隷従の道しかない。また勝者たるギリシアも、神の怒りに触れたために繁栄は約束されない。
戯曲は読まれるたびに、あるいは上演されるたびにひとつの世界を構築する。そして終劇を迎えると、その世界は終わる。少なくない演劇作品が、この世界の終わりをまさに主題として扱おうとしてきたように思える。未来が費やされ、完全な行き詰まりにぶちあたっている。先日読んだ渡邉大輔『新映画論』でも、現代映画における重要なモチーフとして「絶滅」を挙げていたが、紀元前に生きていたエウリピデスも、19世紀のイプセンも、現代に生きる我々も、同じく未来のなさを実感しているのかもしれない。もちろん、これら異なる時代の作家が、全く同じことを感じていたと言うつもりはない。しかし21世紀を生きる我々は、21世紀における終末観、世界の終わりの実感をもちながら、過去の様々な戯曲の終わりを体験する。その体験そのものに、現在において様々な戯曲を読み、上演することの意義があるだろう。
今自分が取り組んでいる戯曲に、サミュエル・ベケットの『クワッド』がある。テレビのために創作された作品で、4人の人物が決まったパターンで歩行するだけの、非常にシンプルなものだ。ジル・ドゥルーズは後期ベケット作品について論じた『消尽したもの』の中で、『クワッド』について「空間を消尽することが問題なのだ」と書いている。
疲労したものは、ただ実現ということを尽くしてしまったにすぎないが、一方、消尽したものは可能なことのすべてを尽くしてしまう。疲労したものは、もはや何も実現することができないが、消尽したものは、もはや何も可能にすることができないのだ。
宇野邦一、高橋康也訳
空間に対して、「可能なことのすべてを尽くしてしまう」こと、「もはや何も可能にすることができない」こと、すなわち「消尽する」ために『クワッド』の上演は行われる。様々なパターンの歩行の組み合わせによって、4人の人物、ひとつの正方形とその対角線をめぐる、あらゆる全ての可能性が尽くされる。ここには、これまで例に挙げてきた『トロイアの女たち』や『幽霊』に続く、世界の終わりを体験する戯曲の系譜を見出すことができるだろう。『クワッド』はそもそも演劇作品ではないし、内容からしても異端な作品であるとみなされがちだが、扱っていることそのものは戯曲の歴史からすればまさに王道と言っていいかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
