
Black lives matterイン スウェーデン、そして、ガンビアとの知られざるつながり
先週、種田麻矢さんがデンマークでのBlack lives matter運動と、それに関連した歴史について書いてくださいましたが、隣国スウェーデンでもBlack lives matter運動は大きな盛り上がりをみせ、新型コロナウイルス対策で50人以上の集まりが禁止されているにもかかわらず、各地で大規模なデモが行われました。私の住んでいるマルメでは、ソーシャルディスタンスに配慮して海沿いの広大な公園をデモ会場としたのですが、それでも参加人数が多すぎて、距離を守りきれていなかったと思います。
時節柄、こうした大規模デモに参加したくない人、参加できない人も、多くの人がオンラインで意思表示をしていました。在スウェーデンアメリカ大使館にタグ付けして下の画像をSNSにアップしたり、真っ黒な画像をアップする「Black out Tuesday」に参加したり、といったぐあいです。

「アメリカの問題でしょ?」と冷ややかな目でこれを見ている人々は、もちろんスウェーデンにもいます。ですが、アメリカとはまた違った形にせよ、スウェーデンにも明らかに黒人差別は存在します。「スウェーデンには関係ないって思ってる人、目を覚まして!」とばかりに、各分野で活躍する黒人たちが情報を発信しているのを見て、私も、いろいろ考えるところはありつつも(それについてはあとのほうに書きます)Black out Tuesdayに参加したりしていたのですが、SNSで意思表示するだけで終わらせてはいけないと思い、自分なりに少し勉強してみることにしました。
****
デンマークの植民地と奴隷貿易については、先週種田さんが書いてくださったとおりですが、スウェーデンにも同様の黒歴史があります。たとえば、デンマークが現在のガーナを拠点として奴隷貿易を行っていた、と記事にありますが、実はスウェーデンも1650年前後、ガーナに交易拠点を獲得して奴隷などの交易を行っていました。いまもガーナに残るケープ・コースト城は、もともとスウェーデン国王カール10世グスタフにちなんで、カロルスボリ(Carolusborg)の名で建てられた要塞です(1658年にデンマークに奪われ、数年後に取り戻し、最終的には1663年、イギリスにこの地を奪われて終わっています)。さらにその後、1784年にフランスと取引して手に入れた植民地、カリブ海のサン・バルテルミー島(現フランス領)で、奴隷貿易による利益を得ていたのも、わりと有名な話です。
とはいえ、現代のスウェーデンで暮らしている黒人は、こうした奴隷取引の直接的な結果としてこの国にいるのではなく(間接的な結果だとは思いますが)、政治上の理由で逃れてきたり、働き口を求めて移り住んできたり、スウェーデン人と結婚して移住してきたりしているようです。そして、彼らに対する差別は、スウェーデンにも確実に存在します。2018年の調査では、アフリカ系スウェーデン人が管理職に到達する確率が、それ以外のスウェーデン人の10分の1ほどにしかならないこと、管理職になってもほかに 比べて給与が低いこと、アフリカ系でないスウェーデン人が高校卒業後に大学や専門学校で3年の教育を受けた場合(ちなみに大学の場合、専攻にもよりますが、学士号は3年で取れます)の可処分所得と、アフリカ系スウェーデン人が博士課程まで行った場合の可処分所得が、だいたい同じぐらいであること、などが明らかになっています。これはそのアフリカ系スウェーデン人が外国生まれであろうとスウェーデン生まれであろうと、あまり変わらないそうです。(注1)
2015年にはこちらの本、『Svart kvinna(黒人の女)』が話題になりました。フリーライターでアクティビストのファンナ・ンダウ・ノルビー(Fanna Ndow Norrby)が2014年に開設したインスタグラムアカウント、@svartkvinnaに寄せられた、黒人の女性が受けた差別の体験談を、一冊の本にまとめたものです。人種差別と性差別という二重の被害にあっている彼女たちの体験は、もうショッキングとしか言いようがなく、読んでいて吐き気のする内容です(いくつか訳して載せようかとも思ったのですが、あまりにも気分が悪いのでやめました。またの機会に)。
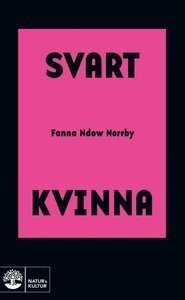
さて、このファンナ・ンダウ・ノルビーは、ガンビアにルーツがあります。西アフリカの小国ガンビアにルーツを持つ人がスウェーデンに多いことは、前から少し気になっていました。セネガルに三方を囲まれたガンビアは、人口200万人ほどですが、スウェーデンにはガンビア生まれの人が5000人以上いるそうで、スウェーデン生まれでガンビアにルーツのある人を含めれば、数はもっと増えるでしょう。かつて文化・民主主義大臣を務め、いまEU議員をしているアリス・バー・クンケや、歌手のセイナボ・セイ、そして上記のンダウ・ノルビーなど、各界でガンビア系スウェーデン人が活躍しています。(言うまでもありませんが、一部の人が活躍していることと、上記のような差別が歴然と存在することは、矛盾しません。)
やはりガンビアにルーツを持つジャーナリスト、アマット・レヴィーン(Amat Levin、注2) の本『Slumpens barn(偶然の子)』は、今年4月に刊行されたばかりで、今回のBlack lives matter運動に関連していろいろなところで紹介されていたので、さっそく読んでみました。「スウェーデンがガンビアに出会ったときの、ありそうにない物語」という副題がついています。

各分野で活躍するガンビア系スウェーデン人へのインタビュー、中世のマリ帝国の時代から植民地支配を経て独立したガンビアの歴史、近年の政治情勢についての解説などが盛り込まれている中で、すべてをつなぐ糸のように、著者自身の生い立ちが語られた本です。
この本によると、ガンビアとスウェーデンの強いつながりが生まれたのは1960年代。ある意味「現代の植民地主義」と言ってもいいのかもしれない、観光業が大きな要因でした。1965年、スウェーデン人の休暇先としてセネガルを開発できないかと考えた実業家ベッティル・ハーディングが、道をまちがえてうっかりガンビアに入り、その美しさに魅了されたというのです。同年末にはスウェーデン人観光客がチャーター機でガンビアに降り立ち、ガンビアの観光業がスタートを切りました。これはガンビアの経済発展に寄与しましたが、その一方で、観光業はもともとあった産業や自然環境を損なううえ、政情などに左右されやすく不安定でもあり、またアルコールや売買春などの問題をもたらしもするので、けっしていい面ばかりではないことが、この本からも伝わってきます。いずれにせよ、ハーディングが道をまちがえなかったら、いまこんなにたくさんのガンビア系スウェーデン人はいなかったかもしれない……そう考えると、歴史はまったくふしぎなものだと思います。
どこをとっても学ぶことの多い内容なのですが、私にとってとても印象的だったのは、ガンビア人の父とスウェーデン人の母とのあいだに生まれ、ストックホルム郊外で育った著者が、自分の生い立ちとガンビアとのかかわりを語った部分でした。幼いころ、地方へ旅行に行ったときにじろじろ見られて、はじめて自分が異質な存在であると意識したこと。おもちゃの店で「これはどう?」「あの子は欲しがらないわよ、そんな醜いニグ● の人形」(注3)という会話を盗み聞きしてしまったこと。成績優秀で、ストックホルムの名門といわれる高校(生徒の大多数が白人で、地下鉄に乗ったことがないという上流階級の生徒までいたそう)に入学した彼が、初日に投げつけられた「なあ、これからジャイアントニグ●って呼んでいいだろ? あだ名でさ。きみ、背が高いし、ニグ●だし」という言葉。その一方で、サッカー選手のヘンリック・ラーション(アフリカ北西沖の島嶼国、カーボベルデにルーツがある)の活躍を見たり、アメリカの黒人音楽に没頭したりしていたので、黒人であることの誇りは失われなかった、とも書かれていて、自分と同じ属性を持つ人の活躍をメディアで目にすることが、子どもにとってどんなに大切か、あらためて実感させられます。
両親は彼が生まれる前に別れてしまい、彼はスウェーデン人の母親のもとで育ちました。それもあって、周囲には「アフリカ人」と見られるのに、自分はガンビアのことをあまりよく知らず、子どものころに行ったきりでしかないことが、ずっとコンプレックスだったそうです。そんな彼が、自分の子どもができたのをきっ かけに、やはり自分のルーツをもっと知りたいと考えるようになり、ガンビアに旅立ちます。スウェーデンにいったん帰国して、まったく知らなかった父親の半生についても話を聞き、生まれた息子にガンビアの文化と強く結びついた名前をつけて、ともにふたたびガンビアに降り立ったところで、この本は終わります。自分の中にある複数の文化、アイデンティティーを、そのまま抱え、大切にして生きていく決意を感じさせる本です。
スウェーデンでは、アフリカ系の作家が何人も活躍しています。代表的なところでは、2017年に権威ある文学賞、アウグスト賞を獲得した、ケニアとウガンダにルーツのあるJohannes Anyuru(ヨハネス・アンユル)や、新人作家に与えられる作家連盟のカタプルト賞を2019年に受賞した、コンゴ生まれでタンザニア育ち、10歳のときにスウェーデンに移ったKayo Mpoyi(カヨ・ムポイ)など。そういう作家も少しずつ、日本に紹介していけたらいいなと思っています。
****
ここからは少し個人的な話になってしまうので、興味のない方はスルーしていただいてかまいませんが、これを抜きにして他人事みたいにこの件について書くのは、あまり誠実でない気がしたので、あえて書かせてください。
最初のほうで、Black lives matter運動に「いろいろ考えるところはありつつも」と書きました。それは、スウェーデンでの黒人差別について考えるときに、アジア人である私もここでは差別の対象である、という事実を抜きにすることは(私には)できなかったからです。他人事ではない。けれど、当事者でもない。そんな微妙な立場に置かれているような気がして、正直なところ、はじめは少しモヤモヤしていました。
これには諸論あると思いますが、私自身は、スウェーデンで露骨に差別されていると感じることは少ないです。吊り目ジェスチャーや「チンチョンチャン」でからかわれたり、いきなり出身国を聞かれたり、お店などで失礼な対応をされたりすることは、皆無ではないですが、これまでに住んだり訪れたりしたことのあるほかの国々と比べると、かなり少ないほうだと感じています。
それよりもよくあるのは、非白人やその文化に対する無意識の軽蔑が見てとれる発言、逆にエキゾチックなものとして手放しで賞賛されること、そういった「さりげない」微妙な差別です。(どちらも、対等な同じ人間として相手を見ていない、という意味では同じです。)また、私自身は履歴書をいろいろなところに送る形での就職活動をここではしていないので、直接の経験はないのですが、「スウェーデン人らしくない名前だと面接に呼ばれる確率が下がる」というのは、さまざまな調査で明らかになっていることでもあります。そういう制度的な差別もあります。
とはいえ、みんながみんなそういう差別をしてくるわけではないので、私自身はわりあい居心地よく過ごしています。(私の感じ方がそうだというだけで、そうは感じないという人の体験を否定するものではありません。私に見えていないだけで、いろいろなケースがあるでしょう。また、もし私がスウェーデン生まれのアジア系スウェーデン人でこのような扱いを受けていたら、その理不尽さをもっと強烈に感じただろうとは思います。)
しかし、そんなふうに感じるのには、もうひとつ理由があるかもしれない、とも思うのです。それは、「アフリカ系や中東系など、もっと肌の色の濃い人々に対する差別のほうが苛烈そうだ」という実感です。「それに比べたら……」という気持ちが、私の中になかったか。少なくとも私自身は、道を歩いているだけで犯罪者扱いされたり、警察官や警備員に理不尽な扱いを受けたり、差別のせいで身の危険を感じたりしたことはありませんが、アフリカ系や中東系の人々にはそれがある、ということ。
たとえば、2009年から2010年にかけて私の住む街マルメを騒がせた、アフリカ系や中東系の移民を狙った連続銃撃事件。「日本でも報道されたらしくて、家族が心配しちゃって」と話したら、「あなたは肌が黒くないから大丈夫」と言われました。当然、「そうだよね、よかった」なんて思えるわけもなく。「それで片付 けていいの?!」としか思えなかった。
たとえば、移民排斥政党の動きはとても気になる、私も移民だから、みたいなことを言うと、「きみのことは移民だなんて思ってないよ、スウェーデン人と変わらないでしょ」などと言われる。褒め言葉のつもりで言っているようだけれど、私には「アンタの移民観どうなってるわけ?!」としか思えないし、勝手に「モデル・マイノリティー」のカテゴリーに入れられたようで腹が立つ。
そんな中で盛り上がりはじめたBlack lives matter運動。黒人に対する構造的な差別に抗議する、という主旨には賛同の意しかないものの、自分はどちらの側に立って、なにを言えばいいのだろうか、というところで、私は少し立ち止まってしまいました。私は差別される側だけれど、黒人ではなく、マジョリティーに片足突っこんでるような立場ではあるけれど、白人特権をフルに享受しているわけでもない。ここで「アジア系への差別だってある」と声をあげるのは、大怪我をしている人をさしおいて「ほら見て、私も怪我したの!」と浅い傷を見せるようなものだろう。だからといって、「浅い傷なんだから我慢しろ」というのも、なにかちがう気がする。
でも今回、こうして本を読んだり、いろいろな人の発言を見聞きしたりして、少しだけでも勉強して、スウェーデンの奴隷貿易の歴史を知り、現代の黒人差別の根源にある根深い歴史的経緯もあらためて学んで、思いました。たとえ自分が怪我をしていても、大怪我をしている人のために声をあげ、助けようとするのは当然のことだと。人種でカテゴリー分けして考えすぎていたのは私のほうだった。上に書いたシチュエーションでも、私は「肌の黒い人」への差別に対して、もっとなにか言うべきだった。人間として、すべての差別にNOと言う。当たり前すぎて、「考えた末の結論がこれ?!」ってちょっとへこむけど、やっぱりそれしかないのではないか。
その過程で、負った傷がどんなに浅くても、「私も怪我をさせられた!」と言っていいのだと思います。ただし、言う先はあくまでも、大怪我をしている人ではなく、怪我をさせた人のほうですね。
ナイジェリア系アメリカ人作家、イジェオマ・オルオ氏がtwitterに書かれていたことを、ずっと心にとめておきたいと思っています。
「反人種差別のいいところは、反人種差別主義者を名乗るのに、差別意識をまったく持っていないふりをする必要はない、ということ。反人種差別は、どこであれ人種差別を発見したらそれと闘う、という誓約であって、その“どこであれ”には、あなた自身も含まれる。前に進む道はそれしかない」(注4)
注2:彼もインスタグラムのアカウントを持っていて、「アフリカ」とひとくくりにされがちなアフリカ諸国・地域の多様な歴史を発信しています。 https://www.instagram.com/svarthistoria/ 英語版もあり https://www.instagram.com/panafricanhistory/
注3:『Svart kvinna』でも『Slumpens barn』でも、この「ニグ●」にあたることばは一貫して「n***r」等と伏せ字にされているので、この記事でもそれに倣います。
注4:https://twitter.com/ijeomaoluo/status/1150565193832943617
*補足:トップの画像は、本文に直接は関係ないのですが、タンザニアのザンジバル島、かつて奴隷市場だった場所に残っている、奴隷をぎゅうぎゅうに閉じこめていたという部屋です。ちなみにここには、スウェーデン人彫刻家クララ・セルネース(Clara Sörnäs)の手になる、奴隷貿易の過去を忘れないためのモニュメントもあります。
(文責:ヘレンハルメ美穂)
*このブログは、にほんブログ村の
「海外文学」と「翻訳(英語以外)」に参加しています。*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
