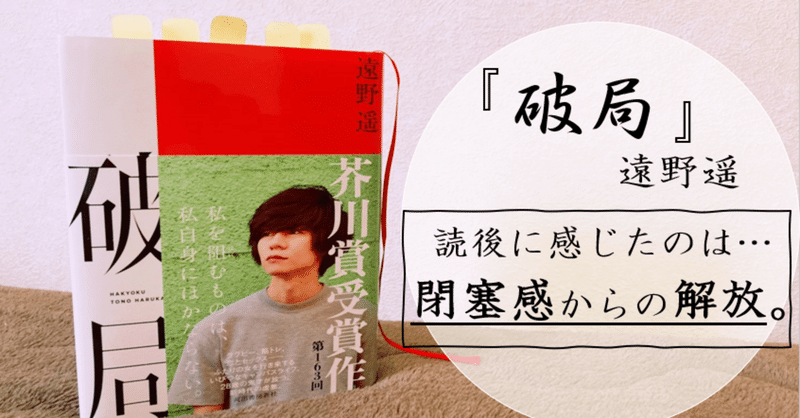
全身にタックルを受けたような重くて鈍い衝撃と妙な解放感を覚えた【『破局』遠野遥】
第163回芥川賞を受賞した『破局』は、昨年2019年に文藝賞を受賞してデビューしたばかりの新人小説家、遠野遥(とおの はるか)によって書かれた。
破局は彼の第二作目にあたり、二年目にして芥川賞まで受賞してしまった。注目すべき作家が増えて心底嬉しい。
未読の方へ向けて簡単なあらすじ
主人公の陽介は、ラグビー部のOBとして後輩を指導しながら公務員試験を控える大学4年生。彼は規範を重んじ、自分にも厳しく筋トレに傾倒する模範的な学生である。友人や彼女もいて、ごく平和的に生きている。
しかし、ある出来事を境に陽介の中の何かがぷつっと切れてしまう。
・・・その先に迎えるのは、”破局”。
芥川賞選考委員会による選評
平野啓一郎 氏
(あらゆることに対して”自律的に他律的”である)主人公が例外的に”自律的に自律的”であったスポーツによって他者を滅ぼし、同時にセックスによって他者から滅ぼされてゆく展開は見事。
吉田修一 氏
わりとよくある就活物の青春小説だが、そこはかとなく新しい時代の香りが漂っていて新鮮に感じられた。
個人的には本作を「若い依存症患者たちの物語」として読んだ。トレーニング依存、ステータス依存、セックス依存、いろいろな依存が出てくるなか、主人公が抱えた「常識・マナー依存」が一番恐ろしい。
松浦寿輝 氏
カミュの『異邦人』や丸山健二氏の初期作品を思い出させる乾いたハードボイルドな文体。抑制された心理描写が返ってこの主人公の不穏な内面をなまなましく暗示する。その不穏さと、公務員志望という一種堅実な保身性との奇怪な対比、ミスマッチ。
しかし、意外性がなく、若さゆえのちょっとした失態といった程度にしか読めない。この男、公務員になり損ねたところで、先輩のつてでそこそこうまくやっていきそうではないか。
小川洋子 氏
正しさからはみ出した奇妙や邪悪を描く小説は珍しくないが、『破局』は正しさへの執着が主人公を破綻させる点において、特異だった。
彼は曖昧な男であるにもかかわらず、見捨てることが出来ない。彼の味わう違和感にいつの間にか共感している。もしかしたら、恐ろしいほどに普遍的な小説なのかもしれない。
島田雅彦 氏
「ラガーマンがストーカーやファシスト、ゾンビ、自粛警察になったら」という設定で読むと不愉快極まりない。この不愉快な読後感は、無知とゆがんだ正義感と過剰な体力のスクラムに押し切られそうな不安とセットになっている。主人公がもし公務員試験に合格していたなら、続編は現代日本を覆う官僚ファシズムの実態を描くホラーになり得る。
川上弘美 氏
表現しようとしていることと、言葉の間に、美しい相関関係があり、その相関関係は一つの完成した数式で表せる、そんなふうに感じました。その意味で、この小説は検算ができるのかと、二度三度読んでいったのですが、いつの間にか検算ができなくなっていた。興味深いです。
奥泉光 氏
「欠落」を抱える主人公は、だからこそ世間の通念に過剰に従おうとするので、そのアイロニーが笑いを生んでおもしろい。
が、「欠落」とは一体何なのかと思考を誘う力が弱い感じがした。暗黒の天体のごとき「欠落」の重力が伝わるならば、それはもう大傑作であるが。
堀江俊幸 氏
ゴールまでの距離感がしっかりしている作品だった。終着点の不意打ちを活かす加速にも無理はない。徹底して自慰的な主人公の、自前のマナー元首にはしばしば笑いを誘われる。
トライを決めない無意識の節度と、見えない楕円球を手放したまま警官の頭越しに見える空の抜け具合に、敵と味方の言葉の呼吸がうまくかみ合っていた。
(文藝春秋 第九十八巻 第九号より引用)
※以下、筆者の感想と考察。
私見:「破局」は「解放」でもあった
素直に読むと、ルールにがんじがらめにされた男の因果応報的な結末に捉えられるだろうが、私はハッピーなラストとして捉えた。
というもの、破局を迎えるまでの私は何やら暗澹たるもやもやした気持ちを引きづっていたのだ。陽介を何かが縛り付ける息苦しさを感じた。陽介は規範を重んじ、悪いとされることをうかつにしでかしてしまうことはあり得なかった。
だが、今にも切れてしまいそうなほどゴムがピンと張ったときの緊張感を感じた。陽介の行動すべてに安心感はなく、そのいつでも弾け飛んでしまう可能性にびくびくしていた。つまり、弾け飛んでしまうことは悪いことだと思っていた。その規律のゴムひもをどうか切らないようにいてほしいと願っていた。
しかし、最後に警官に倒されて何もかも失ってしまった陽介を通して私が感じたのは、一種の安心感であった。これまで私を胸あたりを締め付けていたゴムひもがふっと緩み、「ああ、よかった」と思った。
彼が初めて能動的に起こすべき行動を決めた瞬間だからだ。痛みを感じないゾンビが、初めて痛みを知った瞬間。物質的には、陽介は恋人と将来を同時に失ってしまったのだが、私にとって陽介は救われたようにみえた。
しかし、陽介が救われたように見えたのは、ひもが切れたのがあのタイミングだったからなのであろう。
事実、これまでに陽介は何度も破局へ誘う機会があった。女の白く柔らかい脚を見るために隣の席に座ったり、うっかり未成年の彼女に酒を飲ませようとしてしまったりと、彼が渡らなくて済んだ一線はいくらか存在した。
ただ、陽介が渡ってしまったのが、あのタイミングだっただけである。それも、あれほどの陽介があまり深く考えなかった点が唯一、破滅へ追いやった最大の原因になってしまったのが皮肉である。
いや、灯と知り合うまでのすべての行動が、破局への布石であったか。
陽介についての6つの違和感
陽介には、何か人間らしさというものを感じない。それと対照的に描かれる“膝”という人間臭い友人のおかげで、余計に陽介の無機質な感じが目立つ。読み進めていくと、読者はいくらか違和感を感じるだろう。そして、少し気味悪さと嫌悪感を抱くかもしれない。
作者の遠野遥はインタビューで“陽介に親しみをもって読んでほしい”と、陽介を気味悪がられるのを残念そうに語ったのだが、陽介に対して違和感を感じる理由はそれなりにあった。
――行動を起こす理由が不自然――
陽介の行動はすべて一貫した社会的望ましさによって合理的に決定されていく。しかし、どこか不自然。
”公務員を目指しているから”
”父に言われたから”
”彼女に悪いから”
まるで合理的な判断に見えて、自らの意志というものが微塵も感じられず、形骸的であるように見える。ただ、言われたから正しいのだとしか考えていないようで、独自のステレオタイプで物事を判断している。
また時々、陽介は紙に平和や他人の幸福を祈ってみるのだが、それもやはり本心ではなく、あくまで形式的なもののようだった。
この無機質的な行動原理が、読者を不安にさせ、かつ気味悪がられてしまう理由なのかもしれない。
作中に何度も登場する“ ゾンビ ”という言葉は、彼のことを表しているのか?
――自らの感情さえ分からない――
自らの感情が分からなくなる瞬間が何度かあり、これには私も少し怖かった。様々に入り乱れる感情の最中に、自分の感情を把握しきれなくなってしまったというより、そもそもの感情の捉え方が分からないような。
“それを見た私も嬉しかったか?”
“それを見た私も幸福だったか?”
“悲しむ理由がないということはつまり、悲しくなどないということだ”
このような自らの感情に対するクエスチョンマークが、私には不気味に思えた。
こうした様子を見て、改めて陽介の行動原理に彼の中にないことを悟った。
――ワンピースの色――
最も分かりやすいものに、恋人・麻衣子(まいこ)のワンピースの色の見え方が挙げられる。
おそらく紫に対して “茄子のような”
おそらくダークブラウンに対して “チョコレートケーキのような”
おそらくベビーピンクに対して “ハムのような”
一方で登場人物の灯(あかり)はハムに対して“桜のような”と例えているものだから、その感性の差は歴然である。
麻衣子のワンピースだから興味がないのかと思いきや、灯の手を“焼く前のパン”、唇を“メダカが集まったような”と例えていることからも、どうやら人物には関係なくそのように見えているようだ。それとも、どちらの女にも興味はないのか。
陽介の興味の大半は、「スポーツ」と「色欲」に偏っているらしい。
――花の種類を何一つ知らない――
花を見たとき、陽介はその花の種類を知らないという描写が何度か見受けられる。
“私には花の区別がつかないから、花の名前は分からない。”
“桜とほかの木の区別が、私にはつかない”
ワンピースの色と同様に、興味のないものに対する極端な教養の無さを露見している。
――相手のセリフの異常な長さ――
これが私が最も気になった点の一つである。
相手の話が、やけに長い。
会話は互いに言葉を交わしながら行われるものであるにも関わらず、なんと相手のセリフだけで何ページにも及ぶ場面が多々ある。
膝の話は毎回長い。
さらに、灯や麻衣子、コーチの佐々木の話の間に陽介は一切口を挟まず、黙って聞いているのだ。真剣に聞いている訳ではないということは分かった。それを呼んでいる私までは無の長さにうんざりしてしまうほどだ。他人の話にある程度興味を持つ人間ならば、あれほど長い話は耐えられないだろう。
そして、灯と麻衣子の長話とは個人的な打ち明け話であるのだが、これにも疑問が残る。
灯は自分の家が事故物件だったという話。
麻衣子は幼少期に見知らぬ男に襲われたトラウマの話。
そして、この2人の長い長い打ち明け話は、物語に何ら関係ないように見える。何の意味があるのだろうかと考えてみたが、これについては未だに分からない。
――自分が見られているという自意識の過剰さ――
誰かに見られているという自意識が異常に発達していた。横断歩道を渡る子どもや、膝の卒業ライブの舞台に立った女など、自分を見ている者への注目度が高かった。
この事柄と物語への関係性を考えてみると、一つ思い当たる。
「かくれんぼ」だ。
灯はかくれんぼが得意だ。陽介の部屋のベッド下に隠れているのを、人の目線や気配に敏感な陽介はとうとう見つけられなかった。
もしかすると、あの麻衣子との夜も、灯はどこかで見ていたのかもしれない。クローゼットの中や天井裏、あるいはベッドの下で。
そして最後のシーン。遠くへ逃げたはずの灯は、警官に捕まった陽介を警官の裏からじっと見ていた。
本当にかくれんぼの上手い女だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
