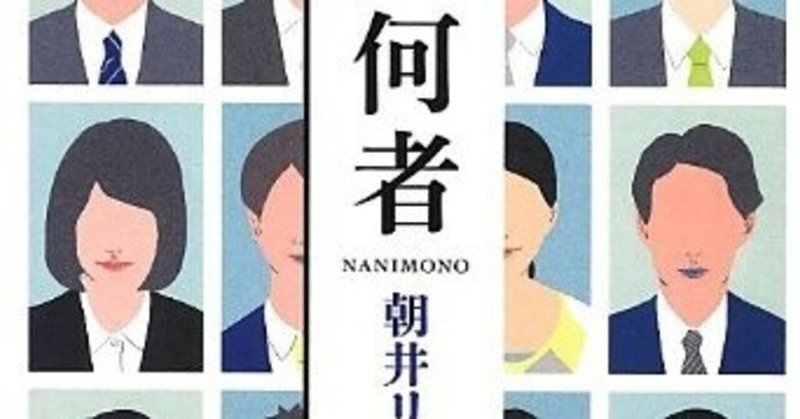
朝井リョウ『何者』 : 〈無根拠な救い〉という、エンタメ的陥穽
書評:朝井リョウ『何者』(新潮文庫)
本書を読んで、何かに「気づかされる」人は少なくない。しかし、本気で「考えさせられる」人は、ほとんどいない。
たとえば、本書のレビュアーたちのうち一体どれだけが、自分のレビューが、本作中に描かれた「ツイート」と「どこかで似てしまうかもしれない」と怖れてみただろうか。「単なる自己顕示」以上のレビューを書こうと明確に意識したレビュアーが、一体どれだけいたことか。
本書に書かれたことを「我がこと」として考えることもなく、漫然と本作の感想を書いて投稿したのだとしたら、それは、本作に描かれた登場人物たちの「イタさ」の意味を、他人事としてスルーしてしまった、何よりの証拠にはならないだろうか。
(※ 以降、本作の「弱点」を論証的に説明する上で、本作における、ある〝仕掛け〟について、あらかじめ言及しなくてはならない。したがって「一切のネタバレは困る。白紙の状態で読みたい」という方は、本作読了後に、当レビューをお読みください)
本作は「若者たちの自意識」の「イタさ(痛さ)」を描いた作品であると言えよう。
社会心理学的には、すでにありふれた指摘に類することだが、ネット上に見られる若者たちの言説に、色濃く看取できるのは、彼らの「承認欲求」の、痛々しいほどの強さだ。
平たく言えば「自分をひとかどの人間と認めてほしい。凡庸一様の人間ではなく、特別な存在であると認めてほしい」という、満たされない欲望の強さだ。
言うまでもなく、こうした「若者の欲望」は、昨日今日に始まったものではない。若者というのは、昔からたいがいは、こうした強い「自意識」を持ち、それに苦しめられてきた。
しかし、それがこんにちほど目につくようになったのは、もちろん、ネットが社会を覆い、SNSなどで誰もが自身で発信できるようになったからだ。
多くの若者たちは知らないだろうが、ネット以前の社会においては、「公的な発言」をする「権利」というものは、一部の「知識人」や「著名人」に限られていた。たとえば「無名の市井人」が政治について物申したいと思った場合、いったい何ができたか。
「多くの人に、自分の意見を知らせたい、読んでほしい」と思えば、まず可能だったのは「新聞の読者投稿欄への投稿」くらいだった。これに採用されれば、何百万人という新聞読者に、自分の意見を読んでもらうことが出来る。しかし、これは多数の投書の中から「幸運にも選ばれたら」の話であり、「幸運」とは滅多に訪れはしない。それに、そこには極めて厳しい字数制限などもあって、自分の意見を根拠を示して理路整然と語るほどのスペースは与えられていない。要は「読者の声」などというものは、新聞編集部の意図の(順逆の)代弁として採用されるだけで、書き手本人の「個性」などは、そもそも問題にされていないのだ。
では、どうするか。
小説や詩歌などの創作なら「同人誌」を作って、そこへ発表することも出来るが、それを読むのは全国でせいぜい数百人程度だ。同人誌は、書店には置いてもらえない。自費出版も基本的に同様である。今でなら「文学フリマ」などもあるだろうが、それとて読み手は「同好の士」に限られて、けっして「世間一般」に届くことはない。
こうした「同人誌」や「自費出版」などでは物足りないというのであれば、あとはその人が「プロの文筆家」になって、公刊されている雑誌や新聞などに作品を発表できるようになるしかない。ただし、うまくプロになったとしても、売れっ子にならなければ、書きたいものを自由に書くというわけにはいかない。言い変えれば、書きたいものが書けるわけではない。つまり、あなたの「個性」など、求められはしないのである。
以上のように、ネット以前の社会では、「名も無き人」が「世間にむけて発信する」というのは、ほとんど不可能事であった。「名も無き人」というのは、世間一般的には「その他大勢」であり、言論表現的には、ほとんど「いないも同然の人々」だったのである。
したがって、特別な才能を持たない多くの人は、「自己表現欲求」や「承認欲求」を、おのずと自身の周囲に向けるしかなく、そこからせいぜいどのくらいまで広げられるか、という問題でしかなかった。自分の「声・言葉」が、世間の誰からでも接続しうる場所に提示される、などといったことは絶えてなかったのである。
だからこそ、ネットが普及すると、それまでは自分の「身の程」を知って諦めていた、そうした「自己表現」の可能性に、多くの人が「希望」を抱き、ネット上で自分を表現するようになった。
「ネットの広い世界でなら、自分を正しく(高く)評価してくれる人が出てくるのではないか」と期待して、それまで「何者」でもなかった自分が、「何者」かになれるのではないか、と期待するようになったのである。
しかし、その「期待」や「夢」や「希望」が満たされる人というのは、ごく一部である。
というのも、拡張されたのは「表現の権利であり場所」であって、「表現者の能力」ではないし、その一方「評価者(読み手)」の方は、「読み手」としての特権的な、昔の評価基準(=プロの物書きに対する評価基準)のまま、彼ら「新たな参入者(素人)」を「選別」することができたからである。
つまり、人々は、「表現者」としては「百円ショップ」にならべられた商品のように、「評価者(買い手)」の厳しい選別に、その身を委ねなければならなくなったが、いったん「評価者(買い手)」の立場にたてば、「評価者としての能力」について、何の評価を受けていない「ズブの素人」であっても、「お客様は神様」的な特権的立場から、商品棚に並べられた「表現者」たちを、無造作かつ残酷に選別する権利を保持していたのである。
そして、一人の人間が、「表現者」であると同時に「評価者」であるということ、言い変えれば「商品」であると同時に「買い手」でもあるという「立場上のギャップ」を抱え込まざるを得なくなった時に、本作に描かれたような「タテマエとホンネ(表現と評価)」の極端な二分化が、多くの人たちのなかに生まれざるを得なかったのだ。
○ ○ ○
さて、本書である。
前述のとおり、本作は「若者たちの承認欲求にかかわる葛藤」を描いた物語であり、それはその内面における「ギャップによる苦しみ」の問題を描いているといえるだろう。「自分はこういう人間なのに、他人はそれを正しく認めてくれない」という問題である。
しかし、「自分はこういう人間なのに、他人はそれを正しく認めてくれない」という、このシンプルな認識には、二重の不確実さがある。一つは「その自己評価は、はたして正しいのか?」という問題。二つ目は「他人は、本当にそう評価しているのか?」という問題である。
言うまでもなく「自己評価」というのは、ほとんど当てにはならない。その多くのものは「過大評価」だろうし、時に「過小評価」であって、「適切妥当な評価」というのは、極めて困難なものなのである。だが、そんなことにすら気づけないような評価無能力者が自分の評価をするのだから、自己評価が間違っている蓋然性は極めて高い、と言えよう。まして、自分のことも冷静に見られない人が、どうして他人のことを、その内面まで正しく評価できるだろうか。
このように考えていくと「自分はこういう人間なのに、他人はそれを正しく認めてくれない」という「認識」は、ほとんど「独り善がりの戯言」でしかないということになってしまう。
そして、多くの若者は、こうした「独り善がりの戯言」という「迷宮」の中で、ナイーブに悩み苦しみ傷つきながら、彷徨うことになる。
もともと「自分への正しい(肯定的)評価」などという出口自体が「幻想」でしかない蓋然性の方が高いのだから、そこから「正しく」脱出することなど、ほとんど不可能。「脱出者」つまり「承認された者」となれる可能性は、原理的にほとんどないのである。
つまり、多くの若者が、その辛く苦しい「迷宮」から脱出する為には、多くの場合、その迷宮には「出口が無い」ということを認め、その迷宮から出ることの不可能性を認めることしかないのだ。それを認めた時にこそ初めて、その迷宮は消えてなくなり、彼は自分が迷宮の外に立っていることに気づくのである。
本作では、主人公(一人称の語り手)拓人による、友人たちへのツイートに対する辛辣きわまりない評価が語られていく。ひと言で言えば「おまえらのツイートは、イタいんだよ」ということになる。
実際、友人たちのツイートはしばしば「イタい」。聞かれもしないのに、自分の「価値観」や「他者評価」や「理想」を語り、その中身によって、自分が「非凡な人間」であるかのように見せようとするのだが、しかしそれは、そうした「自己顕示」の意図が簡単に見透かされる程度のものでしかないから、友人たちは、「評価者」である主人公から「三流の表現者」だと評価されてしまうのだし、その評価は間違いではないのだ。
そのため、読者の多くも、主人公の、友人たちへの評価に共感する。「そうそう、こういうイタい奴、多いよね」と。
しかしながら、それは自分を「評価者」の位置に置いているから言えることで、いったん自分が「被評価者=評価をされる側」である場合を考えるなら、自分もまた十二分に「イタい奴」でしかないことに気づくだろう。しかし、そういう「自己相対化」ができる人は、きわめて少数でしかない。そして、それができる人だけが「少数の選ばれた表現者」になれるのである(つまり、自身を他人の評価に晒し、さらには、それとの対決も辞さない覚悟を持つ者だけが「表現者」たりうる)。
したがって、主人公もまた、多くの読者と同様に、自身を「評価者」の側に措くことはしても、自分を「被評価者=評価をされる側」に措こうとはしない。それは、自分が友人たちに対して、内心で極めて残酷であるように、友人たちの目もまた、自分に対して残酷である蓋然性の高いことを知っているからだ。
だから彼は、その本音(評価)を友人たちの前で語ることはなく、ツイッターの「裏アカウント」でこっそりと書き連ねることになる。つまり、彼は「裏アカウント」によって「透明な存在」となり、「一方的な評価者」としての「安全圏」から、心置きなく友人たちを断罪していくのである。
しかし、物語の終盤で主人公は、ある友人に「裏アカウント」を暴かれ、その「裏表のある卑怯なふるまい」を断罪されることになる。「たしかに私たちのツイートは、イタいかもしれない。でも、それを、正体を隠して、上から目線で一方的に馬鹿にしている、あなたの方が、もっと救いがたく根性悪で卑怯で、イタいのではないのか」と、真正面から批判されてしまう。
主人公は、その「正当な告発」に対し、ただ「否認」するしかない。それを認めてしまえば、自分が自分に見ていた「本当の自分という幻想」を、完全に打ち砕かれてしまうからである。
また、ここに至って、主人公の語る「友人たちへの酷評」に共感してきた多くの読者は、この「告発」が、自分にも向けられたものでもあることを知って、ショックを受ける。
その「告発」を「否認」することしかできない、主人公の見苦しくも弱々しい「負け犬」のような姿に、読者の多くもまた「自分の本性」を見なければならないからである。「私も主人公と同様に、身の程知らずで独り善がりな、愚か者であった」と。
だから、本書には、読者に対する「告発」とまでは言えないにしろ、一定の「問題提起」がなされているというのは確かだ。「君自身は、どうなんだ?」という問いである。
しかし、「本書の問題点」は、その先にある。
本書のラストで、主人公の拓人は「一方的な評価者」という「安全圏」から踏み出して、自分を「他者の評価に晒す」ようになる。彼は、人を評価し、人から評価される、という「社会」のなかへと、一歩踏み出したのだ。彼は、たしかに「成長」したのである。
一一こうして、この物語は「ハッピーエンド」を迎え、読者は気持ちよく、本作を読み終えることができる。「ああ、面白かった」と。
しかし、その時にはすでに、読者は、自分が主人公の拓人とはちがい、「卑怯な一方的評価者」の位置に止まったままであるという事実を、忘れてしまっている。
主人公の拓人が成長し、それによって「救われた」ことで、彼に共感していた自分までもが成長し「救われた」ような気になってしまうからである。
しかし人は「娯楽小説を1冊読んだくらいで、途端に成長したりはしない」のだ。
つまり、本書の決定的な「弱点」とは、このラストにおける「安易な救い」の提供でなのである。
これによって、読者に対して適切に提起された「問題意識」が、無効化されてしまったのだ。
言い変えれば、本作がそのテーマ性において、何がしかの価値を持とうとするならば、最後の「救い」を、主人公にも読者にも、安易に与えるべきではなかった。
むしろ「人は、そう簡単には変われない」という、困難な現実を読者に提起した上で、それを読者に委ねるべきだったのだが、作者の意識は、「エンタメ」的な「心地よさの提供」という慣習に流されてしまったのである。
したがって、本作を「所詮はエンタメ」と割り切るのであれば、充分に高い評価を与えることもできようが、それ以上の価値を見いだそうとするのであれば、本作はラストを誤った「失敗作」だと評価せざるを得ない。そこに、「エンタメ」の限界を見、「エンタメ作家」としての作者の限界を見ないわけにはいかないのである。
そして、これこそが「作品」を世間の評価に委ねる、ということなのだ。作者は、本作の主人公拓人のように、読者の盲目的な追認にだけ、その身を委ねて満足していてはいけないのである。
じっさい、本作の問題点は、本書文庫版の、三浦大輔による「解説」文にも、はっきりと表れている(三浦は、映画『何者』の監督)。
三浦はその「解説」で、露悪趣味的に、自分も「内心での負けず嫌いだった」だと告白したうえで、しかし、そんな自分でも、この『何者』という小説には兜を脱ぐしかなかったと認めて、その上で、作者・朝井リョウを次のように褒め上げる。
『 でも、朝井さんは、過去の自分のような人間のために、この小説を書いたわけではないだろうし、この小説の登場人物のような人間たちに、「罰」を下そうとしたわけでもないと思う。むしろ「赦そう」としたのではないだろうか。朝井さんの作品は、社会に警鐘を鳴らすような、強い問題意識を提示するような、いわゆる説教じみたものであるはずがない。ただ、そこにいる人間のをありのままに描き、その愚かさをも含めて、全てを受け入れる。高尚なテーマを掲げたがる、頭でっかちな作家たちが目もくれない「俗」を見つめ続け、そこに無防備に石ころのように転がっている「本質」を逃さず拾い集める。』(P345)
ここに示された「読者・三浦大輔の醜態」こそが、そして、三浦の姿の象徴される「自分に対し盲目的甘い読者に、自己正当化お墨付きを与えるしか能のない作品」というこの点が、この小説の「弱点」なのである。
三浦が、ここで書いていることとは何か。それは所詮「独り善がりで一方的な、自己承認欲求」の表現でしかない。「成長した拓人」ではなく「成長前の独り善がりな拓人」であることを、そのまま「許されよう」という、度しがたい「甘え」でしかない。
たとえば、ここで三浦は『社会に警鐘を鳴らすような、強い問題意識を提示するような、いわゆる説教じみたもの』を書く『高尚なテーマを掲げたがる、頭でっかちな作家たち』を、もっともらしく「批難し見下している」が、この態度は、友人を見下していた時の拓人となんら変わるところのない、一方的なものだ。
自分が『演出家・脚本家・映画監督』(P346)と「肩書き」を並べなければならない、あるいは、並べることのできる、中途半端な「有名人」であることだけを根拠に、『社会に警鐘を鳴らすような、強い問題意識を提示するような、いわゆる説教じみたもの』を書く『高尚なテーマを掲げたがる、頭でっかちな作家たち』を見下すことができると「奢り高ぶり」、彼らの努力を無視して良いのだと「勘違い」している、「今の自分が見えていない、イタい人」なのである。
言うまでもないことだが、本作の作者・朝井リョウは、主人公の拓人を『その愚かさをも含めて、全てを受け入れ』ているわけではない。
だからこそ、彼に過酷な試練を与えて、彼の「成長」を促したのである。
そんなことすら、この「解説者」には理解できていない。
しかし、そんなことすら理解できなかったのは、もちろんその主たる理由が「解説者の承認欲求の強さとその無反省」にあるとはいうものの、本作が、この「解説者」三浦大輔に対して「反省を促す」力を持っていなかったからなのである。
最後の最後で、安易に「救い」の手を差し伸べてしまったからこそ、三浦大輔をふくむ少なからぬ読者が、十分な反省のないまま、その手にすがって、自己を「そのまま承認する」という「甘え」に逃避してしまったのだ。
解説者・三浦大輔は、そうした「朝井さんは、優しいから、私たちをそのまま承認してくれた」という、得手勝手な理解から、「解説」の最後を、次のように締めくくっている。
『 とある日、自分がツイッターに関して、ぶつくさ言っていたら、とあるギャルたちにこう言われた。
「別にそんなことどうでもよくないー。楽しければいいじゃーん」
彼女たちのことを知性がないと言い放つのは簡単だろう。でも、自分にはどうしても、その楽観としか捉えられないだろう言葉の中に、うだうだ考えてるこっちがバカバカしくなるくらい、芯食った、そこはかとない説得力を感じずにはいられなかった。堅物が「じゃあ、ツイッターなんか見なきゃいいじゃん」と、ほんとは気になってるくせに、達観しているふりをするために吐く言葉とは全然違う、どこか神々しさを感じるくらい、大仰だが、「真実」のようなものの気がした。
もしかすると、彼女たちは『何者』を読んでも、主人公のことを「こいつ、うざーい。きもーい」としか思わないのかもしれない。
でも、朝井さんは、このギャルたちのことを、「馬鹿だ」と一蹴しない。彼女たちの「俗っぽさ」を、きっと「愛」する。そして、彼女たちの価値観までも凌駕するような物語を、いつかきっと紡ぎ出すはずだ。
そして、ギャルたちは、こう続けた。
「ツイッターに、何書いても死ぬわけじゃなくねー?」
強敵だが、朝井さんなら勝てるはずだ。』(345〜346P)
この文章に、「解説者」三浦大輔の「鼻持ちならないエリート意識」を読みとった人は、拓人なみの読解力がある、と言ってもいいだろう。つまり、その評価は、完全に正しい。
要するに、三浦は、ギャルたちを内心では馬鹿にし見下しているのだが、彼女たちを持ち上げることによって、自分自身を「朝井さんと同様の、人を見下さない良い奴(大人)」に見せかけ「イマドキの若者の支持を取りつけようとしている」だけで、このあたりの「三文芝居」は、本書作中人物たちの「自己美化の為の無自覚な演技」よりも、よほど「薄汚れた大人らしい、意識的な手管」である点において、悪質だ。
実際、三浦がギャルたちを、まったく見下していないのなら、そのまま肯定する気があるのならば、『強敵だが、朝井さんなら勝てるはずだ。』などと書くはずがない。
これはギャルたちの中に「倒すべき手強い負性」としての『馬鹿』を見ているからに他ならないのである。
そして、もしも三浦が正直な人間であれば、ギャルたちの「思考放棄としての感覚主義」については是正され、彼女たちも拓人と同様に「成長」すべきであり、その可能性において彼女たちも否定されるべきではない、と主張したはずなのだ。
ところが、三浦の「解説文」は、小説『何者』を解説するふりをしながら、じつは「自分を大きく見せる」ためにこそ書かれている。つまり三浦は、有名人の名前を引き合いに出して、自分を大きく見せようとした拓人の友人と、同じようなことをしているのである。
そして、このことが意味するのは、本書の「解説者」ですら、本書を読むだけでは、まったく「成長」できなかった、ということであり、本作『何者』は、そのような「文学としての力」を持たなかった、結局は拓人たちの弱点を「読者自身の問題として、思考を促すこと」ができなかった、ということなのである。
終盤の「ドンデン返し」で「拓人の醜さは、読者の皆さんそれぞれのものではありませんか?」という「適切な問い」を突きつけておきながら、エンターティンメントとしての収まりの良さを優先して、最後の最後で、拓人への「無根拠な救い」を与えてしまった為に、そこで読者も「読者への問い」から逃げてしまった。そして、その結果が「私はギャルの理解者だよ」などと、鼻持ちならない上から目線で語る「解説者」を生んでしまったのだ。
小説『何者』が、単なる「うさ晴らしのエンタメ」にすぎないものでいいと、作者自身は考えていたのだろうか。
私は「そうではない」と考えるからこそ、本書の本質的な問題点は、是非とも指摘されなければならなかったのである。
初出:2020年5月4日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
