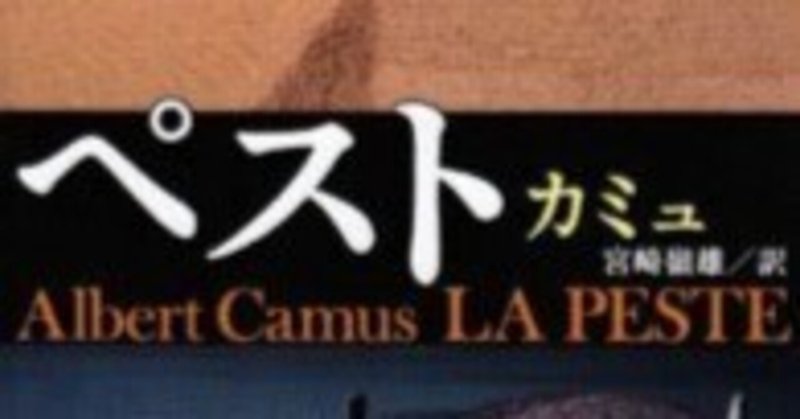
1928 『ペスト』
◇1928 『ペスト』 >カミュ/新潮文庫
背表紙あらすじ:アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
新型コロナウィルスに触発されての読書としては4冊目。これまでにも『首都感染』を購読し、『夏の災厄』『復活の日』を再読してきた。これらの前作がウィルス蔓延を「事件」として捉えているのに対して、本書『ペスト』は、そこから生まれてくる人間の「感情」の襞を丁寧に描いた作品だと感じた。
そもそもウィルスというのは、広く蔓延するものであり、非常に多くの人々が関与するものなので小説の中にヒーローを作りづらい。それぞれの筆者もそのことを自覚しながらも、主人公らしき人物にスポットライトをあてながら物語を進めていく。しかしながら、本書『ペスト』は、主人公群とでもいおうか、主要な複数の人物に均等にライトをあてながら物語が進行していったように感じた。
さて、本書を読み始めたのは1カ月ほど前のこと。仕事が忙しかったり、仕事のために優先して読むべき本があったりして、本書は断続的に読む形になってしまった。そのせいだろうか、物語の中でペストの感染が広がったり収束していく時間軸が、まるで現実世界のように長く感じられた。
その一方で(私が外国人の人名を覚えるのが苦手だからかもしれないが)、時間が空いたことで登場人物のキャラクターを忘れてしまい、あれっこの人はどういう人物だったかなと思い出しながら読むことになってしまった。よって、本書の特徴である心情の襞に対して、感情移入をすることが出来ないまま、読了してしまったのだ。
恐らくこういった読み方では、本書をきちんと味わったとは言えないであろう。自分としては納得のいかない読書であった。
それにしても、100年近く前の出来事であるのに、現在のコロナ禍との相似は何ということであろうか。人々の行動、町中の状況、密閉された中での心理状態などなど。在宅勤務ができるなど、テクノロジーの恩恵は多分に受けてはいるものの、人間の深層心理というものは昔から変わらないのだなぁと改めて実感した。
一番怖いと感じたのは、人々が「死」に慣れてしまっていく様。死者が名前ではなく、「数」で語られていく怖さ。日本ではコロナ禍は落ち着いてきたとはいえ、二次、三次の波がいつ来てもおかしくない状況。コロナ疲れも分からなくはないが、油断せず、感染予防に努めていくべきだと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
