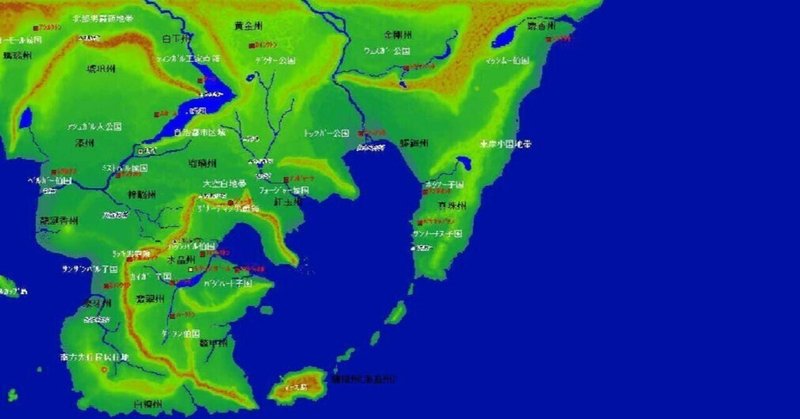
ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(35)
第八章 天剣の子(その1)
ケーシの日々が続いている。
あれほど勿体をつけていたのは何だったのだろう。ミッテルがティルドラスから預けられた金銀を手土産に各所を回り始めてからわずか三日後、ティルドラスは王宮に呼び出され、諸侯を取り仕切る官である大鴻臚の府で爵位の継承を認められたあと、財政や農業を司る官である大司農の府で朝廷の官位を授けられる。与えられた官職は「籍田令」。籍田――王が祭祀に使う花や作物を育てるため自身で(形式的に)耕作する農地の管理責任者だという。
官職の授与と併せて籍田の手入れを行うようにという命が下る。就任に当たっての慣例のようなものらしい。普通は(自費で)人を雇って済ませるようだが、ティルドラスは自分自身で畑の手入れを行うことを申し出て「殊勝の至りである。」という褒め言葉とともにすんなり受け入れられた。
「よくあそこで機転を利かせたな。おかげで朝廷の高官たちの間で君への評判が格段に良くなったらしい。」翌日さっそく籍田を訪れて農地の手入れに精を出し、一仕事終えたあと手近な石に腰掛けて休むティルドラスにミッテルが言う。
籍田は王宮から少し離れた御苑の一角にあった。庭園の一角に設けられた二引(ほぼ60メートル)四方ほどの農地に祭祀に使うらしいさまざまな作物や花が植えられているが、心を込めて手入れする者がいないのだろうか、見たところ出来はそれほど良くなく、畑の土も痩せているようだった。
「別に機転を利かせたつもりはないのだが。しばらくぶりに畑仕事もしたかったし、この近くの地味がどのようなものかも見ておきたい。むしろ良い機会だと思って申し出ただけだ。」とティルドラス。
「そうなのか。まあ、君の本心がどうあれ、高官たちの間で君が王家に忠実だという印象が強まれば話も進めやすくなる。今回認められなかった旧バグハート領の件もな。」爵位の継承・官位の授与とともに願い出ていた旧バグハート領をハッシバル家がそのまま領有することへの承認については、すぐには認められないという回答だった。「本来バグハート領は自分の所領であると言い出す者が現れたらしい。亡びたチャプタイ子爵家の傍流の子孫で、五代ほど前の先祖がチャプタイ家本家からマクドゥマルを中心とする地方の平定を命じられたという当時の書き付けを持って朝廷に訴え出たそうだ。回答はその訴えについての結論が出てからになるだろう。」
「そんな訴えが認められるものなのか? そもそもチャプタイ家が過去にマクドゥマル周辺を支配したことはないし、当のチャプタイ家自体が二十年以上前にケーソン家に亡ぼされている。」
「おそらく当人も認められるとは思っていないさ。君が面倒ごとを嫌って幾ばくかの金で事を収めようとすることを期待しているんだろう。体のいいたかり屋だ。ケーシにはそういう手合いが数多くいる。まあ、銀の三十両も掴ませれば喜んで訴えを取り下げるだろうが、どうする?」
「相手の言うことに多少でも道理があるなら金を出すことはやぶさかではないが……、正直、そういう思惑で訴えを起こしたのだとしたら応じたくはないな。悪しき前例を作ることにもなる。」
「同感だ。応じてしまえば他にも似たような者たちが押しかけてきて、かえって面倒が増えることにもなりかねない。幾分日数は余計にかかるかも知れんが、ここは動かずに朝廷の沙汰を待つのが良策だろう。」ミッテルは頷く。「願い出が認められなかった理由はもう一つある。勤王を説く在野の士たちが、諸侯が戦いで他の諸侯から奪った土地はすべて朝廷に返上させるべきと訴えていて、朝廷の高官の中にもそれに同調する者がいる。こちらの方が、金で黙ってくれない分むしろ厄介かも知れん。」
「その中にマウアーという学者がいないか?」
「議論の主唱者だ。知っているのか?」
「ケーシ入りする前日に宿舎を訪ねてきて、旧バグハート領を王に返上するべきだと進言してきた。応じはしなかったが。」
「断ったのか。まあ当然ではあるが――、ただ気をつけた方がいい。彼らはおそらく君が思っているよりはるかに危険な連中だ。なにしろ――」
ミッテルが何か言いかけたその時、圃場の横の道に数人の女官を従えた一台の輦――人力車が停まり、そこから華やかに刺繍された衣装に身を包んだ年の頃十歳ほどの金髪の少女が降り立つ。「王女ルシルヴィーネさまのお越しである。控えられませい!」付き添っていた守り役らしい女官が二人に向かって声を張り上げる。
「お姫様のお成りだ。跪拝の礼を。」ミッテルに促され、ティルドラスは王女に向かって跪き、深く頭を下げる。「王女におかれましては、ご機嫌うるわしく祝着にございます。こちら、このたび籍田令に任ぜられましたネビルクトン伯・ティルドラス=ハッシバル公にございます。」自分も跪きながら、王女に向かってミッテルは言う。
「大儀である。」ティルドラスに向かって抑揚のない口調で無表情に声をかける王女。しばらくそぞろに籍田の中を歩き回ったあと、一言も発しないまま輦に乗り込み、彼女は去って行く。
「何というか人形のような子供だな。王家の子女はみんなああなのか?」遠ざかる輦を見送りながら、ミッテルに向かってティルドラスは囁く。
「まあ、いろいろと不憫な目に遭って、その中で感情を押し隠すようになったんだろう。他の王子や王女はもう少し子供らしいところもあるさ。」
「というと?」
「さっき言いかけた勤王の士連中が危険な奴らだという話の、まさに当事者だ。」周囲を見回し声を潜めながらミッテルは言う。「ルシルヴィーネ王女はデクター家のハリオス公子と婚約している。当代のカッツォール公爵の弟で彼女より十四歳年上、もちろん周囲が押しつけた話さ。縁談を主導したのは彼女の生母の兄であるウィスキノス=アニコフ男爵だ。姪を嫁がせることでデクター家の後ろ盾を得て、朝廷内で権を握るつもりだったらしい。ところが、その縁談に異を唱える者たちが現れた。それが勤王の士たちだ。もちろん彼女の幸せを考えての事じゃない。連中の間で声望の高いヒッサーフ=オーモール侯爵の長男・ウラストス公子に彼女を娶せてオーモール家を王室の藩屏とすべきだというマウアーの主張を受けてのことだ。アニコフ男爵がデクター家の後ろ盾で朝廷の権を握ろうとすることへの反発もあった。」
「そんな大人たちの勝手な思惑で……。」
「ああ。だが話はまだ終わりじゃない。そのアニコフ男爵だが、ほんの一月ほど前、王宮に参内したあと宮門を出たところで覆面の刺客に襲われ、護衛二人もろともその場で殺された上に首を持ち去られた。護衛はどちらも名の知れた手練れだったにもかかわらずだ。持ち去られた首は翌日近くの河原に晒されていた。弾劾文が添えられていて、アニコフ男爵がルシルヴィーネ王女を利用してデクター家と結び王室を蔑ろにしたことへの天誅であると書かれていたそうだ。ついでに言うと下手人はまだ捕まっていない。」そしてミッテルはかぶりを振る。「そもそも父君の今上陛下からして、さして寵愛が深いわけでもない側室が産んだ第九王女の彼女など単なる手駒の扱いだ。彼女が五歳の時に、当時宮廷で横暴を極めていた権臣を除くためにその男の息子と彼女との縁談を持ちかけ、婚約披露の宴席に兵を伏せてその権臣を息子もろとも討ち取るということもやっている。もちろん彼女の目の前でな。王女にすれば何も分からないまま縁談を強いられてはそのたびに周囲で人が死んでいくわけだ。心を閉ざすのも当然さ。」
「気の毒な。」ため息をつくティルドラス。「それにしても、ケーシといえば格調高い雅やかな場所かと思っていたが、何か想像していたのと違う話ばかり聞かされるような気がする。」
「……畑の手入れがやりかけだ。済ませてしまおう。」そう言って、ミッテルは近くに転がっていた鎌を手に取る。
「そうだな。しかし君の役目でもないのに手伝わせてしまって、何か済まないな。」自分も鍬を拾い上げながらティルドラスは言う。
「気にするな。宮廷の中で汚い話ばかり見聞きしているとな、たまには美しい花の世話でもして心を洗い清めたくなるんだよ。」鎌を手に花木の根元の草を刈りながら、ミッテルは答えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
