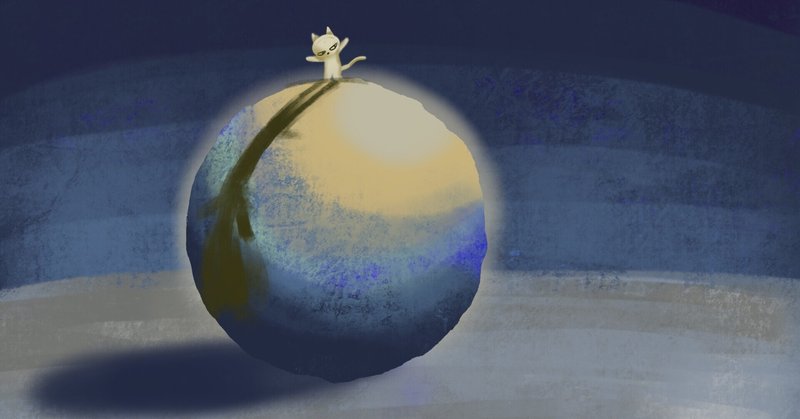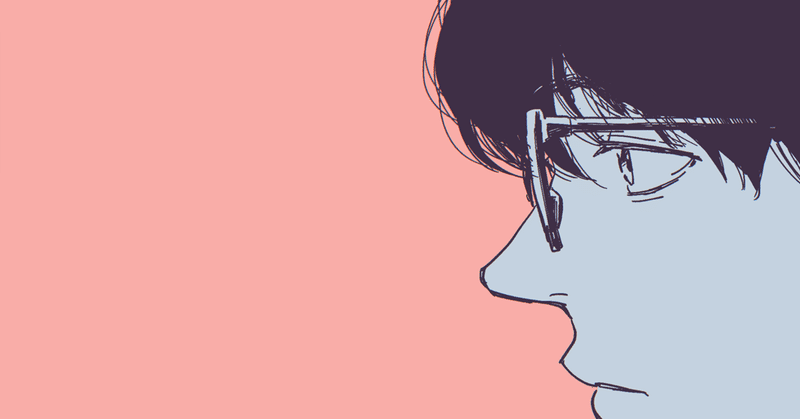2020年12月の記事一覧
新しい彼女たちの発見
彼は言った。「やっと見つけた」
彼女は言った。「見つけたって、ずっとここにいたけど」
ふたりの言ったことはどちらも間違ってはいなかった。彼にとって、彼女はその瞬間に発見されたのであり、彼女にとっては彼女はそれまでもずっとそこにいたのであり、発見されるまでもなくそこにいたのだ。もしも少しだけ正確さを求めるのならば、彼が少し傲慢だったということになるだろう。害の無い程度の、誰もが持つ傲慢さ。しか
Fly me to the moon
「わたしを月まで連れて行って」と、彼女は言った。微笑みながら。満月の夜のことだ。寒くて、空気がピンと張り詰めていた。吐く息は驚くくらい白かった。真円の月は、漆黒の闇夜に穴を穿っているかのようだった。もうじきそれは中天に昇るだろう。
「月って」と、ぼくはその満月を指差しながら言った。「あの月?」
「あの月」と、彼女はうなずいた。「他にどんな月があるの?」
ぼくはしばらく考えた。衛星という意味でなら
丸い地球の上でぼくが考えたこと
ぼくの父は地球が丸いということを認めなかった。学校から帰って、その日学んだことを何気なく話すと一笑にふされた。
「地球が丸いって?」と、父はニヤニヤしながら言う。そして、近くにあったバスケットボールを指差し「じゃあお前、そこにあるボールに乗ってみろ」
断っておくが、父は科学的な一切を頭から否定するような人ではなかった。進化論は認めていたし、それを学校で教えることも支持していた。地球の年齢は四十
残酷な世界で傷ついたふたりが出会う話
わたしの目の前で女の子が泣いている。わたしはどうしていいのかわからない。女の子がなぜ泣いているのかがわからないからだ。もちろん、なぜ泣いているのかが分かったところで、わたしにはなす術がないかもしれないけれど、それでも、それがわかれば、慰めの言葉のひとつでもかけてあげられただろう。それで事態が好転しなくても、少なくともわたしがそれ以上いたたまれない気持ちになるのは防げる。女の子は泣き止まない。わた
もっとみるすべての引かれ合う力
彼が選んでくれた変な色のアイシャドーを捨てた。つまんでいた指を離すと、スッと落ちて、ゴミ箱の底に当たって派手な音を立てた。いや、そんなに大きな音じゃない。わたしの中では大きく鳴ったってことで。たぶん、部屋が暗いせいだ。
「万有引力」と彼が言ったのを思い出す。「すべて、物と物は引き合っているんだ」
「わたしと、君も?」と尋ねようかと思ったけれどやめた。バカみたいだし、完全にバカみたいだからだ。だか
あなたに名前を付けてあげる
「あなた達は私が怖くないんですか?」男は言った。
妻と結婚し、一緒に暮らし始めた最初の夜のことだ。部屋の明かりを消すと、男が現れた。ぼくらはただただ茫然としていた。それもそうだろう。その男は音もなく、すうっとそこに現れたのだ。怖いとかなんとかよりも、驚きと困惑が先に来た。妻も怖がる素振りなんて見せず、ただぼんやりと男を見つめている。
「全然、怖くないけど」妻は首を横に振った。「なんであなたはそん