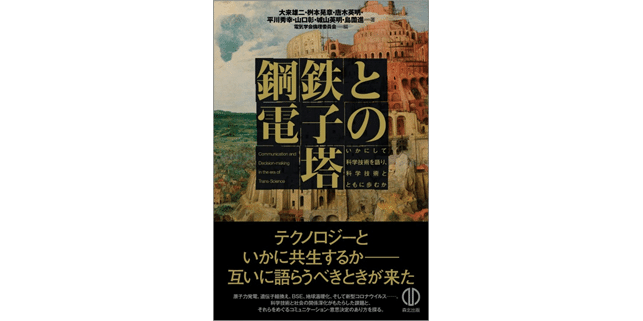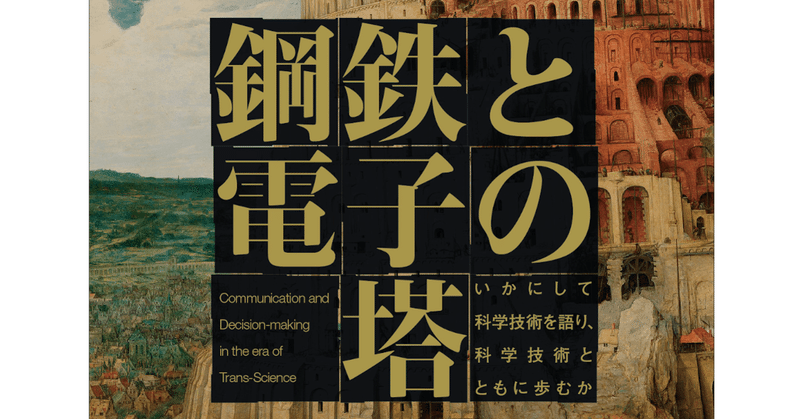
科学技術といかに共生するか(近刊『鋼鉄と電子の塔』座談会公開 2/3)
前回の記事に引き続き、2020年12月上旬刊行予定の『鋼鉄と電子の塔:いかにして科学技術を語り、科学技術とともに歩むか』座談会より
2 未知の脅威にどう備えるか
(次の感染症、次の大津波はいつか必ず来る)
を公開します。
『鋼鉄と電子の塔』
第4部 塔を囲む人々―執筆者座談会
2020年5月15日(金)、Web会議システムによりオンラインで開催
参加者:
桝本晃章 (一社)日本動力協会会長
唐木英明 東京大学名誉教授、(公財)食の安全・安心財団理事長
平川秀幸 大阪大学COデザインセンター教授
山口彰 東京大学大学院工学系研究科教授
城山英明 東京大学大学院法学政治学研究科・公共政策大学院教授
島薗進 上智大学大学院実践宗教学研究科教授、同グリーフケア研究所所長
司会:大来雄二 金沢工業大学客員教授、電気学会倫理委員会コーディネーター
司会補:佐藤清 電気学会倫理委員会コーディネーター
2 未知の脅威にどう備えるか
(次の感染症、次の大津波はいつか必ず来る)
唐木
イントロとして、リスクの専門家が考えている分類を紹介させてください。ラムズフェルド米国元国務長官が2002年に、リスクには三つあるといっています。一つは「Known Knowns」で、これは既知のリスクをみんな知ってるということです。たとえば、自動車事故とか食中毒とか、ほとんどのリスクがこれです。2番目が「Known Unknowns」で、未知のリスクが存在するということだけがわかっている。新興感染症や巨大地震など、必ずやってくるけども、それがいつどんな形かはわからない。放射能や化学物質も未知のリスクとしてここに分類する人もいる。3番目が「Unknown Unknowns」で、未知のリスクの存在を誰も知らない、いわゆるブラックスワン問題です。ヨーロッパ人は黒い白鳥はこの世に存在しない悪魔の鳥と信じていたので、オーストラリアで黒い白鳥を初めて見たときに死ぬほど驚いて、ここは悪魔の土地だと恐れたという話があります。私の分野では、誰も想像しなかったBSE問題が突然発生したことがこれにあたります。新型コロナをブラックスワン問題という人もいます。
その後、評論家のオトゥールが「Unknown Knowns」を追加しました。これは既知のリスクを無視するという姿勢で、政治家がよく使う手です。たとえばトランプ大統領は温暖化など存在しないといいますが、彼も問題が存在することはわかっているでしょう。では、福島原発事故はこのうちどれなのか、それが一つの議論ですね。
山口
これは結局、理解の欠如というか、私たちが物事をどれだけ知らないかに尽きると思います。先ほどの汚染水の問題でもそうですが、知るべき知識に蓋をするとか、データがないとか、知ろうとしない態度とかがある限り、未知のリスクにはなかなか対応できないと思います。
パンデミックも、自然現象も、地球温暖化もそうで、リスクにはいろんなタイプがあって、正面から向き合って知ろうとすると、知識の足りないところが明らかになります。どこがわからないのか掬い上げるという行為は、まさにリスク評価が長年努めていることそのもので、それにも踏み込まないといけない。さらに、いまはリスクをわかりやすく整理したものを用意して、未知のリスクに対して全体をバランスよく対処することが求められています。そうでない限り、未知のリスクが新たに出てくるたびに右往左往してしまう。
未知のリスクにも適応できるような共通する考え方を一番上位にして、下層にいくほど個別に適応できるようにする、そういう階層構造が必要です。えてして我々は、下層の発生頻度などに注目しがちですが、それだけでは未知のリスクに対応する考え方とか思想はないという結果になると思います。
城山
感染症だとか自然災害っていうのは、いつ来るかがわかっていなかっただけではなくて、いろんなリスクが複合的に作用を起こしたときに、どのくらい相互作用するかわかっていなかったところがあったんだと思います。
福島の場合でいうと、地震や津波が原子力災害に直結するということは必ずしも十分議論できてなかったし、たとえば放射性物質が出ることで、医療施設の高齢者が避難の移動を強いられて亡くなるという、まさにこういうカスケードが起こったわけですね。おそらくコロナの話もそれに近くて、たぶんいつかは起こると思っていたけども、どういう経路で、どうリスクが複合化して、社会的に何が起こるかまでは想定されてなかったのが問題だろうと思います。
逆にそれに対応しようと思うと、トレードオフの中で判断が求められますよね。健康上とか経済上とか、いろんな安全があるので、複合的なリスクに対して、社会としてトレードオフを判断するという、心の準備も仕組みの準備も必要なわけですね。だからいろんな専門家を巻き込んで相互に議論するという仕掛けが必要で、これは福島でも、今度のコロナでも同じではないかと思います。
どういう複合パターンが起きるかは毎回違うので、そこをどう考えるかというのはなかなか難しいなあと感じます。どこまで想定して、しかもリソースは限られているので全部は対策できないという中で、社会としてどう決断していくかが大きな課題ではないかと思いました。
大来
テーマ1で平川先生が現実的な将来シナリオ、納得・諦念の合意についてお話しされました。我々は何かというと、すぐ目の前の対策が必要という方向に議論がいくけれども、やはり現実を見極めて将来のシナリオを描くという、その諦めの部分はいままで考えが及んでいなかったと思いますが、いかがですか。
平川
さっきの城山さんのトレードオフの判断というのは、何を選び、何を捨てるかという点で、諦めということを含んでいると思います。さらに、次にどう備えるかということに関して、いま挙げたい論点としては二つあります。
一つは、行政組織での、あるいは専門家集団もそうかもしれませんが、組織的なメモリーというのが弱いなあと。たとえば今回、新型コロナでは約10年前の新型インフルエンザの経験を活かせるはずです。特措法に関連して、リスクコミュニケーションのやり方とか、ワクチン接種の優先順位、トリアージュについてどう社会合意するかという話を、じつは10年前にもしていました。リスクコミュニケーションのやり方や専門家助言のあり方については、2000年代のBSE問題、2011年の福島第一原発事故の際にも、議論されていました。しかし現在、そうした積み重ねは何もなかったように見えてしまって、とても残念な思いです。組織的に継続して課題に取り組んで、それに資源投入していくのが、未知の危機にどう備えるかという観点から重要です。万全でないにせよ、組織的に回避しなければいけないこと、やらなければいけないことの記憶を保持して、取り組み続けるのが大事です。
二つ目は、専門家の育成です。国内はもちろん、国際的なネットワークも広げておく。そのためには助言できるシステム、有事の際に、どこにどういう専門家がいて、どう活躍してもらえるのか、政府なり学会なりで把握して、号令を掛けられる仕組みを平時からつくっておく必要があると思います。その仕組みの中で、いろいろな事態を想定した頭の体操を、専門家間で定期的にするような取り組みが必要なのかなあと。具体例としては、アメリカのナショナルアカデミーズには常時600ぐらい委員会があって、それぞれが学術的なものから今後の世界規模の課題まで、さまざまな報告書を2年に1回くらい刊行しています。これによって、有事に備えた最低限での合意ができる。何が不明なのかを踏まえたうえで、政策判断やさらなる専門的な判断をする。その共通の土台を平時につくっておかないと、どうしても有事の際に右往左往してしまう。
大来
2点目にアメリカの例を挙げられましたが、じゃあ日本は現実を踏まえて何ができるかですね。彼らのアカデミーというのは専門知識をもつスタッフが大勢いて、科学者とアカデミーの組織がリンクして、何か問題が現実化したらすぐレポートを出すという状況になってると思うんですよね。日本だと、学術会議とか日本工学アカデミーとかありますが、いずれもスタッフの力は弱いのではないでしょうか。
島薗
今回のコロナウイルスのことでも、PCR検査や医療体制整備が遅れた。少なくとも行政と医療現場との間の連携、対処するスピードがとても遅かったと思います。しっかり情報を収集して対策を立てる体制の弱さが目立った感じがします。
二つ述べたいことがあって、一つは福島の問題の影響の有無です。先ほど申しましたが、福島の事故後の種々の調査は非常に限定的で、情報発信もわかりにくい。その過程で、下手に不安を招きたくない、自分たちの料理した情報に沿って理解してもらえばよいと考えたのではないか。たとえばSPEEDIも、汚染水の問題もそうですね。広く情報を公開し、議論して意思決定するという手順を避けるほうがうまくいくという意識が、行政や政治家の中にあった可能性を考えないといけないと思ってます。
もう一つは、私は国の委員会で、生命倫理のヒト胚研究に長くかかわってきましたが、当初は科学技術庁が事務を仕切っていました。情報の蓄積能力も、会議の準備も、問題点の把握も手際がよくて、多様な専門家の意見が集約できる体制でした。これが省庁再編で内閣府になり、科学技術会議から総合科学技術会議に変わりました。このとき国レベルでの科学技術の討議の力が非常に落ちたと感じています。少なくともヒト胚問題ではそれが起こった。内閣府にはあちこちから出向してきますが、スタッフの力が弱くて、蓄積性、継続性がない。つど政府に都合のいい人を集めてきて、中途半端に議論して、結論ありきのようなことをやっている。だから2004年にヒト胚研究の指針が出たときにも、主に文系委員から反対意見があって混乱しました。このあたりに、国の科学技術に対する構えが政治中心になり、公共的な議論で足腰を強くするという意識の薄れが出てきたんじゃないかと思います。
山口
民間かアカデミアか、国がどうやるのかという問題もありますが、その前に、こういった未知のリスクに対する意思決定のためのリスクリストをつくる、という意思表示が必要だと思います。そのうえで、最適の部局が連携して対応策を講じる体制を構築すべきです。たとえば、NASAでは隕石の軌跡を調べて、問題になりそうならその軌跡を変えるようなことをやる。また、ライフラインである電力網のテロリスクの話はずっとやっている。一つのリスクに集中せず、シナリオ研究を通じて、想定されるさまざまなリスク対策にバランスよくリソースを投入して、向上を図るべきだと思います。
日本では、防災は原子力を含めて内閣府が担当していますが、いまあったように内閣府自体がある意味縦割りになってしまっている。本当は、たとえば原子力事故なら医療とか通信インフラとか、交通とか経済とか、いろいろ関連してくるけども、それがしにくい体制になっている。そういう話を内閣府の方もされてました。ですから国としての仕組み構築が必要というのは私も同感です。
唐木
ラムズフェルドの分類でいう「Known Knowns」であれば、行政はリスク管理ができるわけですね。難しいのは「Known Unknowns」です。実態がよくわからないリスクを誰がどう管理するのか。たとえば、70年代のアメリカにOTAというテクノロジーアセスメントの部局があって、新技術の問題点や影響を評価してリスク回避策を議会に提出した。ところが、共和党政権のときにテクノロジーアセスメントはテクノロジーハラスメントだということで、OTAを廃止してしまった。新技術の客観的評価は、政府の責任でやるべきで、実際やっていたけれども、そういう経緯で潰されてしまった。日本でも検討したけどできなかった。この問題をもう一回考え直す必要があると思っています。
城山
テクノロジーアセスメントはかかわってきたので話したいところですが、それとも関連するので少し戻って、山口先生がいわれるリスクリストの作成ですが、各所でオールハザード・アプローチみたいな議論がされるんですね。イギリスではホライズン・スキャニングといって横断的にリスクを全部洗い出すことをする。日本がどうかというと、先ほどの話のように内閣府に防災が来て、それから原子力防災もあって、レジリエンス、国土強靱化室ができて、国家安全保障局というのもある。このように内閣府にいろいろ来ているけども、バラバラで、横断的ではないという課題が一つあるだろうと思います。
最近の問題は、島薗先生のコメントにもつながりますが、何でも内閣府にもってきたがるんですよね。だから本来はもっと連携が必要なのに、内閣府が過重負荷になって課題の扱いも怪しくなるっていうのが多いように思います。こういう日本特有の問題があるのかなあという気がします。
今回のコロナもそういう面があって、新型インフルエンザのときに議論もして、包括的な取り組みもしてるんだけど、記憶が失われているところがあるんです。これも、やはり内閣府の体制が弱かったというところがあって、なかなか機能しなかったですね。専門家レベルでは当時と今回の新型コロナ関連ではキーパーソンが重なっていて、彼ら個人の知識が維持されていてなんとかなっていると思いますけども、組織としてはきわめて弱いのではという印象をもってます。
桝本
私は二つ、感想と意見をいいたいと思います。一つはさっき話が出た諦めですが、諦める、あるいは忘れるというのはある意味でおそらく生物には必要なもので、たとえば欧州が歴史的な争いを経ながらも仲良くやっているのを見ると、そのような力が往々にして働いているのかなと思いながら興味深くお話をうかがいました。
二つ目に、私のような者からいうと、この「未知の脅威にどう備えるか」というテーマは、エネルギーという視点で見て非常に重要です。エネルギーで備えといえば、やはりその具体例の一つは、備蓄なんですね。日本は200日以上の石油の備蓄がありますが、いま電力は4割をLNGに依存しています。少し前にフィナンシャル・タイムズが、そのLNGの備蓄が2週間しかないという日経のAsian Reviewの記事を転載しました。つまりイギリス人から見ても興味深いわけで、やはり日本の備えに関する考えは、国際的に見ても甘いのでしょう。今度のコロナの不況でおそらく10年ぐらい、エネルギー需要は後退するのではと思いますが、それによってさらに備えが甘くなることを危惧します。地球温暖化問題もありますし、日本はどうエネルギーを確保するのかという基本的な備えが、おそらくこの先5年10年甘くなるんですね。国防とエネルギーは同じような重さがあって、やるべきことはきちんとやる必要がある。私は、原子力発電はそのうちの一つだと思います。
山口
いまの諦めというお話は印象的なんですが、原子力の安全の世界では、その諦め、トレードオフが、どこか想定外という話になってしまうんですね。どこかで割り切って、そういうシナリオがないものとすると。しかし原子力に関して必要なのは、割り切って捨ててしまうのではなくて、ウェイティングリストというか、脇に置いておくことだと思うんです。いつでもそれをレビューできて、元に戻せる。なぜウェイティングリストに入れたか、トレーサビリティがあることだと思います。
そういう観点でアメリカの原子力委員会はヒストリアンという職業の方がいて、アーカイブとしてしっかり記録しています。一方、たとえば福島事故では全電源喪失は考えてなかったという話がありますが、じつは昔の議事録を見ると、議論をして、電源の信頼性が高いから30分だけ外部電源装置を考えればよいという結論になったと書いてあるんですね。ところがその議事録以上のものが何もなくて、誰がどういう考え方を述べて、どう30分に決まったのかが追えない。全電源喪失に対する設計基準がウェイティングリストにあって、それを取り出して設計できる、つまりそのときの議論が追えるようなアーカイブ、それもただあるのではなくて、それが体系化されている。それによって過去の経験とか教訓とかがきちんと伝わっていく機能が必要であると思います。
大来
ここまでの議論を整理して、さらに議論を深めたいと考えている問題が三つあります。一つ目は行政組織の縦割り問題です。もともと行政組織は縦割りで専門性を発揮するだろうからです。官邸主導で行政を遂行することは、両刃の剣の危うさがあると感じます。二つ目は、専門家どうしのコミュニケーションの難しさです。平川先生から国際的な連携が重要だという話が出ましたが、専門家の横の連携は本当に可能かという問題意識です。三つ目は山口先生が話してくださったヒストリアンにかかわることです。日本の科学技術基本法は、意図的に、法律的に人文科学、あるいは人文学を排除しました。島薗先生はまさにその領域で最先端を走っておられますが、人文学の知見というのは、科学技術政策を考えるうえで絶対必要だと思っています。
島薗
まず、山口先生もご指摘された歴史の問題、これはたいへん重要です。感染症の歴史は人類史全体にわたる文明論とかかわります。人間社会に広く影響を与えたことですから、感染症の医学専門家はもちろん、人文学、社会科学のあらゆる分野の人が関心をもつことになります。
今回のコロナウイルスは大きな文明的変化をもたらすともいわれます。歴史を顧みながら現在を理解する、その中で科学技術の変化も見通すことが重要になると思います。科学技術史だけでなく、文明史、人文学など幅広く照らし合わせながら考えることになるでしょう。
科学の領域から見ると「Unknown Unknowns」でも、人文、歴史からは「こういうこともあったのか」と見えることがあります。人文知、人類の知恵の蓄積は無視できない。また我々には将来の世代に対する責任があります。哲学者ハンス・ヨナスから重要な問題提起がなされています。我々は自ずから近視眼であると。しかし将来に生きる人々が人類として健康を保ち幸福を享受するということは、現代人にとっても重要な、我々の存在意義の問題でもあるわけです。
専門家間のコミュニケーションでは、自然科学だけではなく人文・社会科学の協力というのも重要であると思います。城山先生や平川先生はまさにその領域で頼もしい仕事をされていますが、今世紀に入って、ますますそうならざるを得なくなっていると思います。原子力の問題、生命科学、今回のパンデミックもそうです。
これについて日本の学会はどうか。日本学術会議は文理の協力が自然と成り立たざるを得ない構成になっていて、これは大きな利点だと思います。もっとも、科学技術の展開に対してうまく機能してきたかは定かでなくて、原子力についても生命科学についても、人文社会系から警鐘が鳴らされていますが。
しかし学術会議と政府の問題となると疑問です。政府が学術会議に科学的助言での貢献を望んでいるかというと、非常に怪しい。いまは首相が主宰する総合科学技術・イノベーション会議で科学技術政策の基本が決まる。そこに日本学術会議の代表が常任委員として入るという体制が、科学的助言のあり方として適切なのかどうか。政府と科学の関係という点からも大きな問題ではないかと思います。日本学術会議は政府の介入、予算カットの脅しを意識したりもしている、そういう状況でもあります。
平川
いまの話に絡めて、僕もコメントを。前半で話に出た複合的、社会的なリスクも含めて考えるときに、歴史の話が重要だと思います。人間性は歴史が経っても社会が変わっても、根本の部分で変わらないところがあって、新しい事象をきっかけに古くからの問題が繰り返されるということはあると思うんですね。たとえば今回の感染症でも、自粛をしない人に対する過度な非難、あるいは医療従事者に対する差別的言動とか、ある種の異端、異物を排除する動きは、関東大震災での朝鮮人虐殺のように、歴史の中で何度も起きている話です。その意味で歴史を振り返る、知っておく活動の継続は必要だと思いました。
ちなみに、原発事故のときも、人文社会系の研究者から、水俣病と同様の差別問題がきっと起きるという話が出ていて、実際に起きました。そういう意味では、歴史の中に未知のリスクに対する備えや予測の可能性が眠っていて、文系の知見、人間性に対する洞察や蓄積が重要と思った次第です。
島薗
先ほどの続きですが、1990年代には脳死臨調というのがありました。哲学者の梅原猛さんなどが加わって、脳死は本当に人の死か、国民的な議論になりました。そこでの洞察は、世界に先駆けている面があって、その後、むしろ欧米で問題にされるようになってきたことを先取りしていた。
ですが医学系の、特に臓器移植の関係者から見ると、このせいで日本はひどく遅れたという理解なんですね。そのため行政は、同様の人文系も巻き込んだ大きな議論をやると、時間がかかり、遅れにつながってしまうという考えになったのではないか。
1997年にクローン羊のドリーの誕生が発表された後に、世界各国が生命倫理の協議を立ち上げました。日本も生命倫理委員会を立ち上げて、そこに私も入りました。哲学者や人文学者もかなり入っていて、ヒト胚の地位などについてがっちり議論しました。それが2000年になると、そういうのを通り過ごして、結論ありきでそこに向かって議論するというふうになってしまった。
これは新自由主義の経済効率重視の流れとかかわっていて、結果を出すのがまず先で、議論をしっかりやるのはあまり意味がないという方向に流れてきた、このように見ております。これが先ほどの行政の問題で、内閣の強化で本来うまくいくはずが、逆に政治が勝手に走ってしまう体制をつくり、官庁と科学の底力が軽視されることにもなったと見ております。
大来
同様の議論で、思い浮かぶのはBSEの問題です。BSEはいまの話に比べて、唐木先生を始め、かなり情報があって整理され、一般の方向けのドキュメントもあると思うんですが、この点についてご意見いただけませんでしょうか。
唐木
BSE問題では本を2冊ばかり書きました。あれだけ問題が大きくなったのは、社会に対する影響が直接的だったことがあるだろうと思います。しかし、脳死臨調の話というのは、多くの人にとって実感がない。その距離感の違いがあると思います。
日本の医療の実態は社会あるいは政治が認識しているものと乖離があって、それが今回のコロナの問題で如実に現れています。コロナ対策が遅れたといわれている。確かにそうですが、それは日本の医療が皆さん思うほどには整っていないためです。日本には10万の診療所があるけれど、病院は1万もない。新型コロナの患者が入院できる指定医療機関はさらにその1/10で、感染を防ぎながら新型コロナ患者のケアができる集中治療室の数は世界的に見てきわめて少ない。
中国や韓国は、MERSやSARSのコロナウイルスの洗礼を受けました。日本にはどちらも来なかったから、経験がないんです。季節性のインフルエンザしか経験がないところに今回のコロナが来たから、大きなパニックになった。政治の遅れではなく、医療体制の遅れが一番の原因だと思います。
統計的には、新型コロナによる死者は、70歳、80歳で、基礎疾患のある人たちですが、イタリアやスウェーデンなどではトリアージュをやっている。80歳以上で基礎疾患がある人には、人工呼吸器をつけないとかICUに入れないという措置です。それは、限られた数の医療用機器や設備を誰に使うのかという深刻な問題であり、患者の選別を許容するのはその国の文化につながるかもしれない。
日本の医療では、助かるかもしれない命を救わないことは絶対許されない。だから、新型コロナ感染者の救命施設が足りないとき、誰を優先的に治療するのかを決めるのは現場任せで、現場は到着順にせざるを得ない。それが公平なのか、議論することはない。
また専門家会議には医療関係者しかいない。彼らにとってはすべての人を助けること、感染拡大防止が最大の義務ですから、そのための対策を政府に提言した。経済やリスク管理など他分野の専門家がいないので、政府は医療中心の政策を実施せざるを得なかった。
その結果、ビジネスが崩壊し、失業者が続出し、自殺者が増えるという予測もある。政府のリスク管理、危機管理の体制ができていない。野党やメディアが文句をいうので、政府も医療の専門家に意見を聞いて、お墨付きをもらわないと対策が動かなくなってしまった。
危機管理を国がきちんとやるには、政府に科学顧問を置かなくちゃいけない。科学顧問は個人ではなく、科学の組織が対応することが必要です。本当は日本学術会議がやればいいんですが、島薗先生もいわれるようになかなかそうではない。
島薗
科学的助言については、総合科学技術・イノベーション会議に科学者の代表が入っていればよしという体制になっていますが、機能面で非常に悪いのは明らかで、変革が必要です。
今回のコロナでも一方に専門家会議、他方に諮問会議があります。新型インフルエンザの審議会の中に諮問委員会というのを新設してあったわけですね。この両者の関係がよくわからない。法律の関係でそうなってますが、責任の所在が不明確です。両方に入っている先生がいればよいという問題ではなく、この形では政治家も責任を取りにくいし、科学者も自分の役割を明確にできない。政治家の判断を科学者の名前でいつのまにかやるということになりかねない。
山口
いま唐木先生がおっしゃった、外国の考え方が伝わらないことの例で、原子力で象徴的なのはイギリスのALARP(As Low As Reasonably Practicable)があります。これはアメリカでもALARA(As Low As Reasonably Achievable)といって、さんざん議論されていますが、日本にちゃんと伝わっているかというと疑問です。日本ではALARPというと、いまだに「つまりリスクをいくらでも低くすることではないか」という議論になってしまう。そうではなく、「あるだけのお金を払ってリスクを減らすのが皆に受容されるかを決めること」なんですね。
そういった国際的にはコモンセンスになっている考え方を日本も共有するというのは、情報交換といいますか、そういうコミュニケーションという問題に尽きるのではないかと思います。
島薗
いまのALARAの話は、トレードオフ、リスクはさまざまでそのバランスをとるという考え方ですね。こういうこととかかわり合いが出てきているんですね。
先ほど提起されたトリアージュですが、専門家会議の武藤香織さんが、生命・医療倫理研究会有志名で提言を公表しました。障害者団体その他から厳しい批判が出ていて、これには究極の選択において命は量の問題になる、すべて救うという原則から、どちらが多く救えるかという原則に転換すると書いてある。これを政府公認の文書として出すのは、私は反対です。これは尊厳死とか、安楽死につながる問題ですね。終末期医療の差し控えなどでも、長く議論されてきた。
緊急下では、医療資源の分配問題は避けられない。しかしそれをある基準に沿ってやるのは、命の選別に踏み込みかねない。高齢者は後回しとなると、同じような場合に対する、一種の規範として提示することになるわけですね。これは相模原の津久井やまゆり園事件と、どこで違うのかということになってきます。
安楽死に対する考え方も、たとえばドイツやフランスと、スウェーデンやオランダでは違う。イタリアの場合は、本当に仕方なくそうなったということはあるかもしれませんが、規範として認められたことはなかったのではと思います。カトリック文化の強い国ですから。
大来
先ほどのALARPについてですが、私の理解はこうです。生命倫理でもトリアージュでも低線量放射線でも、リスクや生命の危機を表す直線的なグラフをイメージします。政府が基準を示すということは、その間に1本線を引くということだと思うんです。
ALARAとかALARPの基本的な思想には、議論しましょうというのがあると思います。まず両端の間に中間領域があることを認める、それが議論の出発点。ところが日本では、中間領域を認める議論がまったく成立していないんじゃないかと。本書のテーマであるコミュニケーションや合意形成は重要ですが、その基盤がないところで合意形成とか政策決定をすることになる。これは絶望的なんじゃないかとも思いたくなります。最後のテーマには無関心の問題を取り上げますが。
山口
基本的には大来先生がおっしゃったことと同じで、ALARAは規則ではないんですね。考え方であると。
ユヴァル・ノア・ハラリは、AIについて語る中で、自動運転車のプログラミング問題、飛び出した歩行者を守るか運転者を守るかという例を出しています。人工呼吸器もそうですが、そういう選択を問う問題はたくさんあって、最後には何かで決めなきゃいけないんですね。それが規則なわけですが、それはいろいろな要因によって決まってきます。それを原子力の世界ではintegrated risk informed decision makingといいます。つまり意思決定というのは決してリスクベースではない。リスクはinformed、参考に使うものだと。integratedの意味は、判断の物差しが1次元ではなくて、複数次元のいろいろな要因を統合して決める。そういう考え方なわけです。
それでALARPを改めて見直すと、reasonably practicableなんですね。ではreasonablyとは、practicableとは誰が決めるのか。その規則はないし、物差しもないんです。ないけれど、そういう考え方で決めていく。それによって最後の意思決定を可能にしましょうという合意がALARPだと、私は思っています。ですから日本とイギリスでは、ALARPの使われ方や、使ってできる規制・規則は違うかも知れません。でも考え方は共有できる。状況が変われば、規制・規則も変わるかもしれない。基本的な考え方、発想法を国際社会で共有し、さらにケース・バイ・ケースで判断して意思決定できればよいと思います。
それから大来先生の、中央に不確かな領域があることを認めるのが先決だと、これはまったくそのとおりで、現象そのものも、人間の心も不確かなわけで、それが包含された思想だと思います。
城山
不確かさもそうですが、どういうスコープでものを考えるかということが問題ではないでしょうか。トリアージュの問題でいうと、集中治療室という特定の局面を見て、そこに誰を入れるかというスコープが妥当かという問題です。集中治療室のキャパシティに収まるならトリアージュをしなくてよいという意思決定をしてしまうと、逆にそうなるように経済活動を抑え込むことで、自殺など別の被害が出てきてしまう可能性があります。
そういう意味で、生命倫理なりトリアージュの問題は、医療現場に焦点はあっても、社会全体を考えないといけなくなる。それをどこまで考えるのかが問われると思うんですね。
同じことが原子力にもあって、ALARPの話も統合的に考える必要がある。ではどこまで考えるんですかと。たとえば原子力とエネルギー安全保障のトレードオフを考えて、原子力をやるという意思決定は当然あり得るわけです。しかし、リスクマネジメントの原子力関係の決定過程で、それを定量的にやっているのは見たことがない。どこまで広げて考えるのか、やりだすときりがない話でもあるので、そこも判断が問われるのかなという気もします。
出典:『鋼鉄と電子の塔:いかにして科学技術を語り、科学技術とともに歩むか』第4部
★第1回、第3回の記事はこちら:
***
『鋼鉄と電子の塔:いかにして科学技術を語り、科学技術とともに歩むか』
大来雄二、桝本晃章、唐木英明、平川秀幸、山口彰、城山英明、島薗進 著
電気学会倫理委員会 編
四六判、304ページ、定価3520円
2020年12月上旬刊行予定
科学技術と社会の関係がいま、大きく揺らいでいる。
高度に進化し、日常に深く浸透したテクノロジーは、もはや科学的知見だけでは制御しきれないものとなった。それにより、科学技術の専門家、ひいては科学技術そのものが、しばしば疑いの目で見られ、時にないがしろにされるような状況が生まれている。しかし私たちの日々の生活は、科学技術なしには到底成り立たない。
科学技術といかに共生していくか――。この問いがいま、現代社会に生きる人々すべてに対して突きつけられている。テクノロジーへの無自覚・無関心な依存を脱し、互いに語らうべきときが来た。
原子力発電、遺伝子組換え、BSE、地球温暖化、そして新型コロナウイルス――。科学技術と社会の関係深化がもたらす課題と、それらをめぐるコミュニケーション・意思決定のあり方について、産業・理工学・人文社会学の各分野の第一人者たちが、それぞれの視点から切り込んでいく。
〈人類にとっての科学技術の意義とは〉、〈なぜ人々は科学技術に不信感を抱くのか〉、〈科学技術の光と影に、どのように向き合うべきか〉・・・。
各章で示される主張はまた、我々自身へのさらなる問いかけでもある。これらは現実の複雑さを投影して、さまざまな視角をもつ多次元の写し鏡をなしている。多面的な対話の重要性を、あなたは理解することになるだろう。
突きつけられた問いに向き合い、ともに語り、そして前進するための燈火となる書。
【目次】
第1部 シンアルの地――社会にとっての科学技術を理解する
1章 不可避的に深まる科学技術と社会の関係(大来雄二)
第2部 言語の混乱――コミュニケーションとは何かを考える
2章 科学技術の恩恵は見えているか:電気の“空気化”がもたらしたもの(桝本晃章)
3章 不信と誤解が招く不安(唐木英明)
4章 コミュニケーションのすれ違いをどう理解するか(平川秀幸)
第3部 王《ニムロド》のいない街――誰が、何を、どのように意思決定するべきか
5章 「安全」の描像:リスクといかに共存するか(山口彰)
6章 社会における科学技術のガバナンスと専門家の役割(城山英明)
7章 科学技術専門家が市民の信頼を失う経緯(島薗進)
第4部 塔を囲む人々――執筆者座談会
1 原子力発電の過去・現在・未来(福島原発事故と汚染水)
2 未知の脅威にどう備えるか(次の感染症、次の大津波はいつか必ず来る)
3 無関心問題(メッセージが届かない人にどうアプローチするか)
4 座談会の最後にあたって(読者へのメッセージ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?