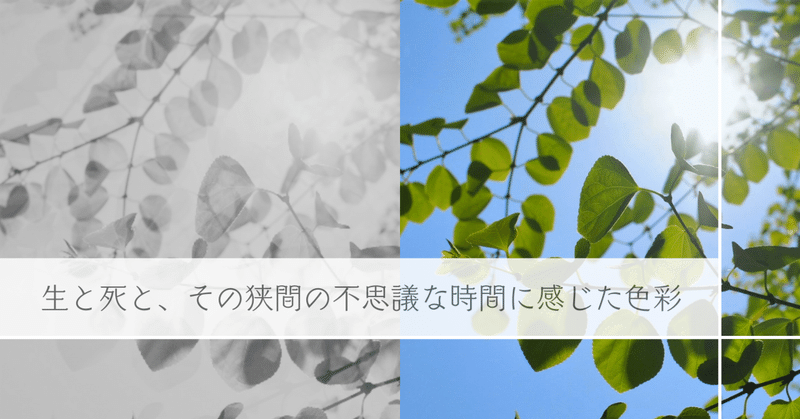
生と死と、その狭間の不思議な時間に感じた色彩
弔事用に包みなおしてもらった菓子の紙袋をさげたまま、ふらふらと食品売り場へきてしまった。自宅の冷蔵庫になにが入っているのか、ちょっと思い出せない。食欲もあるのかないのか、よくわからない。なんの目的もないからカゴも持たず、ひんやりした生鮮コーナーを歩く。
今夜は家で食べるのだから、食べたいものを買えばいい。いつの間にか夏になっていたから、枝豆を買おう。枝豆が大好きな娘は家を出てしまったから、ちいさいほうの袋でいい。水耕栽培の3種の寄せ植えレタスもなんだか色がきれい。そうだ、セロリを切らしていたはずだ。
あっという間に緑・緑・緑になった左手を見て、ちょっと笑った。モノクロームの世界のなかで、左手だけが鮮やかに彩られている。エネルギーを感じる色。左手のなかの、生命ある世界。
❅
「お夕飯の時間になる前に、ちょっとだけ寄っていこうか」と、予定を変更して父方の祖母の家に寄ったのは、先月末のこと。両親と妹夫妻といっしょに2年半ぶりの外食を楽しんだ帰りだった。
10年前に祖父に先立たれてから祖母は頑なにひとり暮らしを続けている。気軽に会えなくなったこの2年のあいだに99歳を越えて足腰こそ弱ってきたけれど、頭ははっきりしているから、あの日も短い時間にいろんな話をした。
父が「そろそろ帰るぞ」と立ちあがった瞬間、ふと思いついた。
「ね、写真撮ろう?」
すぐさま「いいねぇ!」とみんなが祖母の椅子のまわりに集まった。カメラマンを交代しながら、スマホで写真を撮る。普段は恥ずかしがることの多い祖母もその日はなんだかうれしそうにしていて、和やかでいい時間だった。写真のなかの彼女は、とても楽しそうに笑っている。
撮った写真を見せたあと、「じゃあね、おばあちゃんまたね。また来るね!」と言って、祖母の家をあとにした。
そのときはまだ、みんなで撮ったその写真から祖母を切り出して遺影にするなんて、思いもよらなかった。
骨折の手術のために祖母が入院することになったと母から聞いたのは、その2日後のことだった。
❅
「病院の浴衣をお召しになってますが、浴衣をとって白いお着物になさいますか? それとも、浴衣のうえにお着物を着せましょうか」
納棺師さんのことばに、みんな一斉に父を振り返ったけれど、父の答えはわかっていた。
「そのままで、浴衣のうえに着せてください。お願いします」
亡くなったとはいえ、大切な母親のあられもない姿を他人に見られるのは、やはり耐えがたいのだろう。
亡くなってすぐはまだ頬も手も温かだったのに、一日経った祖母の身体はすっかり冷えていた。重力と硬直や弛緩の加減なのか皺もいくぶん伸びて、おだやかに微笑んでいる。わたし達姉妹と両親、叔母たちは、斎場の祖母の眠る親族控室で納棺の支度に同席させてもらっていた。
「それ、手につけるんだ」と誰かが言って、「あぁ、手甲ね」と叔母が言った。わたしが「旅支度だからか」と つぶやいたら、納棺師さんは振り返ってうなずいた。
「そうなんです。あの世への旅なので、手甲のほかに脚絆もつけておられますよ」
白い着物のすそをそっとめくると、たしかに白足袋の上のすねのあたりに白い布が巻かれている。
「おばあちゃん、草鞋の履きかた、わかるかなぁ?」
「そりゃあ、わかるでしょ」
「今は寝ていらっしゃる状態なので草鞋は履かせないで、棺に入られてから足もとへ置かせていただきますね」
祖母の手足は思いのほか やわらかに動いているように見える。着付けが終わると、納棺師さんは祖母の手をとり、ゆっくりと胸の下へおろして両の指を静かに組んだ。むくみのとれた元どおりの祖母の手がそこにはあった。
「ふだん、お化粧はしっかりなさっていましたか?」
全員が首を横に振る。
祖母は日ごろ、身だしなみ程度にしか化粧をせず、素肌になじむローズベージュの口紅だけをつけていた。
「そうですか。それでは、お肌の色を整える感じにさせていただきますね」
そう言って広げた彼の道具箱には、見たことのないさまざまな道具や綿や化粧品が入っていた。
綿をちいさくちぎって丸め、そっと開けた口のなかに先の細いピンセットで詰めていく。本人が感じるわけがないと知ってはいても、なんだか痛々しくて、思わず目をそむけた。頬がわずかに膨らんで、鼻の奥にも綿が詰められると、急に祖母の顔が若々しくなった。幼い頃に隣の布団から見た祖母の横顔は、こんな感じだった気がした。
何色もファンデーションの色を使って、ていねいに肌を作っているのに、全然厚塗りの感じがしない。むしろ透明感が宿って肌が若い。
化粧を終えると、髪にミストをかけ、くしで整える。
「髪の根もとはどうしましょう?」
毎月1回、美容室で白髪を染めていた祖母の髪は、このひと月の間に伸びて、根もとが白くなっていた。90歳を過ぎても、自転車に乗ってひとりで美容院に行っていた祖母。ここ数年は、叔母が車に乗せて通っていたという。髪を白くするという選択肢は、彼女にはなかったらしい。
「黒くしてください」
「真っ黒ですか? それともすこし茶色っぽくします?」
「真っ黒ではないですね・・・染まってるところに合わせる感じでお願いします。色を混ぜてもいいかな」
納棺師さんはすこし色味を迷ってから、ファンデーションのスポンジのようなもので、すこしずつ色を塗り重ねていく。時間をかけて、祖母の髪は境目のないきれいな色になり、ていねいにセットされた。
「お化粧が終わりしましたが、みなさんご覧になって直したいところとかありますか?」
「いえいえ。おばあちゃん、元どおり・・・っていうか、若くなった!」
「すごい! ありがとうございます! 眠ってるみたい」
「おばあちゃん、笑ってるね」
「きっと、みんなに見られて『いやだぁ、恥ずかしいわ』って言ってるよね」
みんなで祖母の顔を覗きこんでいたら、不意に涙がこみあげてきた。目の前にいるのに、今にも はにかみながら喋りだしそうなのに、もう、その唇は動かない。
今までに、大切な家族や友人を何人も見送ってきたけれど、これほどまでに生前の様子が再生されたように感じたのは、はじめてだった。
すごいと思った。
心の底から、すごいと思った。
納棺師とは、なんという尊い仕事なのだろう。
祖母の「ご遺体」には、みるみるうちに彼の手で生気が描き足されて、まるで生命が吹きこまれたかのように見えた。通夜と葬儀を終えたら荼毘に付されてしまうその身体だけれど、もう一度だけ。
「みなさま、どうぞお力をお貸しください」と、彼はわたし達に祖母の眠るちいさな布団の周囲を持つよう、声をかけた。彼のかけ声にあわせて、わたし達は祖母を持ちあげ、そっと棺のなかに下ろした。
ずいぶん軽い身体だった。
❅
「感染拡大を防ぐため、喪主様おひとりでお願いいたします」という説明は、全然ぴんとこなかった。火葬場のスタッフが運ぶステンレスのトレーには、ちいさく砕かれた白い欠片が並んでいて、目の前の遺骨と灰を眺めながら頬が熱いなぁとぼんやり思っていた。
スタッフから金属の長い箸を渡された父は、白くちいさな骨壷に、足の骨から順に祖母の身体を入れ、最後にゆるやかな曲線を描く頭の骨を乗せた。
「おひとりで」って、そういうことか。ようやく説明の意味がわかった。初めて骨上げを見る姪っ子に本来の方法を説明しながら、だんだん頭がはっきりしてくる。骨上げは、ひとつお骨を入れたら次の人に箸を渡さねばならないから感染の危険があるし、使い捨ての木の箸ではお骨が高温過ぎて箸が発火してしまう危険性があるだろうから、この方法をとるしかなかったのだろう。
❅
ちいさな骨壷におさまった祖母を父が抱き、あの日みんなで撮った写真から切り抜かれた祖母を母が抱いて、わたし達はほの暗くひんやりした廊下を進んでいった。
駐車場へとつづく自動扉がひらいた瞬間、蝉しぐれに呑みこまれる。暑い。強い陽射しが緑の葉におどっていて、まぶしくて目を瞑った。
すべてがビビッドだった。
生命ある世界。
あぁ、祖母は旅立ってしまったけれど、わたし達はまだ、こちら側なのだと思った。耳で聴き、目で見て、唇からことばを発し、暑さを感じることのできる肉体を持って、生きている。
モノクロームの世界のなかで、息づくビビッド。
生と死と、その狭間の不思議な時間に感じた色彩。
ここまで読んでくれたんですね! ありがとう!
