
照井翠句集『泥天使』を読む 龍宮からの使者と、二つの「時」
十年前のあの日、照井翠氏は岩手県沿岸の町、釜石で被災した。照井氏が教師として勤めていた高校の体育館は、避難所となった。被災者たちが身を寄せたその場所は、多様な「被災」の集積地であったと想像される。
ロングセラーになっている前句集『龍宮』は、照井氏個人の直接の被災体験に加え、避難所で様々な被災者から過酷な体験を聞き、その息遣いや体の震えを通して伝わったものが、俳句の源になったのではないだろうか。その意味で、照井氏の震災に関する俳句とは、表現する言葉を持たぬ被災者たちの声が、俳人の奥深くでその想像力と交り合い、ある共同的な無意識として汲み上げられたものではなかったか。
喪へばうしなふほどに降る雪よ 『龍宮』
双子なら同じ死顔桃の花 〃
喉奥の泥は乾かずランドセル 〃
鰯雲声にならざるこゑのあり 〃
虹忽とうねり龍宮行きの舟 〃
「降る雪」は、まさに今、喪い続けている人々の心の深淵に降り積もる悲しみの雪だ。
遺体が見つからない双子の片方の死顔は、幻視するしか術がない。二人の子に、桃の花が供花として捧げられた。そう私は読みたい。
照井氏にとって、震災の究極的な象徴物は「泥」だった。津波による災害とは、「喉奥の泥」といった凄絶で生々しい身体実感を伴う体験だったに違いない。
師・加藤楸邨の句〈鰯雲人に告ぐべきことならず〉への返歌のように、「声にならざるこゑ」を聴こうと照井氏は耳を澄ます。それは、からがら生き延びた者達の「こゑ」であり、彼の世へ渡っていた人々の「こゑ」でもある。
「龍宮」は、そのような死者たちの住む世界で、虹の向こう側の根元の、海の底にあるらしい。
震災十年目に合わせて刊行された新句集『泥天使』では、『龍宮』以降の震災詠と、震災以前からの「常の句」も収録されている。照井氏の句は、震災を題材にしていても、同時に人間存在の深層を詠もうとする。震災以前から人間の生と死に向き合ってきた常の句の延長線上に、照井氏の震災の俳句があっただろう。句集題となった
三・一一死者に添ひ伏す泥天使
には、震災で亡骸となった死者の傍らに「泥天使」が現出する。〈三・一一神はゐないかとても小さい〉(『龍宮』)と、救済者なき現世を詠んだ照井氏にこの「泥天使」を幻視させたのは、経過した「時」であったように思われる。
時は、物事を風化させ、忘却させ、ゆえに人を癒すこともある。しかしその一方で、時が経っても決して癒えない痛みがあり、繰り返す恐怖が、人を喪った悲しみがある。「泥天使」とは、そのような「時」による癒しと、痛みや悲しみへの祈りという両義的な存在の現れではなかったか。
ここで折口信夫の民俗学を援用すれば、前句集の「龍宮」とは霊の国である〝常世〟であり、「泥天使」とは常世からの来訪神である〝まれびと〟ではないだろうか。折口の〝常世〟〝まれびと〟は、生死・禍福・善悪の両義を合わせ持つ概念であった。命を奪いも与えもする「泥」から誕生した、龍宮からの使者「泥天使」は、震災をきっかけとした死と生の真実を私たちに何度でも問い掛けてくる。
盆の月海は砂浜喪ひぬ
被災沿岸地域に建てられた、巨大防潮堤の光景だろうか。砂浜は、海と、人が暮らす陸の間であり接点だ。盆の月は、海と人が共に育んできた砂浜の記憶を照らす。その記憶もまた、喪われつつあるのだろうか。
三月の針ばらばらに指されをり
私たちはどこまでいっても、私以外の当事者にはなり得ない。他の被災者にはなり代われない。百人百様の三月の時計の針を前にして、絶句してしまう。しかし照井氏は、そんなばらばらの他者に流れる時を直視し、思い遣りつつ、詩の言葉を紡ぐことで、自らの一つの時を刻もうとする。
双蝶の息をひとつに交はりぬ
単なる生殖行動を越えた、生物の個体同士の甘美なる交感の一瞬が捉えられている。「息をひとつに」という性愛における生の歓喜の裏には、全てを委ねて息を止めてしまいかねない、死への衝動が蠢いているように思われる。
海を発つ群青列車流れ星
群青色の列車「SL銀河」は、釜石と、照井氏の故郷・花巻を結ぶ。思えば、宮沢賢治の童話「銀河鉄道の夜」で、主人公ジョバンニが共に銀河の旅をした親友のカンパネルラも、水死だった。津波で多くの死者を出した海沿いの町から内陸の故郷への列車の旅は、深い鎮魂の祈りの先に一筋の流星の光を見た、銀河鉄道の旅でもあったのだろう。
三月を喪ひつづく砂時計
十年前に喪われた三月は、デジタル時計や文字盤の時計のようにリセットされない。砂時計の落下する砂のように、何年たっても、積もり止まない喪失体験がある。それは、時の経過による忘却で薄まっていく記憶とは逆に、時が経つにつれて募っていく思いなのかもしれない。繰り返す喪失は、辛く苦しい。しかし翻っていえば、喪うことは、死者との邂逅であり、祈りの時なのだ。忘却の癒しと喪失の祈り、二つの「時」を生きるからこそ、生者は、未来に向けて歩いてゆけるのかもしれない。
*俳誌「草笛」503号、「コールサック106号」より転載

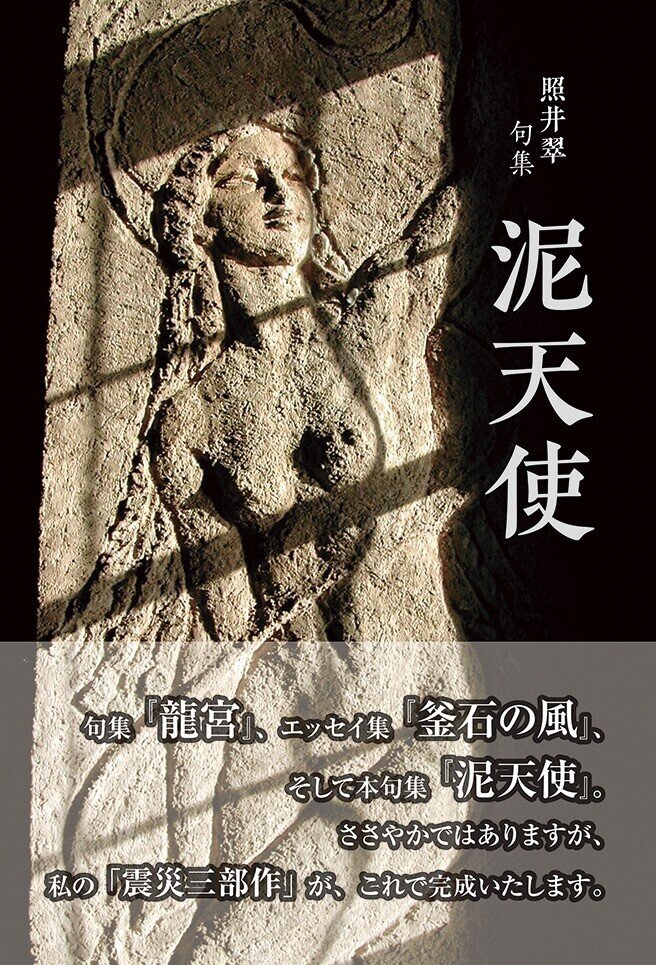
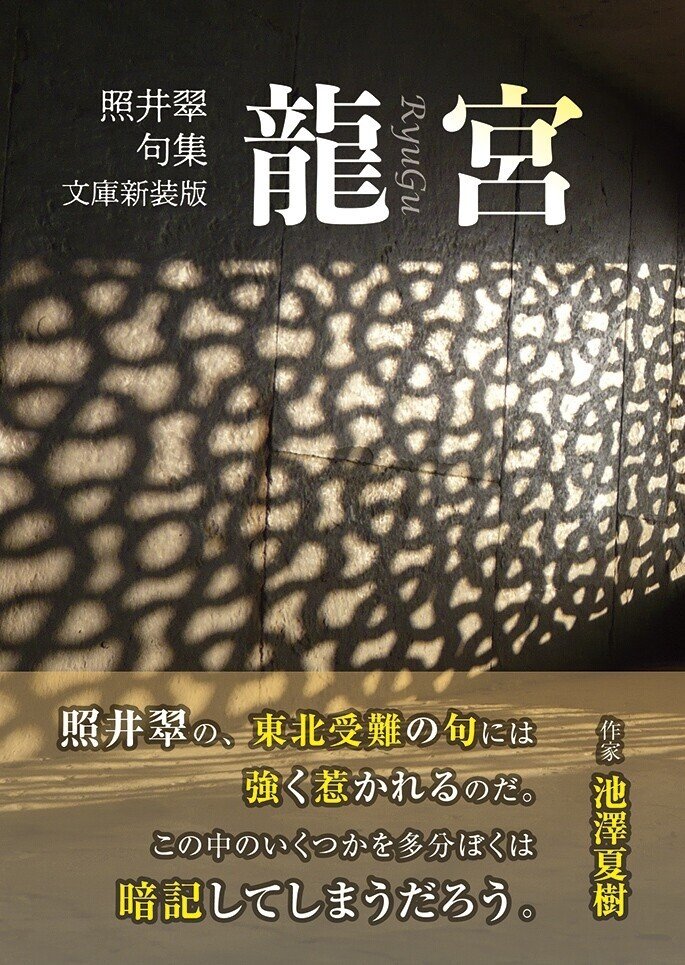
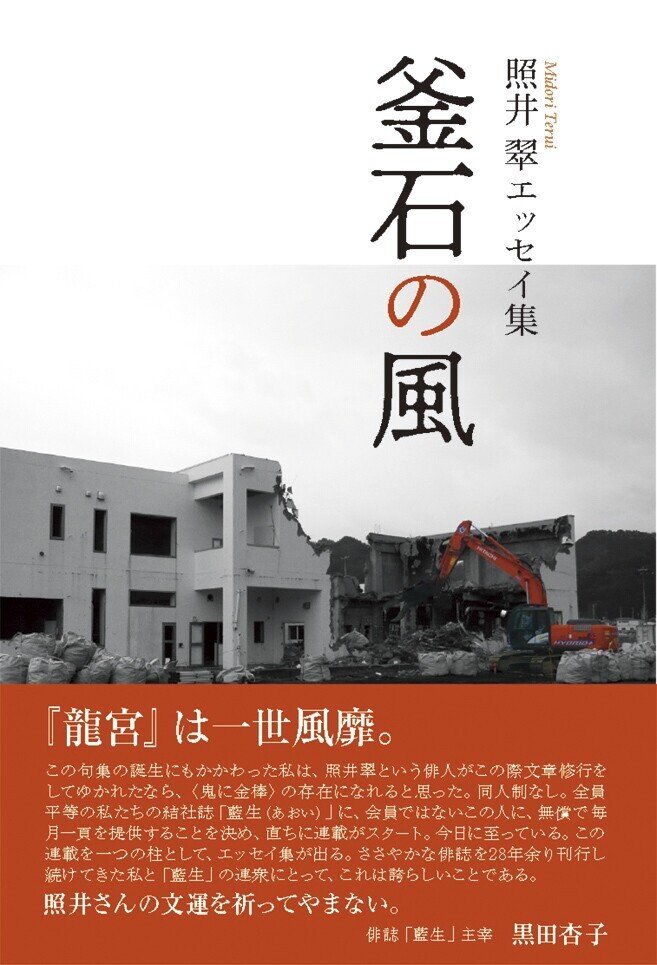
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
