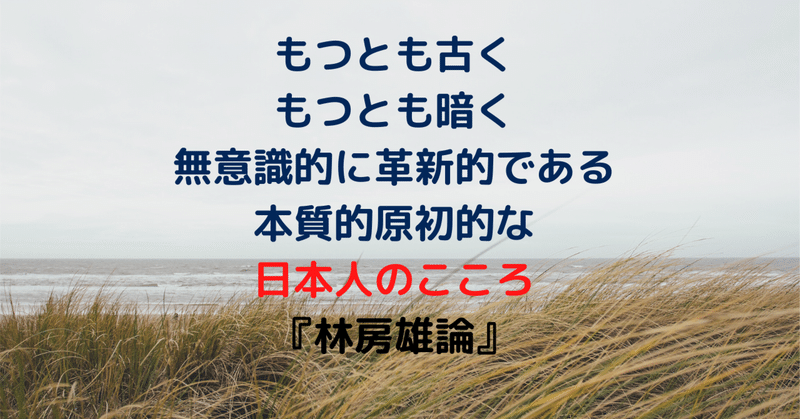
『林房雄論』を読む(2)
真の開国主義
林の小説「青年」では、明治維新の元勲である井上馨をモデルとする聞多と、伊藤博文をモデルとする俊輔が、攘夷〔外国を追い払うこと〕を目的に、若き日西欧に留学したが、後に開国論者になって日本に帰って来る。三島はこの小説に登場するプウランという名の外国人医師の次のようなセリフを引用する(決定版32,378ページ)。
幕府の開国主義は、封建主義の自己保存の見地から生まれた見せかけの進歩主義にすぎない。しかし、長州の排外主義は一見反動的に見えても、(中略)根本において現状打破の急進主義であって、それはある時期には、容易に正しい開国主義に転化することの可能を示すものにほかならぬ。言ひかへれば、長州の現状打破精神とあの二人の青年によつて代表される正しい国際認識の上にたつた真の開国主義とが結合するとき、日本の革命的潮流ははじめて文明への方向をとるのだ(上巻百二十二頁)
プウランによれば、幕府の開国主義とこの二人の青年の開国主義とは似て非なるものである。前者は「自己保存の見地から生まれた見せかけの進歩主義である」のに対し、後者は長州の現状打破の精神、急進主義と結合した真の開国主義である。
現状打破の精神
このようなプウランの見方について三島は次のように解説を付ける(378~379ページ)。
俊輔の開国論は一見、西欧風の明るい、理智的な啓蒙主義のごとくに見えながら、ひとたび日本の革新の問題に触れると、むしろひたすらに、長州藩の激しい現状打破精神の底流に身をひたし、さらにその奥に「聖天子」〔徳の高い君子〕の光輝を仰ぎ見ることになる。つまり、革命を思ふときに彼は自分の伝統と心情の底へ下りゆかざるをえず、もし彼の「理想」がそこまで下りてゆかないならば、彼の転向も贋物にすぎなかつたことになる。なぜなら彼の攘夷論から開国論への転向は、攘夷論の心情の裏附けを失ふときに、そのもつとも本質的なものを失ふことになり、それはもはや真の転向ではないからである。
三島によれば上述の青年の一人、俊輔の攘夷論から開国論への転向は、かつて彼の攘夷論を支えていたはずの、長州藩の激しい現状打破精神に裏附けられて初めて、真の転向となるのである。
日本人のこころ
三島はこのような青年たちの、攘夷論から開国論への転向を、林の共産主義から右翼思想への転向に、次のように重ね合わせる。
さて、共産主義と攘夷論とは、あたかも両極端である。しかし見かけがちがふほど本質はちがはないといふ仮定が、あらゆる思想に対してゆるされるときに、もはや人は思想の相対性の世界に住んでゐるのである。そのとき林氏には、さらに辛辣なイロニイがゆるされる。すなわち、氏のかつてのマルクス主義への熱情、その志、その「大義」への挺身こそ、もともと、「青年」のなかの攘夷論と同じ、もつとも古くもつとも暗く、かつ無意識的に革新的であるところの、本質的原初的な「日本人のこころ」であったというイロニイが。
三島によれば、上述の二人の青年の攘夷論が、長州藩の激しい現状打破の精神、急進主義に支えられていたのとちょうど同じように、林のマルクス主義への熱情も、実は本質的原初的な日本人のこころだったのである。
つまり、林において「日本人のこころ」は一貫しているのに対し、彼がマルクス主義から転向した右翼思想は、表面的、相対的なものに過ぎない。この「日本人のこころ」は、後の三島の「文化概念としての天皇」につながっていくだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
