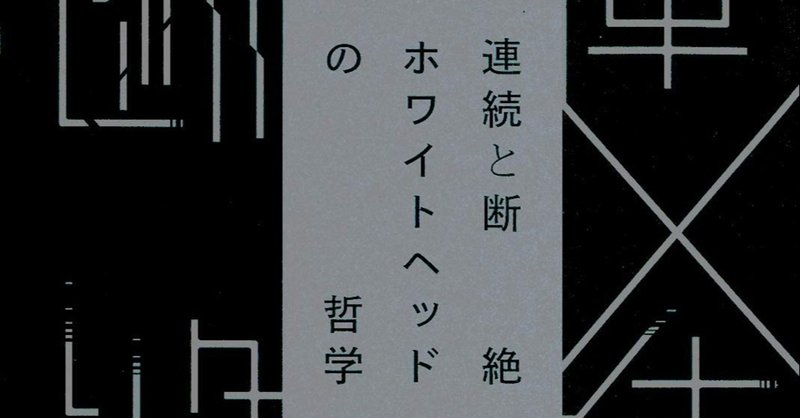
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」について -「仮に断絶する」ということ- (前編)
本テキストは飯盛元章氏の「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(以下「本書」)の書評のようなものである。
00. 「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」について
書評・・・と言っても、僕は他の人のことを客観的に論じるのはあまり得意ではない。
さらに、本書が研究対象としたホワイトヘッドに関しても二次文献を読んだぐらいの知識しかなく、「正確な記述としての書評」ができるかは、正直自信がない。僕個人の感想と熱意として受け取ってもらうのがちょうどよいのかもしれない。
より正確に、深く理解したい方は、ぜひ自身で買って読んでほしい。特に、建築を含むデザイン分野の人に広く読んでもらえると嬉しい。
本題を始める前にもう一点、この本の社会的意義についても少し話したい。
もちろん本書は新型コロナウイルスが蔓延する前に書かれ、発売されたものだ。しかし、主題の一つであり、本文中で丁寧に整理されている「断絶」は、こういう社会状況だからこそ、その意義や使い方を見直さなくてはいけない言葉だ。
「リスクからどのように断絶するか?」
集まるだけが社会じゃないし、つながるだけが倫理じゃない。こういった社会状況の変化を肌身で感じ、僕自身も前回テキストに起こしてみたが、僕だけでなく実際多くの人がそのようなことを思い始めているのではないだろうか。
社会的に根拠ができてしまうと「断絶」の断絶たる魅力、つまり、超越的なものへ思いをはせるワクワク感が色あせてしまう。そうした天邪鬼な気分はありつつも、こういう状況になったからこそ、本書の見え方は変わってくるのではないかと思う。
創造的な無関係のデザイン手法、つまり後述する「仮に断絶する」作法を始めるきっかけを本書は与えてくれると、僕は考えている。
01. 「連続と断絶」について(1) -どこまでも連続的なホワイトヘッドの「有機体の哲学」-
本書はホワイトヘッドの「有機体の哲学」から4種類の「断絶」を見出すことを論旨としている。
有機体の哲学は、ザックリいうと「宇宙に存在するすべての物事は予定調和的に繋がり、連続している」ということを体系化した理論(形而上学)だ。
例えば僕がカップのコーヒーを飲む時、その行為は、「カップ」や「カップに入ったコーヒー」、「僕の身体」といった「カップのコーヒーを飲む」直前に存在する諸々の条件が集められた結果ととらえることができる。また、「カップのコーヒーを飲む」行為は、その直前に見た「窓の外の京都の風景」とも何かしら関係しているとも言えるし、もっと俯瞰的に見れば、「関西地方の天気」「日本の経済状況」「地球の地殻変動」さらには直前に起きた「宇宙のどこかの星の超新星爆発」などなどの宇宙全体の事物とも、多かれ少なかれ、紆余曲折しつつも関係している、と考えることもできる。
そうした物事の関係の無限連鎖を、ホワイトヘッドは「現実的存在」「抱握」「消滅と客体的不滅性」といった概念によって理論体系化(有機体の哲学)している、と本書は述べる。
無数の契機のそれぞれは、そのつど絶えず消滅する。だが他方で消滅した契機は、前節で確認したように客体的不滅性を得て、後続の新たな契機のうちへ客体として入り込むことになる。有機体の哲学において、存続する実体は、無数の契機がこのように関係しながら連なっていく系列として解釈しなおされるのである。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p41
前述のコーヒーの例でいえば、現実的存在(「コーヒーを飲む」行為)は、その直前にあった客体(コーヒーカップ、自分の身体、京都の風景、世界の動向、などなど)を契機として起きる(生成する)が、その瞬間、その現実的存在は消滅し客体となる。そして、次の現実的存在、例えば「コーヒーカップをテーブルに置く」行為の与件となる。
宇宙に存在するすべての物事は、直前の宇宙全体を予見として発生し、発生した瞬間その事物も宇宙の中に組み込まれ、次に発生する物事の与件となる。・・・そうした連鎖が宇宙全体の客体と現実的存在に絶えず起きているとするのが、有機体の哲学であると本書は述べている。そのため有機体の哲学によれば、すべての事物は徹底して連続的な関係によってできており、僕たちが日常的に思い浮かべる実体(カップ、ペン、iPhone、家など)は、実はそういった関係性の束が個物の対象に見えているだけである、としている。
ホワイトヘッドは、このようにあらゆる存在者を徹頭徹尾、関係によって貫かせるために、絶えざる消滅という概念をもちいたのだと言える。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p67
他から自律して無関係なモノなど存在しないとするのが、ホワイトヘッドの有機体の哲学であるということだ。
02. 「連続と断絶」について(2) -相対的な断絶-
このように、筆者によればホワイトヘッドの「有機体の哲学」は徹底して連続的な形而上学だ。
しかし筆者によれば、実はそのような徹底した連続的な関係の中にも避けがたい「断絶」がある。そして、そうした「断絶」を発見し、分類するということが本書の目的となっている。
「断絶」、つまり事物Aと事物Bが無関係であるということは、前章で確認した通り、ホワイトヘッドの「有機体の哲学」に従えば、一見すると存在しないように思われる。そこで筆者は、グレアム・ハーマンとカンタン・メイヤスーという、物事の無関係さや偶然性を肯定的に論じる二人の哲学者を引用し、有機体の哲学に潜む「断絶」を以下の①~④の4つに分類し論じている。
① 共時的断絶
まず筆者は共時的、つまり同じタイミングで存在する物事の場合、物理的距離が限りなく離れていれば、それらは断絶していると考えられると述べている。
第一の断絶は共時的断絶である。第4章の結論にしたがえば、媒介者が介在しえないほど空間的に離れた同時的存在者どうしであれば、限りなく純粋なしかたで因果的独立を維持することが可能だ。ここに強い断絶を見いだすことができる。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p253
実際距離が離れている状態、例えば日本にいる僕とブラジルにいる誰かでは、間接的にたどっていけばギリギリ関係しているとしても、その相互影響は限りなく小さく、ほとんど無関係な状態であると考えることができる。さらには、地球にいる僕たちと、遠くの銀河系にいるまだ見たこともない宇宙人とは、僕とブラジルの人よりもはるかに無関係で「断絶」した状態と考えられるだろう。
② 通時的断絶
①に加えて、事物が存在するタイミングが過去と未来で、とてつもなく時間的に離れていれば、それらは断絶していると考えられるとも述べている。
第5章で考察したとおり、時間的にひじょうに離れたはるか未来において、わたしたちが属すものとはまったく異なった、新たな宇宙時代が到来するとホワイトヘッドは言う。この未来の宇宙時代は、想像力によってでさえもけっして予見することができないほどにまったく異質なあり方をしている。現在のある現実的存在と未来の宇宙時代とのあいだには、強い断絶がある。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p253
西暦2020年に生きる僕たちと、794年に平安京に遷都した桓武天皇とは直接的な関係はないし、もっとさかのぼれば、ジュラ紀の恐竜と僕たちとの間にある関係性はさらに薄い。そうした時間の隔たりが積もり積もれば、遠く遠く離れた2つの時代の間にほとんど無関係な状態、つまり断絶を見いだすことができる。
ここまで、①②の断絶は筆者によれば「地平線のあり方に類比的であると言える(「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p253)」。確かに、①共時的断絶も②通時的断絶も、ある時代のある特定の場所で生きる僕たちから見れば、はるか遠い距離や時間にある物事とは無関係であり、「断絶」と言えるものである。しかし、それはあくまで僕たちの認識の上での話であり、「有機体の哲学」によれば、距離や時間がいくら離れていても、一つ一つ関係性をたどっていけばいつかはすべての物事にたどり着けてしまう。そのため、筆者はこれら2つの断絶を相対的なものとして整理する。
それに対し、筆者は以下の③④を、より絶対的な断絶として、より徹底した物事の無関係さとして論じる。
03. 「連続と断絶」について(3) -絶対的な断絶-
③ 垂直的断絶
上記①も②も特定の場所や時代から見た「断絶」だった。
僕たちはどこまで行っても特定の自然法則に従ったある特殊な宇宙時代を生きている。時間が経つことで次第にその特殊さの内実は変化していくものの、また別の特殊性をもった宇宙時代(別の物理法則が支配する世界かもしれないし、もしかしたら333次元の世界かもしれない)であることは変わらない。
それに対しホワイトヘッドはより一般的な「根底的宇宙」の存在を論じており、その「根底的宇宙」と現在僕たちが生きている宇宙には決定的な「垂直的断絶」があると筆者は述べる。
・・・わたしたちの宇宙時代と根底的社会とのあいだにある垂直的な断絶だ。根底的社会が有する秩序は一般的で必然的である。それゆえに、その秩序は根底的社会があらゆる形態の存在者を含みこむことができるほどの許容力をもったものであるだろう。したがって、特殊で限定された力強い秩序を有するわたしたちの宇宙時代の観点からすれば、根底的社会は混沌としたものに映る。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p231
垂直的な断絶は、絶対的で固定的なものだと言える。(中略)・・・。根底的社会のあり様は、現在の地球上の現実的存在にとっても、数万光年離れた宇宙空間をただよう現実的存在にとっても、138億年後の新たな宇宙時代に生じる現実的存在にとっても、等しく闇である。なんらかの特殊な法則の恩恵にあずかることによって生成する現実的存在にとって、根底的社会の〈特殊性のなさ〉は等しくとらえがたいものとなる。垂直的断絶の線は、どの現実的存在に焦点をあわせるとかは無関係に、つねに等しく存在し続ける線なのである。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p257
上記の①②の断絶に比べると③の「垂直的断絶」は少し想像するのが難しいと思うので、僕なりの例え話で説明してみたいと思う。
僕たちは今、無限に続く森の中にいる。
この森はどうやら様々な種類の木々によってできており、歩くと先ほどいた場所とは全く異なる生態系に変化していく。
しかし、どこまで歩いても森は無限に続くので、「森全体」として一体どのようになっているかを知ることはできず、どこまで歩いても、「自分たちの周りの生態系」のあり方しか理解することはできない。
ドローンを上空まで飛ばしてみても森はどこまでも続いているので、森全体をとらえることはできない・・・。
このたとえ話における「自分たちの周りの生態系」が、今僕たちが生きている宇宙(時代)であり、「森全体」が「根底的社会」に該当すると思ってもらうのが良いと思う。
根底的社会は「有機体の哲学」の関係性全体(過去未来含めて)なので、どこまで行っても僕たちはその全体をとらえることはできず、そのような等しくとらえきれない状況を筆者は「闇」と呼んでいる。
④ 「実在の深み」による断絶
しかし筆者は③の断絶よりもさらに絶対的な断絶が存在すると述べる。
確かに③垂直的断絶は、たどり着くことができないほどに一般的な全体と僕たちの今いる世界との断絶ではあるが、それは逆を言えば、有機体の哲学の体系内であるという意味で、全く関係性がないというわけではない。「森全体」をとらえることができなくても、現に僕たちは森の中を歩いているという意味で、「森全体」の一部として、関係性があると言える。
それに対して、④の「実在の深み」による断絶は最も決定的だ。それは身も蓋もない、「有機体の哲学」自体がひっくり返る可能性がある、という断絶だ。
「思弁哲学は「作業仮説」(working hypothesis)の方法を体現している」(『観念の冒険 p222』)とホワイトヘッドは言う。つまり、思弁哲学という方法論にしたがって構築された形而上学的体系は、あくまでも仮説にすぎないのである。それは仮説であって、最終的に完成された理論ではない。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p258
ホワイトヘッドは、さまざまな形而上学的範疇から成り立つ整合的な体系を構築した。だがそれを、絶対的に確実なものとして提示したのではない。諸事情の本性は、わたしたちの合理的な探求を超えた、さらなる深みを隠しもっている。(中略)・・・。この諸事情の深みからの要求が、いつ、どのようなものとして噴出し、体系に対してどれほど深刻な影響をもたらすのかは、まったくの未知である。ここに第四の断絶を見いだすことができる。それは、体系構築の方法論である思弁哲学が示唆する実在の深みと、有機体の哲学という体系とのあいだにある断絶である。
「連続と断絶 ホワイトヘッドの哲学」(著:飯盛元章)p260
「有機体の哲学」は古今東西の宇宙全体を記述しようと試みた形而上学的体系であり、実際にものすごい完成度で成り立っているらしい。しかし、この体系が「作業仮説」としての形而上学である以上、突然この体系をひっくり返すような事態が発生することを絶対に否定することはできない。
否定できないということは、もしかしたらこの瞬間の次にでもドカーンと宇宙がひっくり返って、全く別の何かになる可能性がある。先ほどの森の例でいえば、突然隕石が降ってきてどこまでも続く焼け野原になるようなものだが、筆者は、この「有機体の哲学」自体がひっくり返る要因を「実在の深み」とし、これ以上ない決定的な断絶として論じている。
メイヤスーの読者であれば、事実性と偶然性の話と言えば一発で理解できる話だと思う。
(実際、筆者もメイヤスーの論を引用しながら④の断絶を論じている。)
04. 「連続と断絶」の後で -0番目の「断絶」の追加-
ここまでまとめた通り、本書で論じられている「断絶」には4つの種類がある。そしてそれらの断絶は、論じる範囲がマクロなものになっていくにつれより決定的な「断絶」となり、最終的には形而上学的体系の枠組みをも飛び越えた「実在の深み」の断絶に至る。
ところで、本書に関連してトークイベント(入不二基義 飯盛元章 対談)が行われており、そこで入不二氏はこの4つの「断絶」に加えて、現実的存在が生成するその瞬間の最もミクロかつ決定的な「断絶」を提起している。
これを仮に「⓪生成の断絶」とし、⓪~④の5つの「断絶」を物事のスケール順に並べると以下のようになる。
[ミクロ]
⓪生成の断絶 :(超?)絶対的
①共時的断絶 :相対的
②通時的断絶 :相対的
③垂直的断絶 :絶対的
[マクロ]
④「実在の深み」の断絶:(超?)絶対的
上のトークイベントでも議論にあがっていたが、相対的断絶と絶対的断絶はそれぞれ「認識論的断絶」と「存在論的断絶」と整理することもできる。つまり、僕たちの視点から見て(つまり認識論的)無関係と思われるような物事は①や②の相対的断絶に分類されるが、それは実際関係性をたどっていくと遠くのどこかでつながっている可能性がある(存在論的には断絶していない)。しかし、⓪および③④の断絶は関係性をいくらたどっていってもたどり着くことがあり得ないほどの断絶(存在論的断絶)であり、⓪④に至っては、連続的な関係性(「有機体の哲学」)を前提としない、そもそも根源的な「断絶」ということだ。
ここでいう認識論的と存在論的の違いを説明するには、龍安寺の石庭が分かりやすいと思う。龍安寺の石庭の石はどの場所から見てもすべての石が見えることはなく、どれかが必ず陰に隠れてしまう(認識論的)。しかし、石は現に庭にすべて存在している(存在論的)。
05. きめ細やかな「断絶」概念の整理
本書の面白さはこのきめ細やかな「断絶」概念の整理にあると僕は思う。
本書で取り上げているハーマンもメイヤスーも、自身の哲学で提示する「断絶」は一種類のみであり、両者とも自身の「断絶」をある種の絶対的なものとして語る。一方、そのおもむきは全く異なる。ハーマンにおいては、宇宙全体どこにでも素朴に存在するすべての対象が他から退隠=「断絶」していると説き、メイヤスーは世界の法則が突然ひっくり返って別の、前の世界からは完全に「断絶」した世界になる可能性を説く(事実性、偶然性)。
ところで、建築デザインにおいては、特にハーマンがアメリカを中心に頻繁に取り上げられてきた。
これは、ハーマンの哲学(オブジェクト指向存在論)が実体を認めるものであり、素朴に存在する対象を論の中核においているため、実体、対象を前提として業務を行う建築家の世界観とマッチしやすかったからなのでは、と僕は考えている。
一方、ハーマンの「断絶」である「実在的対象の退隠」は、実体という馴染みやすいフックを持つ反面かなり超越論的で崇高なものだった。そのためハーマンの「実在的対象」を引用することで、オブジェクト指向存在論は「素朴かつウィアードな対象が崇高さを持ちうる」という建築論にすり替わったように思う。
ここで「連続と断絶」を通して見えてくるのは、実は多種多様に存在するはずの「断絶」概念の混同援用という問題だ。
連続的な相関主義のカウンターパンチとして出現した21世紀の各実在論は、「断絶」の概念を語りつつも、相関主義へのカウンターパンチであるがゆえに、それぞれが語る「断絶」同士の違いや「相対的 / 絶対的」「認識論的 / 存在論的」の峻別を積極的には行ってこなかったように見える。連続的な世界に対して
「いやいや絶対的かつ根源的な「断絶」が現にあるんですよ・・・!」
と言えることこそに価値があったからだ。
その結果、受容する側の人間は、絶対的かつ崇高な「断絶」を都合よく利用できる窓口として、ハーマンやメイヤスーの実在論を利用してしまったのではないだろうか。
一方本書で語られている4つ(+1)「断絶」は、ハーマンやメイヤスーの断絶を横断的に分類し、「連続」との折り合いの中でそれぞれを区別する枠組みを与えてくれる。メイヤスーは、繰り返しになるが④に近いと言えるだろう。ハーマンに関しては、自分の知識の範囲内で明言することは難しいが、⓪親戚のようなものだと、僕は暫定的に理解している。
いずれにせよ、「断絶」と一言で言ってもそこには、少なくとも筆者が提示した4段階(+1)の決定的な区別がある。そして「連続と断絶」は、僕たちが言及し実践する「断絶」がどのようなものかを理性的に教えてくれる、ガイドラインとして機能する。
そうすると、「連続と断絶」を通してきめ細やかに分類された「断絶」を受容する側の僕たちは、どのように「断絶」を考え、実践していけばいいのだろうか。
何かを創作する、デザインする分野にとって⓪や③、④の「断絶」は超越論的すぎるので、直接的な利用と実践は不可能だと、僕は考えている。それらの分野の作為はどこまで行っても相対的であり、絶対的かつ超越的な「断絶」のフリをしても結局どこかで連続しているのがオチだろう。
しかし一方で、現に僕たちは何かしらの「断絶」を、勝手に「連続」してしまう社会の中で考えなくてはいけない局面に立たされている。
おそらくここで考えるべきは、相対的な断絶として「仮に断絶する」ということの作法であり、その創造的なバリエーションなのではないかと思う。ハーマンと建築の例に限らず、本流ではないものの、民主主義的な「連続」のイデオロギーに反発するかのように「断絶」や「無関係」を志向する創作は一定数存在してきた。それらには「連続と断絶」ほどの「断絶」概念の峻別が存在しないと想像できるが、「断絶」を実践し、現実の中で試された先行事例として、考察する価値は十分にある。
おそらく、それらの作品を制作した作家の思惑以上に、それら先行事例は、多種多様な「相対的断絶」の様相と「仮に断絶する」作法を与えてくれるはずだ。
(後編へ続く予定)
[お仕事の依頼や相談は下記連絡先まで]
nishikura.minory@gmail.com
MACAP代表 西倉美祝
ウェブサイト : https://www.macap.net/
インスタグラム: https://www.instagram.com/minoryarts/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
