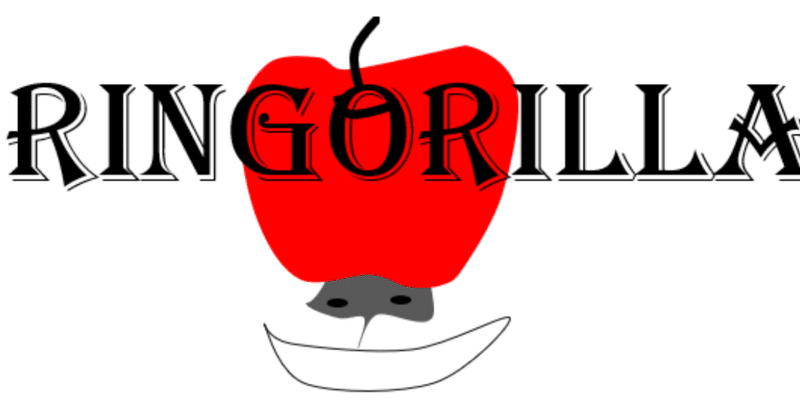
リンゴリラ #8(最終回)
月島神社前
覆い茂った杜の手前に、片脚の男が立っている。
季節外れの黒いロングコート。
だが、薄闇の中では、違和感はあまりない。
ウォンの生首は、今はコートの下に隠されて見えない。奇妙なことに、パンツは何の手がかりもなしに月島神社にたどり着いた。まるで、ウォンみたいだ。ウォンは、犬並みの嗅覚を持っていた。パンツは、半ばその能力に呆れ返りながら、その恩恵を蒙ってきた。
ウォンはいつでも、その嗅覚でターゲットを追い詰めた。その変質的な追及ぶりは、まったくもって恐るべきものだった。
パンツは、ウォンの生首のある辺りを見やる。生首の結合によってウォンの嗅覚が自分に乗り移ったというようなことが考えられるのだろうか?
パンツは先ほどの恍惚の夢を思い出す。
なぜ自分が、中国の娘と妄想のなかで交わらねばならなかったのか。その理由が分からなかった。だが、確かなものもある。胸の奥底から湧き上がるマグマ。
「俺の息子」
あるときルーベンスは、パンツにそう呼びかけた。パンツはその言葉に表情ひとつ変えなかった。ルーベンスがパンツの仕事ぶりに対して信頼を表現したに過ぎないことがわかっていたからだ。
だが、その言葉の響きに、心のある一部で反応していなかったとしたら嘘になる。パンツがそれまでガムシャラにルーベンスの下で働いてきたのは、その言葉を勝ち取るためかもしれなかった。
人を一人殺すたびに、「俺の息子」という言葉が脳裏を掠めた。
そして、第二豊洲アパートメントの炎上で、その言葉は一塊のマグマに変わったのだ。
だから、シュウウウウウウウっという空を切り裂くエンジン音は、パンツの耳にはあまり聞こえていなかった。
目の前に広がる杜があっという間にオレンジに燃え上がったとき、パンツは自分が眼力で杜を一つ燃やしたのだと錯覚してしまったほどだ。そんなことは、今の自分には造作もないことのように思われた。
パンツは炎の杜の中に飛び込んだ。片脚の男が駆け抜けるには、いささか炎は強すぎたが、己の胸のなかの炎に怯える者はいない。
まだ、月島神社前
まるで飛んで火に入る案山子だな──。
庵月は、片脚だけの黒マントの男がケンケン跳びで炎上する鎮守の杜に飛び込んでいく様子を背後から眺めながら、そう思った。
いくら変わり果てていても、それが月島アークホテルで庵月を迎え入れた二人の男の片方であることはすぐに分かる。あの強烈なスキンヘッドの男だ。ほんの数時間の間に、スキンヘッドにもそれなりのことが起こったのだ。数時間後の劇的な変化。ビフォーアフター。世界はこの繰り返しだ。
庵月は考える。
この炎の先に、ルーベンスはいる。
果たして、この炎を越えてまでルーベンスやあの案山子男の顛末を知る必要があるだろうか?
庵月は回れ右をして、次の依頼人のために体力を温存するべきかもしれなかった。どうせ眠れないにせよ、漫画喫茶のマッサージチェアに横たわってウォークマンで「リベル・タンゴ」を聴くくらいのことはするべきなのではないか。
だが、庵月の体はここから動く気がないらしい。
炎の魔力なのか、その先の何かのせいなのか。
いずれにせよ、そんなわけで庵月は自分の首の左右に冷たい刃物が当てられていることにしばらくの間気づかなかった。
「そこからじゃよく見えない」
タクシーの運転手の声だった。
「特等席に案内しよう、庵月ユウジ」
庵月は諦めて目を閉じた。ずいぶん有名人になったものだ。
ふたたび、月島神社
ルーベンスは周囲を見回した。
まだ近くに、中国人の男の首をへし折った奴が潜んでいるはずだった。少なくとも、匂いはちゃんと残っている。
「カホリ、オレから正体を隠す必要はないだろう」
返事はなかった。
「お前がオレの味方でもないってことは最初から分かっていたさ。お前はあのアホ小説家からリンゴを奪う機会を狙っていただけだ。違うか?」
火の海は答えない。
だが、やがて一発の弾丸がそれに答える。
弾丸はルーベンスの肩を掠める。
ルーベンスは、中国男の死体からセミオートマチックピストルを奪い取り、目をつぶったまま肩から後方に向かって撃った。
引き金を引いた瞬間、骨折している掌に燃え上がるような痛みが走る。
だが、それなりの成果はあったはずだ。
弾丸の飛んできた方角は右斜め後方、それも下方から発射されている。ルーベンスは自分の肩を掠めた弾丸のベクトルを、スローモーションでも眺めるみたいに的確に把捉する。経験則だ。
「お前のバックにいるのはアメ公か?」
リンゴを奪えと言ってきたのは、国家だった。彼らは、ルーベンスにカホリを提供した。カホリと連絡を取り合い、一カ月の間にリンゴを手に入れる。そのためにカホリは事前に中国マフィアに潜入する、と聞かされていた。だが、実際にカホリから連絡が来たのは、今夜を除けばたったの一回だった。「隠れ家を用意してほしい」用件はその一言だけだった。プラトニ・カルキが死んだ辺りから、国家は姿勢を変えた。
──リンゴの問題からは我々は手を引く。
お前も手を引け、と暗黙のうちに言ったのか、お前は国家ではないから自由に動けと言いたかったのかは分からないが、とにかくルーベンスとしては今さら手を引く理由もなかった。
そして、今夜カホリから再び連絡が来た。
──リンゴを手に入れた。ホテルに迎えに来てほしい。場所は……。
事前にリンゴの問題から手を引くと国家から連絡が入った以上、カホリが国家の差し金で動いているわけでないことは明白だった。カホリは単体で動いているか、あるいはアメ公やその他の外国集団とつながっている可能性も否定しきれなかった。だから、この神社でカホリが自分の命を狙ってくることは想像できた。ルーベンスはその事実を恐れはしなかった。あっちが狙っているなら、こっちはそれより早く仕留めるだけだ。狩人とはつねに先んじる者なのだ。
「違ったか、アメ公はお前のバックじゃなく、国家のバックにいるんだったな。すると、お前はピン芸人か。リンゴでタルトを作る気か? オレはタルトが大の好物なんだ。タルトを知った十歳の夏に、オレは三本の永久歯を虫歯にしてしまった。そのことについては、まったく歯に申し訳ないと思う。でも、それでもタルトはやめられない。だから、お前の気持ちは分かるよ」
返事はない。銃撃による返事も、ない。
やはりさっきのルーベンスの銃弾が命中しているのだろう。
「だが、世の中には手を出しちゃマズいリンゴだってある」
炎が枝を焦がし尽くす音の隙間、微かに吐息が聞こえる。
「……痛いか、カホリ。それが戦争だ。どんなオッパイだってゴミ屑に変えられる最終手段だ。お前が俺をけしかけた。そして俺があんたのオッパイに弾丸をめり込ませた。俺からの愛の接吻だと思って……」
言いかけたルーベンスの口が止まる。
言葉が消えた。
目の前に現れた影のいびつさゆえに。
金属の塊のようだった。
頭蓋骨が部分的に覗いた顔。ぼろぼろの黒マント。
破れた左足の部分から覗いている、逆さの生首。
「お帰り、坊主」
金属の塊は、人間ではない奇声を上げ、ルーベンスに拳銃を向けた。
ルーベンスは微笑んで両手を上げた。
だが、塊は叫ぶばかりで発射しない。
塊は、矯正中の歯を悲しげに開き、目に涙を溜めていた。
ルーベンスは手を上げた状態で、その脳天を撃ち抜く。
塊はドサリと後方に倒れた。
近くに寄る。確かにパンツだ。なぜ失われた片足の代わりにウォンの生首をくくりつけているのか理由は分からなかったが、とにかくその表情は、十五年前にルーベンスが拾い上げ、育て上げた少年の顔だった。
ルーベンスはその塊を抱き上げ、泣いた。
犬の死体を抱く夢のことは、まったく思い出さなかった。
ただ、体の中から泉のように湧き出る涙だけは、ルーベンスにはどうすることもできなかった。奇妙なことに、失われた左目からさえも涙は溢れていた。
したがって、ルーベンスの右目の視界は曇り、パンツの左足に縫い付けられたウォンの目がぎょろりと動いたことは全く気づけなかった。
ルーベンスは、ただ撃ち抜かれたパンツの額を撫でていた。
自分のこめかみに銃口がつきつけられたとき、ルーベンスには何が起こったのかまったく分からなかった。
そして、次の瞬間にはルーベンスの顔面は失敗したスイカ割りのスイカのように目茶目茶に粉砕された。そして、その直後、ルーベンスの左目に埋め込まれた義眼の焼夷弾が爆破した。
ルーベンスの腕に抱かれていた塊のうち、パンツの首から上が吹き飛び、頭の数は二つから一つに再び戻った。ウォンの首だけになった塊は、パンツの右腕に握られた拳銃を仕舞いこむと、両手を使って身を起こし立ち上がった。
そして、再びケンケン跳びで炎の中に消えていった。
そして、月島アークホテル
室内はほんのりと明るさを増しつつある空の青さと、燃え上がる杜のオレンジ色とが混ざった複雑な色に染まっている。
庵月は窓際にいて、ルーベンスの死の瞬間を見つめていた。
「お前はどうしてここにいる?」
「あんたが連れてきた」
庵月は背後を見ないで答える。
相手はその返事を聞いていないのか、再び尋ねる。
「お前はどうしてここにいる?」
「掃除屋と間違われた」
そして、三たび。
「お前はどうしてここにいる?」
「何と答えれば満足する?」
相手は沈黙を保つ。庵月は少し迷ってから答える。
「依頼人を安らかに眠らせるためだ」
四たび。
「お前はどうしてここにいる?」
「…言っておくが、俺はリンゴのことは何も知らない」
「お前はどうしてここにいる?」
庵月は口を閉ざす。相手の真意が見えない。
まだ庵月は、相手の姿を見ていない。彼が何者で、これから何をしようとしているのか、庵月には何の知識もない。分かっているのは、いま首を挟んでいるハサミが、いつ庵月の首と体を分断してもおかしくはないということだけだ。
「お前はどうしてここにいる?」
「……」
首にずっと突きつけられていたハサミが、ふいに退く。
「こっちを向け」
振り返る。相手はソファに座っている。
「お前はラッパを捨てて寝かせ屋になった。なぜだ?」
庵月はしばらくじっと男の顔を見つめる。
「音楽を聴かせる必要がなくなった」
「誰に?」
外の色が微妙に変化していく。それに応じて、室内の色も変化する。それまで判然としなかった男の顔が、徐々に見えてくる。
「母さんだ。俺と、あんたの」
あの頃と同じ、大きな目。庵月と同じ目だ。
双子の兄、ユウイチがそこにいる。
「死んだからか」
「殺す必要はなかった」
「あった。お前には分からない理由が。下手くそな殺し屋のせいで死に損なった。死に損ないは死より惨めだ」
何者かによって人工呼吸器が外され、瀕死の重態となった母親。死を覚悟してください、と医師は確かに言った。だが、まだ呼吸は完全に止まったわけではなかった。
とどめを刺したのは、兄、ユウイチだった。
「天命に任せるべきだった」
「オレが天命を全うした」
「今さらどうでもいい」
「いまお前が見たのは、その殺し屋の雇い主の最後だ」
庵月は黙った。
「兄貴は死の番人になったわけだ」
「お前は眠りの番人になった。そしてお前はお前の正しさを主張する」
兄は伸縮高枝バサミをくるくると弄ぶ。
弟には武器はない。
「お前が首だけになっても、正しさを主張できるのか試す」
「俺はあんたに正しさなんか訴えない。無駄だからだ」
「首だけのお前から同じ結論を聞く」
「首だけの俺に結論はない。結論を出すのは兄貴だ」
兄は笑う。弟はおどけて首をすくめて見せる。
「祈ってみろ、お前の幸運を」
兄はハサミを弟の首につきつける。
弟は口笛を吹く。
その口笛は途中で途絶える。
月島アークホテル・エレベータ
ウォンは、エレベータを待っている。血管の浮き出た顔が、左足の付け根から階数表示ランプが19まで上がってくるのを睨んでいる。
ウォンは、十九階にいる。
リャンリャンを連れて中国へ帰るためだ。だが、計画はうまく行かなかった。リャンリャンはもうどこにもいなかった。誰かが持ち去ったのだ。
エレベータが開く。
ウォンはケンケン跳びで乗り込み、一階のボタンを押す。
これからリャンリャンを探さなくてはならない。だが、日が明るくなってくると、表立った行動は難しい。
二階で、大男が乗ってくる。
掃除屋だ。
「掃除は終わったのか」
「ああ、ようやく」
「俺はこれからだ。恋人を中国に連れ帰る」
大男はウォンを見返す。
大男が何かを言う。何と言ったのか、はっきりとは聞き取れない。
ウォンは目を閉じる。眠くて仕方がない。
ずっと眠っていない。
「お前はいま、リャンリャンを抱いている」
「俺はいまリャンリャンを抱いている」
「お前はリャンリャンと中国へ帰る」
「俺はリャンリャンと中国へ帰る」
「祈ってみろ、お前たちの幸運を」
ウォンはエレベータを降りる。
ウォンはホテルを出る。
ウォンは中国を目指す。しっかりと腕のなかにリャンリャンを抱きしめている。リャンリャンは白く長い腕をウォンに回している。
「雲南まであと少しだ」
月島ステーション
月島駅のホームは、まだ眠い目をこすっている。
その上の隅田川では、無数の魚たちが獲物を探す旅をしている。
ベンチには、男女が背中を向けて腰掛けている。
男は、両方の手をポケットに入れ、巨体をゆらゆらさせている。
女は、黒いスエット、短いソバージュ。
ホームの床には一筋の血。
女の腹部から流れ落ちる一滴一滴が、カオスの流れを作る。
「血の匂いだ」
眠っているようなはっきりしない声で男が呟く。
「鼻がいいのね」
かすれた声で女は答える。
「飼い犬に似たらしい」
「……犬を飼ってるの?」
「フェラリアにかかって死んだ。もう十五年以上前だ」
「飼い犬の名前は?」
「ルーベンスだ」
女は笑う。男も眠ったまま笑う。
「上り電車はあと五分でくるわ」
「お前はあと五分くらいで死ぬ」
「らしいわね」
女はふふっとかすれた笑みをこぼし、それが咳に変わる。
女は床に血の唾を吐く。
「ねえ。あの日、動物園に来なかったこと、後悔してる?」
「俺は行った。あんたを見てた。ずっと見てた」
「声をかけるべきだったわ」
男は答えない。
女はまた咳をし、血痰を吐き出した。
「ウィー・マスト・ゴー・トゥー・ザ・ズー・ネクスト・サンデー」
「来週の日曜には、あんたは骨だ」
「でも代わりに、ここが動物園よ」
「……」
ホームを複数のサルとリスが駆け抜ける。
ヤギの群れが階段をゆっくりと下ってくる。
そして、象はエレベータから降りようとして、ドアに挟まれて苦しんでいる。
「我ながら、いい演出だと思うけど」
風が吹く。
空気が圧迫される。
電車がやってくる。上りの電車だ。
男が立ち上がる。
「結局、今夜は眠れなかったわ」
「あんたには死のほうが似合ってる」
女は笑う。
「さよなら、庵月ユウジ」
その言葉を聞くか聞かないかのうちに、庵月ユウイチは電車に乗ろうと踏み切りに近寄る。
目は閉じられたまま。
だが、まだ電車はホームに入ってきてはいない。
落下。
そして電車が入ってくる。興奮するサルの叫び声。
ヤギの群れが小競り合いを始める。
彼らが頼りにしてきたのは、女のつけている香水の匂いだ。アニマリック。この香水の主こそが、彼らを檻から解放した自由の女神。彼らはその救世主を求めてさまよい、深い地下にまでたどり着いた。
けたたましいブレーキ。だが、その音が間に合ったことは、あるのだろうか?
ベンチに置き去られた長い棒がコロンと落ちる。
伸縮高枝バサミ。
その主が、初恋の少女と弟が音楽室で話す光景を回想しながら肉片となった頃、ベンチの反対側では、女がぐったりと静かに息絶えた。
まだ駅員は彼女を発見していない。それまで、彼女は俯いた格好で待っている。夢を見ているような顔で。
そして、月島ステーション
案山子はケンケン跳びで去った。
庵月ユウジは、それを見送った後、ゆっくり月島駅へと向かった。
兄がどこへ消えたにせよ、もう自分の前に現れることはない。それが、庵月のかけた唯一の催眠暗示だ。その暗示は、十五年前に仕組んでおいたものだった。兄にとっても、当然思い入れの深い「うずくまる女」の口笛。それを吹いたときが、兄弟の本当の別れのときだ。そういう暗示だ。
すべては終わったのだ。
兄の復讐も、自分の復讐も。
死んだ依頼人の寝かせ方は、むずかしい。だが、どうにかなった。
また依頼がひとつ終わった。
終わりは始まりだ。今夜はまた次の依頼人のところへ向かう。
一昨夜もべつの依頼人がいた。依頼人は、プラトニ・カルキ。
内容はいつもと変わらない。不眠の解消。だが、依頼を遂行したとき、庵月はかつてない憂鬱に襲われた。
理由は分かっている。眠らせるために、プラトニ・カルキの内側に入る必要があった。
──もう「うずくまる女」は弾かないのかね?
プラトニ・カルキは、催眠を受けるためにベッドに仰向けになりながらそう尋ねた。
庵月はプラトニ・カルキへの殺意をやり過ごした。
──深い眠りが欲しい。もう何も後悔しないほど、深い眠りが。
つい先日、ジョージ・オーウェルの変奏曲ともいうべき『動物O嬢』を出版し、ベストセラーの記録を大幅に塗り替えた男とは思えない憔悴ぶりだ。
庵月は、依頼にしたがって、深い眠りを与えた。
──私の愛が、君のお母さんに死を……
それが、眠りに落ちる前にプラトニ・カルキが口にした最後の言葉だった。眠りに落ちた後、彼がどうなったのかは庵月は知らない。
過ぎ去ったことは、絵画に接するように。
庵月はプラトニ・カルキの言葉の意味について考えるのをやめた。
月島駅の前には救急車が止まっていた。庵月は地下鉄の階段を降り、改札を電子通貨で通る。
さらに階段を下り、ホームへ。
月島駅の階段は狭く、つねに強風が吹いている。
だが、それもホームに着けば落ち着く。湿気。川の匂い。
一台の担架が、庵月の横を通り過ぎていく。白い布で覆われた担架から白い腕が、たらんと垂れているのが、目に留まる。そして、あの女の匂い……。
電車が人身事故で止まったらしい。復旧作業が行われている最中だ。庵月はベンチに腰掛ける。
三つ並んだ椅子のうち、左端の椅子の上にバッグがある。見覚えのあるバッグだ。
「アニマリック」
あの女が持っていたバッグだ。
庵月は、先ほどの担架からはみ出た白い腕を思い出す。
リンゴ。恐らく、バックの中にはリンゴが入っているのだろう。
庵月はそのバッグを手にとると、ゴミ箱に捨てる。捨ててしまってから、一瞬だけプラトニ・カルキのマンションですれ違った女のことを思い出す。その女が持っていたバッグのことを。
あの大きなサングラスの下に隠された素顔が、アニマリックの女と同一でなかったとは言い切れない。
リャンリャンが庵月を呼び出したのも、あの女の指示だろう。あの女は、何としても庵月を巻き込みたかったのだ。
何のために? リンゴを渡すためか?
隅田川では魚たちが次の月を目指す。
リバーサイドでは、まだ誰かがリンゴを探している。
だが、リンゴは、隅田川のさらに下にあるゴミ箱の中だ。
庵月は一つあくびをする。まあいい。女への疑問は、いつだって尽きるものではない。
時刻は五時五十五分。
いい子たちが、元気に動き始める時間だ。
どこかのファミレスでフレンチトーストとコーヒーをとろう。
庵月は目をつぶる。眠れるわけではない。ただ、目を休めるために。そして頭のなかでトランペットを手にする。
演目は「うずくまる女」。
お前がクソ何者なのかは、自分の血に問えばいい。これまで何を選び、何を捨てたのか。
演奏は、これまでで最低であり、最上の出来だった。
庵月は目を開く。
復旧作業は長引いている。誰かが朝から面倒なことをしたせいだ。さらに、駅員たちはエレベータから象を救い出す作業や、逃げ回るサルたちの確保にと各々忙しい。
東京湾の船から逃げた動物たちは、ここにたどり着いた。
逃がしたのは誰か?
──眠れないの。
眠るために動物でも数えようとしたのかもしれない。だが、最後までキリンは船から出られなかっただろう。
庵月は、キリンだけが東京湾から船出するところを想像してみた。
キリンには愉快な孤独が似合う。あらゆる動物たちが脱走したあとで、ゆっくりと首を折り曲げながら外に出たかもしれない。
庵月はいま、幼少の頃訪れた動物園にいた。
母は後方でプラトニ・カルキと話をしている。
庵月と兄は、二人でキリンの檻の前に張り付いている。
その風景に意味はない。だが、意味もなく輝いている。
庵月はつかの間、まどろんだ。失われたものは、まぶたの裏に、まだ月のように燦然と輝いていた。
END
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
