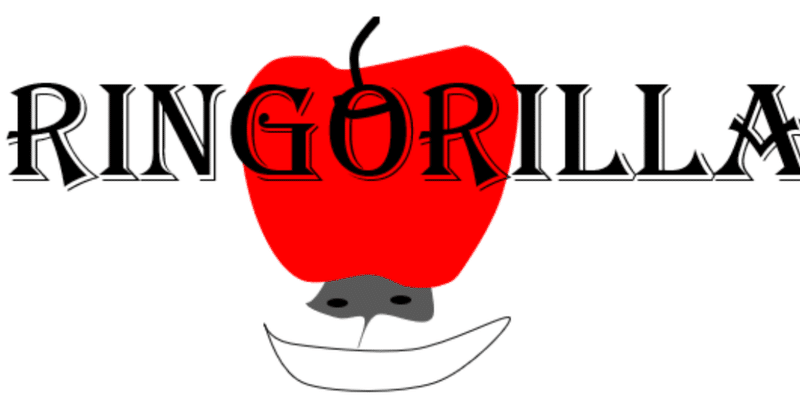
リンゴリラ #1
月島アークホテル
月島アークホテルのフロントにその男たちが現れたとき、ホテルのフロントマンはテレビの通販番組を見ていた。マッチョな男がトレーニング用品の良さを語り、司会者がそれに大げさな相槌を打った。「気になるお値段は」のところでフロントマンはデスクに組んでいた脚を下ろし、身を乗り出した。だが、彼がその値段を知ることはなかった。代わりに、フロントマンの脳みそはそこら中に吹っ飛び、目は天井の辺りをぼんやりと見つめる羽目になった。回転椅子のフロントマンはしばらく地球とは反対の方向にだらしなく回った。腕時計は十二時十五分。良い子は寝るが、悪いヤツはまだまだ目覚めたばかりの時間だ。
一九〇四号室の客は、クッションにしっかりと女の顔を押し当てていた。女は苦しそうにもがきながらじたばたと自慢の尻をくねらせた。
「おい、何が小さいのかもう一回言ってみやがれ」
女は言いたくてもクッションに顔を押さえつけられてものが言えなかった。本当は、お前のアレが小さすぎたんだよと女は言いたかったのだが。
女は中国人だ。だが、日本語はうまい。もっとも、あまりきれいな言葉は知らない。日本語を教えた人間に問題がある。
男の手がふいに緩んだ。男は急に静かな声の調子で言った。
「いま何か音が聞こえなかったか?」
女はその瞬間、男の股間を利き手で強く握りしめた。男の絶叫が室内にこだまする。女はそこでようやく顔を上げ、室内を見回した。いい部屋だった。こんな小さなモノをぶらさげた紳士にはもったいない。窓際に配されたキングサイズのベッドからは隅田川の夜景が望めた。勝鬨橋がかかり、その向こうにはネオンの光が揺らめいている。女はあまりに長く叫び続ける男の頭をベッド脇の照明でたたきつけて黙らせ、枕元に置かれた男の財布から一万円札を九枚抜き取った。
それから、ふと男の言っていた言葉を思い出した。女には物音は聞こえなかった。クッションに顔を押し付けられ、頭が真っ白になっていたせいだ。あんな目に遭うことは珍しいことではない。この辺は大手デベロッパー隅島グループの巣窟であり、彼らは金をもっている代わりに大抵暴力性を内側に溜め込んでいる。土建屋、広告屋に無理難題をつきつけて楽しんでいる彼らは、夜の楽しみでも同様に無理難題を吹っかけて楽しんでいるのだろう。
とにかく、女はそんなわけで男が聞いたらしい物音を聞き逃した。
だが、すぐにやわらかいカーペットの通路をひた走る二つの足音を聞き取る。いくつもの部屋を同時にノックして回っている。何か特定のターゲットを血眼になって探している。恐らくそのターゲットを生かしておく気はないだろう。女の元締めの爪楊枝がそうだ。獲物は絶対に逃がさないし、生かしておくこともない。だが、それは死を意味するのではない。ターゲットに待っているのは、死よりももっとひどい世界だ。
女は倒れている男にシーツを被せ、自分も隣に横たわってじっとしていた。ほどなく気短に二回、ドアがノックされる。
「今行くってば!」
女は怒鳴ってベッドから降りる。ドアの向こう側にいるのがどんな面倒な奴らでも、とにかくうまくやり過ごそう。そして九万円をもってこの場から一刻も早く立ち去るのだ。長居は無用だ。
女はドアを開いた。
ほとんど同時に女の眉間に穴が開いた。
ひとりの男が部屋の中に入ると、ベッドに転がった男を発見する。丁寧に脳を撃ち抜いてから、男は部屋のあらゆる空間を探し回った。クロゼットを、シャワールームを、換気口を。その目は鼠一匹逃すまいとしていたし、鼠一匹逃れられないに違いなかった。男はさんざん探し回った後で、ドアの前に戻ってきて改めて女の顔を確認した。そこでふとしゃがみこんだ。
廊下に立っていたもう一人の男が言った。
「どうした」
いや、としゃがみこんだ男は短く答えた。
「幼馴染に似ている。別人かもしれんが」
「雲南の二人が月島で再会か? 面白いな」
「──たぶん人違いだろう」
男は立ち上がると、次の部屋のドアをノックした。
一九〇五号室では全身に脂汗をかいた太った男が、ドアと向かい合うようにして椅子に座っていた。男の体にはロープが巻かれ、そのロープは膨れ上がった体脂肪をぎゅうぎゅうに締め付けている。
ドアがノックされた。
だが、ロープで巻かれた男は出たくても出ることができない。
「いま手が離せないんだ」
面白いジョークだと男は思った。だが、ノックの主はその手のジョークは意に介さないらしい。その様子は先ほどから聞こえる不穏な音から察しはついていた。どんな事情であれ、ドアを開けないということは彼らの不快感を煽ることになるだろう。でも仕方ないじゃないか。これはお前たちとロープとで解決すべき問題なんだ、俺じゃない、と男は思う。もちろん、こんな子供じみた言い訳が通じる相手ではない。だが、男は金持ちの一人っ子で、自分が子供じみているかどうかを客観的に判断する機会を持たないまま大人になった。ゆえに、それは彼のなかではじゅうぶん有効な理論だった。
「もし急いでるならこのロープをだな……」
言いかけたところでドアノブが彼の股間のところまで飛ばされてきた。「ドアノブを股間に抱く男」という名の静物画があったら、そのモデルは自分だ、と男は思った。
ドアが開いた。
サングラスをかけた男が拳銃を持って入ってきた。男はミートロール状態になった男をみて、拳銃を下ろした。男の背はひょろ長く、それ自体、夕闇に伸びた人影のようだった。
「隅島サン、こんなとこで何を?」
「隅島」と呼ばれた太った男は、このサングラス男に見覚えがなかった。だが、自分が有名人であることは理解していた。少なくとも、この界隈で自分を知らない人間はモグリだ。
「そう、まさにそれだ。まず、女だ。あの女が…」
そのとき、別の男が部屋に入ってきた。今度の男は隅島も知っていた。男の名はパンツ。スキンヘッドに眉毛なし、歯は矯正中だった。だが、不動産屋にとってはわずらわしい石の下の虫を排除してくれるありがたい存在。
「リンゴをどこへやった?」
「リンゴ……?」
「旦那、あんたは我々に仕事をくれる大事な人間だ。だがね、世の中には食べちゃいけないリンゴがある。食べちゃいけないリンゴを食べたアダムとイブはその昔どうなったか知ってるか? 丸裸にされて、暗闇に放り出されたのさ」
待ってくれと隅島は思った。なんだかとんだ誤解をしているようだ。
「いいかい、パンツさん、食べちゃいけないリンゴはあるだろうさ。だけどな、たとえばヘビの小さい歯じゃ、リンゴはかじれない、そうだろ?」
「丸呑みにしてるのかも」
パンツはそう言って隣の男に笑いかけた。男は少しだけ笑った。それに気をよくしてパンツはさらにヒステリックに笑った。
十秒後、隅島の体は穴だらけになっていた。
つきっ放しのテレビでは、いかにも億ションらしい外観フォルムをした高層マンション前で女性リポーターが台詞を棒読みしている。
「昨夜、小説家のプラトニ・カルキさんが自宅で殺害された事故で、警察は強盗を目的とした殺人事件とみて……」
自社のマンションで起きた事件の捜査進展を知りたくてテレビをつけていた隅島だが、報道を見逃した。視線は、テレビの位置より三十度ほど上を見つめたままだ。
「ずいぶん丁寧な縛り方だ。SMプレイにしちゃ念が入ってる」
パンツは隅島を縛っているロープの縛り目を確認しながら呟く。パンツの隣にいた男はロープに鼻を近づけて嗅いだ。
「この匂い、さっき下のロビーでもしたな」
「出て間もない…か」
月島ステーション
東京メトロ有楽町線月島駅から新富町駅間は、隅田川を挟むため、当然隅田川の川底より下を走っていることになる。だが、ホームで電車を待つ人々は、行き来する無数の魚たちより下にいることなどあまり意識していない。
庵月ユウジは巨体をゆらゆらと揺らしながら少し匂いの籠もった月島駅のホームをぶらぶらと歩いている。予定より十五分早く駅に着いてしまったのだ。
時計を見る。クライアントの待ち合わせ時間は夜の一時。通常の職業では考えられない時間の呼び出しだが、庵月には日常茶飯事だ。
場所は月島アークホテル。初めていくホテルだ。
ホームに人気はない。
上りの終電は二分前に出発したところだ。
庵月はあくびをしながら階段からいちばん近いベンチに向かう。先客がいる。
庵月は彼女と背中合わせのベンチを選ぶ。庵月の視力は歳月とともに等加速度的に衰えていたから、背後にいるのは実際には女の格好をした男かもしれなかった。
庵月はいつからか、目に見えるものを見極めようと努力しなくなった。女らしい何か。それでいい。
これから庵月が行く先で待っているのも女だ。夜の十二時にホテルの密室で女と逢う。それだけ聞けば、人に誤解されることは間違いない。あるいは、独活の大木のような庵月の巨漢は、殺し屋を連想させ、二重の嫌疑を生む。
彼の業務はいたって簡単で平和的なものだ。眠れない人を眠らせる。それだけだ。
睡眠を仮死状態ととるなら、庵月はある種の殺し屋ということになるのかもしれない。「寝かせ屋」そう呼ばれるようになって五年が経つ。その前はテレホンオペレーターをやっていた。今考えると、自分にもっとも合っていない職業ではないかとさえ思う。人間やろうと思えば鷹狩りだって何だってやれるのだろう。
庵月は地下鉄の湿った空気の中で、鼻孔をくすぐる仄かな甘やかな香りの正体を探る。
「アニマリック」
庵月の呟きは、ホームのわずかなノイズに紛れて消えてしまうほどの小さいものだ。だが、女はそれを聞き逃さなかった。
「鼻がいいのね」
女の声は格別女らしくもなかったし、かと言って低いのでもなかった。化粧っ気のない声。こういう女にこの手の香水は似合わない。いや、スカートだってふさわしくはない。休日にはデニムにタンクトップという軽装でいるタイプだ。
「飼い犬に似たらしい」
「犬を飼ってるの?」
「フェラリアにかかって死んだ」
二人は背中合わせのまま、会話を続ける。この時間の、この場所ではそうするのが慣わしだとでもいうみたいに。
「上りの電車ならもう来ないわよ」
「ここで降りたんだ。仕事でね」
「この時間に?」
「どんな駅にも落し物があるのと同じだよ」
女が笑う。庵月は少しだけホッとする。女に話しかけられたのも、笑われたのも久しぶりだ。
「つまり、あなたは落し物を拾いにきたわけね」
「誰かが先にネコババしてなければ」
女は笑った。さっきよりも少しだけ長い笑いだった。
「俺たちは今、東京でいちばんでかい川の底よりも深い場所にいる」
「そしてこの街の半分以上の人はもう眠りの底にいる」
「キミはこれから眠るのか」
「家に帰ったらね」
「眠るのは得意か?」
「好きじゃないのに得意みたい」
「いいことだ」
「あなたはまだ眠らないのね」
「十七の終わりから眠っていない。睡魔に見放されたらしくてね」
女はまた笑った。今度はそれほどおかしくはなかったのか、さっきより短い。それからひとつ大きなあくびをする。そして手を上にあげている。伸びでもしたのだろう。
「ああ、もうクタクタ」
「よく眠るといい」
「眠れなかったら?」
電車がやってくる。
風は電車から全力疾走で逃げ、月島駅ホームに突風をもたらす。
「眠れなかったらここにかけてくれ」
庵月の声は電車にかき消された。だが、庵月が肩越しに背後へ回した名刺を彼女の手は受け取った。返答はない。だが、彼女は受け取った。電車が停車する。
サイレン。
ドアが閉まる。
庵月は振り向いたが、ぎゅうぎゅう詰めの電車のなかに彼女を見つけることはできなかった。
時計を見た。待ち合わせの時間まであと十分。
庵月は、名刺が手元から離れていく瞬間をリプレイした。ホームに巻き起こった突風が名刺を奪って逃げたのかもしれない。いずれにせよ、大方の営業努力と同様、すべては確率でしかない。庵月は女のことを忘れた。その女に、自分が何を期待したのかも。
月島アークホテルロビー。
現れたのは、長身で髪をオールバックに、濃いサングラスをしたニ十代後半の男だった。男自体が影絵に見えた。男は庵月を物色した。
「早かったな」
庵月は時計を確認した。丁度一時を指していた。
「時間通りです」
オールバックは首を傾げ、それからエレベータに向かって歩き始めた。ついて来いということらしい。庵月は従った。恐らく女は金持ちの令嬢か何かなのだろう。この男は従者でボーイフレンドといった役どころに違いない。
エレベータの内部は赤い防音マットに覆われている。
男は十九階のボタンを押す。
男の体からはただならぬ暴力の匂いが嗅ぎ取れる。いくつもの死体を作り上げた者から漂う独特の雰囲気。ボディガードというようなきれいな職業ではないだろう。腰には恐らく拳銃が差してあり、もしもエレベータ内で庵月が奇妙な動きを見せれば即座に庵月の脳天に穴が開くはずだ。
十九階。
窓からは隅田川とその向こう側に東京夜景が広がっている。
男は先へ進んでいく。庵月は遅れないように男の跡を追う。
廊下の一番端の部屋の前で男は止まる。ノックもなしでドアを手で押す。
そのドアには取っ手がなく、ぶらりと何の抵抗もなく開く。
「連れてきました」
室内のベッドにはスキンヘッドの男が腰掛けている。
「ずいぶん早いな。しかもデカイ」
スキンヘッドはそう言ってニヤっと笑って見せる。矯正中の歯が覗く。この歳になるまで歯の矯正を思いつかなかったのか、それともこの歳になってから矯正する理由が生じたのか。
「俺は俺の仕事を終えた。あんたはあんたの仕事をすればいい」
「質のいい仕事にはいくつかの条件が要ります。私は仕事に入る前に、まずその条件を満たすことにしています」
庵月はいつもの前口上を述べた。こういう文句は自分のなかで定型文にしている。句読点の打ち方や、助詞の位置は時折変わるが、内容が変わることはまずない。
「同感だ」
スキンヘッドは目を見開いた。剃り落とされた眉毛のせいか、その目は魚の目のように大きく見える。瞬きするための目蓋をどこかに置き忘れてきたような人間離れした目。
案月は続けた。
「まず第一に、依頼されたご本人以外は作業中別室へ移動してもらいたいのです。作業が終わったらまたお呼びします」
「我々は今すぐここを去るし、去ったが最後、二度と戻らない」
案外ものわかりがいい。庵月は静かに頷いてみせる。
「もう一つあります。作業後一時間は絶対に眠っている方の携帯電話を鳴らさないでください。せっかくの作業が台無しになってしまいますから」
スキンヘッドは笑った。矯正器具がいびつな輝きを放った。
「たとえ電話を鳴らしても、出てはくれまい」
スキンヘッドはそう言ってクツクツと笑った。
「ざっと数えたんだが、十三人いる」
「十三人?」
「多いか? でもそのぶんあんたも儲かる」
いくら何でも多すぎた。手荒な催眠術をかけるとあとあと問題が生じるから、できれば安全性の高い催眠法を用いたい。そのためには、眠れない理由を見つけ出し、障壁を一つ一つ丁寧に取り除く作業だけで、一人三十分は必要だ。夜明け前に十三人全員を眠らせるのは至難の業だ。
「では、その十三名の方々は、まだ起きているわけですか」
「いや寝てるさ、もちろん」
寝ている──。
「目は開いてるがね」
「それはいけませんね」
眠りが浅いということか。だとすれば、まったく眠れていないわけでもないのだろう。それなら案外早く片付くかもしれない。
「我々は次の仕事に取り掛からなくてはならない。ここはあんたに任せる」
スキンヘッドは庵月の肩を軽く叩いてから、部屋を出て行った。オールバックの男は庵月に鍵の束を渡した。少しだけ疑わしそうな視線を寄越しながら。
「全部で十二部屋。ドアの開いてる部屋がそうだ」
「ドアを開けたまま眠っているんですか?」
男は不審そうに庵月を見上げる。庵月は不相応な巨体を少し猫背にして畏まる。
「念のため鍵も渡しておく」
庵月は黙って頷き、鍵の束を受け取る。
オールバックの男はスキンヘッドを追いかけて廊下に消えた。
ふと、ベッドの足元が濡れて光っているのに気付いた。血痕。ベッドの脇に引っくり返っている椅子があり、そこに血の肉塊が縛り付けてある。確かに目は開いており、すでに眠っている。
「ただし、ベッドではない」
どうやら寝かせる必要も起こす必要もなさそうだ。
二時間前の電話のことを思い出した。
「眠れないヨ、私。すごく困ってる。朝には起きて出なきゃいけないのに、すごく困ってる」
名を「リャンリャン」と名乗った。どうせ偽名だろう。寝かせ屋ごときに本名を伝える必要もない。
隣接する一九〇四号室にあった二体の死体のうち、ドア付近に倒れていた女性の遺体は中国系の美人だった。死体の声を確かめることはできないが、おそらく「リャンリャン」だろう。
誰かが先に彼女を眠らせてしまったらしい。
庵月はすべての部屋を丁寧にチェックし、無事十三体の死体を確認した。問題は一つ。このままでは、明日の携帯電話の料金が支払えないということだ。
「リャンリャン」は庵月に依頼をした直後に殺された。ここに残っていた二人の男はそのことを知っていて、庵月に死体相手に仕事をさせることにしたわけだ。
「頭のおかしい奴らだ」
挙げ句、十三体すべてを朝までに寝かせろというタイムリミット付きだ。
狙いは何だ? 金は支払われるのだろうか?
答えは分かっていた。金は支払われない。何故ならクライアントはすでに死んでいるからだ。そして、先ほど去った男たちは二度とここには現れないだろうし、庵月とコンタクトをとる気もないのだ。
ふと、背後に人影を感じて振り向く。
女が立っていた。眼鏡をかけた薄ぼんやりした印象の女だ。
「あの…ここでいいんでしょうか?」
女は明らかにおどおどしているように見えたが、死体だけは見慣れているらしかった。
「遅れてしまって申し訳ありません!」
女は深々と頭を下げた。案外整った顔をしているし、スタイルのわりに大きすぎる尻も見ようによってはセクシーだ。だが、自信のなさそうな態度が女を下げている。
女はレイと名乗った。
「セイワクリーナーから派遣されて参りました」
「クリーナー?」
「先ほどご依頼のあった、掃除屋です」
「……なるほどね」
庵月は笑う。掃除屋と間違われたわけだ。
「どうして遅れた?」
「ホントはセイワが直接来る予定だったんですが、実はセイワは病気で来られなくなってしまいまして…」
「経験は?」
「一人でやるのは初めてです。でもこれまでにも何度か経験はありますし、一通りの流れは理解しているつもりです」
「頼もしいね」
庵月はそう言ってから床に転がった女の死体をもう一度眺める。
「あの、これ一体で…よろしかったでしょうか?」
庵月は静かに首を振る。
「まだだ。でもちょっと待ってくれるか? 実はこっちの作業が終わってなくてね」
「……そちらの作業、ですか」
庵月は枕元に転がった女の財布を確かめた。そこには九万円が入っていた。庵月はそこから三万円だけ抜き取った。
「五千円はツケでいい」
それから開いたままの女の瞳を手で閉じさせた。
そのときだった。
床に転がった彼女のバッグがXJAPANの古いヒットソングを歌い始める。庵月はバッグの中からショッキングピンクの携帯電話を取り出す。
「爪楊枝」と表示。通話ボタンを押す。
低い中国語で、男が話し始める。
「中国語は分からない。日本語は話せるか」
電話の向こう側でしばらく沈黙がある。
庵月はレイに断り、レイを廊下へ追い出してドアを閉める。
「お前、誰だ」
男が日本語で言う。
流暢とまでは言えないが、それなりに在住歴のありそうな訛りだ。
「あんたは彼女の雇い主か? それとも恋人か?」
「ワタシの質問が先だ。お前、誰だ」
「あんたには関係のない人間だ」
「なぜ彼女が電話に出ない?」
「死んでいる」
「どこで?」
「月島アークホテル、1904号室だ」
「なぜ死んだ?」
「脳天に穴が開いているようだ」
「お前がやったのか?」
「自分の目で確かめればいい」
「ジンジャエールのせいか?」
庵月は電話を切る。「ジンジャエール」という単語が頭に引っかかったが、もう電話を切った後だ。そのまま電源をオフにする。
再びドアを開く。レイはまだそこに立っている。
「これから小一時間かかりそうだ」
レイは何も言わない。ただ挙動不審な目で庵月を見上げている。
「べつの人間がここへ仕事をしにくる。我々はここにいないほうがいい」
庵月はレイを連れ立って月島アークホテルを出ると、大通りでタクシーを拾った。
「どこへ行くんですか?」
「時間をつぶさなくちゃならない」
レイは黙っていた。タクシーは夜の勝鬨橋を渡る。
八丁堀の明かりが見えてくる。月島が遠ざかる。かさかさとした抜け殻を捨て去るような感覚が、庵月に付きまとう。
八丁ビリーズキッチン
交差点を少し過ぎたところで、タクシーを止め、料金を払って庵月は降りた。続いてレイも降りる。「八丁ビリーズキッチン」という看板の前で、庵月はタクシーを止めた。
「ここで少し時間をつぶそう」
レイは反対も賛成もしない。ただ、そわそわと落ちつかなそうに周囲を見回している。
「あの…あのホテルでは今何が起こってるんでしょうか?」
レイは殺されるのを覚悟するように、目をつぶりながら尋ねる。
「月島アークホテルで何が起こっているか。それは君が君の仕事をするときに確かめればいい」
「はあ」
レイは五年分の緊張を使い果たしたように息を吐き出す。
庵月は店内に入る。レイがその後に続く。
店内ではアンダーワールドのナンバーが頭の割れるほどの大音量で流れている。青い灯の中を魚の影が飛び交う。中央に円柱の水槽があり、その中の魚の影が壁に大きく映し出されているのだ。
カウンターに着く。カウンターには八丁の拳銃を口にくわえたコックの人形が置いてある。これが、この店のマスコットということになるのか。
庵月はビールを、レイはウーロン茶を注文する。
「ここには初めて来た」
庵月は、大音量のカールの声に負けない大きな声でそう宣言する。
「ここに仲間はいない」
いくぶんレイはホッとしたように見える。
「何でも話してくれていい」
「何でも?」
「文字通り何でも」
レイは考え込むように黙る。
「私は何か疑いを持たれているのでしょうか?」
「違う。君は何の疑いも持たれていない」
その言葉を聞いても、それを信じることはできないようだった。
「今夜の俺は、ツイてなかった。でも、できれば明日にまでこのアンラッキーを引きずりたくない」
レイは小さくうなずく。
「そこで君にお願いがある」
ビールとウーロン茶が運ばれてくる。
「簡単なお願いだ。君が受けた仕事の内容を教えてほしい。依頼した人間がこんなことを聞くのは変かもしれないが」
レイは黙る。その間にレイが北極まで散策に行っていたと言っても、庵月は信じただろう。
「それは、あなたが私のクライアントではないということでしょうか?」
「クライアントは俺だ」
「じゃあ確認の必要は…」
「通常なら、ない。だが、ここに問題が生じた。俺は記憶喪失になってしまったんだ」
今度の沈黙はさらに長い。庵月は、その間レイがサバンナで象の背中に乗っていたと言われても信じただろう。
「その話を私に信じろと?」
「信じてもらえないと話が先に進まない」
レイは笑いながらウーロン茶を口にする。庵月は、以前にウーロン茶を飲む女を隣に座らせたのはいつだったかと考える。
「でも、あなたは私が電話でしゃべった相手とは違います」
「俺には部下がいる。何ら不思議なところはない」
レイは、先ほどより幾分冷静さを取り戻した調子で語り出す。
「差し支えなければ、その部下の声の特徴を教えてもらえますか? 私としても、ご本人とはいえ、記憶喪失の方に業務内容を伝えるというリスクを背負うわけですから」
「もちろん。でも、残念だな。俺はどの部下に電話を頼んだか忘れた。おそらく男だと思うが」
味噌汁の具になる前に息絶えた貝のように、レイは完全に黙る。
レイはウーロン茶の入ったグラスを指で静かに回している。
「私の仕事は掃除屋です。クライアントから依頼され、現場に赴き、文字通り清掃するのが仕事です」
「その仕事、儲かるのか?」
「決まった組織からの依頼だけでは食べていけませんから、最近は個人からの仕事も請け負っていました。でも、個人から仕事を請けると、情報が漏洩しやすくなるので、それほど手広くもやれないというのが現状です」
一度開くと、レイの舌は滑らかによくしゃべった。ただし、肝心な部分は保っている。
「ですから、今夜も私は清掃を依頼されたのです」
意外と用心深い女だ。
「何部屋ぶん?」
「部屋の数は聞いていません。人数も」
「十三人だ」
今度は違った種類の沈黙が流れた。
「それは言ってなかった?」
レイはうなずいた。さっきより目の瞳孔が開いて見える。
「十三人なんだ。朝までにできるか?」
「やったことはありませんが」
庵月はしばらく黙っていたが、やがてこう言った。
「じゃあさぁ、やめちゃおうよ」
レイは庵月の顔を見た。
「やめちゃおう」
庵月は念を押すように繰り返す。
レイは庵月の顔を覗き見る。とても興味深そうに、レイは初めてまじまじと庵月の顔を見る。
「うちの組織が、おタクにこういうことを頼むのは何回目になる?」
「七回です」
「もう一つ。それだけ仕事をしているのに、君がプロらしく見えないのはどういうわけだ?」
レイは黙っている。
「冗談だ。最後に一つだけ。部下に連絡したいんだ。ケータイを忘れたから貸してもらえないか?」
レイはやはり黙っている。庵月の真意を測りかねているのだろう。
だが、やがてゆっくりと口を開いた。
「どうぞ」
レイの差し出した携帯電話はシルバーのスタイリッシュなデザインだった。どちらかと言えば男性が好みそうなデザインだった。
庵月はレイに仕事を依頼した男の電話番号を聞きだす。ボタンを押す前に「186」を押す。
ベルがなり始める。やがて電話がつながる。
電話口で男はただ黙っている。庵月は沈黙を気にせず話し始める。
「俺だ。掃除屋は帰すことにした」
「……誰だ」
深みのある声だった。まるで本当はすべてお見通しであるかのような、落ち着き払った「誰だ」だった。
「死体の数は十三。とても朝までに片付けられる量じゃない」
「どこの誰だか知らないが、あんた、自分のしてることが分かってるのかい?」
「俺は俺の仕事をしてるだけだよ。遅ればせながらね」
切断。電話番号はもうすでに頭にインプットされていた。コウモリに頼めばすぐに調べてもらえるだろう。コウモリというのは、以前の会社の同僚のあだ名だ。なぜそう呼ばれているのかは、聞いたことがない。
と、このとき、レイが思いもよらぬことを言いだした。
「あの、さっき本当は『184』を押したかったんじゃないですか?」
庵月は不思議そうにレイを見つめた。
「そうだよ、だから『184』を押した」
言いながら、庵月は自分の表情が曇る音を聞く。
「『186』でしたよ」
つい数年前、庵月はテレホンオペレータをしていた。クレサラ系の会社で、非通知設定が基本になっていたため、非通知電話拒否設定をしている顧客に対しては『186』をつけて発信していた。さっき、非通知にしようとしたときに、どういうわけかその古い習慣が指先の神経を伝ったらしい。
「すまんが、右手を出してくれないか」
レイは言葉の意味を考え躊躇しているようだった。
「とても大事なことだ、早く」
レイは恐る恐る右手を差し出した。庵月はその手のひらを両手で柔らかく包みこみ、親指を器用に動かす。
止まりかけの駒のように、レイが揺れる。レイの黒目は天井を見上げ、やがて完全に白目だけになる。カウンターに頭が倒れる瞬間、庵月は素早く腕を差し出し、それを受け止める。催眠完了。
「マスター、勘定」
庵月は言いながら、レイのバッグを探り出す。
ふたたび月島アークホテル
一九〇三号室に、男が二人いる。一人は破裂が目的で膨らまされた風船に似ている。隣の男は非常に細く、背が低い。明らかに義眼と分かる右側はつねに正面を向いている。男は口髭をいじりながら、横たわった女の死体を眺めている。
「お前、これ食べるのにどれくらいかかる?」
風船男は死体をしげしげ眺める。
「ざっと四五キロってとこですかいねえ。十五分ありゃ余裕じゃないっすか?」
「レアで、だぞ」
「ミディアムなら水なしの十分なんですがね」
「レアだ」
「じゃ、十五分が限界です」
「すぐ始めろ」
痩せの長身は中国訛りの日本語で話す。風船男は、作業に入る前に、靴下を脱ぎ、それをきれいにたたんで脇に置くと、正座して「いただきます」と手を合わせた。それから、すぐに作業にとりかかる。太っているわりにモデルみたいに細い指先が、器用に女の体から服を破り捨てる。わずか五秒。続いて肉体を骨に沿っていくつかの切れ目を入れていく。筋の通り方は心得ているらしく、包丁の流れはスムーズだ。風船男にかかると、まるで元来人間とは骨と肉とに分けられるべくして存在しているような気にさえなる。ほどなく骨と肉は見事に仕分けられる。風船男は肉をさらに細かくカットし、カットしたそばから口に放り込んでいく。
「朝から何も食べてなかったんです。ラッキーでした」
「良かったな」
痩せの義眼はしゃがみこんで財布に手を伸ばす。
「六万も入ってる。ずいぶんぼったくったね」
男の名は爪楊枝。東京に棲息する中国マフィアだ。爪楊枝はベッドでうつ伏せのまま倒れいてる男を見た。コールガールを頼んできたのはこの男に間違いなさそうだ、と爪楊枝は考えた。
「ジンジャエールのせいですかね?」と風船男。
「黙って食べろ」
爪楊枝はもう一度戻って女の骨の脇に落ちているショッキングピンクの携帯電話に手を伸ばす。だが、すぐに手を引っ込め、ゴム手袋を着用する。最新の着信履歴。爪楊枝は、そこに「ジンジャエール」の文字を確認し、発信ボタンを押す。
「お客様のおかけになった電話番号は、現在使われていないため、かかりません」
爪楊枝は笑う。それから携帯電話を丁重にビニール袋に入れる。
十五分後、風船男が、最後の一片を口に放り込む。
「完了」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
