
【短編】賢者とともに
本の魔物がいた。
人の頭を喰らい、その知識をエサとする、おそろしい魔物だった。
魔物は、知識を得れば、ページが増えて成長する。
次々と人を襲い、大きくなった魔物は、もう平凡な者の頭では満足できなくなっていた。

ある日、本は最高に美味な知識を持つ、賢者の存在を知った。
風のうわさに聞き耳を立て、血眼になってゆくえをさがす。
さまざまな大地を転がった末、とうとう最果ての、小さな村の片すみに住んでいる彼の者をつきとめた。
本は言う。
大きな牙を向け、よだれを垂らし、威嚇するようにページをめくって。
「知識が欲しい! お前の頭を喰うぞ!」
――と。
慧眼の賢者は、落ち着いて答えた。
「本の魔物よ。あと十年待てば私の知識は増え、今よりもっともっと、おいしくなるぞ」
十年。
人間からすれば長い時間だが、魔物にとってはほんの一瞬のこと。
本はうなずいた。
「待とう」

十年の歳月が流れた。
その日は、季節のなかでいちばんいい風が吹いた朝だった。
陽を背にした本の魔物は、寝屋の中で賢者に告げた。
「十年待った。約束どおり、お前を喰うぞ」
賢者は、まなこをこすりながら大きなあくびをほどこした。
「まぁ、待ちなさい。私には、同じくらい研鑽を積んだ良き友人たちがいる。これからは私も遠出して、お前に彼らを紹介してやろう。そうすれば、お前ももっとたくさんの知識にありつける」
本は少し考えた。
「待とう」

ところが、その旅は長く続いた。
花の舞う街。
海に没した古代の遺跡。
雲海に浮かぶ庭園。
巨大な鳥のすむ森。
ひとときを楽しむことはあったが、肝心の友人は、不在や行方不明の者、すでに死んでしまった者たちばかり。
西へ行っても、東へ行っても、誰一人として会うことはできなかった。
やがて、旅は終わりに近づいた。
賢者の背中は小さくなった。
彼がとうとう歩みを止めたとき、すでに十年が過ぎていた。
ある日、そのことに気づいた本の魔物が憤慨した。
「もう我慢できない! まずはお前から喰う!」

さむい冬の日だった。
しんしんと雪が降り積もる最中、粗末な宿屋の一室には、賢者の咳が響いていた。
かすれた声で、賢者は答える。
「本の魔物よ。残念だがもう、私の頭はそれほどおいしくなくなってしまった。なぜなら、この二十年、ありとあらゆる知識を、お前と共有してきたからだ。
すでに知っていることを喰っても、おいしいはずがない。しかも、人間は記憶を失くしていく生きものだ。今では、私より、お前のほうが、ずっとずっと、賢いのだよ」
本は、口ごもった。
本は、ページの紙をパラパラ、パラパラと左右に鳴らし、自らもぐるぐると旋回しはじめた。
おかしい。
――『賢い』だと? このオレが?
奇妙な言葉を聞いたと思った。
一方、賢者は、目元に優しげな皺をつくりながら、言葉を継いだ。
「本よ。見るがいい、今の自分の姿を。
私と出会ったとき、お前はボロボロの姿だった。
ページはやぶれ、穴にひもを通しただけの粗末な装丁の、吹けば飛ぶような、たよりない姿だった。
それが、今は、どうかね。
革張りのかたい表紙に、金の箔押し。
見る者の興味をひかずにいられない、整った文字列と重厚な内容。
手ざわりのいいページは、もちろん一枚ずつ、しっかりと糊がついている。
本よ。私の、大切な本よ。
ずっと隠していたのだが、私はもう、先が長くないのだよ。
知っているだろう、人間には病というものがある。
寿命という言葉も、お前の中に、すでに在るだろう。
私は、新しい知識を持てば、すべてお前に与えてきた。
ときどき、お前を読み返すと、おどろくほど役に立った。
生きる気力がよみがえり、涙を流したこともある。
お前と一緒に学んだ旅は、私にとって何よりも勝る、宝のような日々だった。
そばにいてくれて、ありがとう。
おかげで、私はひとりではなくなった。
しかしもうすぐ、私は動かなくなる。
そのとき、お前は思う存分、私の頭を食べればいい。
私にできるのは、もう、それくらいしかないのだから。
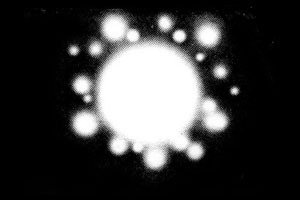
本の魔物は、動けなくなった。
口はぽかんと開いたまま。目の前にいる、白髪(はくはつ)の賢者を凝視する。
どういうわけか、ページが歪む。
シワシワにねじれ、小さく、小さく、ちぢれていく。
ふいに息苦しさが襲い、体を二つに折った。
けれど次の瞬間、とてつもなく熱い力が降りた。
じわりじわりと、変化する。
漆黒の装丁だった表紙は、輝くような純白へ。
金の模様は、輪郭をそのまま残し、中央にとある文字を浮かびあがらせた。
『ガブリ』
それは、本に付けられた、この世でただひとつの名前。
大昔、生まれて間もないころに、雨に打たれ、泥にまみれて、失くしてしまったもの。
取り戻すことさえ忘れていたそれは、本の大事なこころだった。
ページの一部が、羽根に変わる。
つやつやで柔らかな、ぴんと張った白い翼が、本と空をつないだ。
本は、賢者のそばに降りたち、告げた。
「待っていろ。オレがお前の病を治してみせる。ほんのひととき、オレが新たな知識を得て、帰ってくるまで、待っていろ。――安心しろ。もう人は喰わない」

賢者の瞳から、涙がこぼれた。
とうの昔に枯れてしまったと思っていた涙がとめどなくあふれ、賢者の頬をぬらしていった。
「――そうか、友よ、私は待っている。いつまでも、待っている。
ありがとう、ガブリ。私の大切な、かけがえのない友よ」

また十年の歳月が過ぎた。
本は今も、旅を続けている。
ともに歩き、ともに学ぶ。
賢者の傍らで、世界をめぐっている。
「賢者の友」
いつしか人々は、本の魔物をそう呼ぶようになっていた。
<おしまい>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
