
「シティ・アズ・キャンバス」(後編)
本セッションは、都市空間での表現の在り方を探索するアートコレクティヴ「SIDE CORE」の方々にご登壇いただきました。
後編となる今回ではまず、都市と個人の表現のせめぎ合いの中でエッジを攻め続けるための戦略について議論します。そこから、地域に溶け込みながらコミュニティを巻き込み、街と表現を両立させる実践としての「鉄鋼島フェス」についてお話いただきます。(前編はこちらから)
本記事は、2019年1月に開催した『METACITY CONFERENCE 2019』の講演内容を記事化したものです。その他登壇者の講演内容はこちらから。
・TEXT BY / EDITED BY: Shin Aoyama (VOLOCITEE), Tomoya Matsumoto
・PRESENTED BY: Makuhari Messe
*
アウトとセーフの線引き
青木:今回のセッションで議論したいのは、『シティ・アズ・キャンバス』ということで、街をキャンバスにしていくこと。その意味とは一体何なのかというところです。
昨日市長もお話されていましたが、街に根付くには少しカオティックな状況が必要だと。でも完全にカオスだと問題があるから、ある程度は構造化されている必要がある。では、それを許容できるレギュレーションの幅ってどういうのがあるんだろうかという疑問があります。
たぶん、今日のみなさんのやつは結構ギリギリだと思うんです。もちろん許可を取ってるものもあると思うんですけど、それをどう捉え直せばもっと自由にアーティストが来てくれて、面白がってくれるのか。アーティストが作品を生み落として、また面白いと思って人が来てくれるような循環ができるのか。そんなところが、皆さんのお話から少し見えてきたらいいなという風に思っています。
私はさきほどの「catcher in the city」、落書き禁止の張り紙を取り除く作品が、そこのヒントになるかなと思いました。おっしゃったように、皆さん個人個人としてはそういう作品を面白いと思っている。でも誰が実施を決めたか分からないし、誰が許してるかも分からない。曖昧なルールの上だからこそ誤解が生まれて、この作品のようなことが起きると。では、それが問題とならないようにするとしたら、一体どんな形がありうるとお考えでしょうか。
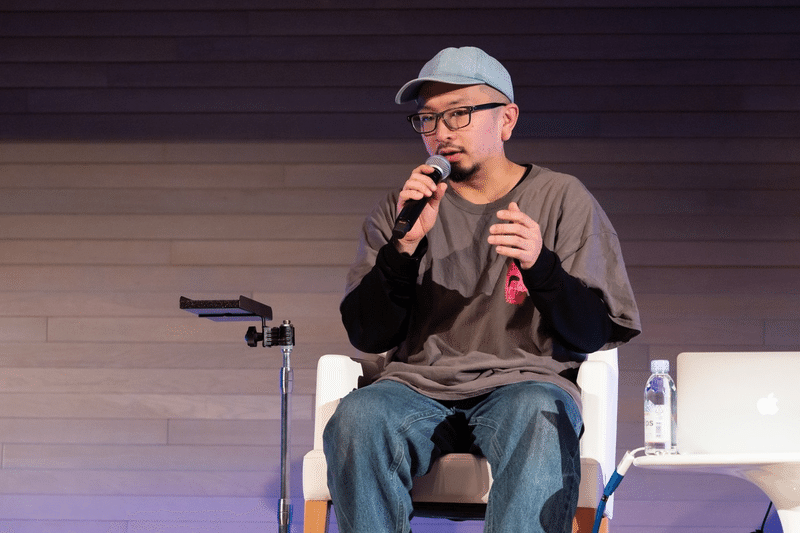
松下:まず寛容さとか許す力みたいなものはあると思います。例えば、デベロッパーの方とかも僕たちにいろんな話をしてくださって。ストリートカルチャーのアイデアで、街を新しくデザインしていくアドバイスをしてくれませんか、何か一緒にやりませんかって言ってくださっていた。だから向こうだって、街をきれいにするために邪魔者を追い出せなんて思ってないんですよね。
ただ、できないことももちろんあって。例えば下町の風景をぱっと思い出すと、道が狭くて、建物も変な形してて、道路に木とか置いてあったりするじゃないですか。でもこれってほぼ違法なんです。今のレギュレーションでは、二度と同じ風景は造ることができないんですよね。
僕らがストリートカルチャー、特にグラフィティについて面白いと思ってる点をお話しします。昔、ニューヨークでグラフィティが始まったときっていうのは、街の中に急に絵の描かれた地下鉄が出現したときだったんですね。つまりニューヨークの街が置かれたカオスな状況が、街の風景の中に個人個人の行為によって投影されたっていうことだと思うんですよね。落書きのすごいところって、一人一人の単純な行為が、80年代のニューヨークとして思い出される風景をつくっていったことなんですよね。今同じことを落書きでやって、それを許容して街を表現しようよって言っても、難しいと思うんですよ。だからこそ、落書きだけじゃない形で表現するのが大事で。さっきのスケートボードの例もそうです。このパークには再現性があって、たとえば幕張でも同じ夜間工事現場の道具を借りてきて、スケートボーダーたちが来て、ランプを持ってくれば同じことができるわけじゃないですか。膨大な予算をかけたり、特別な申請をしなくてもできる。それが、風景が変わるきっかけとしての作品なんだと思うし、そういうものが増えてきたらいいなって思うんすよね。
寛容性の話に戻ると、大きなレギュレーションで計画したら起こらないような個人の考えと発想で、ギリギリのラインのものをどれだけ実現できるか、みたいなとこだと思うんですよね。僕たちも毎回、企業さんや自治体さんとかと交渉して実現したことのほうが、大きくて面白いと思ってるから。そういうことがどんどんケーススタディーとしてできていったらいいなと。
青木:なるほど。ニューヨークに行ったときに、人のクリエイティビティーが街に染み出ちゃってる感じがしました。街が唯一無二性を秘めてるというか、こういう街はつくろうって思ってもつくれない。でもそれは、どちらかというとそれを許容してる街の人たちがいるっていうことがすごく大切なんだなと思います。
松下:そうですね。あとは一回突破してしまえば、それにみんなが続いていけるので。行動が連鎖するかどうかが大事なのかなと。
青木:行動の連鎖。なるほど。ちなみに、先ほど軽く触れましたけど、幕張っていうのは、国家戦略特区になっていて、幕張メッセを管理している会社がOKを出せば道路も自由に使えるらしいですね。そういう形で大きなスケールでやってみるっていうのも一つ、面白いかもしれないですね。
松下:そうですね。1個のプロジェクトができれば、それをきっかけにしてどんどん続くと思うから。「俺はこういうことやってみたいよ」っていうのが続いていくといいですよね。
高須:この辺って住んでる人は結構、多いんですかね。
青木:ええ、いらっしゃいます。
高須:こういうコンベンションセンターとか、大きいホテルとかだけじゃなくて、もうちょっと住宅街みたいなところもあるんでしたっけ。
青木:駅から離れたほうにあるのかな。僕もそこまで詳しいわけではないんですけど。
高須:夜と昼の状況が違う街ほど可能性があるなと思っていて、この辺とかも、国際会議場で昼間はこういうふうにたくさんの人が来ているけど、夜になるとほとんど人がいない。警備員さんだけみたいな。そういうギャップがある場所はすごい魅力的だなって思います。
松下:例えば、この施設のエントランスは夜になると誰もいなくなって、がらんとするわけじゃないですか。そこを週に1回スケートボードのためにオープンにすると、みんな滑りに来ますよね。それによって、夜と昼の風景に面白いギャップを生むとか。ずっとスケートボードパークにするのは難しいと思うので。
青木:なるほど。ポップアップ的に。
松下:そういうことが地道に続いていけば、変わるんじゃないかなと。
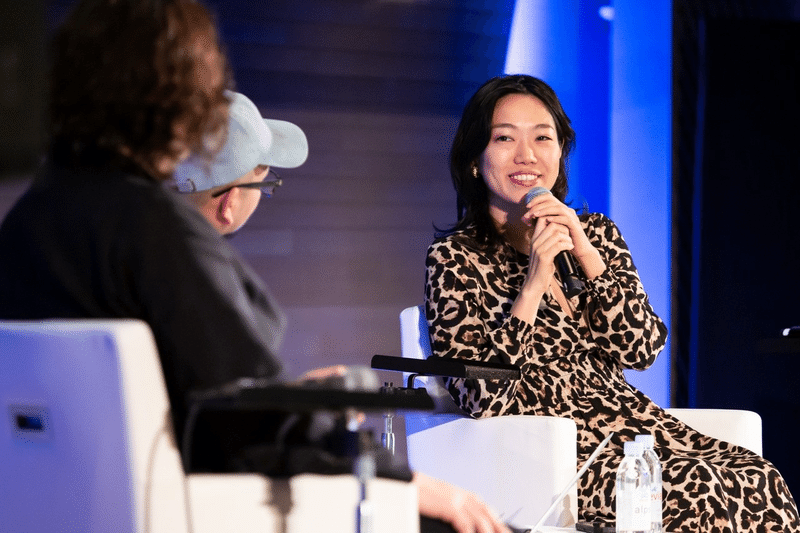
高須:私個人としては、秘密がありそうな場所に見えるんですよね。普段人がいる場所に人がいなくなって、自分だけになる。そういうドラマチックな状況になることで、昼間の用途とは別のことを考えられるっていうか、そういう意味でギャップがあると面白いなっていうこと。
青木:なるほど。インスピレーションが得られるような。
鉄工島フェス
松下:最後に鉄工島フェスの話をしたいと思います。僕たちは、大田区の京浜島という羽田空港の隣にある人工島でスタジオを運営しています。ここは住んでる人はいなくて、全部町工場の島なんですよね。その町工場の一角を僕たちが借りて、アトリエにしています。かなり大きいところなので、大きい作品を都内でつくりたいアーティストは使いに来てくださいって感じでやってるんです。
東京都内ってギャラリーと美術館はあるけど、アーティストのスタジオってないじゃないですか。だから、都内で大きい作品をつくれるスタジオを造るために運営してます。そしたら、根本敬さんというマンガ家の方が、会田誠さんのプロジェクトでゲルニカを描きたいって言ってうちのスタジオを使ってくださった。根本さんはカルトなファンが多いので、みんな根本さんの作品の完成を祝いたいってことで集まってきたんですよね。あれよあれよと、じゃあDJ呼んでみたいな感じで。一緒にスタジオを運営している寺田倉庫のアドバイザーの伊藤悠さんも「ブロックパーティーがやりたい」って言い始めて。僕たちが石巻から帰ってきたら、だいぶ大規模なフェスになっていたんですよね。それが鉄工島フェスの始まりです。鉄工所の人や区の方々、商工会と、みんなで協力して、他の工場もオープンにしたり路上封鎖したりとかして。
今思ってるのは、これも開かれてくことの一つなんじゃないかと。もともと京浜島にはものづくりの人たちがいるんで、なにか新しいことをやりたいというポテンシャルはあったんです。そこから、フェスができる可能性がでてきた。だから、工場が集まる湾岸ベルト地帯とかの海岸沿いに、もっとアーティストがアトリエ借りたりしていけば、東京も作品がつくれる街になるんじゃないかと思いますね。
青木:鉄工島フェスの面白さって、1ヶ月間くらいこもってつくるっていう規模感と、工場の人たちとコラボレーションしてることですよね。工場の人たちの意識も変わっていって、街に溶け込んでるというか。最初はちょっとしたパーティーから始まっていったわけですし。
松下:工場の人たちはものづくりの方々ですから、僕たちに対しても「これ何つくってるの?」みたいに話しかけてくれたり、当たり前のように協力してくれたりするんです。僕のスタジオの下の階は半分別の方が借りてるんですよ。その方はもう83歳なのに現役の旋盤工。そこで普通生まれないコミュニケーション、例えば毎日顔をあわせてコーヒーおごってもらうみたいなのができたんですね。だから、コミュニティのありがたみっていうのは都心でも経験できるんだと思います。
青木:都市の隙間である京浜島っていうところで、こういう新しいカルチャーが生まれていってる。ありうる新しい都市を考えていく際に重要な、隙間で湧き起こってくる創造性を支えるために、さっきの寛容度とか挑戦するとか、巻き込まれてくアーティストを増やしてくみたいなことが大切なんだなということに、皆さんとの対話を通して気付けたかなと思います。ありがとうございました。
松下:ありがとうございました。
*
NEXT:「アート系スタートアップの出現と都市文化に与える影響」は こちらから!
登壇者プロフィール

SIDE CORE
アーティスト・コレクティブ。2012年から高須咲恵と松下徹により活動を開始。2017年より、西広太志が加わる。美術史や日本の歴史を背景にストリートアートを読み解く展覧会『SIDE CORE -日本美術と「ストリートの感性」-』(2012年)を発表後、問題意識は歴史から現在の身体や都市に移行し、『SIDE CORE -身体/媒体/グラフィティ-』(2013年)、『SIDE CORE -公共圏の表現-』(2014年)を発表。2015年の『TOKYO WALK MAN』からは表現の場を、室内から実際のストリートへと広げる。 ゲリラ的な作品を街に点在させ、建築や壁画、グラフィティを巡る『MIDNIGHT WALK tour』は、現在まで不定期に開催している。公共空間にある見えない制度に、遊びを交えた視覚化をするアプローチの手法が確立されていく。2016年からは東京の湾岸地域のスタジオの運営など、都市での表現のあり方を拡張し続けるアーティストたちが、流動的に参加できる場として、活動を展開している。これらの活動は公共空間のルールを紐解きその隙間に介入し、新しい行動を生み出していくための実践である。

青木 竜太|RYUTA AOKI
コンセプトデザイナー・社会彫刻家。ヴォロシティ株式会社 代表取締役社長、株式会社オルタナティヴ・マシン 共同創業者、株式会社無茶苦茶 共同創業者。その他「Art Hack Day」、「The TEA-ROOM」、「ALIFE Lab.」、「METACITY」などの共同設立者兼ディレクターも兼任。主にアートサイエンス分野でプロジェクトや展覧会のプロデュース、アート作品の制作を行う。価値創造を支える目に見えない構造の設計を得意とする。
Twitter | Instagram | Web
皆様の応援でMETACITYは支えられています。いただいたサポートは、記事制作に使わせていただきます。本当にありがとうございます!
