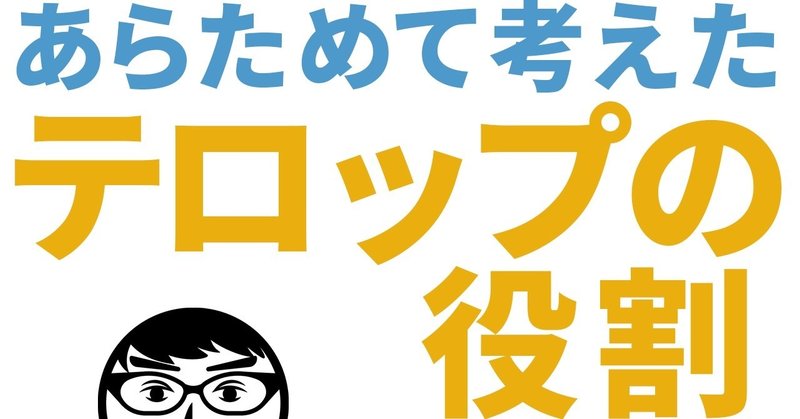
VGTに登壇することになってあらためて考えた、テロップの役割
5月25日〜29日に開催される「VIDEOGRPAHERS TOKYO」というオンラインイベントに登壇することになったナカドウガです。
僕といえばテロップですので、当然テロップについてお話しすることになりますが、一体何を喋ろうか?と思い悩んでいるわけです。
とりあえず、お話するテーマ自体は「初心者にもできる、見やすいテロップの作り方」ということに決めましたので、正直なことをいうと、過去のnoteに書いていることの焼き増しになります。
なんですが、ちゃんと芯のある話をするためには、1度は「テロップって何?」という哲学的なことをちゃんとクリアにしておいたほうが良いだろうということで、こうして書きなぐってみようと思います。
いつもの記事のように実用的な話はありませんし、推敲もしませんので、普段よりも読みにくいかと思いますが、思考の整理としてお付き合いいただければと思います。
テロップの役割
まずはテロップの役割ってそもそもなんだろう?ということです。
1:映像の内容を文章で補足するもの
映像や音声だけでは伝わりきらない細かい情報をフォローする役割ですね。そもそもテロップの成り立ちはこれなのかなと。
たとえば無声映画では、声で状況を伝えることができませんので、その代わりに文字で伝えるという手法が取られました。
これは技術的な問題をなんとか解決するための苦肉の策でしたが、こういう創意工夫から発展して、今のような「テロップ」という分野になりました。
無声映画の頃から映像に必要なパーツだったわけですが、今も昔も変わらずに押さえておかないといけないことは、「文章としてちゃんと読み切れる」ということでしょう。
音声がなかった頃であれば、今よりももっと重要視されていたはずです。だって文章が読めないとストーリーが追えないわけですからね。
ここで大切なポイントが出てきました。ちゃんと文章として意味をつかめるようにしないと、テロップがテロップである理由が保てないということ。
これは1つテロップの要素として大事なことのように思われます。
2:画面のにぎやかしのため
デザイン的に高度なことができるようなると、今度は画面そのものを装飾するという試みも出てきました。
広告や誌面と同じような成り立ちだったのではないでしょうか。いろんな手法で持ってテレビ画面を彩るようになります。
テロップで画面を飾り立てることで、テレビ番組っぽくなるということは現実に起こりますので、これもテロップの役割として重要なことです。
映像は雰囲気でもそれなりに伝わる。という特性を持っているもので、他のメディアにはあまり見られない「ながら視聴」が成立します。
それもそのはずで、「映像」・「音声」・「文字」と3つ媒体が同時に展開するので、情報量が豊富なんですね。
ただし、一方で情報の交通渋滞が起こることも否めません。
となると、前項で紹介したような「ちゃんと文章として意味をつかめるようにする」という役割と全く逆の「雰囲気だけでもちゃんと内容が伝わる」ようにする役割も、同時に存在するのです。
これは広告のキャッチコピーと同じです。短い文章で見る人をその気にさせたり、納得させたり。こんなことをテロップでもやらないといけないのですね。
3:映像のブランディングのため
そうこうしているうちに、モーショングラフィックスを取り入れたり、複雑な画面合成もできるようなってきました。
番組の個性をビジュアル的に主張できるようになってきたのですね。内容や企画に最適なデザインを意図的に選ぶということは、今では当たり前になっています。
たとえばフォントもゴシック体メインで行くのか、明朝体メインで行くのか。これによっても画面の見え方は結構変わります。
またその番組ごとのテーマカラーを決めたりもしますね。僕の印象では報道番組にその傾向は強いように思います。
「ニュースZERO」は緑色だったり、「報道ステーション」は紺色だったり。番組タイトルロゴが起点になり、テロップの雰囲気も統一されるのは、もはや一般的です。
となるとテロップをデザインする最初の段階で、しっかりと番組のコンセプトデザインから考えておかないといけません。
テロップは番組の目印としても機能するようにしないといけないということです。だって毎回の放送ごとでテロップのデザインが違うというのも不自然ですよね。
ここでももう1つ重要な役割が見えてきましたね。思っている以上にテロップの役割は拡張されているように思います。
ざっくりとまとめると・・
1:テロップはちゃんと読めて、意味が理解できるように
2:過剰な情報量に流されないように、雰囲気だけで伝わるように
3:番組の個性を伝える目印でないといけない
テロップには少なくともこの3つの役割が備わっているのは事実として捉えておいたほうが良さそうです。
テロップって本当に必要なの?
それを踏まえてもう1度疑ってみます。「テロップって本当に必要?画面を汚すだけじゃないの?」
これは必要でもあるし、不必要でもあると言えます。
たとえば漫才にコメントフォローがあったら、絶対面白くなくなりますし、過剰な装飾がされた映画字幕があれば、内容に集中できなくなるはずです。
一方で、お店や商品を紹介する映像で、店名や商品の値段が表示されないと、ストレスになります。「この店はなんという店名で、なんという商品やねん!」と思うことでしょう。
要するに適材適所。押し引きをちゃんと考えないといけないということ。
テロップがそれそのものだけで主張してはいけないのですね。あくまでテロップは映像のパーツです。
映像とテロップと音声が調和する、ということを心がけてテロップは作るべきです。
難しいことですが、テロップにはTPOに基づいた着せ替えをしてあげないといけないのですね。
テロップはデザインか?
TPOに基づいた着せ替えということで、イメージするのは「色やフォント」ではないでしょうか。
なるほど、どんな色を組み合わせるか、どのフォントにするのか?ということはテロップを作る上でかなりの時間を割いて考えることです。
そう考えるとテロップはグラフィックデザインの1つとは言えるのですが、ここで考えたいのはそういうことではなく・・・。
うまく伝わるか自信がありませんが、「デザイン」は何か・誰かの問題を解決したり、役に立つことだと思っています。
デザインは世の中に明確に必要とされているし、実際に世の中の役に立っている・・・。
UIデザインなら、ストレスなく目的の機能にたどり着けるようにするでしょうし、プロダクトデザインなら、もっと使い勝手良くデザインするものです。
これって役に立つ行いですよね。
しかしテロップは人の役に立つ?かと言われると、ちょっと疑問に思うことも事実です。別になくても誰も困らないよな・・・。と考えたりもします。
ただ、今回考えていったように、テロップは情報を伝える媒体のひとつ。そう捉えるならテロップはデザインの1部と言えるのかもしれません。
ちなみに個人的にはデザインとかデザイナーというものに、ものすごいコンプレックスを持っているもんで、素直にテロップをデザインということができません(笑)
まとめ
テロップには役割があって、その役割は長い歴史の中である程度整理されてきました。
意味を伝えるものから、雰囲気を伝えるもの、番組の個性を伝えるもの・・・
ちょっとずつ役割を拡張しながら、今のようなテロップの形に収まっています。
これからも時代やメディアに合わせてアップデートされるんだろうなと思いつつ、テロップのことを漠然と考えた今回の記事。もっと良いテロップを作るヒントは見つかったでしょうか。
うーん。わかりませんね。。。見つかったような見つかってないような。
兎にも角にも29日のVGTに登壇することには代わりありません。「当日が楽しみ!」と空威張りするほど、経験値があるわけでもありませんので、当日はブルブル震えながら過ごすことでしょう。
ま、やれることを頑張ることが大切なのかなと。
興味ある方はこちらから詳細をご確認ください。当日はアワアワしないように頑張ります。
どうかよろしくお願いいたします。ナカドウガでした。
noteやtwitterでの発信をもっと良くするために、活用させていただきます!
