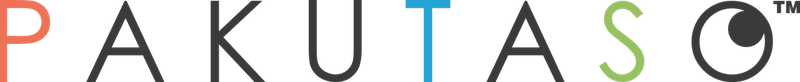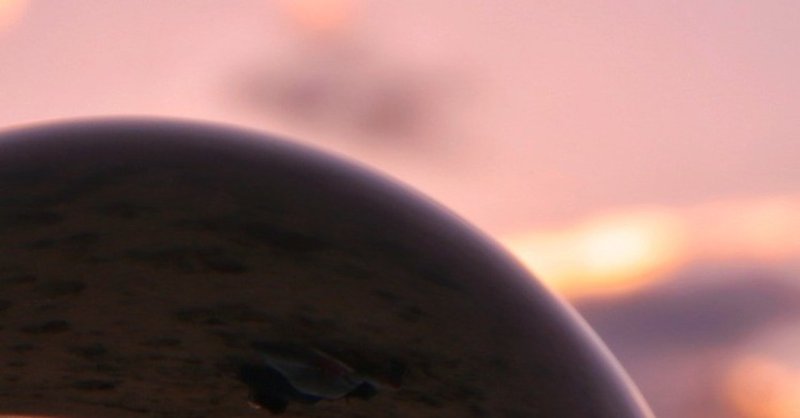
【短編小説】灼熱の風が吹くこの星で ④
【SCENE 4】
僕達の住む世界の空は紫色をしている。
とは言ってもそれは真上だけ。
太陽の輝いている方角は常に赤く輝いているし、反対側には、見ているだけで吸い込まれてしまいそうな闇が広がっている。
太陽と大地の間には二つの月が回っていて、それぞれが一周する毎に一日と決まっていた。
歴代の天文学者達によって、月の角度は毎日少しずつズレていることがわかっている。
ちょうど三五〇日でまた元の位置に戻るらしい。
だから三五〇日を一周期と表現している。
ミリスに尋ねたところ、この時間の計測方法は、水の民も同じであるらしい。
ただ、寿命は僕達と違ってバラバラだった。
地の民が十五周期から十七周期を生きるの対して、水の民は、短ければ十周期くらいで死んでしまう。
だけどその一方では、三十周期以上を生きている人もいるみたいだ。
寿命に二周期くらいしか差のない地の民とは違って、寿命の幅が広い。
そして水の民は、長生きをすればするほど、寿命ではなく、病気とか事故とかで死んでしまうケースが増えるらしい。
そういった意味でも地の民とは逆だ。
僕達が病気や事故で死んでしまうのは、そのほとんどがまだ幼い頃なのだから。
毎日のように、僕達は色々な話をした。
ミリスの語る水の民の生活は、そのほとんどが初めて知ることばかりで、何もかもがとても面白かった。
せっかく教えてもらった貴重な情報だ。
僕はいつかこの事実を他のみんなにも知ってもらえるよう、本にしたいと思いながら、ノートにたくさんのメモを取った。
「ねえレルフ、これは何?」
ある日のこと、ペット用のガラスケースを指差しながら、ミリスがそんな質問をしてきた。
「マルネ虫だよ」と僕は答える。
「マルネ虫?」
「うん。僕のペットなんだ」
「どこにいるの?」
ちょうど土の中に隠れていたらしい。
僕は手に持っていたコロモイを一気に喉へ流し込み、腰を屈めているミリスの隣へ移動した。
それからケースを軽く叩く。
すると音と震動にビックリしたマルネ虫の幼虫が、土から飛び出してきた。
円筒形の体に疣足(いぼあし)というのが特徴的で、幼虫の頃には僕達が主食にしているモイ科の根を食べることから、モイ虫とも呼ばれている。
その俗称は水の民でも同じだったようだ。
「マルネ虫って、モイ虫のことだったんだね」とミリスが呟いた。
「地の民の人達って、モイ虫のことを。マルネ虫って呼んでるの?」
「他のモイ虫は普通にモイ虫って呼ぶよ。だけどマルネ虫だけは特別なんだ」
「何か違うの?」
「他のモイ虫は、成虫になったら飛んで逃げていってそれっきりだけど、マルネ虫だけは産卵の時期になると、必ず戻ってきてくれるんだよ」
「へぇ~え?」
「帰巣本能って言われてるんだけどね、灼熱の風に焼かれずにちゃんと戻ってきてくれたら、飼ってる人に幸運をもたらすって言われてるんだ」
「幸運?」
「うん。僕の飼ってるマルネ虫はね、これで六代目なんだ。これまでちゃんと毎周期ここに戻ってきて、産卵してくれてるの」
「そうなんだ」
「普通は二回くらいしか連続で戻ってくることはないみたいだから、六回連続ってのは、凄く珍しいことみたいなんだ」
「じゃあ、レルフはいっぱい幸運を手に入れることができたのかな?」
「うん。凄い幸運があったよ。
だって絶対に会話なんてできないと思っていた水の民のミリスと、こうして一緒にいられるんだし」
「そっか」
素っ気ない態度でうなずくミリスだったけど、少しだけ照れているのは、朱色が差した頬から窺い知ることができた。
「そう言えば卵で思い出したけど、レルフには親っていないの? 一緒には暮らしてないみたいだけど」
「僕達地の民には、親なんていないよ。
地の民はその名の通り、大地から生まれるんだ。
だからあえて親が誰なのかと言えば、『この大地そのもの』ってことになるんだと思う」
「へぇ~え?」
ミリスが意外そうな顔をしている。
そりゃあそうだろうと思う。
地の民以外の生物には全て親がいて、普通は卵から生まれる。
だから大地から産まれるだなんて、とても珍しいことで、水の民としては不思議なのだろう。
僕はそう考えたのだけれど、どうやら違ったらしい。
「地の民も、わたし達水の民と同じなんだね」
ミリスの台詞に「え?」僕は思わずキョトンとした。「同じって、どういうこと?」
「わたし達水の民にも、両親がいないんだよ」
「そうなの? 両親がいないのに生まれるのは、地の民だけだと思っていたのに……。
じゃあ、水の民はどこで生まれるの?」
「赤熱の大海の側だよ」
「……あんな過酷な場所から?」
赤熱の大海の周辺は、太陽に近い分、大地もかなりの熱を帯びている。
生物が生きていけるような環境ではない。
それに――。
「そこって、地の民のお墓になってる場所だよ」
「地の民のお墓?」
「うん」
僕は手に持っていたコロモイを食べてから言った。
「地の民はね、自分が寿命で死ぬ時ってのが何となくわかるんだ。だからその時期が近付くと、自然と赤熱の大海を目指すの」
「自分でお墓に向かうってこと?」
「僕も他の仲間から聞いたことがあるだけで詳しくはわからないんだけど、そういう本能みたいなのがあるみたい。
だから赤熱の大海を目指したくなったら、ああ……寿命なんだな……って感じで、キミ達水の民に殺されたり病気になったりしないで最期まで生き延びられたことを、大地の神様に感謝するんだ」
「そうなんだ……」
ミリスが感慨深げにうなずく。
「そういう風習みたいなのも、わたし達と一緒だね」
「どういうこと?」
「わたし達もね、自分達の寿命を感じ取ることができるの。そして死期が近付いたらマリスの湖へ向かうんだけど」
「マリスの湖? そこは僕達にとっては聖地だよ」
何故ならマリスの湖は、僕達地の民が生まれる場所なのだから――と、本当はそう続けるつもりだったのに、再び感じた空腹が強過ぎたので、僕は会話を中断してコロモイに手を伸ばした。
創作活動にもっと集中していくための応援、どうぞよろしくお願いいたします😌💦