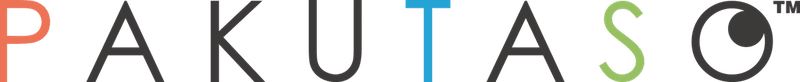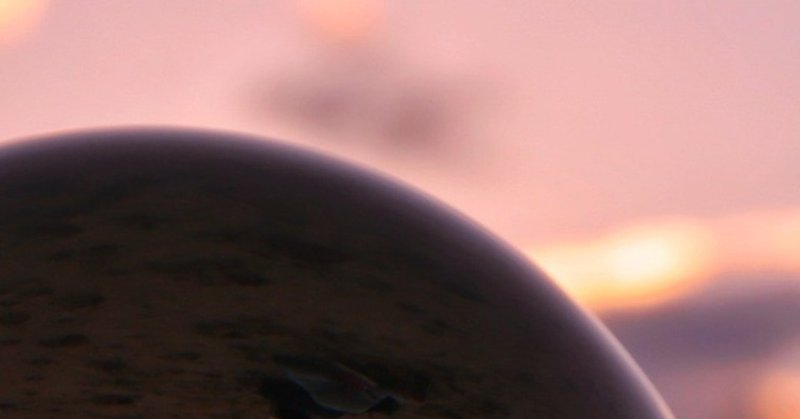
【短編小説】灼熱の風が吹くこの星で ⑤
【SCENE 5】
ミリスと出会った頃くらいから、僕は食欲がだいぶ増していた。
以前は起きている時間の半分くらいを食事に遣っていたのだけれど、現在はほぼ四六時中空腹感に襲われていて、眠る時以外は常にコロモイを口にしている。
きっと寿命が近いのだろう。
ただ、死ぬ前にやっておきたいことがある。
ミリスから聞いた話を本にまとめることだ。
僕はコロモイを食べながら、水の民について新たに知った事実を原稿用紙に書き続けていた。
そんな僕を見ているだけでミリスは幸せなようだ。ずっと側にいる。
そしてミリスの火傷が見た目にはわからないくらい治ってきた頃、僕はとうとう原稿を完成させたのだった。
完成した原稿を本にしてもらうためには、出版社にお願いしなければならない。
出版社は当然、街の中にある。
なので僕は、久しぶりに街まで旅に出ることにした。
最初はミリスも一緒についてくると言っていたけれど、僕は説得して止めさせた。
本来、水の民は地の民を一方的に殺戮する死の象徴だ。
街になんか姿を現すと、大混乱が起こるのは間違いない。
それに僕と一緒の時は平気なミリスだけど、他の地の民が近くにいる時にでも殺意衝動が芽生えないとは限らない。
だからミリスには、この家で待っていてもらうことにしたのである。
大きな背負い鞄の中に、道中必要となるであろう大量の食料を詰め込む。
大切な原稿は灼熱の風が吹いた時にも守れるよう、しっかりと左腕で抱き締める。
僕達地の民はコロモイからだけでも必要な水分は補給できるので、水筒などは必要ない。これで準備はOKだ。
ミリスに見送られて家を出た僕は、灼熱の風が吹いた時でも大丈夫なようにと、なるべく低い土地を選んで歩いた。
これまで誰も知らなかった水の民の生活、習慣。
僕はそれらをまとめたのだ。
中でも、水の民が本当は地の民を殺したくないと思っていること。
地の民が大好きで、七日に一回くらいは陰から覗き見をしているということ。
これら二つの情報は、地の民の社会全体に衝撃を与えるはずだ。
三日かけて街へたどり着いた僕は、真っ直ぐに出版社へ向かった。
受付の人に話をして、知り合いの編集者を呼んでもらうようにお願いをする。
しかしその名前を出すと、「申し訳ございません」と謝られた。
「実は彼なのですが、寿命を迎えたようで、赤熱の大海へと向かってしまい……」
「……ああ、そうでしたか」
地の民には良くあることだ。僕は仕方がないとすぐに割り切った。
「では、代わりとなる編集の方はおりますか?」
「現在、色々と立て込んでおりまして……」
受付の人は手元のお皿に載っていたコロモイを食べながら予定表を眺め、「二つ目の月が昇り始める頃にでしたら、一人、お会いできる者がおりますが」と言った。
「そうですか……」
それは僕にとって、時間的にはかなり厳しかった。
街へ向かっている間は天候も良く、灼熱の風の回数も少なかったので三日間でたどり着くことができたけれど、帰りも同じだとは限らない。
水の民であるミリスは、七日に一回くらいは地の民を見たいという衝動に突き動かされる。
そうなる前に帰らないと、ミリスが地の民を見たいという欲求を我慢できなくなり、結果的に誰かを殺してしまうかもしれないのだ。
だから僕は早く帰る必要があったのである。
約束の時間に出版社行くと、女性の編集者が僕を待っていた。
「リルルと申します」
握手を求められる。
気さくな感じの人だった。
地の民にしては、かなりスタイルが良くて可愛い。
だけど水の民とは比ぶべくもない。
やはり美しさという点においては、水の民の方が圧倒的に優れている。
リルルはレストランを予約していてくれていた。
色々な雑談を交えながら僕との打ち合わせをしたかったのだろう。
本来ならば僕も、そちらの方がやりやすい。
でも急がなければならない現状、何とかお願いをして、応接室でコロモイを食べながら、急いで話し合いをさせてもらうことにした。
さっそく原稿を渡す。
それからすぐに、僕が水の民と一緒に生活をしていることを伝えた。
「――それは本当ですか?!」
リルルが驚きつつも訝しむような目を向けてくる。
無理もない。
水の民は地の民を見ると、必ず殺そうとしてくるもの。そう決まっているのだから。
天敵とも言える水の民と一緒にいるのに生きていること自体、あり得ないくらいの奇蹟なのである。
話を信用してもらえないだろうという覚悟は、最初からできていた。
それでも僕はなんとか信じてもらうため、原稿にも書いてある水の民の情報を、根気強く説明した。
やがて熱意が伝わったのか、相変わらず疑っているような気配は残っていたが、「わかりました」とリルルはうなずいた。
「レルフさんの原稿ですが、当社から出版させていただく方向で検討はいたします」
「本当ですか?」
「まあ、最終的には出版会議の結果次第ですが、わたしが頑張ってみますよ」
「ありがとうございます!」
僕は深々と頭を下げた。
たとえトンデモ本的な扱いをされるのだとしても、僕の記録が書籍として残るのはありがたかった。
最初は信用されなくてもいい。
いずれは本当であることが証明されるはずだ。
だって、僕は事実しか記録していないのだから。
その時に僕が生きているかどうかはわからない。
いや、たぶん死んでいるだろう。
それでも先駆者として後世の人達に名前が伝わるのかと思うと、少しだけ誇らしかった。
何はともあれ、こうして僕は原稿料の代わりに受け取った大量のコロモイを背負い鞄に詰め込み、帰路に就いたのである。
創作活動にもっと集中していくための応援、どうぞよろしくお願いいたします😌💦