三浦大知『球体』
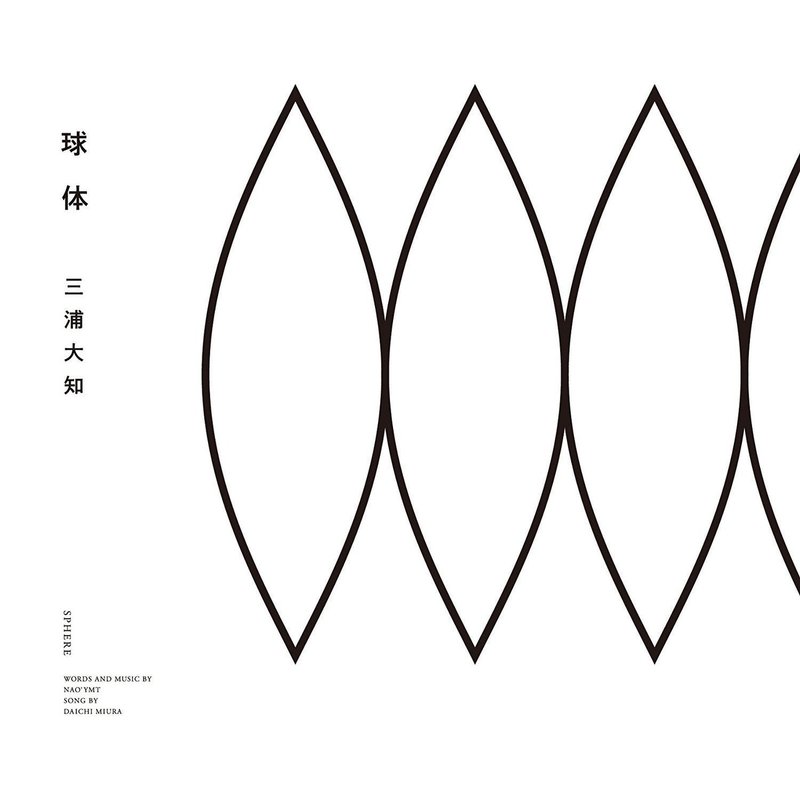
去年はシングル“EXCITE”で初のチャート1位を獲得するなど、ようやく正当に評価されはじめた三浦大知が、ニュー・アルバム『球体』を完成させた。これまでもたびたびコラボを重ねてきたNao'ymt(ナオ'ワイエムティー)が全面的に作詞・作曲・編曲・プロデュースで参加した本作の始まりは、今年の5月から6月にかけておこなわれた同名のツアーだった。三浦自身が演出、構成、振付を手がけたそれは、ひとりの男によって時空を越えた17の物語が描かれるという壮大なドラマだ。これらの物語は連鎖し、最終的には“おかえり”という言葉にたどり着き、そこからまた始まる。
この構成は輪廻を想起させるが、それはこれまでも多くの表現者がモチーフにしてきたものでもある。大今良時の漫画『不滅のあなたへ』は、不死身の主人公・フシがさまざまな物の特性や記憶を受け継ぎ、長い時を生きていくという作品だし、時代が異なる複数の物語が絡み合っていく点は、デイヴィッド・ミッチェルの小説『クラウド・アトラス』的とも言える。
そうした連想の中で筆者がもっともピンときたのは、ヴァージニア・ウルフの『オーランドー』だ。1928年に出版されたこの小説の主人公は、不老不死のオーランドー。青年貴族であるオーランドーは、世紀を跨いで生きるなかで幾多の恋をし、さらには突如男性から女性になるなど、並の人間では得られない多くの想いや記憶を抱える。オーランドーは、時代ごとに得た感情や記憶を『The Oak Tree』という詩集に込めた。制作期間が数世紀にも及んだこれは賞を獲得し、女性となったオーランドーに名声と安定した生活をもたらした。
このようなオーランドーの人生と、時空を越えた17の物語を紡ぐ本作での三浦は、どこか重なる。本作には“「球体」独演”という撮りおろしの映像を収録したディスクも付属するが、そこに映る三浦は物理法則の鎖から解放されたと思わせるほど自由に踊り、『球体』の世界を全身で表現する。変瞼のごとく体の表情を変え、物語を紡いでいくその様は、同じく姿を変えながら生き、詩を書きあげたオーランドーのようである。
こうした古典的とも言える構成が際立つ本作が素晴らしいのは、そこへ多面的に解釈できるキャンバスを置くことに成功しているからだ。たとえば、時空を越えた17の物語が折り重なっていく構成は、表現者としての三浦が築いてきた歴史とシンクロする。『ミュージック・マガジン』2018年3月号のインタヴューでも、「僕はすごく周りに恵まれていて」と語るように、三浦は多くの出逢いから刺激を受け、表現者としての独創性に磨きをかけてきた。影響源となった音楽やアーティストを隠さず、そのうえで自分にしかできない作品を生みだしてきたのだ。これを本作の内容に言いかえると、17の物語はこれまで交流してきた人たちの表象であり、その物語が交わりひとつになっていく流れは、多くの支えもあって活動してきた三浦自身の歩みともとらえられる。もちろん17の物語を紡ぐひとりの男は、三浦大知その人だ。受け手の想像や解釈を受け入れる余白が多い本作の裏に、三浦のパーソナルな想いを見いだす者も少なくないだろう。
現在の聴環境と共振できるのも、本作の面白いところだ。レーベルJazz Re:freshedの設立者アダム・モーゼスいわく、現在はシャッフル・ジェネレーションの時代だという。Spotifyなどが象徴するプレイリスト的な聴き方は一般的になり、ゆえにジャンルの境界線が明確でなく、さまざまなサウンドに自然と触れてきた世代が現在の音楽シーンを牽引している。この視点に立つと、本作のサウンドはシャッフル・ジェネレーション的とも言えるだろう。アンビエントに通じる繊細な音像に幽玄なピアノが交わる“序詞”を筆頭に、2:06あたりでSH-101のようなシンセ・ベースが飛びだすエレ・ポップ“円環”、トランシーなグルーヴとアコースティック・ギターの絡みがロバート・マイルズ“Children”を彷彿させる“硝子壜”など、そのサウンドは多彩を極めている。そこにジャンルの境界線はもちろんのこと、時代や国といった壁も存在しない。この特色が、面白いものは何でも聴くという三浦の感性と共通するように聞こえるのも興味深い。
なかでも耳を惹かれた曲は“硝子壜”だ。トランス的な浮遊感のあるシンセとイーブン・キックの組み合わせは、安室奈美恵やD&Dといった90年代のJ-POPにおけるユーロビートブーム的なベタさも一瞬頭によぎるものだが、そこに三浦の繊細かつレンジの広い歌いまわしと、ウィークエンドやフランク・オーシャンを彷彿させるメランコリックなコーラスなどが加わることでモダンな響きも獲得している。この絶妙なバランスを保つプロダクションは見事という他ない。
本作は、J-POPのど真ん中だけを通ってきた者はもちろんのこと、J-POPをバカにし、アングラやインディーという名のぬるま湯でふやけてしまったエリート主義的な者も辿り着けない、いわばJ-POPの王道を通過したからこそ到達できたオルタナティヴの境地にある。それを象徴する曲こそ“硝子壜”だ。
全編日本語の歌詞も見逃せない。すべてNao'ymtが書いたこともあり、彼の特徴である文学的で奥ゆかしい言葉選びが前面に出ている。〈夢をほどく(u) 踏む茨(a) それとも遠く(u) ふたりなら(a)〉(“淡水魚”)といった、規則性がある母音使いも際立つ。こうした日本語の特性を活かした歌詞は、多彩なサウンドをまとめる一定のグルーヴをもたらし、壮大な物語に一本の線を通している。もしNao'ymtによる歌詞がなければ、本作は多彩なサウンドが特徴の良盤という佳作レベルのアルバムになっていたかもしれない。
あらゆる面で質の高さを見せる『球体』は、ある種の問いかけを孕んだ作品だ。膨大な量の情報が行き交う現代に生きていれば、憎しみを隠さない者たちが世界中で闊歩し、それによる分断も至るところで見られるようになった現実は嫌でも実感する。そうした現在において、多くの者が未来を見ることに絶望してしまうのも無理はないだろう。だが、それでも本作は、〈めくる頁の先を信じたい 疑うことは誰にでもできる〉(“対岸の掟”)と祈るように歌い、〈支え合って 愛し合って それは未来へ〉(“世界”)というまっすぐな言葉を紡ぎ、未来への信頼を示す。“朝が来るのではなく、夜が明けるだけ”は物哀しさを漂わせるが、それでも汽笛は鳴り響き、始まりは繰りかえすのだ。そんな未来に対する希望で満ちあふれる『球体』は、私たちの世界にどのような波紋をもたらすのだろうか。
サポートよろしくお願いいたします。
