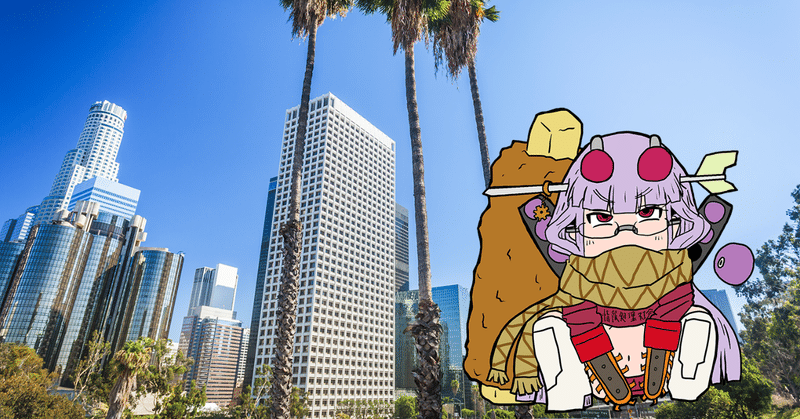
マシーナリーとも子ALPHA 白昼のUFO篇
都内の某テレビスタジオでは白熱した議論が行われていた。テーブルには5名の人類が腰掛けており、中心に座るのは司会進行を務めるベテランアナウンサー。残りの4人はそれぞれが類い稀ない知識と知恵を持つ学者である。彼らの背後にはVTRやプレゼン用資料を映し、視聴者に見せながら番組を進行するための巨大ディスプレイが置かれている。出演者の手元にはタブレットが置かれ、巨大ディスプレイと映像が同期されている。これのおかげでいちいち背後のディスプレイを振り返ったりせずにスムーズに番組が進行できるという仕組みだ。
そしてその画面にいま映されているのは……アメリカの空を飛ぶ、謎の飛行体だった! その表面はツルリとして凹凸がほとんどなく、ボールのようだった。
「これは2018年の12月にサンフランシスコで撮影されたものです。多くの市民に目撃・撮影され、SNSを賑わせました。これほど多くの人間に同時にUFOが目撃された例はとても珍しい」
UFO研究家の安藤氏が落ち着いた口調で、しかし情熱を込めて話す。それに突っかかるのはUFO慎重派の宇宙研究家、丹羽氏であった。
「安藤さん。昨今、なぜこの番組のような幽霊、超常現象、宇宙人を取り扱ったテレビ番組が激減したのかおわかりですか?」
安藤は非常に穏やかな男である。滅多に感情を表に出すことはなく、物腰柔らかで、誰に対しても優しく、仙人のように柔和に接し、周りの人間はそんな安藤をグランドファーザーとあだ名して慕った。まるで泣き言に相槌を打ちながらお小遣いをくれる、優しいお爺ちゃんのような親しみを感じるというのがその由来だった。
が、そんな安藤がこのときばかりは自分の額に血管が浮き上がるのを覚えた。私にそれを言わせるのか……。安藤は胸がグチャグチャに掻き乱されるような錯覚を覚え、思わず胸骨に左腕を添えた。
「……あなたの言いたいことはわかります。私なりの見解もあります。ですがまずは自らの口で語ってみてはいかがか、丹羽さん」
「ではお答えいたしましょう。この20年でパーソナルコンピューターは非常に発達しました。DTPの技術が普及し、プロが使う画像加工ソフトが一般層にも普及しました。それにスマートフォンの急速な浸透も忘れてはならない。いまでは写真を撮影し、加工し、インターネットにアップロードするのは写真趣味を持つ人間だけが行う凝り性な趣味ではない。朝起きて歯を磨くくらい一般的なことなのです」
「では、あなたはこう言いたいのですかな?」
安藤は気づかないうちに机に向けて手のひらを付き、這うような体勢で身を乗り出していた。
「この、カルフォルニアで撮影されたUFO群の撮影はフェイク写真だと!」
「自明ですな。敢えて言いましょう。こんな写真は私でも作ることができる!」
グヌヌヌ……と安藤は喉を鳴らした。だがこんな反論は当然想定している。丹羽が言うようなオカルト番組が放映されない理由など、こちとら百も承知なのだ。事実、安藤自体もここ数年のフェイク写真の品質向上に悩まされていた。だが今回は違う……違うのだ。安藤には確信があった。
「スタッフさん、次の写真を写してください」
安藤の指示でディスプレイの写真が入れ替わる……そこに写ったのは同様のUFO群。だが写された角度が違う。撮影している場所が違う!
「次の写真を」
またディスプレイの写真が入れ替わる……写っているのはやはりUFO群! だがこれまでの2枚と異なる点は撮影場所がビルの屋上だということだ。写真は、ビルの中腹を飛ぶUFO群を真上から捉えていた。出演者のみならずスタッフ達からもおぉ……と声が漏れる。
「このようにさまざまな場所からUFOを撮影して写真が数十枚投稿されています」
ディスプレイにぽぽぽぽ……とタイルのように無数の写真が表示される。その数は数十と言わず100を超えているように見えた。
スタジオ内がざわ……ざわ……と喧騒に包まれる。だが討論相手の丹羽は不敵な笑みをニヤニヤと浮かべていた。
「安藤さん……私はあなたが羨ましい。いや、本当にあなたのようになりたい、替わってあげたいと思うよ。あなたの人生は私のような聡明な人間の人生より数倍豊かだろうからね」
「……なにが言いたいのですかな丹羽さん」
「私に言わせればこの無数の写真はすべてフェイクだ。その作り方も検討がつく。加えて言うなら、私はこの無数の写真がSNSに投稿される現象の巻き起こしかたについて2つの方法を思いついたよ」
「なんだと!?」
安藤は思わず声を大きくしてしまった。揺るぎない証拠となるはずだったこの写真がフェイク、しかも方法がふた通りあるだって……?
「聞かせてもらおうじゃないか丹羽さん。その方法を」
「ひとつはこの写真の撮影者を騙すというやり方だ。先ほどパソコンやスマートフォンの普及について話したが……いまはこんなものもあるよね」
丹羽が懐から小さな機械を取り出しスイッチを入れる。すると機械の四方に伸びたプロペラが回りだし、浮いた……。ジャイロコプター……ドローンだ!
「バカな! 君も見ただろう。写真のUFOは表面が下から見ても上から見てもツルっと滑らかだ。ドローンであるはずがない」
「例えばだ。細かいネットでドローンを覆ったとしたら……? 推進力は失わず、スマートフォンのカメラではネットの網目を確認できないのではないか?」
「推論だ、推論に過ぎない!」
「すべては推論だよドクター安藤……。推論を研ぎ澄まし、真実を究明するのが科学だ。君がこの写真に写っているのが未知なる飛行体だというのも推論に過ぎないだろう」
「グムーッ」
安藤は唸った。言い返せない……。確かにあのUFO自体が人為的なフェイクという可能性は残されている。数十年前とは人類のテクノロジーのレベルが違うのだ。
「もうひとつの方法は、この投稿しているアカウントすべてがフェイクという可能性だ。さまざまなシチュエーションの画像を作り、不特定多数のアカウントに与える。金を払ってね。後は予定通りの時間に同時多発的に投稿してもらう。するとネットリテラシーの低い人間は、これが仕組まれたフェイクニュースだと気づかずに本物のUFOだ! と騒ぎ立てるわけだ……あなたのようにね」
「なにーっ!」
「BUZZの界隈ではよくある、ありふれた手法ですよ。つまりこんな写真はなんの証拠にもならないんです」
「グヌヌ、丹羽!貴様ーっ!」
穏和な安藤が丹羽に摑みかかる!
「ギャーッ! バカ! 安藤のバカ! 宇宙人なんかいるわけがないんだ! 私は宇宙科学者だぞ! ギャーッ!」
「おい! カメラ止めろ!」
司会進行のアナウンサーが冷や汗をかきながら指示を出す。そのとき、スタジオに澄んだ声が響いた。
「私は第3の説を提唱する」
その瞬間、スタジオの喧騒がスン……と止んだ。
慌てていたスタッフも、アナウンサーも、大喧嘩をしていたふたりの科学者も手を止め、声のする方を見た。
「このUFOは宇宙人の円盤ではない。ましてや、人類に仕組まれたフェイクニュースでもない」
アナウンサーはメガネを直しながら司会進行らしく問いかける。
「で、では……この円盤をなんだと思われますか。ドクターココス」
ココスと呼ばれた科学者がヒゲを弄びながら、雄々しく応えた。
「この円盤は……サイボーグの仕業だよ諸君」
***
「まったく無礼な連中だ!」
控え室でココスはパイプをふかしながら周囲に当たり散らしていた。UFOはサイボーグの仕業という彼の説は一笑に付され、カッとなった彼はスタジオで大暴れを始めた。その結果番組半ばで警備員につまみ出されてしまったのだ。
「あぁー、せっかく各所に頭を下げて出演させてもらったのに……これじゃあオンエアできませんよドクター」
傍らで頭を抱えるのはドクターココスとコンビで雑誌や書籍の編集をしているヨシズミだ。今日は彼らがなんとか出版にこぎつけた古代サイボーグ文明本第2巻の宣伝も兼ねての出演だった。だがこのぶんではココスの登場シーンは全カットだろう。完全な無駄足だった。
「うるさい! 私の学説をジョークかなんかだと思い込むような奴らとテレビに出れるか! クソッ!」
ココスは吸っていたパイプを床に叩きつけた。怒りが収まらない! なんで宇宙人はいると信じ込んでる奴らがサイボーグは信じないんだ!
「あんな奴らサイボーグに殺されちまえばいいんだ!」
「またそんなこと言って……」
「フン、スタッフが詫びに来たりもせんのか!おもしろくない。帰るぞヨシズミ君!」
「え、あ、待ってくださいよドクター!」
***
「いやはや、ドクターココスには参りましたね。サイボーグとは……」
「ああも血走った目でサイボーグ説を主張された後だと安藤さんの宇宙人説もあながち否定できなくなってしまいますね」
「ははは、調子がいい方ですな丹羽さん」
「はは……いえいえ、私もさっきは熱くなりすぎました。宇宙人説を肯定するわけではないが、お互い建設的な議論を交わして真相を究明しようではありませんか……」
「丹羽さん……」
憎み合っていた安藤と丹羽が固く握手する。UFOが結びつけた友情だ! 司会進行は目元をハンカチで拭った。
そのときである!
スタジオの扉がバンと開き、不快なモーター音が轟いた! そこに現れた人影は頭や背中のあたりから何かが伸びる奇怪なシルエットをしていた……逆光でよく見えない!
「なんだ!?」
「あー! ちょっと!音が入っちゃうよ! 止めて止めて!」
入ってきた人影にADが走り寄る。だが次の瞬間、ADは縦半分にスライスされていた。少し遅れて血が噴水のように噴き出す!
「うわーーーーーーっ!!!!!!!!」
「ギャーーーーーーーーーッッ!!!!!!!!!!」
スタジオ内が恐慌に陥る! 演者と司会者は突然の惨劇に金縛りにあったように動けないでいた。一体なにが起こっているのだ!? 充分な照明で照らされているセットの中からは、暗くなっているスタジオ作業部の様子がよくわからない! 伝わってくるのは悲鳴、肉が切り裂かれる音、謎の轟音! そしてなによりも恐ろしいのはだんだん悲鳴が小さくなっていくこと……。悲鳴をあげる人数が少なくなっているのだ!
「な、なにが……なにが起こっているんだ……」
安藤はガタガタ震えながら、ようやく困惑の言葉を喉からひり出すことができた。スタジオの悲鳴が止み、不快な轟音だけが残った。轟音は蠢く影とともに近寄ってくる。
「い、一体なんなんだ。シリアルキラーか? 宇宙人か? それともまさか……ハハハ、サイボーグだったりして」
「そうだぞ」
闇から返事が返ってくる。丹羽は恐怖のあまり軽口を叩いたことを後悔した。蠢く影が、セットの豊かな照明にあたりその姿を明らかにする。
紫色に輝く腰まで伸びた髪、同じく長く垂らしたマフラー。頭からはキャンディーのような球状のユニットが細長いロッドを介して伸びている。そして腕からは不快な轟音の元となる凶悪なダブル・チェーンソーを備えていた。どう見ても人間でも、ましてや宇宙人でもない!その機械的姿は……!読者のみなさんはもうお判りだろう。シンギュラリティ最強のサイボーグ……!
「ネットリテラシーたか子です。あなたね。私のファンネルを全国放送しようとした愚かな人類は」
「えっ……へっ……?」
その間抜けな声が、安藤が最期に発した言葉となった。
***
「もぉ〜ドクターなにやってんスか。パイプを忘れるなんて!」
「仕方ないだろ! カッとなって投げてしまったんだ」
「物に当たるのやめたほうがいいですよ。えらい学者さんなんだから……」
「うるさい! 偉かったら物に当たってはいけないと誰が決めた? 女王陛下か? とにかく控え室にあるはずだ……」
忘れ物をしてしまったココスとヨシズミがスタジオの扉を開ける。
一瞬、違和感を感じた。すごく鉄くさい臭いがする……。いったいなぜ?
足を踏み入れると鉄くさいのに収まらない、吐き気を催すほどの異臭が漂ってた。明かりが灯っているセットを見ると、血しぶきがバケツをひっくり返したように広がり、生気を感じられない演者たちが倒れ込んでいた。
「エッ……これは!?」
ヨシズミが慄いて後ずさる。すると足元に転がっている異物に脚を取られ、転びかけた。なんだこれは……と屈んで暗闇を凝視すると、それは柔らかいロープのようなものだった。なんでこんなものが……? 正体を確かめようとしばらくロープを睨みつける。が、ふとそのロープの正体に気付いた時、彼は叫び声をあげそうになった。これは人間の腸だ!
目が暗闇に慣れてくる。あたり一面に十数人の惨殺死体が転がっていた。ヨシズミは恐怖で気が狂いそうになる。だが、彼を狂気から救ったのは相棒であるドクターココスの奇行であった。ココスは、両断されたスタッフたちの死体を持ち上げ、その断面を観察しているのだ! なにをやってるんだこのオッさんは!
「ドクター! ダメですよ死体を弄っちゃあ!」
「むぅー! 見たまえヨシズミくん!この断面を!」
「見たかないですよ。恐ろしすぎます! 逃げましょう、警察を呼びましょう」
「これはチェーンソーの跡だ! それも2枚の刃が並行に重なったタイプの凶悪なものだ!」
「凶器にチェーンソーを使ったんですか? まるでレザーフェイスですね。恐ろしい……。まだ犯人が近くにいるかもしれませんよ。逃げましょう」
「違うんだよヨシズミくん。チェーンソーだが奇妙なんだ。断面がキレイすぎるんだ」
「キレイすぎる?」
「チェーンソーってのは……木を切るための道具だろう? だから人体の破壊に使ったら……こう、肉や皮が引っ張られてズタズタに切り裂かれるはずなんだよ。でもここに転がっていいる死体は……どう思うね?」
「見たくないです。ドクターの見立てだけ教えてください」
「まるで研ぎたての包丁で切った根菜みたいにキレイな切り口なんだ!こんなことは通常あり得ない。私は興奮してきたぞヨシズミ君! 我々は自分たちで思っている以上に答えに辿り着いているのかもしれない!」
「一体なんだっていうんです?」
「この大量殺人事件の犯人は……サイボーグだ!!」
***
読んだ人は気が向いたら「100円くらいの価値はあったな」「この1000円で昼飯でも食いな」てきにおひねりをくれるとよろこびます
