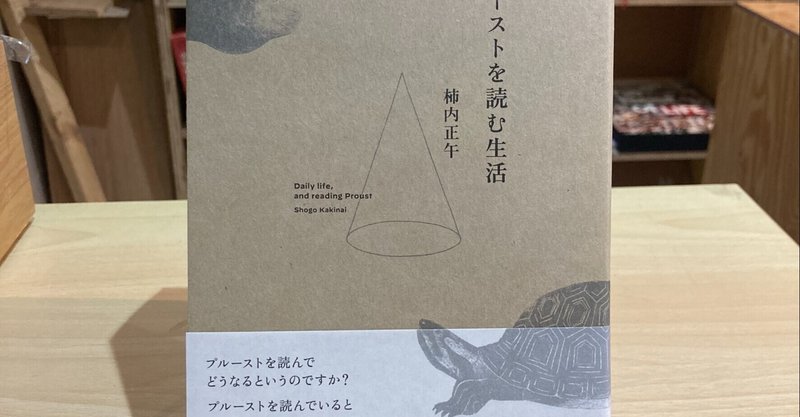
連載「プルーストを読む生活」を読む生活⑦
”Seems the wisdom of man hasn't get much wiser
Than the very beginning of the time"
Stevie Wonder "Feeding Off the Love of the Land"
2017年に亡くなったナット・ヘントフの2004年の著作「消えゆく自由」("The War on the Bill of Rights")は、9.11テロをきっかけに、愛国の名の下、自由を縛ろうとする動きが顕著になりつつあったアメリカ社会に対する異議申し立てであった。
時に「気骨の評論家」などと評される彼はまた、児童文学作家でもあった。
「誰だ ハックにいちゃもんつけるのは」(原題 "The Day They Came to Arrest the Book")
発表されたのが1983年。
タイトルにある「ハック」は言わずと知れたマーク・トゥエインの名作、「ハックルベリー・フィンの冒険」のこと。同作中で黒人に対して侮蔑的な表現が使われていることに対して腹を立てた大人が、自分の子どもが通う学校の図書館にたいして、この「ハックルベリー・フィンの冒険」を図書館に置かないように抗議をする、という出来事がこの本のモチーフとなっている。
最近の風潮に照らせば彼のような書き手はむしろ、マーク・トゥエインの原作中の黒人差別的な表現を告発する立場にあるのかもしれない。
にもかかわらず彼は、その作品を図書館から取り除こうとする大人たちに対する、批判的な視線で「誰だハックに――」を世に問うている。
彼のこういった姿勢を矛盾していると取るか、一貫していると取るかはそれぞれあるだろう。
私自身、彼のこういった姿勢は「間違ったものは間違っている」という極めてシンプルなもので、なんの矛盾も感じない。むしろ「こういうことを言った人は、このことに関してもこう考えるはずだ」という決めつけや、人に対してポジショントークを求めがちな昨今の風潮に、強い違和感を覚える。
ここで私が「誰だハックに――」を引き合いに出したのにはもう一つ理由がある。
私は、大学卒業も間もないころ履修していた図書館司書課程において、この「誰だハックに――」を課題図書として読んだ。
「図書館の自由に関する宣言」というものをご存じだろうか。
図書館にかかわったことのない人にとってはなじみがないかもしれないが、図書館司書にとってこの宣言は金科玉条である。
看護師にとっての「ナイチンゲール誓詞」、医療に携わる人々にとっての「ヒポクラテスの誓い」みたいなものと思って間違いない。
この宣言は戦中、図書館が思想善導機関として機能してしまっていたことへの反省からうまれた。その宣言の第一項目が「図書館は資料収集の自由を有する」というものだ。
この「資料収集の自由」は、第二項目の「資料提供の自由」をもって、利用者の「知る権利」を保証するためのものであり、その知る権利を行使し個人がどんな本を読む(読んだ)かということは、全きその個人のプライバシーとして守られるべきであり(第三項目「図書館は読者の秘密を守る」)、「知る権利」に立脚した民主主義を毀損するものとしての「検閲」に、図書館は断固として反対する(第四項目「図書館はすべての検閲に反対する」)というものである。
資料収集の自由を実現するため、第一項目の細目には「個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない」と定められている。
つまり保護者からの抗議に屈して「ハックルベリーフィンの冒険」を図書館から撤去することは、このポリシーに反するというわけだ。
先にあげたヘントフの著書が、図書館司書課程の課題図書として挙げられいた理由は、先人の努力によって獲得されたこの資料収集の自由の大切さ、ひいては「図書館の自由」の重要性を学生たちに教えるためだった。
そのような教育を受けたものにとって、いうまでもなくこの本は、図書館に押し掛ける大人たちに対して批判的な立場から書かれているものとして受け取られる。しかし中にはそう思わなかった人もいるかもしれない。
思えなかった人も無理はないと思う。
なぜなら現代では、ポリコレの名の下、この物語の大人たちがしていることのほうがスタンダードになりつつあるから。
ポリコレの正式名称であるポリティカル・コレクトネス(political correctness 政治的正しさ)は、その昔、笑いのネタだった、といえばさらに信じられない人もいるかもしれない。
まあ、今でも笑いのネタにしている人もいるが。
「政治的に正しいおとぎ話」は1995年にデーヴ・スペクターの翻訳で出版されたジェームズ・フィン・ガーナーの著作で、ご存じの方も多いだろう。
内容は、「赤ずきんちゃん」や「白雪姫と七人のこびと」を、ポリコレに照らして問題のない表現のみを使い(そして言うまでもなくそのことがいかにバカバカしいかを示すため)書かれた、昔話のパロディー集である。
もちろん当時も、このガーナーの著作に対する批判もあったかもしれない。ただ支持するにせよ批判するにせよ、当時は両方の意見がちゃんと世の中にあって、意見を戦わし、健全な議論が成り立つ余地があったように思う。
少なくとも、「この本はけしからん!」という抗議が殺到し、本が出版中止に追いやられた、とか著者がその職を追われたなどということがあった、なんてことは寡聞にしてしらない。
ガーナーの本から20年以上たった現在はどうかというと、近年ではアメリカで、児童文学作家ドクター・スースの作品が絶版に追い込まれている。
日本においても過去、「ちびくろサンボ」や「ピノキオ」が不当に扱われ、先人たちの努力でその汚名は返上されたが、歴史はまた繰り返されてしまうのか。
「誰だ ハックにいちゃもんつけるのは」が発表された1983年。
そこから人類は少しは賢くなれているのだろうか。私の感想は、冒頭に引用したスティーヴィー・ワンダーの歌から引いたとおりだ。
「人類は地上に生まれてから
そんなに賢くなってないんじゃないかな」(筆者訳)
最後にもう一冊、ヘントフの著作の名前を出しておこう。
”Free Speech for Me Not for Thee"( Harper Collins, 1992)
アマゾンの解説によると、この本の基本的な考え方は、合衆国憲法修正第1条で保障される言論の自由は、「たとえ嫌悪感を催す考え方の持ち主であっても」すべてのアメリカ国民に与えられるものである、というものだ。
そしてこの本の内容はそのサブタイトルにあるように、左翼と右翼がいかに互いを検閲しあっているかについての事例集であるが、日本語版のないこの本のタイトルをあえて訳すなら「都合のいい言論の自由」。
検閲の愚かしさについて人々は充分に学んだはずと私は思っていたが、残念ながらそれは楽観的に過ぎた考えなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
