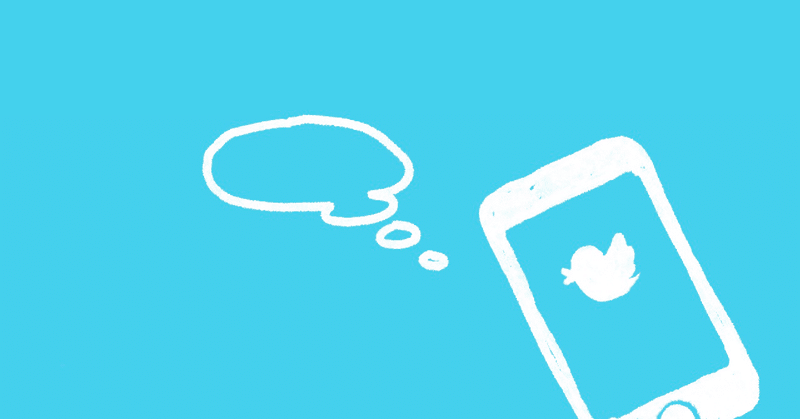
熱病と臆病③
ホームルームで校内新聞が配布されたのは水曜の終礼だった。陸上部の県大会入賞は夕真が思っていた以上の快挙だったらしく、その立役者である喜久井の写真が新聞には大きく使われていた。無論それは、夕真の撮ったあの写真だ。
「──お兄ちゃん、本気出し過ぎ。意味分かんないんだけど」
「は?」
塾から帰ってきたあとの遅い夕食中。まひるから予想外のクレームを受け取り、夕真は眉を寄せた。
「意味がわからないのは今のお前の言い分なんだが?」
「だってお兄ちゃんがあんな写真撮るから、みんな重陽先輩がカッコいいことに気付いちゃったじゃん!」
「ああ、そういうこと」
理不尽なクレームだが、聞いてみればその理屈も分からないではない。
「なにお前、喜久井のこと好きだったの?」
「そういうんじゃないけど」
と早口で言いながら、まひるは憤然として夕真の向かいの椅子を引く。
「普段はおちゃらけてるけど、いざって時はカッコいいっていうギャップをさ。知ってるのはウチら陸部だけだったのにさ。ああやってみんなのものになっちゃったらつまんないもん」
そう言ってまひるは口を尖らせ、無邪気にぼやいた。その言葉は「走ってる間だけが楽しい。あとは全部苦しい」と言った喜久井の内心と大きく剥離していて、さすがに少し同情する。
「……そういうの、どうかと思うよ。そもそも喜久井は誰のものでもないだろ」
「そんなこと分かってるよ。でも、いいじゃん。見てるだけだもん。お兄ちゃんだって部活で運動部の写真撮りに来て、別にいちいち許可とか取らないでしょ。勝手にイイ感じの構図とか表情とか狙って写真撮るでしょ?」
微妙に論点が違う気もしたが、それに関してはぐうの音も出ない。
「でもまひる。それってやっぱり好きなんじゃない? お母さんはそう思う。ほかの子に取られるのがイヤなんだなーって。それってきっと好きってことだよ」
リビングで風呂敷残業に勤しんでいた母も、眼鏡の奥の目を光らせながら話に割って入ってきた。
「喜久井くん、確かに結構カッコいいもんねえ。ちょっとルパート・グリントに似てる」
「は? 別に似てないんですけど。背なんかあたしより低いし」
「いや、俺も似てると思う。ハリーポッターの最初の頃のルパート・グリントに似てる」
「似てないってば! それに本当に別に好きとかじゃないし!」
二対一で形勢不利と見るや否や、まひるはそんな捨て台詞を吐いて自分の部屋へ引っ込んでいく。
「……あれは“好き”だよねえ。夕真」
母は臍を曲げたまひるの背中を見送ると、にまにま笑いを浮かべながらその視線を夕真に移した。
「さあ。違うって言ってるんだから違うんじゃないの」
「ええっ。なにその掌返し」
確かにその話へ水を向けたのは自分に違いないし、まひるのクレームも理不尽だとは思う。けれど、かと言って同じ論調で一緒になってからかう気にはなれない。
「別に掌返しはしてない。ルパート・グリントには似てると思うけど、本人が好きじゃないって言ってるんだからきっと違うんでしょ」
なので実に腑に落ちないという顔で「えー」と首を傾げている母を横目に、皿を洗って夕真も二階の自室に引き上げた。
鞄から塾のテキストを出して机に並べ、けれどもなんとなくやる気が湧かず、ベッドの上に体を投げ出し意味もなくSNSのアプリを開く。青い鳥のミニブログでは、同じようにぐだぐだとアプリを開いてしまったらしい他校の写真部仲間が「模試の結果詰んでる」とぼやいている。
夕真のタイムラインは似たような受験の愚痴とゲームのスクリーンショット、それに中古レンズやカメラアクセサリのセール情報ばかりが流れていく。
そして時折、それらを堰き止めるダムのように、アプリは「知り合いかも?」といってお節介にも同じ学校に通っているだけの赤の他人を出してくる。
「うわ……」
その中に喜久井の名前を見つけ、夕真は思わず声を上げた。無視できずにホーム画面まで行ってしまったのはひとえに、自分の撮ったあの写真を喜久井がアイコンに使っていたからだ。
興味本位で書き込みを遡ってみたが、大会への意気込みやレースの結果が投稿されているだけだった。喜久井はあまり日常生活のことは書き込んでいないようだ。
にも関わらず同じ学校に通う生徒からのフォローがたくさんあったようで、最新のポストで喜久井は「みんなフォローありがとね! でも陸上のことしか呟かないから、あんま面白くないかも」と苦笑の絵文字付きで弁解している。
確かにまひるの言う通り、校内新聞によって喜久井は全校的に三枚目から二枚目に「昇格」した印象が夕真にもある。学校を出てくる道すがらグラウンドを覗いたら、陸上部が練習しているあたりのフェンスの外側には小規模ながら人垣ができていた。
もしかして、ちょっと悪いことしちゃったのかも。と一瞬考えてから、夕真はすぐにその考えを打ち消した。
確かにあの写真は渾身の出来ではあったものの、彼を取り巻く状況を変えてしまった原因があの一枚だと思うのはさすがに傲りだろう。写真のあるなしに関わらず、喜久井はあのレースで類稀なる走力を発揮し脚光を浴びたことには変わらないはずだ。
そんなことは分かっている。分かってはいるけれど、調子に乗ってしまう。
同じ部活の後輩に「普段はおちゃらけてる」と言わせた彼が、SNSで遠慮がちに「あんま面白くないかも」と呟いた彼が、きっと夕真にだけ「走ってる間だけが楽しい。あとは全部苦しい」と打ち明けたことについて。
喜久井はまるで悪さが見つかったような、共犯を持ちかけてくるような顔をしていた。
その瞬間に少しだけ、ほんの少しだけ、夕真の心臓はぎゅっと甘い痛みを訴えた。
だからあの時は戸惑いのあまり、間抜けな声で「へえ」としか言えなかった。受験を控えた高三の冬に、兄が妹の憧れの人に横恋慕。なんて、世界一たちの悪い冗談だ。
だからまひるの「別に好きとかじゃないし」という言葉を否定できようもなかったし、母親の「あれは“好き”だよねえ」という言葉にも同調できなかったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
