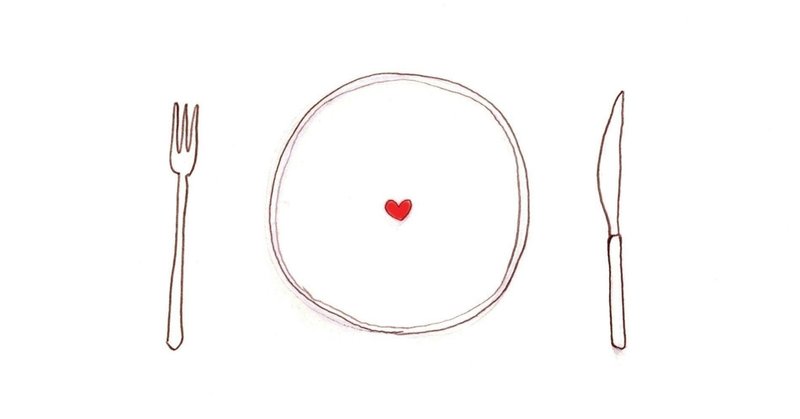
【小説】扉越しに囁いて
朝。ピピピと小さな電子音が聞こえて、枕の横に置いてある携帯の画面を見つめた。5時40分。誰かの目覚まし時計が鳴っているのだ。こんな時間にセットするなんて。
暫くして音が止む。彼女が目を覚ましたらしい。おはよう、と心のなかで呟く。どうせ口にしたところで隣の部屋までは届くまい。
ボクはもう少し眠るよ、いいかな、いいよね、その回答を得られないままに二度寝の誘惑を断ることも出来ずに眠る。次に目が覚めたのはドアを叩く音がしたからだった。
携帯電話を探す。枕の横ではなくボクの背中に押し潰されて、いやぁ、どいてくれるのを今か今かと待っていたんですよ、と言いたげな表情で見つめてくるディスプレイには7時45分とある。2時間も寝ていたのか。
「起きてる?」
「起きてるよ」
「朝食、作ってあるから。私もう出ないとだから」
「ああ。食べたら洗っておくよ」
「お願いね。この前はそう言って朝食、昼食、間食の食器が流し台に置かれたままだったんですけど。こびりついたソースとか見た時にはぞっとしたんですけど」
「大丈夫だって、さっさと会社行けよ」
「言われなくても行くんですけど。あー、在宅勤務っていいわね」
「そういう会社に転職したら?」
「このご時世に転職? 馬鹿なんだから」
その声は本当に馬鹿だと思っている時に出る音としてボクの耳に届いた。別に夫婦関係が破綻しているわけでもないし、ちょっとしたことで喧嘩することはあるし、わけがわからないタイミングで仲直りするわけだから、まだ大丈夫なんだと思っている。いや、二人の関係性のことなんだけれども。
ボクはベッドに体を起こし、寝室の扉の、多分すぐ側にいるであろう妻の顔を思い浮かべた。はてさて、前に彼女を直接見たのは、直接会話をしたのはいつだっただろうか。1週間前? 2週間前?
「あのさ」
「なに?」
ちょっとだけ声が遠くなった。もう出かけるためにカバンを掴み、玄関に向かっているところなのかもしれない。
「いやいい。もう出てもいいかな?」
「駄目よ。何言ってるの。声聞こえてるでしょ。私がここにいるんだから」
「ああ、そうか。いるんだよな、そこに」
「いるよここに」
「帰りにさ、ビール」
一瞬間があり、足音が近づいてくる。彼女の顔を想像する。怪訝そうに扉を見ている彼女の眉間の皺をイメージして笑いそうになる。ボクはその皺が好きだった。もちろんそんなことは本人には言わない。言えるわけがない。きっと彼女自身は嫌いなんだ、その皺が。可愛い顔が台無しとは思わないけど、ちょっと深く、一瞬にして刻まれるその二本の皺。
「ビール? 飲むの?」
「別に優勝したわけじゃないからかけあわないよ。同僚と今度リモート飲み会やろうって約束してて、それが明日の夜なんだよね」
「そのぐらい自分で買いに行けばいいじゃない。出かけちゃ駄目ってわけじゃないんだから」
ボクはやれやれと思いながら首を横に振った。彼女に見えているわけでもないというのに。
「いいかい。ボクは家で仕事をするんだ。これから夜まで。もしかしたら夕方には残業せずに終わるかもしれないんだ。そういうことなんだよ」
再び沈黙、その後にため息が聞こえた気がした。多分気のせいだろう。ドア一枚とは言え、その向こうにいる人間のため息が聞こえてしまうほどに薄い扉じゃ困るじゃないか。
「そういうことなんだよ、って説明できてないからね。わかってる? いやもうわかっているんだけど」
「わかってるんならいいじゃない。え、いや、矛盾してない?」
「してません。普通にめんどくさいって言えばいいのに」
「小声で言ったみたいだけど聞こえてるよ。ほらもうこんな時間だ。バスに乗り遅れるよ」
パタパタと足音が玄関に向かっていく音に耳を澄ませて、ボクは待つ。彼女がちゃんと外へと出ていくのを。スリッパがフローリングを踏む音、履き替える音、彼女の足がすっと靴の中に忍び込む微かな音、カバンを持ち上げる音、カバンを肩にかける音、玄関の鍵を開ける音、ドアノブを回す音、鉄扉が音を立てて開く音、そして一瞬の静寂。ちょっと待つ。まだだ。まだ彼女はそこにいる。静寂は続く。外へと一歩、二歩と歩き出す。廊下の地面、コンクリートを彼女の靴が擦る音がした。こちらを振り返ったのかもしれない。
「行ってきます」
「行ってらっしゃい」
ドアがゆっくりと閉まり、鍵が閉まる音がして、玄関の外、足音が遠ざかっていく。
「行ってらっしゃい」
再び口にしてみる。目を見て、顔を見て、そう言える、言い合える日が来るのはいつのことだろうか。
「行ってきます、行ってらっしゃい」
ビールを買ってくるとは言ってくれなかったことに今思い当たる。これは買いに出かけないといけないかもしれないなと寝起きの頭で考える。洋服を着替えることすら、髭を剃ることすらめんどうな気がしてくる。
ボクは巣穴から抜け出すプレーリードッグのような面持ちで、寝室の扉を開けダイニングテーブルに並ぶ朝食を目にした。キッチン、リビングのソファに目をやるが彼女はいない。今までいて、この朝食を用意してくれていたのを想像する。確かにいるのだ、ここにいるのだ。でも、ボクには、その彼女がとても遠く感じた。まるでいないもののように。ボクの、妄想、幻想かのように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
