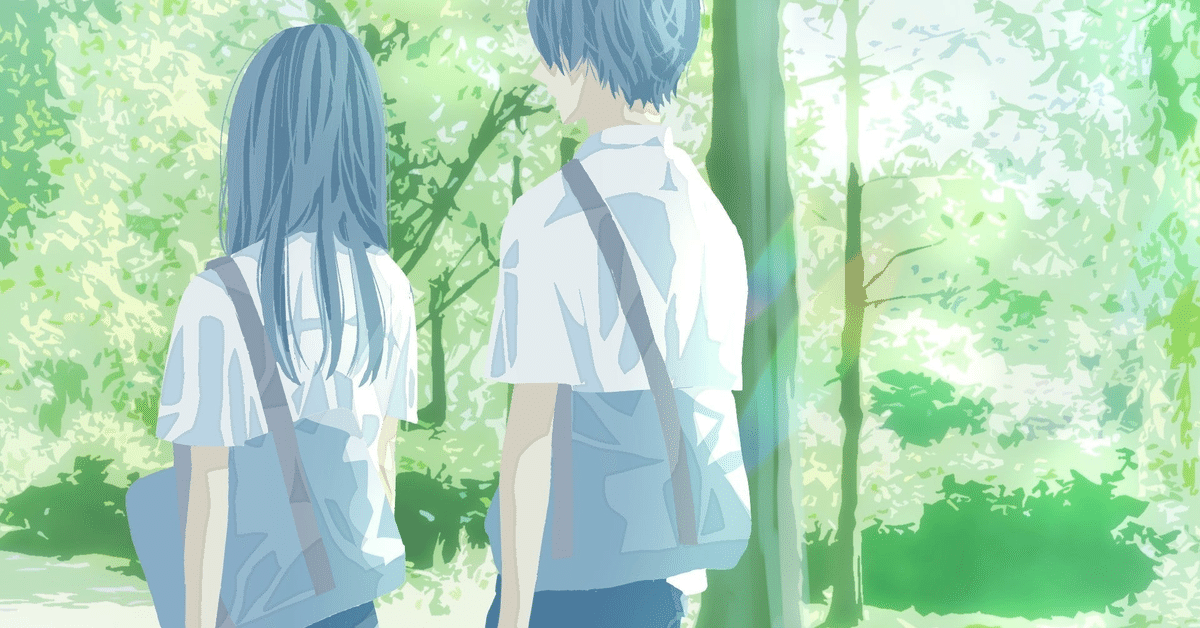
短編小説「君の言葉」
俺の好きな人は親友と付き合っている。
いや正確には親友と付き合っている、時に好きになったしまった。
彼女の真っ直ぐに人を好きになる所に惹かれた。
親友と別れた後も告白は出来ずにいた。
友達の彼女に告白するのは勇気が居る。
彼女の事が好きになってから十年が経った。
そんな彼女が明日結婚する。
過去に戻れたらとも思うが……結局告白出来ずに居ると思う。
明日の彼女の結婚式には、行けそうにはなかった。
もう彼女とも会う事はないだろう。
彼女との初めての出会いは今でも忘れる事は出来ない。
その位彼女が言った、一言が俺の人生を変えたと言っても過言では無い。
だが多分彼女は何も考えずにその一言を言ったと思う。
だからきっとその言葉を彼女は覚えても居ないと思う。
けど……その一言の後とその一言の前では俺の見る景色は変わってしまった。
♢♢♢
彼女との初めての出会いは、高校二年生になったばかりの春頃。
学校が終わり、駅まで着いて俺は携帯を忘れている事に気がついた。
携帯を取りに教室へ戻ると、一人の少女が居た。
黒く透き通る長い髪、肌は白く、儚い美少女を絵に描いたようだった。
俺はこの子の事を知っていた。
親友と最近付き合い始めた女の子。
写真を見せて貰った事があったので顔を覚えていた。
名前迄は流石に覚えていなかった。
「アイツなら今日はサボりだよ」
何も言わず出て行くのも変だと思い、俺は親友の事を伝えた。
「教えてくれてありがとう」
俺は自分の机の中の携帯を取り、立ち去ろうとした時――今度は彼女から話しかけて来た。
「部活とはやらないの?」
この学校は部活動が盛んで大半の生徒が部活に入っている、だから放課後直ぐに帰る生徒は珍しい。
部活の勧誘をされると思った俺は、適当な事を言ってこの場を去ろうと思った。
「努力とかしても虚しいだけなんで」
彼女はその言葉を聞くと悲しそうな顔をした。
「確かに虚しいよね」
想像していた答えと全く違う回答が来て驚いた。
皆否定的な事を言ってくるのに――彼女が肯定的な事を言ってくるなんて……思ってもいなかった俺は不意を突かれた。
「あれ……ごめん」
何故だか涙が止まらなかった。
「大丈夫?」
彼女は心配そうにそう言ってきた。
恥ずかしくなった俺は走って教室を飛び出ていった。
これが彼女との最初の出会いだった。
彼女の結婚式から一年位の時が経ったある日。
家のポストに同窓会の案内が届いていた。
彼女の結婚式以降高校の友達と会うのを避けていてた。
高校の友達に会いたくなって、同窓会へ参加する事にした。
その年の同窓会で聞いた話で俺は後悔した。
しかし人生はやり直す事が出来ない。
俺は後悔を抱きながらも明日も生きていく。
♢♢♢
彼女と次に会ったのは、初めて会った日から一週間経った日の事。
学校が休日で休みだった昼頃、寝ていた時電話が鳴った。
「もしもし暇だろ、俺の家来てくれ」
それだけ言うと切られた。
まだ何も言ってないのだが。
特に何も予定が無かった俺は準備をして向かう事にした。
「よう」
「彼女が居るなら俺呼ぶ必要無いだろ」
親友の家に行くと親友と彼女が居た。
「彼女がお前に会いたいって言うから」
「何か用事でもありました?」
「此間会った時に何か傷つける事を言ってしまったと思い、謝りたくて……」
「いやあの時の事は忘れて下さい」
恥ずかしいから忘れて欲しかった。
「逆なんで嬉しかっただけなんで」
「それなら良かった」
「じゃあ、用も済んだし帰るわ」
「折角来たんだし遊んでけよ」
「邪魔にならないなら、折角だし遊んでいくわ」
俺ら3人はゲームをして遊んだ。
帰りは駅まで親友の彼女と同じ方向で一緒に帰る事になった。
「ごめんね二人の邪魔しちゃって」
「良いよ寧ろ私が呼んだんだし」
今日で仲良くなれてお互い敬語では無くなっていた。
「じゃあここで」
「うん、また学校で」
それからは学校で合っても挨拶する位の仲にはなった。
「久しぶり最近どうよ?」
同窓会の会場に着いて直ぐに親友に声をかけられた。
久しぶりに会っても全然変わってなかった。
「まぁ、ぼちぼちかな」
「そんなもんだよな」
同窓会に行くとこんな感じのやり取りをするのが恒例だ。
「それよりお前なんで来なかったんだよ?」
意味が分からなかった。
「何にだよ?」
「――の葬式にだよ」
頭が真っ白になり理解が追いつかなかった。
「え……」
「お前知らなかったのか?」
「あぁ」
「すまん……抜けて二人で飲みにでも行くか?」
「そうだな」
事情を知りたかった私は親友と二人で飲みへ行く事にした。
♢♢♢
夏休みに入り彼女とオレと親友は三人でよく遊ぶようになっていた。
夏休みになって数日が経ったある日。
俺は担任に呼び出されていた。
「先生、夏休みに呼び出さないで下さいよ」
「私も呼び出したくないから、進路決めてくれ」
俺は進路希望の紙をずっと出していなかった。
正直まだ将来の事を考えたくなかった。
「……分かんないです」
「適当に進学で良いだろ、まだ二年なんだし、お前みたいな奴がいるとこの紙切れにも意味がある気がするよ」
それだと普通は意味が無い事になる、なんだか難しく考えるのも馬鹿らしい気がしてきた。
「何ですかそれ、なら一応進学で」
「はい、はい、気をつけて帰れよ」
用事も終わり、ようやく家へ帰れるようになった。
駅に着くと後ろから声を掛けられた。
「何してるの?」
彼女だった。
「担任に呼び出されて、学校行ってた」
「この後予定ある?」
「特にないけど」
「じゃあ、私に付き合ってよ」
「――の結婚式にも来なかったよな?」
「あぁ行く気になれなくて」
「何回も連絡したんだぞ」
「携帯持って無くて」
皆からの電話が何通も掛かってきて、冷やかしの電話だと思って。
ムカついて海に投げ捨ててしまった。
「結婚式のスピーチはお前に向けた物だったから、皆で電話したんだぞ」
「そうだったのか……ごめん」
「――が好きだったなら、また小説書けよ」
「言ってる意味が分からん」
「俺から言えるのはそれだけだわ」
そう言ってお金だけを置いて出て行った。
♢♢♢
「良いけど、どこ行くの?」
「花火大会」
「彼氏と二人で行きなよ」
「なんか予定あるみたいで断られた」
「彼氏がいる子と二人で花火大会は行けないよ」
「聞いてみて大丈夫だったら良いでしょ」
「まぁ、それなら」
彼女は電話をかけ始めた。
「良いってさ」
「それなら良いけど」
「じゃあ行こっか!」
「あぁ」
電車に乗って向かっていると浴衣姿の人がどんどん増えてきた。
駅には人が溢れる位沢山居た。
次の日――の墓参りに向かった。
高校生の頃に良く通った道が懐かしく感じた。
高校生の記憶は彼女との思い出ばかりだった。
♢♢♢
「人混み凄いな」
「花火大会とか来たことないの?」
「花火自体見た事ないよ」
「十七年生きてて初めて会ったよ、花火見た事ない人」
「見る機会がなかったんだよ」
凄い馬鹿にされてる気がした。
「私のお陰で見られるんだから感謝してね」
「はい、はい、ありがとう」
歩いていると沢山の出店が出ていた。
「林檎飴食べたい」
そう言って彼女は走り出した。
戻ってくると、手にはりんご飴を持っており、美味しそうに食べていた。
「美味しいの?」
「一口いる?」
「うん」
「どう?」
初めて食べたリンゴ飴は、想像よりも美味しかった。
「めっちゃ美味しい!」
「でしょ!」
彼女は笑顔でそう言うと夜空を見上げた。
「綺麗」
「確かに」
夜空には花火が上がっていた。
「花火を見ると夏が始まった気がするんだよね」
「夏といったら花火っていう人の気持ちがわからなかったけど――良いね花火」
彼女の方を見たら目から涙が流れていた。
彼女の視線の先を見たら親友が女の子と一緒に歩いていた。
泣いている彼女から目が離せなかった。
泣くほど好きになれるなんて凄いと思った。
その涙に惚れてしまった。
――の墓の前に女性が居た。
「お久しぶりです」
「久しぶりね少し痩せたんじゃないの? しっかりご飯食べてる?」
「少し痩せたかもしれないです」
「健康より大切な事なんて無いんだからね」
「はい、それで――の結婚式で何があったんですか?」
♢♢♢
私は子供の頃病弱で良く入院していました。
何となく子供ながらに長生きは出来ない気がしていました。
入院中の私の楽しみは読書でした。
私は何度も読み返すくらい好きな小説がありました。
同い年の子が書いた小説と言うこともあり、その子の事をとても尊敬していました。
高校生になる頃には体調も良くなり、学校生活を送る分には何の支障も出ない位には回復していました。
高校一年生の春、私は運命の出会いを果たします。
入学式が終わり進路指導室に呼ばれました。
病気の事もあり今後の高校生活についての相談でした。
その時わたし以外にももう一人男の子が呼ばれていたのですが、仕事の話などしていたから芸能人なのかなと私は思っていました。
私が退室する時に男の子が名前を呼ばれ、何処か聞き覚えのある名前でした。
そう、私の好きな小説の作者の名前でした。
その時から私は彼に惚れてしまいました。
それからも廊下などで彼とは何度かすれ違ったりしたのですが、勿論私は知ってるが彼は私の事など知らないので彼の事を見ているだけで一年が過ぎました。
高校二年生なり委員会で彼と良く居る人と一緒になりました。
それからその友達を通して挨拶ぐらいする様な仲にはなったのかな。
私は友達の方から告白され、嬉しかったのですが友達に恋愛感情は無かったので断ろうとも思ったんですが、断ったら彼との関係も切れそうだったので付き合う事に決めました。
これが私の初めての大きな嘘。
その甲斐もあって彼とは凄く仲良くなりました。
高校を卒業する前には友達とは別れて。
何となく彼が私の事を好きな気がして、卒業のタイミングで告白される気がしていたが、そんな事は起きませんでした。
大学生になっても彼との関係は続いていました。
偶にご飯へ行ったり遊んだりする位だったが、良い感じの仲だったと今になって思います。
私は編集者のバイトを大学から始め。
将来は編集者になれたらと思いはじめました。
そんな事もあってか、彼から新作の小説を読ませて貰って感想を聞かれるようになりました。
私は本当は凄く良かったのに恥ずかしくて、彼に酷い事を言ってしまった。
後になって彼が小説を書くのを辞めてしまったのを知り、私の所為じゃないかと思い怖くて聞けませんでした。
私達はそれから会う日数が減った気がします。
大学が卒業に向かう頃、私は病気が悪化してまた入院を繰り返す日々に戻ってしまいました。
なんとか大学は卒業出来たが、とてもじゃないが社会人はやっていけそうにありませんでした。
両親には申し訳ない気持ちしかなかったです。
病院で両親が泣いているのを見てから私の人生は長くないと悟りました。
お見舞いに毎日来る幼なじみからプロポーズをされて私は悩みました、けど父が娘の花嫁姿を見るのが夢だと言っていたので、今まで何にも親孝行が出来なかっのでせめてもの償いでプロポーズを受けました。
二度目の大きな嘘です。
それからの日々はあっという間に過ぎていきました。
結婚式の招待状は彼にも送りましたが、何の連絡も無く前日を迎えた日。
彼から一通の連絡が来ました。
手紙には一文だけ書かれてました。
「好きです」
と短く書かれていました。
私はその手紙がとても彼らしく思えました。
私はまだ返信を返せていないので、この場を借りて答えさせて頂きます。
「私も大好きです」
ご静聴ありがとうございました。
「これがあの日の結婚式で起きたことよ」
「教えて頂きあるがとうございます」
「あまり気に病まないでね――あの子もきっとそう思っているから」
その話を聞いてから俺は大学生活を思い出していました。
彼女との最後の思い出を。
♢♢♢
大学に入学してから俺はまた小説を書き始めた。
もともと担当の編集者との話し合いで高校を卒業までの休載と決まっていたので、大学では執筆に専念するつもりだった。
次は長期連載のシリーズものを書くとの約束だったので、題材になる話を考えていた。
プロットを書いては担当の編集者と相談を重ねていたが、大学3年でみんなが就活を初めているのに、俺はまだ書く題材を決めかねていた。
彼女が最近編集者のアルバイトを始めたらしいので、勢いで書いた新作を読んでもらう事にした。
「久しぶり、編集のバイト忙しい?」
「忙しいけど楽しいよ」
「よかったら新作書いたから、読んで感想聞かせてよ」
「いいの?楽しみ」
俺は持ってきていた原稿をカバンから取り出し、彼女に渡した。
彼女は真剣な顔で原稿を読み始めた。
彼女は読み終えると、真剣にアドバイスをしてくれた。
俺はその姿を見て納得のいく新作が出来たら、彼女に告白する事を心に決めた。
アドバイスを元に何度も書き直したが……納得の行く作品が出来なかった。
悩んだ末担当編集者と相談して、新作は就活が終わってから書く事にした。
大学を卒業し、働きながら新作の小説が書き上がった時一通の招待状が届いた。
俺は間に合わなかったと気が付いた。
せめて自分の気持ちだけは伝えようと思い。
彼女宛に手紙を一通送った。
家につくと原稿を濡らしながら俺はまた書き始める。
ありがとう言葉《ことは》。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
